

療育を辞めたいと思ってる方「今通ってるリタリコジュニアを辞めたいけど、本当に辞めていいのか悩んでる」
療育に通っていく中で「療育を辞めたい…」と悩まれる方は、少なくないと思います。
そこで本記事では「療育を辞める時の基準・大事なこと・注意点」をお伝えしたいと思います。
この記事の執筆者の私は、療育支援を15年以上しており、現在も発達障害のお子さん/親御さんの支援に携わってます。
また私の息子は “言語発達遅滞・発達性協調運動障害”の診断を受け、2年ほど療育に通ってました。
その支援/育児経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
リタリコジュニアを辞める「判断基準」
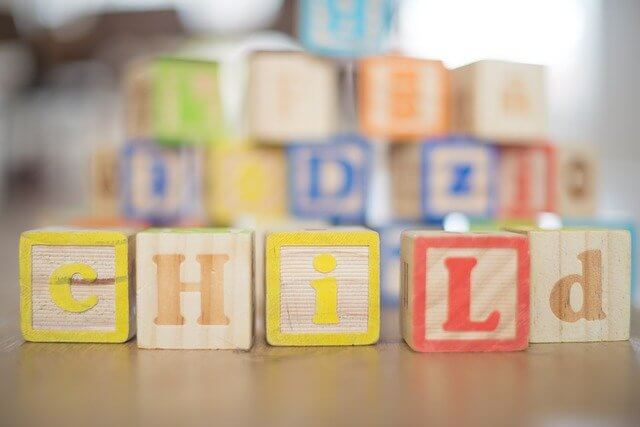
療育(リタリコジュニア)を「辞める判断基準」は4つあります。
①:子ども本人が「嫌がってる」
②:「子どもの成長」が実感できない
③:困りが「解決/対処できる」状態
④:本人に必要な「機会の担保」ができてる
子ども本人が嫌がってる

お子さんが “療育の場所/先生を嫌がる” 場合になります。
例えば、お子さんからの「○○やりたくない!○○行かない!」などの “発言/行き渋り” になります。
慣れる時間は必要ですので、一定期間様子を見る必要はあります。
ただ、療育の先生・ご家族が、療育を楽しめる工夫を最大限(指導内容の見直し/先生の変更)しても、
お子さんが心底嫌がっている場合は、リタリコジュニアを辞める(変える)タイミングになると思います。
個人的な期間の目安としては、週1回で通い、2ヶ月以上続いてるイメージになります。
子どもの成長が実感できない

2~3ヶ月以上通っても、お子さんの成長が実感できない場合になります。
ここで言う “お子さんの成長” とは「リタリコジュニアの指導の中でのお子さんの成長」になります。
親御さんの立場ですと、家や園・学校での変化に目が向くと思いますが、
まず最初に、療育の時間でのお子さんの変化が見られないと、お子さんの日常生活の中での変化には繋がりづらいです。
この “療育の時間中での成長が感じられない” 場合は、お子さんと療育が合っていない可能性があります。
✅「リタリコジュニアの先生」に聞いてみるのも1つ
親御さんの目から見て成長が見えなくても、先生から見たら成長が見えている場合もあります。
療育機関は、指導記録を残してる場合が多いです。
その中でも、リタリコジュニアは、指導記録を丁寧に残している支援先になります(業界最大手でノウハウ・システムが整ってる)。
お子さんのどの部分の成長が見られるのか、確認してみると、具体的なお話が聞ける可能性があります。
困りが解決/対処できる状態
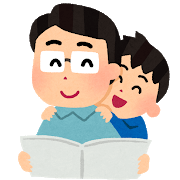
リタリコジュニア(療育)に通う理由になった “お子さんの困り” に対して、
解決できていたり、対処できる状態になっていれば、それは辞める目安になります。
リタリコジュニアとの繋がりがなくても、日常生活に支障がない状態でしたら、検討できる段階だと思います。
✅「今後想定される困り」には注意が必要
例えば、今はクラスの先生・クラスメイトに理解あって、協力を得られてるから問題なく過ごせてる、という場合です。
先生やクラスメイト(環境)が変わった時に、本人が困る可能性がある(過ごしにくくなる)場合は、
リタリコジュニア・その他の療育先の先生に相談が必要になります。
本人に必要な機会の担保ができてる

リタリコジュニアを辞める代わりに、違う療育先で “本人に必要な機会が確保” できていれば、大丈夫です。
例えば、リタリコジュニアでは個別・小集団をしていたけど、
その環境で、できることが定着した為、大きな集団にチャレンジする為に、他の療育先にステップアップするケースになります。
リタリコジュニア(療育先)を辞める場合は、
『新たな療育先が本人に合ってるか確認』ができてから(見学or体験をして)をお勧めします。
万が一お子さんに合わなかった場合、療育が全くない期間が生まれてしまう為です。
親の判断だけで決めるのは避ける
専門家の客観的な意見を聞いた上で、判断することをお勧めします。
その理由は、専門家はお子さんの「未来の困り(可能性)」を想定しやすい為です。
多くのお子さんを見てきて、どういう特性の子が・どの程度の学年で・どの場面で・何に困りやすいか等、ある程度を把握しています。
お子さんの特性・今後のライフステージを考慮して、懸念があるのかを聞くことは、とても大切なことです。
専門的な知識がない親御さんの多くは、「今」に視点が向きやすかったり、今後の困りが想像しづらいことが多いです(当たり前なのですが…)。
「やっぱり辞めなきゃ良かった…」は、一番避ける必要がある所です。
ここに関する、療育を辞めて後悔したケースは、下の記事に事例をまとめてます。
私が実際に携わったケースになりますが、参考程度にご覧ください。
【療育の後悔】受けないと、子どもの将来にどんな可能性が?事例を元に解説
リタリコジュニアを「辞める時の視点」

リタリコジュニア(療育)を「辞める時の視点」は、2つあります。
①:本人に必要な「配慮/環境」の担保
②:「相談先」と繋がっておく
本人に必要な配慮/環境の担保
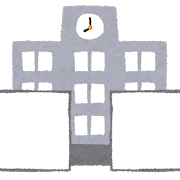
本人の困りが解消されていたり、対処できる状態でしたら、療育は辞めても良いと思います。
ただお子さんの特性自体は、変わるものではない為、
必要な配慮(周囲の人の関わり)・環境が必要な場合も多いです。
・事前に見通しを伝えると安心する
・口頭より見せた方が伝わりやすい
・余計な音/物はない方が集中しやすい
など、お子さんによって、必要な配慮・環境は変わってきます。
こういった部分に対して、リタリコジュニアを辞めても、
親御さんが動いて、”用意できる”、”お願いできる”、
“本人が理解し行動できる” 状態が理想になります。
相談先と繋がっておく
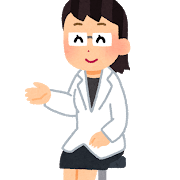
今まで繋がっていた療育先を辞めるのは、不安な方がほとんどだと思います。
そのため、リタリコジュニアか他の支援先に “繋がっておく(いつでも相談できる状態)” のは大切です。
何かあってもすぐに相談でき、早めの対応ができる為になります。
リタリコジュニアを「辞める時の注意点」
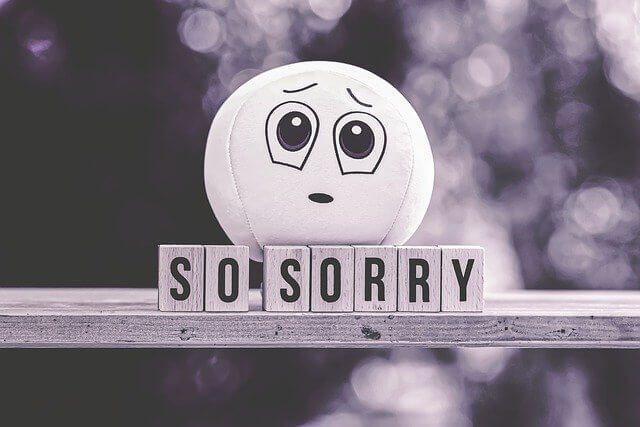
療育(リタリコジュニア)を「辞める時の注意点」は、3つあります。
①:「本人の意思」を無視しない
②:「環境に変化がある時期」は避ける
③:「相談先との繋がり」を0にしない
本人の意思を無視しない
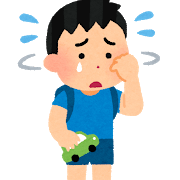
療育は、客観的に見た必要性・妥当性も重要ですが、そこに通う本人の気持ちも重要です。
お子さんの年齢やタイプによりますが、リタリコジュニア(療育)に通うことに対して、
どう思ってるのか…聞くのは、必要になります。
スキル的に必要なくても、お子さんの気持ち的に必要(安心感)な場合があります。
環境に変化がある時期は避ける

ここでいう「環境」とは…
・担任/クラス
・園/学校
・家庭
(引越し/同居する家族)
になります。「療育をやめる」というのは、私たち大人の想像以上に、大きな環境の変化になります。
特に新年度は、生活環境が変わる為、お子さんに負荷がかかります。
「時期的に切りが良いから、4月~辞める」というより、コントロールできる環境の変化を最小限にして、
6月以降の新生活に慣れてきたタイミングで辞める方が良いです。
新年度以外でも、引っ越しや生活する家族の人数が変わる等も同じ考え方になります。
新しい生活で、2~3ヶ月は慣れる期間として、環境の変化は避けたい所です。
相談先との繋がりを0にしない
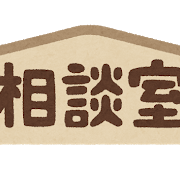
これは、先ほど触れた内容になりますが、“相談先との繋がりを1つは確保しておく” ことです。
「何かあった時に、相談できる状態」が理想的になります。
通っていた療育先(リタリコジュニア)が、希望すれば今後も利用できる状態でしたら、同じ療育先が良いと思います。
ただ、児童発達支援(福祉サービス)など、支援の対象外という場合は、
教育相談など、地域の相談窓口と繋がっておくことをお勧めします。
少なくとも「何か困ったら○○に相談する」となっている状態ですと、安心です。
【リタリコジュニアを辞めたい】まとめ

記事のポイントになります。
✅療育(リタリコジュニア)を
「辞める判断基準」
・子ども本人が「嫌がってる」
・「子どもの成長」が実感できない
・困りが「解決/対処できる」状態
・本人に必要な「機会の担保」ができてる
✅療育(リタリコジュニア)を
「辞める時の視点」
・本人に必要な「配慮・環境」の担保
・「相談先」と繋がっておく
✅療育(リタリコジュニア)を
「辞める時の注意点」
・「本人の意思」を無視しない
・「環境に変化がある時期」は避ける
・「相談先との繋がり」を0にしない
✅療育(リタリコジュニア)を辞めた後
「必要なこと」
・早めの学習フォロー
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】




































