

療育を検討されてる方「療育に通う基準が知りたい。療育を始める人はどの時期に始めることが多いの?」
以前に比べ、 “療育” という言葉を知る方は増えました。
保育園の先生から勧められたり、保健師から発達の指摘を受けたり、学校の担任から検査を勧められたり..
今、様々な場面で「療育」という言葉を知り、検討されてる方が増えています。
一方で、
「療育に通う基準って具体的にあるの?」
「療育を利用すべきか分からない」
と悩まれてる方も多いと思います。
そこで本記事では、
「療育に通う基準」「療育に通う子が多い時期(タイミング)」に関する情報をまとめました。
本記事の執筆者の私は療育・発達支援を15年以上しており、現在も発達障害やグレーゾーンのお子さんの支援に携わってます。
その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
療育に通う「3つの基準」
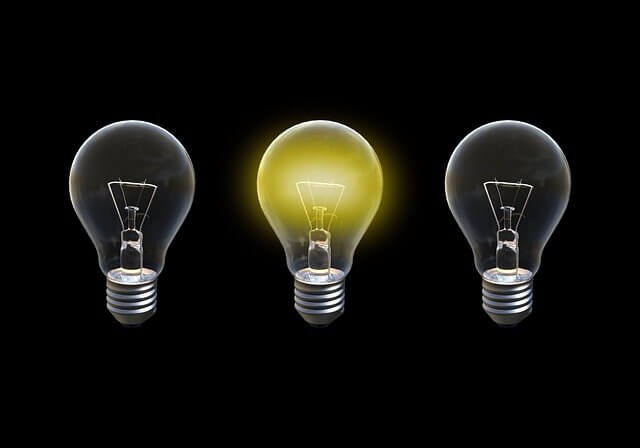
療育を受ける明確な基準はありません。
ただ、現場で支援する中で私が感じてきた、大切な3つの点(基準)をお伝えしたいと思います。
①:子ども本人が「困ってるか」
②:「客観的に見て」困ってるか
③:「機会損失」になってないか
(コミュニケーション/集団参加/学習)
子ども本人が困ってるか

お子さん本人が困りを感じているか、になります。
・友達と上手く関われない
・自分の気持ちを言葉で伝えられない
・勉強が分からない
・イライラすると癇癪を起こしちゃう
など、その子が日常生活で困っているのか、どんな困りを感じているのか、が大切になります。
客観的に見て、困ってるか

ご家族や先生など、身近な大人の方から見て「客観的に見て困っているか」も大切な視点になります。
明らかに困るであろう状況でも、お子さん本人が気にしていなくて「困ってないよ」という場合も、少なくありません。
例えば、
・興味のない集団活動には参加しない
・提出物を出せない
・授業についていけてない
など、今後本人が困る(将来に影響が出る)可能性が高い場合も、療育の必要性は高くなります。
お子さん本人は、先の生活を想像するのが難しい為、本人が困っていない場合も少なくありません。
客観的に見て、本人の困りに繋がる可能性あるなら、療育の必要性は高くなります。
また、ご家族が困っている場合も、療育の必要性はあります。
例えば、家だけで癇癪が出る場合は、外では良い子なので、本人も家族も考え方によっては、我慢して乗り切ろうとする場合もあります。
ただ、本人はもちろん、一緒に過ごす家族が疲弊したりストレスになるのは、良いことだとは言えません。
本人や家族などの過ごしやすさを作る為、療育は大切な支援になります。
機会損失になってないか

本人は困っていないし、家族もそこまで困っていない場合になります。
ただ生活の様子を見ていると、本人自身が機会損失をしてることがあります。
例えば、
・友達とコミュニケーションが発展しない
(交友関係が広がらない)
・授業や人の話の理解が不十分
(学びや興味を持つ機会が減ってる)
など、困ってはいないものの、本人の捉え方やスキルによっては、もっと楽しめたり学べることが沢山あります。
困りがない場合でも、日常生活をより充実させる為に、療育を受けるケースもあります。
【関連記事】
【療育の後悔】受けないと、子どもの将来はどんな可能性が?事例を元に解説
療育を始める方が多い「5つの時期」

療育を始める方が多い時期は、5つあります。
私が支援してきた中で、特に多かった時期になります。
①:3歳児健診
②:就学時健診
③:小学校入学後
(1~2年以内)
④:不登校になった時
(小学校低~中学年)
⑤:授業についていけなくなった時
(小学3~4年)
3歳児健診

未就学のお子さんで、一番多いタイミングになります。
3歳児健診で先生から指摘を受け、療育を検討されるケースになります。
「1歳半健診で様子を見ましょうと言われた」
「何となく言葉がゆっくりだと思ったけど、そこまで気にしてなかった」
など、様子を見ていた方が、3歳児健診をキッカケに、療育を探し始めるパターンが多いです。
また、父親はそこまで心配していないことも多く、
「子どもなんて、そんなもんじゃない?」
「俺も昔は似た感じだったよ」
など、家族間で温度差が出やすい時期でもあります。
【関連記事】
就学時健診
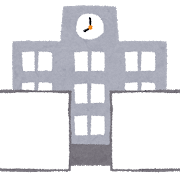
就学時健診(小学校入学前)で指摘され、療育を検討するケースになります。
具体的には、学級に関する個別相談を勧められる等です。
席に座って待つこと、質問への受け答え、指示を行動に移すのが難しいなどの様子から、指摘されることが多いです。
小学校入学後

小学校入学してから、お子さんの困る行動が出るケースになります。
・離席する
・癇癪を起こす
・他害、暴言
・書字、板書が苦手
・提出物が出せない
・集団参加を嫌がる
(興味がない内容)
など、お子さんによって様々な困りが出ます。
幼稚園や保育園が自由保育で、本人の行動もそこまで目立つことなく、先生にも尊重してもらっていた為、大きな問題にならなかった子も多いです。
小学校に入って、より大きな集団で、より長い時間集団に合わせることが求められる様になり、問題が表面化するケースになります。
不登校になった時

小学校低学年~中学年で、学校の行きしぶりが始まり、不登校になったタイミングになります。
・1ヶ月以上学校を休んでる
・五月雨式でしか登校できない
など、学校生活に大きな支障が出始めたタイミングで、療育を検討される方が多いです。
授業についていけなくなった時
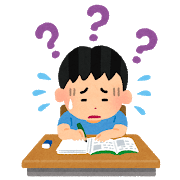
小3~4が最も多いのですが、授業についていけなくなり、学習面の困りが大きくなるタイミングになります。
文章題が増えたり、計算が複雑になったり、問題が難しくなってることも、この時期で療育を検討される方が多い理由になります。
【関連記事】
【発達支援員が解説】週何回?療育の頻度と期間~目的と通い方で変わる~
療育を検討する上で「知っておきたいこと」

療育を検討する上で「知っておきたいこと」をお伝えします。
まず療育には、福祉サービス、民間の療育の2種類があります。
✅福祉サービス
国の助成金が受られる(1割負担)反面、混み合っており、利用までに時間がかかります。
✅民間療育
すぐに始めやすい分、完全実費負担になります。
お子さん、ご家族の状況によって、必要な選択肢は変わってきます。
①:困りが強い場合
⇨民間+福祉サービスの併用
(民間ですぐ始め、福祉サービスは併行で探す)
②:急ぎでない場合
⇨福祉サービスを探す+ペアレントトレーニング
困りが強い⇨民間+福祉サービスの併用

今の生活に支障が出ていたり、すぐに支援を受けたい場合は、民間療育を始めつつ、併行して福祉サービスを探されるのが良いです。
福祉サービスは混み合っている為、待機登録という形で、空き待ちになる場合が多いです。
すぐに始められる民間療育に繋がりつつ、長期的に通いやすい福祉サービスに繋がるのが、多くの方が利用されてる形になります。
急ぎでない⇨福祉サービス探す+ペアトレ
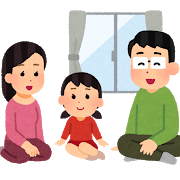
緊急性がなかったり、先々必要性あれば利用したい、という方は、福祉サービスで待機登録され、併行してペアレントトレーニングを受けるのをお勧めします。
ペアレントトレーニングとは、家庭でお子さんと関わる際に必要な知識、ノウハウなどを親御さん向けに伝える講座になります。
療育を受けるまでの間、家で一緒に過ごす時間を少しでもお子さんの成長に繋げる為に、ペアレントトレーニングは、早い段階で受けられる方のが良いです。
福祉サービスは、複雑な手続きの上に混みあっている為、早く受講されたい方は、リタリコジュニア をお勧めします。
詳しくは、リタリコジュニア 公式サイト をご覧ください。
福祉サービスは、通所受給者証が必要になります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
【通所受給者証のデメリット】3つの注意点/メリット/申請方法
【療育に通う基準 3つのポイント】まとめ

記事のポイントになります。
✅療育に通う
「3つの基準」
・子ども本人が困ってるか
・客観的に見て困ってるか
・機会損失になってないか
(コミュニケーション/集団参加/学習)
✅療育を始める方が多い
「5つの時期」
・3歳児健診
・就学時健診
・小学校入学後
・不登校になった時
・授業についていけなくなった時
✅療育を検討する上で
「知っておきたいこと」
・福祉サービスと民間療育がある
・福祉サービス:料金安い、混み合ってる
・民間療育:料金高め、すぐ利用しやすい
・困りが強い方:民間と福祉サービスの併用
・急ぎ出ない方:福祉サービスとペアレントトレーニング
✅療育を検討する前に
「家庭でできること」~学習面~
・特性に合う学習方法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【療育のデメリット】3つの注意点/メリット/心構え/療育の選び方






































[…] 【療育に通う基準】3つのポイント~療育を始める方が多い4つの時期~ […]
[…] 【療育に通う基準】3つのポイント~療育を始める方が多い4つの時期~ […]
[…] 【療育に通う基準】3つのポイント~療育を始める方が多い4つの時期~ […]