

子どもの不登校で悩まれてる方「せっかく復帰したのに、学校をまた休んじゃった。どうすれば休まずに行けるの?復帰後の子にどう関わると良いか知りたい」
不登校問題は、不登校期間中だけでなく、
復帰後の登校の不安定・家での関わり方など、様々な難しさがあります。
「復帰したのに、また休んじゃった..」
「登校を促すべき?無理させないべき?」
など、疑問やお悩みを抱えてる方も多いです。
そこで本記事では「不登校の復帰後」に関する情報についてお伝えします。
この記事を執筆している私は、不登校・療育支援を15年以上してます。
その支援経験・事例を通して、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不登校の復帰後に「また休む理由」

不登校の復帰後に「また休む理由」は、3つあります。
①:「回復」が不十分
②:本人が「無理をしてる」
③:「学校の環境」が悪い
回復が不十分
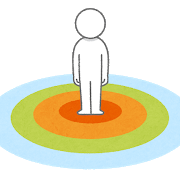
不登校のお子さんは、心が疲弊していて、精神的に弱った状態なことが多いです。
そのため、まず最初に「休息」を十分にとる必要があるのですが、
この休息が不十分な場合、復帰後に休むことがあります。
周囲が登校するように何度も促してることが、原因の1つになります。
本人が無理をしてる

本人が無意識に頑張りすぎてるケースになります。
「学校に行かなきゃ!」と強い気持ちに対して、体が追いついてない状態です。
本人は無自覚なことが多いため、周りが気付くのに遅れることも珍しくありません。
学校の環境が悪い

「その子の特性/状態」と「学校の環境」が合っていないケースになります。
例えば、以下のような理由があります。
・担任の理解がない
・陰湿なクラスメイト
・学校側の配慮がない
(個別対応を認めない)
このような環境ですと、お子さんのコンディションが整っていても、環境的な問題で難しいことが多いです。
不登校の復帰後に「休まない為のポイント」

不登校の復帰後に、「休まない為のポイント」は4つあります。
①:本人に合う「通い方/ペース」を決める
②:「学校に行けない時」の対策も考える
③:「休む時の基準」を決めておく
④:「学校に行く/行かない」以外の選択肢
本人に合う通い方/ペースを決める
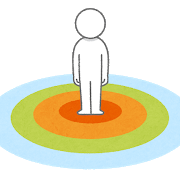
本人と一緒に「通い方/ペース」を具体的に決めます。
あくまで一例ですが、通い方は、以下のような選択肢があります。
・保健室登校
・放課後に課題だけ取りに行く
・好きな授業だけ参加
・オンラインで参加
ペースは「週◯日登校」「好きな授業の日だけ登校」などがあります。
その日のコンディションにもよるので、
“ペースを守ること” が目的にならない様に注意が必要です。(ex.◯曜日は必ず登校、週◯日は必ず登校)
・本人の意思がある
・できそうなイメージが持てる
(本人が)
この2つの条件を満たす選択肢を見つけ、本人に決めてもらう過程が大切になります。
また、学校や担任の理解も必要なため、話を通しておく必要があります。
【合わせて読みたい記事】
学校に行けない時の選択肢も考える

通い方やペースを決めても、学校に行けない時は行けません。
むしろ、行けない時がある子の方が多いです。
そのため「行けない時」にどうするのか、本人と決めておくことが重要になります。
例えば、以下のような例があります。
・別室登校
・特定の授業だけ参加
・オンラインで授業参加
本人に選んでもらい、その日の過ごし方を決めてもらいます。
中には、放課後に課題だけ取りに行くお子さんもいます。
【関連記事】
【別室登校の過ごし方】メリット/デメリット/教室へ復帰する5つのポイント
休む時の基準を決めておく

本人・家族も、共通認識が持てる目安(学校を休む基準)を決めておきます。
不登校の子は、前日まで学校に行くと言っていても、当日に「今日は休む」と言うことがあります。
本人としては、学校に行くのが本当に辛いのですが、
家族としては「昨日は行くって言ってたじゃん」と思われることもあると思います。
そこで本人のコンディションを、数値や天気で表現をします。
例えば、以下のような表現・基準があります。
・10段階中、2以下なら休み
(数字が大きいほど、体調が良い)
・晴れ~曇~雨で、雨なら休み
(晴れが体調が良い)
具体的な表現ですと、周りの人も本人のコンディションが把握でき、必要な配慮がしやすくなります。
学校に行く/行かない以外の選択肢

家で過ごす選択肢も、本人と一緒に決めておきます。
・家の手伝いをする
(洗濯/掃除/ゴミ捨て/買い物)
・家で自宅学習
(ドリル/プリント/タブレット)
「学校に行かない=やることがない=ダメなこと」と本人が思わないよう、事前に選択肢を用意しておきます。
“学校を休んだからダメ” ではなく、
「学校に行く変わりに、今日は◯◯ができた」と、“本人が前向きに思えるような環境” を作っていきます。
不登校の復帰後に休んだ時の「対策」

不登校の復帰後に休んだ時の「対策」は、3つあります。
①:「十分な休息」をとる
②:復帰のプランを「見直す」
③:「違う選択肢」を検討する
十分な休息をとる

休息が足りなかった場合の対処法になります。
本人に好きなことをして過ごしてもらい、十分に休んでもらいます。
休息が足りなかった理由で多いのが、本人が頑張りすぎてたり、周りが登校の促しをしてることです。
“休息が足りてるかどうかの目安” の見極め方は、下の記事をご覧ください。
【関連記事】
【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン/関わり方/注意点
復帰のプランを見直す
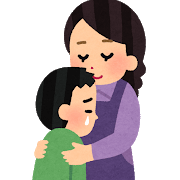
復帰のプラン/方法が、本人に合っていなかった場合は、見直しが必要です。
また、復帰のプラン自体はなく「何となく行けそうだったから」という理由の場合も、プランを考える必要があります。
本記事の、不登校の復帰後に「休まない為のポイント」の①の通り、通い方やペースを本人と決めることが必要になります。
【関連記事】
違う選択肢を検討する
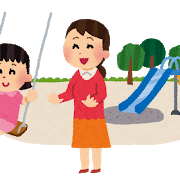
復帰後に休む理由が、環境的な理由(学校の環境が合わない)が大きい場合は、別の選択肢を検討するのも1つです。
こちらは、選択肢の例になります。
・別室登校
・フリースクール
・転校
・自宅学習
(担任が変わるまでの期間)
選択肢を伝え、本人の気持ちを確認することが大切になります。
不登校の復帰後に「大切なこと」

不登校の復帰後に「大切なこと」は、3つあります。
家族が、認識しておきたい点になります。
①:復帰後に「休む子は多い」
②:「学校に復帰」は選択肢の中の1つ
③:「学校を休む」=本人を守る手段
復帰後に休む子は多い
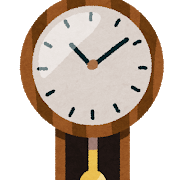
先ほども触れましたが、不登校の復帰後に休む子は多いです。
私の感覚的には、休む子の方が多いです。
復帰しても、本人のペースで通う(ex.体調に合わせて、月に1回休む)ケースも少なくありません。
学校に復帰は選択肢の中の1つ

「学校に行く」は、あくまで選択肢の1つになります。
お子さんの特性/状態、学校の環境によっては、「学校に行く」が最善でない場合もあります。
今は、他の選択肢も増えています。
・フリースクール
・通信
・転校
・自宅学習
「”本人に合う選択肢” を探す」という視点が、大切になります。
“学校” という集団生活が、本人にとってハードルが高い場合は、習い事から始めるのも1つです。
習い事の選択肢など、詳しく知りたい方は、下の記事をご覧ください。
【合わせて読みたい記事】
学校を休む=本人を守る手段

「学校を休む」自体は、悪いことではありません。
過度なストレス、失敗体験、自己肯定感の低下から、本人を守る手段になります。
この認識をご家族が持つこと自体が、本人を守る要素となります。
【関連記事】
不登校の復帰後の「注意点」

不登校の復帰後の「注意点」は、4つあります。
①:「強引に」復帰させない
②:「一喜一憂」しない
③:「成功/失敗」で捉えない
④:「学校の話」を無理に聞かない
強引に復帰させない

本人の意思がない(はっきりしない)状態で、登校を促すことは避けた方が良いです。
また本人が無理をしてる自覚がない場合ですと、口では「学校行く」と言っても、
実際は、登校できる状態でない場合が多いです。
本人のコンディションを見つつ、別室登校/1部の授業だけ参加など、
ハードルを下げながら、学校との向き合い方を、丁寧に見つけることが大切になります。
一喜一憂しない

本人の1つ1つの言動/変化に、過剰に反応しないことになります。
親御さんとしては、本人のポジティブな変化/発言は嬉しいものです。
ただ、それは一時的なもので、根本的な解決に繋がる変化でない場合が多いです。
例えば、これらの様な言動になります。
・「学校に行く」と発言した
・数回登校できた
不登校の子は、気持ちの振り幅が大きいです。
前日の夜に「明日は学校に行ってみる」と言っても、当日の朝には「今日はやっぱり休む」と言うことも珍しくありません。
数日登校できたとしても、その後に反動でしばらく学校に行けなくなることもあります。
家でイライラしやすかったり、疲弊して家でぐったりしてることもあります。
大人の過剰な反応は、本人にプレッシャーを与え、無理をさせてしまいます。
「これ(今の子どもの言動/状態)は、気持ちの波の1部分なんだ」と思うことが、
親御さんの気持ちの負担を減らし、結果的に、本人に良い影響(安心感)を与えます。
成功/失敗で捉えない
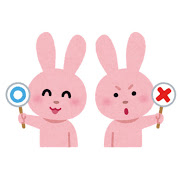
学校の再登校、別室登校など、不登校問題は、チャレンジしても上手く行かないことが少なくありません。
ここで大切なのは「また振り出しに戻った..」と考えず、どんな出来事も大人側が「失敗」と捉えない姿勢を示すことになります。
例えば、保健室登校をした時に「2時間過ごしたけど、疲れて早退した」とします。
この場合は「早退しちゃった(最後まで過ごせなかった)」ではなく、
今は「1時間がちょうどいいんだ(本人に合ったライン)」という気付きを得た、ということになります。
このように、一見失敗に見えることも、良い側面で捉える(リフレーミング)ことが、
本人・親御さんの心を守る意味(前進してる感覚が持てる)で、重要になります。
学校の話を無理に聞かない

不登校の子の中には、学校の話に触れられたくない子も多いです。
私たちもですが、辛い経験/失敗体験など、人に触れられたくないことはあると思います。
「明日は、学校頑張れそう?」
「今日先生と電話で話したよ」
「来週、学校で○○やるみたいだよ」
これらの声掛けは、お子さんの状態に合わせて慎重になる必要があります。
【学校をまた休む 不登校の復帰後】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の復帰後に
「また休む理由」
・”回復” が不十分
・本人が無理してる
・”学校の環境” が悪い
✅復帰後に
「休まない為のポイント」
・本人に合う “通い方/ペース” を決める
・”学校に行けない時” の選択肢も考える
・”休む時の基準” を決めておく
・”学校に行く/行かない” 以外の選択肢
✅復帰後に休んだ時の
「対策」
・十分な休息をとる
・復帰のプランを見直す
・違う選択肢を検討する
✅不登校の復帰後に
「大切なこと」
・復帰後に休む子は多い
・”学校に復帰” は選択肢の中の1つ
・学校を休む=本人を守る手段
✅不登校の復帰後の
「注意点」
・強引に復帰させない
・一喜一憂しない
・成功/失敗で捉えない
・”学校の話” を無理に聞かない
✅それでも復帰が難しい時に
「不登校の子が備えたいこと」
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合う学習方法
・レベルに合った問題の選択
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】
【欠席理由はどう伝える?】不登校の欠席連絡/電話が辛い時の対策









































[…] 【学校をまた休む..】不登校の復帰後の4つのポイント・注意点 […]
[…] 【学校をまた休む…】不登校の復帰後の4つのポイント・注意点 […]
[…] 【学校をまた休む…】不登校の復帰後の4つのポイント・注意点 […]
[…] 【学校をまた休む..】不登校の復帰後の4つのポイント・注意点 […]