

子どもの不登校で悩まれてる方「不登校の子の母親は、どんな過ごし方をしてるの?今より気持ちが楽になる過ごし方が知りたい」
不登校の子の親御さんは、
「いつまで、この生活が続くの?」
「子どもの将来が心配で仕方ない…」
「家で何をして過ごせばいいの?」
様々な不安と戦いながら、生活をされています。
親御さんの負担は、とても大きいものです。
そこで本記事では、親御さんの気持ちを今より軽くする様な
「不登校の子の親の過ごし方/子どもと生活への向き合い方」」についてお伝えします。
この記事を執筆している私は、発達/相談支援を15年以上してます。
今まで、多くの不登校の子/親御さんへの支援をさせて頂きました。
その経験を元に、本記事をまとめています。
不登校の子の親御さんは、精神的に追い詰められる方が少なくありません。
そんな方たちへの支援をしてきて思うのは、過ごし方よりも、気持ちの持ち方(向き合い方)が大事だということ。
気持ちの持ち方が変われば、過ごし方も変わります。
本記事では、過ごし方だけでなく、気持ちの持ち方も参考にしていただけますと幸いです。
目次
不登校の母親「一人での過ごし方」

ここでは、不登校の子の母親の「一人での過ごし方」をお伝えします。
私が支援をしてきた親御さんが、実際にされていた過ごし方になります。
・家事
・TV/スマホ
・友人と食事
・庭園
・カフェ
・買い物
・好きな食べ物を食べる
・夜にお酒を飲む
ここで大切なことは「自分の好きなこと/没頭できること」になります。
生活から離れて無心になったり、夢中になれる時間は、心の静養に繋がります。
ご自身が何をしてる時間が、一番心が休まるのか、見つけていくことが大切になります。
不登校の母親「子どもとの過ごし方」

不登校の子の母親の「子どもとの過ごし方」をお伝えします。
ここのポイントは、お子さんは勿論ですが、
母親も楽しめる、少なくとも “母親のストレスにならない過ごし方” であることが大事になります。
こちらは、参考例になります。
・料理/お菓子作り
・ゲーム
・公園で遊ぶ
・買い物
・ショッピングモールに行く
・習い事+外食
・映画
・友達親子と遊ぶ
親子で楽しめるのが理想的ですが、親も子も違う人間ですので、好みや楽しめるものも違ってきます。
母親が無理なく、一緒に過ごせる方法を見つけることが大切になります。
母親が無理をすると、形だけになり、大人側もストレスですし、結果的にお子さんも満たされません。
不登校の母親「子どもと生活への向き合い方」

ここでは、不登校の子の母親の「子ども/生活への向き合い方」を5つお伝えします。
冒頭でも触れましたが、過ごし方だけでなく、その根本となる “気持ちの持ち方(向き合い方)” が大切になります。
ただ、”向き合い方を変える” ことは、とても難しいことですので、
「これなら取り入れられそう」と思えるものがあれば、参考にしていただければと思います。
①:不登校の「全体像」を知る
②:「ハードル」を下げる
③:「自分(母親)の為の時間」を作る
④:「相談できる人」と繋がっておく
不登校の全体像を知る
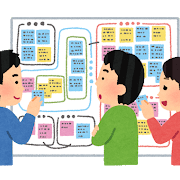
最初に、“不登校の子の状態” を把握することが大切になります。
不登校には、いくつか段階があります。その段階によって “お子さんに必要な関わり/配慮” は、変わってきます。
ここの把握が難しいと、見通しが全く立たないので、
「いつまでこの生活が続くの?」「いつ学校行ける様になるの?」と親御さんの焦りや強い不安に繋がります。
そして親御さんが不安になれば、それはお子さんにも伝わります。
「家族に迷惑かけてる」「自分だ本当に駄目だ」と、お子さんが自分を責めてしまい、ネガティブな影響が出てきます。
そういった理由から、親御さんが “不登校の全体像” を把握することが大切になります。
全体像を把握できることで「今は○○の時期なんだね。こういう関わりが必要なんだね」と気持ちに少し余裕を作りやすくなります。
不登校の全体像については、下の記事にまとめてます。
「不登校ってどんな状態?何をしてあげればいいの?」という方は、ご覧ください。
【関連記事】
ハードルを下げる
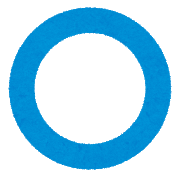
不登校の子の親御さんは、とにかく焦りますし、不安を抱えやすくなります。
その為、お子さんにも、自身(母親)にも、ハードルを下げる必要があります。
ここでは、2つのポイントを見ていきます。
「○○しなくちゃ」を減らす
不登校は、”できていないこと” に、どうしても目が行きやすくなる為、
常に「○○しなくちゃ」と考えやすくなる方が多いです。
「○○しなくちゃ」を、
「○○してもいい(できなくてもいい)」ぐらいに軽く考えることが、心の負担を軽くできます。
60点でOKにする
1つ1つのやることに対して「100点」でなくても、そこそこ出来ていればOKにするイメージになります。
例えば、朝登校できた子が、3時間目に早退したとします。
この時に「3時間目に早退した」ではなく、「2時間目まで授業が受けられた」とハードルを下げるイメージになります。
60点は例ですので、お子さんによってこれが、20点でも30点になることもあります。
“できなかったこと” より、”できたこと” に目を向けることが大切になります。
自分(母親)の為の時間を作る

不登校の子の母親は、とにかく子ども優先で生活される方が多いです。真面目な方ほど、無理をされます。
そのため、“自分(母親)の為だけの時間” を意図的に作ることをお勧めします。
意識して作らないと、真面目でお子さん思いの親御さんは、自身のことを後回しにされます。
焦る気持ちはとても分かります。ただ、お子さんの支えとなる母親のコンディションが悪くなれば、お子さんにも影響が出ます。
逆に母親(親御さん)が安定していると、お子さんも安心しやすくなります(個人差がありますが)。
これは、今まで不登校支援をしてきて、実感している点になります。
不登校の子からしたら、家族のコンディションや雰囲気は、”家の過ごしやすさに直結する大切な要素” になります。
相談できる人と繋がっておく

「話を聞いてもらえる」「分かってくれる人がいる」というのは、
不登校で悩む親御さんの “大きな支え” になります。
知り合いでも親戚でも、支援者でも、信頼できる人なら大丈夫です。
一人でも繋がりができると、お気持ちが違ってきます。
【不登校の母親の過ごし方】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の子の母親
「一人での過ごし方」
・家事
・TV/スマホ
・庭園
・カフェ
・買い物
・好きな食べ物を食べる
・お酒を飲む
✅不登校の子の母親
「子どもとの過ごし方」
・料理/お菓子作り
・ゲーム
・公園で遊ぶ
・買い物
・ショッピングモールに行く
・習い事+外食
・映画
・友達親子と遊ぶ
✅不登校の子の母親
「子ども/生活への向き合い方」
・不登校の全体像を知る
・ハードルを下げる
・自分(母親)の為の時間を作る
・相談できる人と繋がっておく
✅不登校の子と家族
「今後備えたいコト」
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合う学習法
・レベルに合う学習単元
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】









































[…] 【不登校の母親】今より気持ちを軽くする4つの過ごし方・5つの視点 […]
[…] 【不登校の母親】今より気持ちを軽くする4つの過ごし方・5つの視点とは […]
[…] 【不登校の母親】今より気持ちを軽くする4つの過ごし方・5つの視点 […]
[…] 【不登校の母親】今より気持ちを軽くする4つの過ごし方・5つの視点 […]