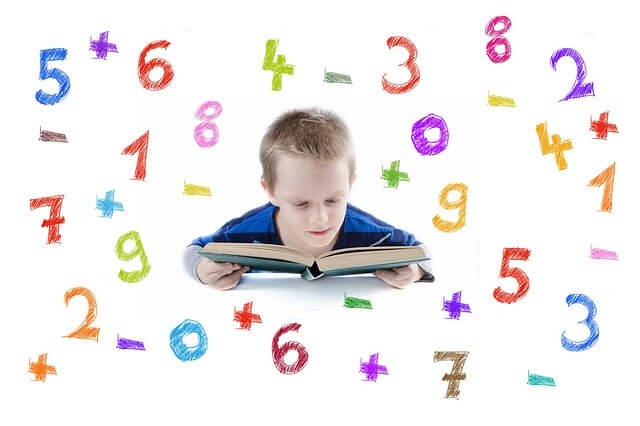

発達障害の子の宿題で悩まれてる方「子どもが毎日の宿題で癇癪を起こしちゃう。癇癪を起こさず、宿題がスムーズになる方法が知りたい」
発達障害の子・親御さんにとって、宿題は大きな悩みの1つになりやすいですよね。
特に、お子さんが癇癪を起こす場合だと、宿題が進まず、毎日が本当に大変だと思います。
そこで本記事では、「発達障害の子が宿題を今よりスムーズにする方法」をまとめてみました。
この記事を執筆してる私は、お子さんの療育/学習支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その支援経験を元に、3つの原因・実際に上手くいった方法・注意点も含め、お伝えします。
参考になれば幸いです。
目次
発達障害の子の宿題「癇癪になる原因」
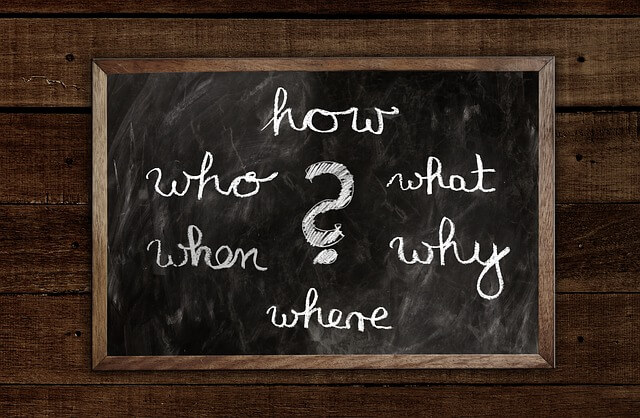
発達障害の子の宿題「癇癪になる原因」は、3つあります。
①:宿題が「分からない」
②:宿題が「やりたくない」
③:「宿題以外にやりたいこと」がある
宿題が分からない
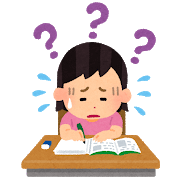
宿題自体が分からない内容だと、取り組むだけでお子さんはストレスが溜まります。そして癇癪に繋がります。
詳しくは、後述しますが、本人が取り組めるようサポートしたり、先生に相談して、宿題自体を調整する方法があります。
長期的には、お子さん本人が勉強できるようなサポートが必要になります(授業や宿題で困ってしまう場合)。
宿題がやりたくない
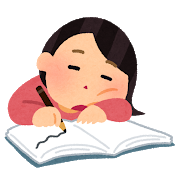
取り組んでしまえば、宿題はすぐ終わるのに、なかなか取り組まないお子さんになります。
何かと理由をつけて、宿題を先延ばしにしてしまいます。
宿題を取り組むこと自体に、時間がかかります。
宿題以外にやりたいことがある
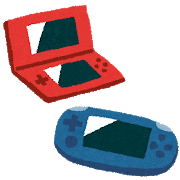
宿題どうこうよりも、他にやりたいことをある場合になります。
例えば…
・ゲームがしたい
・友達と遊びたい
・ユーチューブが見たい
お子さんの「早くやりたい!」という思いから、取り組むこと自体を嫌がったりや、焦って取り組んでしまい、癇癪になる場合があります。
✅宿題の量/質が「本人に合ってない」場合もある
宿題の量や質(難易度)が、お子さんに合ってない場合があります。
実際に支援する中でも、お子さんのこなせる量を超えた宿題の量だったり、解くことが難しい問題が多いこともあります。
この場合だと、宿題がただの苦痛を伴う作業になってしますので、
担任の先生に宿題の調整がしてもらえないか、相談が必要になります。
正直なところ先生次第ですが、私が支援している方には、相談することで調整してもらえたケースは多くあります。
発達障害の子の宿題「対処法」

発達障害の子の宿題の「対処法」は、6つあります。
原因別に、1つずつお伝えします。
①:先に「分かる宿題」だけやってもらう
(原因:宿題が分からない)
②:「分からない宿題」だけ一緒にやる
(原因:宿題が分からない)
③:いつやるか「自分で決めてもらう」
(原因:宿題やりたくない)
④:「デッドライン(期限)」を具体的に伝える
(原因:宿題やりたくない)
⑤:宿題の後の「楽しみ」を決めておく
(原因:他にやりたいことがある)
⑥:宿題が終わった後に「ほめる」
(原因:全部)
先に分かる宿題だけやってもらう

まず、お子さんが “一人でも分かる宿題” だけやってもらいます。
お子さんが少しでも迷う問題があれば、飛ばしてもらいましょう。
分からない問題を分けてやらないと、親御さんが宿題を見る時間が長くなってしまいます。
宿題は毎日のことで、親御さんの負担が大きいですよね。
親御さんのストレスが減ることで、結果的にお子さんの癇癪を減らすことにも繋がります。
親御さんが一緒に宿題を見るのは、できるだけ最小限にできると良いです。
分からない宿題だけ一緒にやる

“分かる問題” だけ取り組んでもらったら、残った “分からない問題” だけ、一緒に取り組みます。
「分からない問題」に関しては、ヒントを出したり、選択式で選んでもらうのが良いでしょう。
宿題の問題数が多かったり、取り組む時間が夜遅くになったときは、すぐに教えて答えを書いてもらいましょう。
何でその答えになるのか、説明だけするだけでも十分だと思います。
お互いイライラしたり、時間がかかって、その後の生活支障が出るぐらいなら、その日は難しい問題を終えてしまっても、良いと思います。
いつやるか自分で決めてもらう
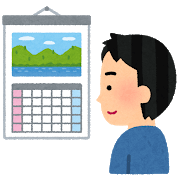
宿題を取り組むタイミングを、お子さん本人に決めてもらいます。
自分で決められると、自分事として、宿題に取り組める可能性が上がります。
これは、私達も同じだと思います。周りに決められたことより、自分で決めたことの方が、「やろう」になりますよね。
もし、お子さんが自分で決められなかったり、非現実的なタイミングを言うことがあれば、選択肢を出してあげましょう。
例えば、こちらのような選択肢があります。
・○時(時間が伝える)
・おやつを食べ終わったら
・夕食後
先延ばしにしやすい子の場合は、時間で具体的に伝えるのがオススメになります。
時間で決めておけると、宿題が終わる時間が遅れて、寝る時間が後ろにズレることを、避けることができます。
デッドライン(期限)を具体的に伝える
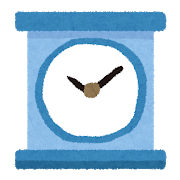
「遅くても、○時までに宿題を始めようね」という、期限を伝えます。
お子さんによっては、宿題にかかる時間などを計算した上で、取り組む時間を決めるのが難しい場合もあります。
「どんなに遅くても○時まで」というリミットを伝えることが、大切になります。
宿題の後の楽しみを決めておく
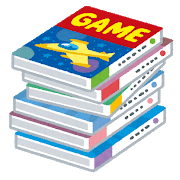
“宿題が終わった後の楽しみ” を事前に伝えておきます。
事前に楽しみが分かっていると、頑張りやすくなる為です。
私たちも先の楽しみの為に、仕事や家事を頑張れることが、あると思います。
お子さんも、全く同じになります。
宿題が終わった後にほめる
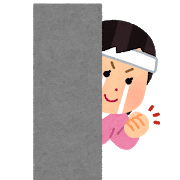
宿題で頑張れていることを、細かくほめていきます。
例えば…
・5問解けたらほめる
・分かる問題だけ解けたらほめる
・プリント1枚終わったらほめる
など、過程をほめられると、お子さんも頑張りやすいので、オススメになります。
ちなみに、宿題のほめ方ですと、下の例があります。
・花丸、シールをつける
・「○できたね!」と言葉でほめる
・点数をつける
(前回より点数UPだとやる気UP!)
実際に支援する中で、効果的だったほめ方になります。
発達障害の子の宿題「注意点」

発達障害の子の宿題「注意点」を2つお伝えします。
①:「細部」にこだわらない
②:「否定・命令語」を使わない
細部にこだわらない

宿題をするときは、細部にこだわらないようにします。
細部とは、例えば…
・字の書き順
・字のきれいさ
・宿題に取り組む順番
などになります。
宿題で癇癪が出るお子さんの場合、まずは「宿題を終える」のゴールが、大切になります。
宿題を終えるかどうかの段階で、細かい所を求めてしまうと、癇癪に繋がりやすくなり、
宿題そのものが終わらなくなる可能性が高まります。
否定・命令語を使わない

宿題に限らずですが、「否定・命令語」は使うことは、避けたほうが良いです。
具体的には、下のような声掛けになります。
・○○は違うでしょ
・○○をしなさい
・○○直しなさい
なるべく、肯定的な表現を使うのは良いと思います。
・○○は惜しい!
・○○はどう?
・○○もう1回やってみようか?
このように、同じことを伝えるにしても、肯定的な表現に伝えられると、お子さんも受け入れやすくなります。
【宿題で癇癪 発達障害の子の対策】まとめ

記事のポイントになります。
✅発達障害の子の宿題
「癇癪になる原因」
・宿題が分からない
・宿題がやりたくない
・宿題以外にやりたいことがある
✅発達障害の子の宿題
「対処法」
・先に分かる宿題だけやってもらう
・分からない宿題だけ一緒にやる
・いつやるか自分で決めてもらう
・期限を具体的に伝える
・宿題の後の楽しみを決めておく
・宿題が終わった後にほめる
✅発達障害の子の宿題
「注意点」
・細部にこだわらない
・否定/命令語を使わない
✅発達障害の子の
「学習対策」
・特性に配慮された学習法
・学習の成功体験を積む
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】







































[…] 【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法 […]
[…] 【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法 […]
[…] 【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法 […]
[…] 【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法 […]
[…] 【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法 […]