

不登校の子向けの習い事を調べてる方「不登校の子に合う習い事ってあるの?うちの子に合う習い事を教えてほしい。選び方/注意点も知りたい」
「家で過ごす時間が長くて、このままだと社会に出た時、自立できなくなりそうで心配」
「学校以外で繋がれる場所を増やしたり、本人に自信をつけさせてあげたい」
など、不登校のお子さんの習い事は、親御さんにとって、とても悩ましい問題だと思います。
私は、不登校・療育支援を15年以上しており、多くの不登校のお子さん/親御さんの支援に携わってきました。
本記事では、その支援経験を元に、習い事だけでなく「不登校の子の習い事の選び方」についてもお伝えします。
習い事は、その教室が無くなればそれまでですが、選び方は基本的に変わらない為、一度把握できれば、ずっと役に立つものになります。
長期的な視点でも、本記事を活用いただけますと幸いです。
※本記事はプロモーションを含みます
不登校の子に「おすすめな習い事」

不登校の子に「おすすめな習い事」を、タイプ別にまとめました。
お子さんが興味を持てたり、取り組みやすいものがあれば、参考にご覧ください。
①:「マンツーマン」学習タイプ
・リタリコジュニア
・家庭教師ファースト
②:「オンライン」タイプ
・ゲムトレ
・オンラインそろばん
③:「好きを追求」タイプ
・プログラミング
④:「自宅でできる」タイプ
・タブレット学習
マンツーマンタイプ(学習)

LITALICOジュニア
- 療育の業界の最大手
- 自立に向けたサポート
- 自己肯定感を上げる支援
- コミュニケーション・自己管理など、幅広い支援
詳しくは、【LITALICOジュニア】 公式サイト をご覧ください。
家庭教師ファースト
- 学習のやる気がある子向け
- 相性の良い先生を選べる
- 子どもの特性に合わせた指導
詳しくは、【家庭教師ファースト】公式サイト からご覧ください。
オンラインタイプ(会話/学習)
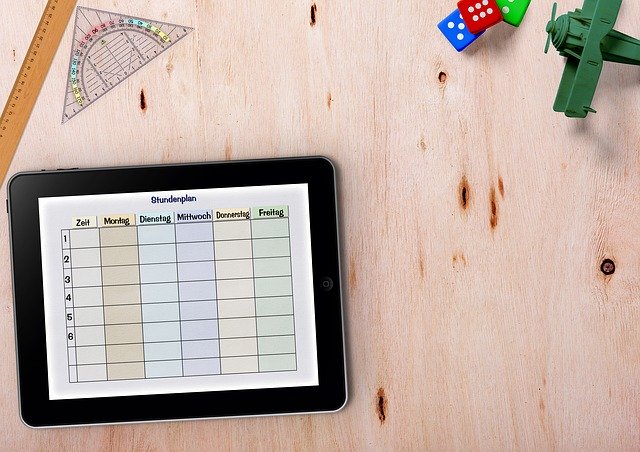
家庭教師 ゲムトレ
- ゲームのオンライン家庭教師
- 不登校の子向けサポート
- オンライン上で会話ができる子向け
詳しくは、【ゲムトレ】公式サイト をご覧ください。
オンラインそろばん
- 個人のペース合わせらる
- 黙々と進めるのが好きな子向け
詳しくは、【よみかきそろばんくらぶ】 公式サイト をご覧ください。
自宅でされたい方は、くもん出版の玉ろそばんをご覧ください。
好きを追求タイプ(プログラミング)
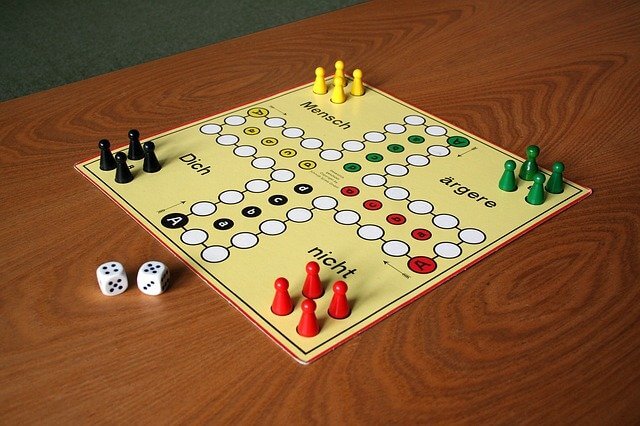
LITALICOワンダー
- 母体がLITALICO(業界の最大手)
- 様々な特性の子の受け入れ可
- 子どもの好きを伸ばす指導
- LITALICO内で進路相談も可能
詳しくは、【LITALICOワンダー】 公式サイト をご覧ください。
【合わせて読みたい記事】
自宅でできるタイプ
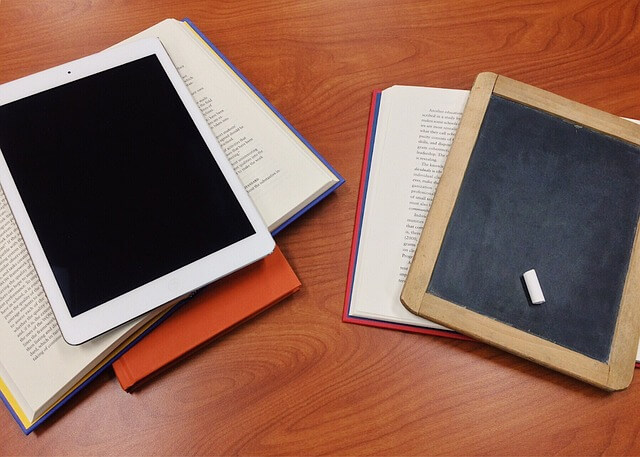
すらら(タブレット学習)
- 無学年式(前の学年の学習も可能)
- AIによる課題・学習PGMの自動抽出
- ゲーム感覚に近く楽しめる
詳しくは、【すらら】 公式サイト をご覧ください。
【合わせて読みたい記事】
不登校の子の習い事「4つの選ぶポイント」

不登校の子の習い事の「選ぶポイント」は、4つあります。
①:子ども本人の「意思」
②:「体験」ができるか
③:先生の「スタンス」
④:本人が通える「時間帯」
子ども本人の意思

子ども本人の「やりたい(やってもいい)」と思う気持ちになります。
当たり前のように感じられるかもしれませんが、
支援する中で、親御さんの意向が強く、その流れで進めているケースは、珍しくありません。
最初の段階で、
「○○できる教室があるんだけど、見学してみる?」
「○○について話ができる先生がいるんだけど、ちょっと話してみる?」
など、本人の意思を確認してから、見学や体験など、次のアクションに進むのが良いと思います。
理由は、お子さんとして、勝手に決められたなど、ネガティブな気持ちに繋がりかねない為です。
体験ができるか
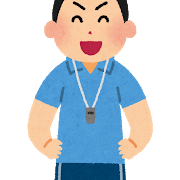
本人の意思が確認できたら、見学 or 体験をしてみます。
可能なら、体験の方をお勧めします。
理由は、見てるよりも体験する方が、自分に合っているか分かる為です。
不登校の子の中には「自身の気持ち/実際にできること」に乖離があることがあります。
例えば「今日から学校行く!授業全部出る!」というけれども、
当日朝になって「やっぱり行かない」と行ったり、初日は行けていたけど、次第に行けなくなる…などです。
実際に体験してみないと、自分に合うか想像がつきにくい子は少なくない為、
“体験を通して感想を聞く” が、一番になります。
先生のスタンス

習い事の先生が “お子さんの特性” に合わせてくれるスタンスがどうかです。
例えば…
不安が強い子に対しては、
“何をするのか事前に見通しを伝えてくれる”
コンディションに波がある子に対しては、
“その日のコンディションに合わせ、課題を変えてくれる”
などになります。
習い事によっても「できること/できないこと」がありますので、事前に先生に相談しておけると安心です。
本人が通える時間帯
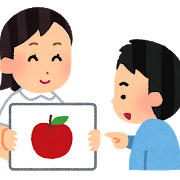
不登校の子は、生活リズムが安定してない場合が多いです。
昼夜逆転してる子や睡眠自体が安定しない子もいます。
そのため、その子が “無理なく通える時間帯” を選ぶのが一番です。
私が支援する中で一番多いのは、平日の午後(12:00~15:00)が多いです。
生活リズムが多少乱れていても、“比較的活動しやすい” 、
“同級生の子とも合わずに済む” 時間帯になる為になります。
不登校の子の習い事「2つの注意点」

不登校の子の「習い事の注意点」は2つあります。
親御さんの考え方(スタンス)になります。
①:「辞める=失敗」と考えない
②:「学ぶ」を一番のスタンスにしない
辞める=失敗(ダメなこと)と考えない
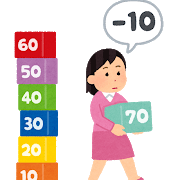
「習い事=続けなければいけない」と考えないことになります。
習い事を「続ける」が目的にならない様にするイメージになります。
言葉にせずとも、周囲の大人がこの考えを持っていると、本人には伝わります。
そしてプレッシャーを感じたり、いざ辞めた時に自己肯定感が下がります。
習い事にチャレンジできたこと、やってみたから分かったこともあると思います。
そういったポジティブな面に目を向けて、本人と一緒に進めていくことが大切になります。
学ぶ を一番のスタンスにしない

「学ぶ」を一番の目的にすると「できた/できない」の思考になりやすい為、
結果として、本人へのプレッシャー・ストレスに繋がりやすくなります。
学ぶことは大切ですが、それ以前に不登校の子の多くは、
「安心できる居場所」
「家族以外の人との繋がり」
「自己肯定感を上げる機会」
などが必要になってきます。
お子さんにとって今、本当に必要なもの(習い事の目的)から逆算して、
習い事を見つけていくことが大切になります。
【不登校の子におすすめ 習い事】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の子に
「オススメな習い事」
・”マンツーマン” タイプ
・”オンライン” タイプ
・”好きを追求” タイプ
・”自宅でできる” タイプ
✅「マンツーマン」タイプ
・LITALICOジュニア(学習塾)
・家庭教師ファースト
✅「オンライン」タイプ
・家庭教師 ゲムトレ
・オンラインそろばん
✅「好きを追求」タイプ
・LITALICOワンダー(プログラミング)
✅「自宅でできる」タイプ
・すらら(タブレット学習)
✅不登校の子の習い事
「4つの選ぶポイント」
・子ども本人の「意思」
・「体験」ができるか
・先生の「スタンス」
・本人が通える「時間帯」
✅不登校の子の習い事
「2つの注意点」
・”辞める=失敗” と考えない
・”学ぶ” を一番の目的にしない
✅不登校の子が
「備えたいコト」
・学習の成功体験
・特性に合う学習法
・レベルに合う学習単元
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事。4つの選ぶポイント・注意点 […]
[…] 【不登校の子におすすめ】習い事~4つのタイプ別に紹介~ […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【不登校の子の習い事】選ぶ時の4つのポイント […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【不登校の子にオススメな習い事】4つの選ぶポイント・注意点 […]
[…] 【不登校】オススメな習い事~4つの選ぶポイント~ […]
[…] 【不登校の子にオススメな習い事】4つの選ぶポイント/注意点 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【療育支援員が紹介】不登校の子にオススメな習い事 […]
[…] 【不登校の子におすすめな習い事】4つの選ぶポイント/注意点 […]
[…] 【不登校の子にオススメ】習い事~4つの選ぶポイント・注意点~ […]
[…] 【不登校の子の習い事】選ぶ時の4つのポイント […]
[…] 【不登校の子向け】オススメな習い事 […]
[…] 【不登校の子向け】オススメな習い事 […]