

人前で話すことが苦手な子の育児で悩まれている方「家では普通に話せるのに、どうして外では話せないの?原因/接し方が知りたい」
「家では普通にしゃべるのに、何で外では挨拶もできないの?」
「自分で話せるまで、何回も促した方がいいの?接し方が分からない…」
家族/特定の人とは、普通に話をするのに、外では挨拶もしないと、「何で..?」と疑問に思われたり、接し方に困ってしまいますよね。
この記事を書いている私は、療育指導を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
これまで場面緘黙/発達障害のお子さんとその親御さんの支援をしてきました。
その経験を元に、本記事をまとめています。お役に立てば幸いです。
目次
場面緘黙とは

場面緘黙(かんもく)とは、家族など慣れている人には、ごく普通に話すことができるのに、
特定の場面になると、話すことが難しい状態をいいます。
例えば、幼稚園/保育園/学校/習い事などの場所や家族以外の人と話せない、などです。
このように「特定の状況で1か月以上声を出して話すことができない状態」をいいます。
「家ではよく話し、家族とのコミュニケーションは全く問題ないのに、家族以外や家以外の場所だと、ほとんど話せなくなる」、このような状態は、場面緘黙のお子さんではよくあるケースになります。
この特徴のため、お子さんが本来持っている力が発揮しづらくなります。
場面緘黙の「原因」

原因は医学的にはっきりしてません。ただ原因として、扁桃体(不安/恐怖を司る脳の一部)の過敏性が指摘されています。
扁桃体とは、身の危険が迫ると対処法(戦うor逃げる)を一瞬で判断する脳の一部になります。
ここは反射に近い反応なので、冷静に思考する余地はありません。
例えば、ジェットコースターが苦手な人が、頭では「安全」と分かっていても、
乗る時に、体は緊張し、冷や汗を流し怖がる方がいらっしゃいますよね。
このメカニズムが、場面緘黙に似ていると言われています。
場面緘黙のお子さんの場合ですと、「話さなきゃ」と分かっていても、
強い緊張/不安(扁桃体が反応)から、話すことが難しい(話すことが危険でないと分かっているのに)と言われています。
挨拶が苦手な「理由」

場面緘黙のお子さんが、挨拶が苦手な理由は、3つあります。
先ほどの場面緘黙の原因を「挨拶の場面」に絞り、お伝えします。
①:「注目」が集まりやすい
②:「失敗体験」の積み重ね
③:「自分から発する」ハードルの高さ
注目が集まりやすい
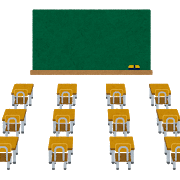
場面緘黙のお子さんは、自分が話すことに注目されることは、苦手です。
そのため「挨拶」という周囲の注目が集まる場面は、緊張/不安が高まりやすくなります。
「挨拶」の場は、場面緘黙のお子さんにとっては、私達の想像以上に、辛い場面になります。
失敗体験の積み重ね
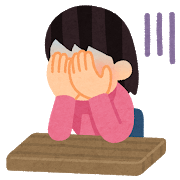
過去の「話せなかった失敗体験」も、理由の1つです。
「挨拶の場面→挨拶できない→家族が挨拶をする(自分は挨拶ができないと思う)」のサイクルに陥ります。
誰でもできないことが続けば、苦手意識がついたり、避けたくなると思います。
場面緘黙のお子さんは、挨拶の場面が失敗経験に繋がりやすいです。
失敗体験が重なると、二次障害になる可能性があります。代表的なのは、不登校・引きこもり・鬱などになります。
詳しく知りたい方は、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法 ご覧ください。
自分から発することのハードルの高さ

「話をする」というのは、「自分から言葉を発する」or「話を受けて返答する」のいずれかになります。
話すことが苦手な場面緘黙のお子さんにとっては、自分から話をする方が、当然ハードルが上がります。
場面緘黙のお子さんにとって、自分からする挨拶は、最もハードルが高い一つの場面になります。
場面緘黙の子供の育児で「大切な視点」
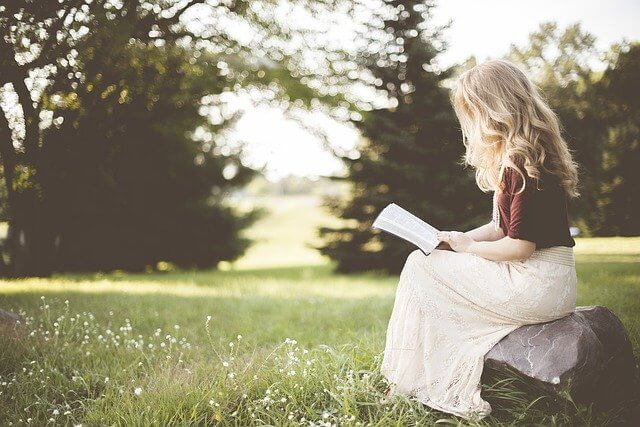
場面緘黙のお子さんと接する上で、大切な視点が2つあります。
話をさせようとしない

場面緘黙のお子さんに対して、「話をさせよう」とされる親御さんが多いです。
ただこれは間違いです。お子さん自身は、話したほうが良いことは、分かっていて、それでも話せないのです。
「話をさせよう」という周囲の意図は、お子さんは必ず察します。
そして、更に緊張/不安が増し、話すことがさらに難しくなります。
場面緘黙のお子さんに話をするよう促したり、練習させようとするのは、最も避けたい関わりになります。
子供の 安心/楽しい が最優先
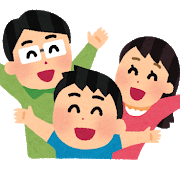
場面緘黙のお子さんに一番必要なのは、お子さん自身の「安心・楽しめる人/場所/活動/時間」になります。
お子さんは心から安心すれば、人に自然に関わることもあります。
お子さんが心から楽しめれば、思わず笑ったり声が出ます。
話をすることは、お子さんの安心/楽しい!の先にあり、後からついてくるものです。
「話をする」が先行すると、失敗どころか、逆効果になってしまいます。
場面緘黙の子の「接し方」

場面緘黙のお子さんへの接し方は、大きく5つあります。
基本的には、お子さんの安心/楽しめる人/場所/活動/時間を作ることになります。
これから説明する内容は、全てお子さんの「安心/楽しい」が前提のものになります。
①:「家族以外で関われる人」を増やす
②:「楽しめるもの/場所」を増やす
③:「話さなくてもいい活動」に参加
④:「本人に合う習い」事をする
⑤:①~④の楽しめたことを「振り返る」
家族以外で関われる人を増やす

『家族以外の人と関わって楽しかった』という経験を作ることが、大切になります。
この成功体験がないと、自分から「関わってみたい!」とはならず、家族以外とコミュニケーションをとることが難しくなります。
特に、お子さんの特性を理解してくださる方との関わりがあると良いです。
例えば、親戚、近所の友達、習い事の先生などです。
楽しめるもの/場所 を増やす

お子さんが『夢中になれるもの/それができる場所』を増やすことになります。
言葉を発して関わることが難しくても、何を通して関わるのは、難易度がグッと下がります。
例えば、ゲームが大好きなら、人とゲームを一緒にする。
サッカーが好きなら、一緒にボールを蹴るなどです。
みなさん経験があると思いますが、自分の好きな共通の趣味などを通して関わることで、すぐ仲良く慣れた!ということあると思います。これに近いイメージです。
話さなくてもいい活動 に参加

場面緘黙のお子さんは『話すことが求められる』ことが負担になります。
誰だって、苦手なことを求められるのは、嫌なものです。
ですので、「話さなくてもいい活動」が良いです。
例えば、サッカーなどの集団スポーツ、一人でモクモクとできるプログラミング(同じ空間には他人がいる)などです。
このように、「話さなくてもいい(気分が乗れば話してもいい)」場所は、お子さんにとっては、選択肢があるので、安心しやすく、楽しみやすいです。
お子さんにあった活動の場を見つけることが大切になります。
本人に合う習い事をする

これまで説明させて頂いた①~③を全てまとめると、習い事が1つの選択肢になります。
お子さんの「安心/楽しい」を前提にした「人との繋がり/居場所/話しても話さなくてもいい活動」は、習い事で作ることができます。
お子さんが興味を示し、楽しめる様子のイメージが湧く場合は、1つの選択肢として検討されるのが良いと思います。
⑤:①~④の楽しめたことを「振り返る」

ここまで説明しました①~④で楽しかったことを、家族で振り返ります。
例えば、「今日のサッカーは、相手チームのゴールに上手にシュートできたね!ゴールして凄かったね!」などです。
『家族/家以外』の人や場所で過ごしたことが楽しかった!というのを
お子さんに実感してもらい、他の人と関わる楽しさをもってもらうためです。
この経験が重なってくると、人と関わりたい気持ちが強まり、少しずつ自分から関われたり、場に参加すれば、人と楽しむことが増えていきます。
✅「勉強を教わる場面」がストレスになることも
勉強で分からない箇所が聞けない、自分の分からない所が伝えられないなど、学習面で困ったりストレスを感じる子もいます。
特に小学校中学年以上ですと、親御さんが教えることも難しくなってくる為、塾や家庭教師が必要になってきます。
ただ場面緘黙の子の場合、家族以外から教わることのハードルが高い場合が多いです。
お子さんの学習の場面で負荷がかかっていそう(かかりそう)でしたら、タブレット学習をお勧めします。
タブレット学習では、アニメーション・音声で解説をしてくれ、分からない箇所は何度も確認することができます。
「伝えられない・聞けない」に加えて、「先生の説明で分からなかったらどうしよう(聞きたくても聞けないから)」という不要な緊張/ストレスを避けることができます。
興味のある方は、こちらの記事をご覧ください。
発達障害の有無に関わらず、困りを抱えてる子に共通する内容になります。
【場面緘黙の子供 なぜ挨拶が苦手?】まとめ

記事のポイントになります。
✅場面緘黙とは
・特定の場面で話すことが難しい状態
✅場面緘黙の原因
・医学的にはっきりしていない
・一説では:脳の扁桃体の過敏さ
✅挨拶が苦手な
「3つの理由」
・注目が集まりやすい
・失敗体験の積み重ね
・自分から発するハードルの高さ
✅場面緘黙の子の育児で
「大切な2つの視点」
・話をさせようとしない
・安心/楽しいが最優先
✅場面緘黙の子の
「5つの接し方」
・家族以外で関われる人を増やす
・楽しめるもの/場所を増やす
・話さなくてもいい活動に参加
・本人に合う習い事をする
・①~④の楽しめたことを振り返る
以上になります。
本記事が、お子さんの安心作りのキッカケになれば、幸いです。
【合わせて読みたい記事】








































