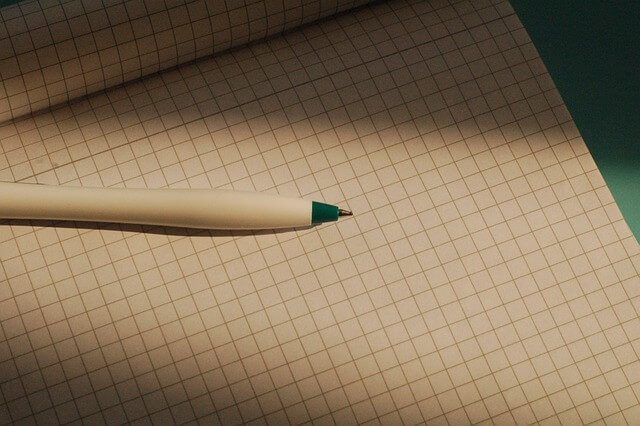

担任の先生で悩まれてる方「担任の先生が発達障害への理解がない。子どもと担任が合わなくて困ってる」
お子さんにとって担任の先生は、学校の過ごしやすさを左右する大きな存在です。
特に、発達障害の特性を持つ子でしたら、理解と配慮が必要になる為、より影響は大きいものです。
ただ現実には、発達障害への理解がなかったり、先生自身のやり方を崩さず、お子さんが辛い思いをしてるケースは少なくありません。
そこで本記事では「発達障害(グレーゾーン含む)の子と担任の先生が合わない時に大切なこと/対処法」についてお伝えしたいと思います。
私は、療育支援を15年以上しており、発達障害の子と親御さんの支援に携わってきました。その中では、担任に関するご相談も多く受けてきました。
その支援経験を元に、どのお子さんにも共通する大切な点をまとめてます。
参考になれば幸いです。
目次
発達障害の子と「担任が合わない原因」

発達障害の子と「担任が合わない原因」は、主に2つになります。
①:子どもの「特性への理解」がない
②:「先生自身のやり方」を押し通す
子どもの特性への理解がない

個人的には、この理由が最も多いと感じています。
「発達障害」「特性」という概念があまりなく、
「努力不足です」「本人の甘えです」「一人だけ特別扱いはできません」と発言される先生になります。
「みんな同じ」「公平」という考えが強く、精神論でお子さんに関わるので、本人が辛い思いをしてしまいます。
先生自身のやり方を押し通す

特に、ベテランの先生に多いです。
先生自身が経験もあり、自身のスタイルが固まっている分、柔軟に対応を変えることが難しいことがあります。
発達障害や特性など、多少の知識があっても、自身の指導が正しいという気持ちが強く、結果として配慮が得られないことが多いです。
担任と合わない時に「大切なこと」

担任と合わない時に「大切なこと」は、3つになります。
①:担任との「関係性の悪化」は避ける
②:担任の「考え」を聞く
③:お願いより「相談」する
担任との関係性の悪化は避ける

担任の先生との対立を避けることが大切になります。
お子さんに理解のない関わりをすることは、親として許しがたいことです。
ただ、担任との関係性が悪くなれば、クラスで過ごす本人が、より辛い思いをする可能性が高まります。
その点を考えると、少なくとも関係性の悪化は避けたいところです。
関係性が悪くなれば、クラスの環境を今より良くすることは、かなり厳しくなります。
担任の考えを聞く
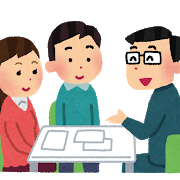
担任の先生も感情ある人間です。一方的に話をされるより、まず話を聞いてもらう方が、協力が得やすくなります。
担任の先生の考えや何を感じてるのかなど、最初に聞いておけると、その後の話の方向性が定まってきます。
ここは、担任の先生がお子さんの様子をどう捉えているのかによって、変わってきます。
主に下の3パターンになります。
「問題ない」
(問題の共通認識をもつ段階)
「問題はあるけど、対処法が分からない」
(方法を伝えれば、変わる可能性あり)
「問題があるから、クラスでは見れない」
(協力を得るのが難しい)
お願いより相談する
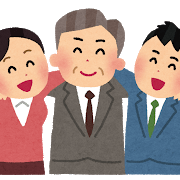
親御さんのスタンスは、「相談」ベースであることが大切になります。
お願いしたい気持ちはとても分かります。我が子が困っているのですから。
ただ、一方的に要望を言うことで、受け入れてもらえない可能性が高まります。
関係性ができていて、理解ある先生でしたら、要望から話しても大丈夫です。そうでない限りは、相談して一緒に決めていくことが大切になります。
先生の心情としても、相談される方が、力になりたい気持ちが湧きやすくなります。
具体的には、
「○○のことで相談したいのですが、いかがでしょうか」
「○○があると、子どもが参加しやすいと思うのですが、クラスでは可能でしょうか」
このように、最初に相談したい意思を伝えることで、その後のお話が円滑になりやすいです。
担任と合わない時「対処法」~親ができること~

担任と合わない時の「対処法」は、大きく3つになります。
①:「子どもを知ってもらう機会」を作る
(原因①:特性理解がない)
②:「具体的な関わり方」を伝える
(原因②:関わりが合ってない)
③:管理職orスクールカウンセラーに相談
(原因③:配慮するスタンスがない)
子どもを知ってもらう機会を作る

先生と個別でお話する時間を作り、お子さんの特性について伝えます。
口頭で説明したり、書面(ex.検査結果や療育の支援計画)を渡すのも1つになります。
書面は、説得力も増すため、先生の意識を変えるキッカケになりやすいです(学校によっては、配慮するには、検査結果が必要という場合もあります)
書面を渡す時の注意点は、情報量です。
情報量が多いと、熱心な先生でない限り、全てに目を通すのは難しいかもしれません。読めたとしても、内容が頭に入る先生は限られています。
そのため、押さえておきたいポイントだけ、マーカーで色をつけたり、要点だけ付箋で貼っておく方法がおすすめです。
まずは、お子さんの特性について、知ってもらう所から始めます。
子どもに合う具体的な関わり方を伝える

お子さんに必要な関わり(配慮)は、具体的に伝えられると、先生も実践しやすくなります。
例えば、こちらの様なイメージになります。
「丁寧に指示を出して下さい」
⇨「○○を引き出しにしまって。教科書○ページ開いて(1つずつ指示を出す)」
「集中して」
⇨「○○の問題を見て(先生が見てほしい問題を実際に指差す)」
先生が行動しやすいように、具体的な表現にすることがポイントになります。
担任のメリットで伝える
新たな関わり(配慮)をすることは、先生によっては、前向きじゃない場合もあります。
「わざわざやる意味あるのかな」「手間がかかるな」と思う先生も少なくありません。
このような先生の気持ちを考えると、“先生のメリット” で伝えられると、協力が得られる可能性が高まります。
具体的には、
「先生の目の前に席を移動して頂けると、指示が通りやすくなって、先生も個別で声掛けの頻度が減ると思います。先生も授業が進めやすくなるので、クラス全体にとっても良いのではと思いました」
のようなイメージになります。
簡単ではありませんが、先生のタイプに合わせて伝えることで、協力が得やすくなります。
管理職 or スクールカウンセラーに相談する

親御さんがどんなに工夫をしても、担任の先生とのやりとりが、難しい場合もあります。
そんな時は、スクールカウンセラー(SC)や学校の管理職(ex.校長、副校長、教頭)に、繋がることをお勧めします。
スクールカウンセラーは、学校と親御さんの間に立つ先生(中立に近い)になります。
学校に非常勤として週数日配置されていることが多いです。面談を申し込み、個別でお話することができます。
担任の先生に話が通らないことは、管理職の先生を通すのも1つです。個別で面談の相談をし、担任の先生との難しさをそのまま相談するのが良いと思います。
ご両親で参加が可能な場合は、ご両親の方が良い場合もあります。学校側にも本気度が伝わりやすくなります(勿論、対立はNGですが…)
【発達障害の子と担任が合わない時】まとめ

記事のポイントになります。
✅発達障害の子と
「担任が合わない原因」
・子どもの特性への理解がない
・先生自身のやり方を押し通す
✅担任と合わない時に
「大切なこと」
・担任との関係性の悪化は避ける
・担任の考えを聞く
・お願いより相談する
✅担任と合わない時の
「対処法」~親ができること~
・子どもを知ってもらう機会を作る
・具体的な関わり方で伝える
・先生のメリットで伝える
・管理職 or スクールカウンセラーに相談
・理解しない先生は一定数いる
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】









































[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つのポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法 […]
[…] 【発達障害の子と担任が合わない時】3つのポイント・対処法 […]