

子どもの不登校で悩まれてる方「不登校の回復期は、よく寝るものなの?どう関わればいいか分からない」
不登校のお子さんの状態を表す言葉の1つとして「回復期」があります。
ネットで調べると、回復期の子は「よく寝る」と言いますが、
具体的にどういう意味を指してるのでしょうか?そして、どんな関わりが必要なのでしょうか?
このような悩みをお持ちの方が増えています。
そこで本記事では「不登校の回復期」に関する情報についてお伝えします。
この記事を執筆している私は、不登校/療育支援を15年以上してます。
その支援経験を通して本記事をまとめてます。参考になれば、幸いです。
目次
不登校の「回復期」とは

不登校には段階があり「回復期」は、その段階の一部になります。
不登校の全体像としては、以下のような状態(時期)があります。
「開始期→引きこもり期→回復期」
ここでは詳しく触れませんが、要点だけ確認していただければと思います。
開始期
行きしぶりが出始める時期になります。
・朝起きるのが、遅くなった
・朝の登校の準備が、遅くなった
・行きしぶりの発言がある
このような様子が、出始める時期を指します。
引きこもり期
学校を本格的に休む状態になります。自室にこもったり、生活リズムが乱れることもあります。
歯磨きや入浴もせず、自分の殻に閉じこもる場合もあります。
ベクトル(矢印の向き)が全て “自分自身(本人)” に向いている状態になります。
回復期
お子さんの言動が外(自分以外)に向く時期になります。
自分自身に向いていたベクトル(矢印の向き)が、”自分以外” に向き始めます。
具体的には、本を買いたい、人に会いたいなどの発言があったり、身だしなみを整えたり、家の手伝いをする、などです。
不登校の全体像と回復期の位置づけの確認ができましたら、
ここからは回復期について、深く見ていきます。
不登校の回復期の「サイン」

不登校の回復期の「サイン」は、3つあります。
①:「自分以外」に関心が出る
②:「外出の頻度」が増える
③:「暇」などのニュアンスの発言が増える
自分以外に関心が出る
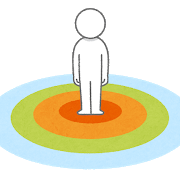
本人の言動が「自分(本人)以外に向く」状態になります。
よくある例としては、以下の言動になります。
・勉強する
・家の手伝い
・買い物
・身だしなみを整える
・将来の話をする
・家族との会話
・必要な物を欲しがる
(ex.勉強に必要な物)
お子さんの発言/行動から、状態が見えてきます。
外出の頻度が増える

ほとんどの時間を、家や自室で過ごしてた子の場合、外に出る機会が増えます。
また、外出できる時間帯が広がる場合もあります。
不登校の子にとって、外出は、負荷がかかりやすいです。
特に、同級生がいる夕方の時間は、外出を避けたがる子も少なくありません。
外で過ごせる時間が増えることは、お子さんのポジティブな変化の1つになります。
暇などのニュアンスの発言が増える

「やることがない」
「家にいても、つまんない」
このような発言があると、お子さんの回復期のサインである可能性があります。
家での過ごし方は、以下のものがあります。
・散歩
・読書
・買い物
・家の手伝い
(洗濯/掃除など)
・学習
(ドリル/タブレット学習など)
・習い事
(本人の好きなこと/オンラインなど)
【関連記事】
不登校の回復期の「関わり方」

不登校の回復期の「関わり方」は、3つあります。
①:本人の意思・関心に「応える」
②:本人の気持ちに「共感」する
③:「ポジティブ」なスタンスを持つ
本人の意思/関心に応える

本人の意思・関心が出たときには、本人がその情報に触れられる機会を作っていきます。
具体的には、こちらの様な例になります。
・資料を取り寄せる
・ネットで、一緒に調べる
・実際に一緒に行ってみる
・購入し、家で触ってみる
・習い事/フリースクールの見学
“お子さんの気持ち” を聞きながら、選びたい点になります。
本人の気持ちに共感する
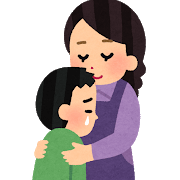
不登校の子は、心に傷を負ってることが多いです。
・学校の辛い経験
・自責の念
・自己肯定感の低下
など、様々なものを抱えています。
「どうせ自分なんて、何もできない」
「皆ができてることは、自分はできない」
「皆に迷惑かけてる自分はダメだ」
このような気持ちを抱えています。
この気持ちに対して「◯◯なんだね」と、寄り添うことが大切になります。
ポジティブなスタンスを持つ
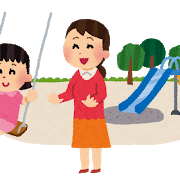
不登校の子の中には、何でもネガティブに捉える子がいます。
被害的に捉えたり、攻撃的になったり、自分自身で失敗したと思い込む場合もあります。
そのため、関わる大人の方は「ポジティブな姿勢」を持つことが必要になります。
すぐできる方法の1つは、大人の言葉の表現を肯定的にします。
「走らないで」→「歩こう」
「片付けできてないよ」→「片づけしよう」
「時間過ぎてるよ」→「◯時までにやろう」
このようなイメージで、否定的なニュアンスを避ける伝え方をします。
不登校の回復期の「注意点」

不登校の回復期の「注意点」は、4つあります。
①:「一喜一憂」しない
②:安易に「学校/将来」の話をしない
③:「失敗」と捉えない
④:「体力の低下」を考慮する
一喜一憂しない

お子さんの1つずつの言動/変化に、過剰に反応しないことになります。
例えば、こちらの様な言動になります。
・「登校する」と発言した
・学校に1回行けた
・ドリルを1Pできた
不登校の子は、気持ちの波が大きいです。
前日の夜に「明日は学校にいく」と言っても、当日の朝には「やっぱり休む」と言うこともあります。
数日登校できても、その後に反動でしばらく学校に行けなくなることもあります。
大人の過剰な反応は、本人にプレッシャーを与え、無理させてしまいます。
「これ(今の子どもの状態)は、大きな波の1部なんだ」と思うことが、親御さんの気持ちを楽にさせ、
結果として、本人にも良い影響(安心感)を与えます。
安易に学校/将来の話をしない

親御さんは、焦り/不安から、以下の声掛けをしやすくなります。
「明日は、学校行けそう?」
「今日学校の先生と電話で話したよ」
「明日は学校で、○○やるんだって」
我が子を心配しての声掛けですので、お気持ちは、とても分かります。
ただ親御さんとしては、心配して伝えているつもりでも、
お子さん本人からしたら、”プレッシャー/心の負担” として受け止めます。
本人から話(関心)が出るまで、大人側から積極的に聞くのは、避けた方が良いです。
失敗と捉えない
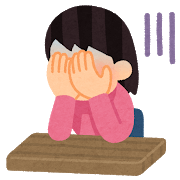
不登校の子の気持ちには波があり、チャレンジしても上手く行かないことも多いです。
ここで大事なのは、どんな出来事も大人側が「失敗」と捉えない姿勢を示すことです。
例えば、自宅学習のため、タブレット学習にチャレンジしたけど、結果的に合わなず途中で辞めてしまったとします。
このような時は「タブレット学習は合わないことが分かったね(他の学習方法を探せる)」と声をかけます。
これは、チャレンジしたからこそ「本人には合わない」と分かったということです。
このように、一見失敗に感じられそうなことも、良い側面で捉える(リフレーミング)ことが、
お子さんの心を守る意味で、重要になります。
もちろん、お子さんの捉え方によって変わるため、上記の関わりも合う/合わないがあります。
これまでのお子さんの言動を想像して、何が合うか考えることが必要になります。
体力の低下を考慮する

不登校期間が長い子は、体力が低下してることが多いです。特に、家で過ごす時間が長い子は該当しやすいです。
大人の想像以上に疲れやすい為、そこを考慮して本人に合うペースで、生活リズムを作ったり、体を動かす機会があると良いです。
もちろん、本人の意思があることが前提になります。
不登校の回復期の「心構え」

不登校の回復期の「心構え」は、3つあります。
①:大人の想像以上に「時間が必要」
②:「学校に行く」≠ゴール
③:「正解はない」「ダメなこと」はある
大人の想像以上に時間が必要
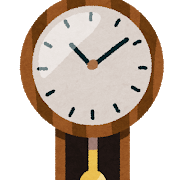
不登校の問題は、時間がかかることが多いです。
私が支援してきた中ですと、早くても数ヶ月、中には数年かかる子もいます。
お子さんの状態(不登校期間の長さなど)によりますが、短期間で問題が解決することは少ないです。
大人側が「数ヶ月~数年の時間がかかる可能性がある」という認識を、持つ必要があります。
学校に行く≠ゴール

お子さんにとって「学校に行く」は、選択肢の1つに過ぎません。
お子さんの特性/状態によっては、「学校に行く」が最善でない場合もあります。
今は、他の選択肢も増えています。
・自宅学習
・フリースクール
・通信
・転校
「”本人に合う選択肢” を探す」という視点が、大切になります。
正解はないけど、ダメなことはある

不登校支援において「正解」はありません。ただ「避けるべきこと」はあります。
そのため、正解を探すよりも、まずは「避けるべきこと」を確認する方が良いです。
理由は、不登校問題の多くは、
「本人にしてはいけないこと/良くない環境」が多いことで、深刻化している為です。
【関連記事】
不登校の子が「備えておきたいこと」

ここでは、不登校の子が「備えておきたいこと」をお伝えします。
不登校の子には「休息、安心感、信頼できる人/居場所との繋がり、楽しみ」が必要になります。
本人の気持ちが安定したり、学校で過ごせる時間が増えたり、フリースクールなど違う場所に通うエネルギーに繋がる為です。
ただ、そんな中でも多くの不登校の子が困る問題が、学習面の遅れになります。
不登校は、個人差がありますが、時間がかかることが多いです。数ヶ月~数年、もしくは、不登校と復帰をずっと繰り返す子もいます。
学校に復帰すること、違う場所に通えるなど、いつどうなるのか、見通しが立ちません。その為、学習対策が後回しになってしまいます。
ただ、卒業までの時間は限られてる為、不登校の長期化にも備えて、早めの学習対策が必要になります。
不登校期間の長さは、学習の遅れに比例する為、影響が大きく出る前に動くことが、問題解決の1歩となります。
進学・将来の選択肢を減らさない為にも、まずは親御さんが動いていきたい点になります。
学習対策「タブレット学習」
不登校の子の学習対策の1つに、
「タブレット学習」があります。
不登校の子にとって、タブレット学習が良い理由は、6つあります。
・自分のペースで進められる
(自分で選ぶ/決める)
・安心して過ごせる環境
(環境に左右されない)
・分かりやすい勉強
(自信がつく)
・成功体験が積める
(学習意欲を高める)
・ゲーム要素がある
(苦手意識がある子向け)
・出席扱いになる場合あり
(学校に相談必要)
また、不登校の子の学習の妨げ要因として、
「どこから勉強すればいいか分からない」
「問題が少し変わると解けなくなる」
「時間が経つと、忘れちゃう」
などがあります。タブレット学習は、この問題に効果的にアプローチできます。
①「何をどう勉強すればいいか分からない」
⇨本人の解答結果をAIが分析し、必要な課題のみ表示
②「問題が少し変わると解けなくなる」
⇨アニメーション解説で本質的な理解を促す
③「時間が経つと、忘れちゃう」
⇨①②の繰り返しでアプローチ
アニメーション/音声解説は、文字の読み書き、参考書・市販教材での学習が合わない子にも、理解しやすいです。
また、タブレット学習は、出席扱いにできるケースがあります。
文部科学省が不登校のお子さんに対して、IT等を活用した自宅学習で出席扱いにするという方針を定めました。
タブレット学習の種類や在籍校によって変わりますが、こちらも心強い要素になると思います。
その他のメリット・デメリットなど、タブレット学習の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
【不登校の子向け】オンライン教材4選
発達障害の有無に関わらず、不登校の子にも、共通する内容になります。
1つの学習方法として、参考になれば幸いです。
【よく寝る?不登校の回復期のサイン】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の「回復期」とは
・不登校の子の回復の兆し
・本人の言動が外(自分以外)に向く時期
✅回復期の「サイン」
・自分以外に関心が出る
・外出の頻度が増える
・”暇” などのニュアンスの発言が増える
✅回復期の「関わり方」
・本人の意思/関心に応える
・本人の気持ちに共感する
・ポジティブなスタンスを持つ
✅回復期の「注意点」
・一喜一憂しない
・安易に学校/将来の話をしない
・失敗と捉えない
・体力の低下を考慮する
✅回復期の「心構え」
・大人の想像以上に時間が必要
・”学校に行く=ゴール” ではない
・”正解はない” けど “ダメなこと” はある
✅不登校の子が「備えておきたいこと」
・学習の成功体験を積む
・本人に合う学習方法の把握
・学習意欲を高める
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】







































[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 休息が必要かの判断基準は、【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 をご覧ください。 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 […]
[…] 【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン/関わり方/注意点 […]