

療育を辞めるべきか迷っている方「療育辞めてよかった子の事例が知りたい。療育を辞める目安が知りたい」
療育を続けていくと、お子さんのできることが増えていき、園や学校、友達と遊ぶ時間、子どもの好きな習い事など、どれを優先するべきか、悩んでしまうことありますよね。
この記事の執筆者の私は、療育指導を15年以上しており、現在も発達障害のお子さん・親御さんの支援に携わってます。
その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
療育を辞めてよかった「事例」

療育を辞めてよかった事例、辞めなければよかった事例を、それぞれお伝えします。
私が実際に、支援した事例になります。
うまくいった事例
“言語発達遅滞” の年中さん👦
療育に1年半通い、課題だった3語文での要求・文章での説明ができるようになった年中さん。
低年齢から通われていたこともあり、当初心配されていた言葉も、先生・友達と会話をするのに困らないほどに。
園であった出来事を両親に話せたり、前日に遊びに行った話を、友達に話すこともでき、
日常生活の中で身につけたスキルが活かせるようになりました。
日常生活で困りが解消されていたので、両親・療育の先生の相談の結果、
卒業ということで、療育を辞めることになりました。
“ADHD” の小2👩
学習への拒否感が強く、苦手な課題が出ると机の下に潜ったり、暴言を吐く小学2年生のお子さん。
1年間の療育で「課題に取り組んだ成功体験」をたくさん積むことで、課題への拒否感を減らしてきました。
また苦手な算数は、解き方を “手順化したメモ” をいつでも見れるようにし、学校の宿題も取り組めるようになりました。
自分に合った取り組み方も分かったので、あとはそれを、家族・学校の先生との間で共有して、使っていくことになりました。
お子さんが対処法が実践でき、家族の理解・サポートもある状態だったので、療育を辞めることになりました。
“自閉スペクトラム症” の小5👦
2年間の療育では、「相手の気持ちを考える・相手の気持ちに合わせた伝え方・会話のキャッチボール」に取り組んできました。
今では、大人の介入がなくても、友達に合わせて伝え方を変えたり、一方的に話すのではなく、
「○○の話してもいい?」と、相手の気持ちに合わせたやりとりが、できるようになりました。
家族・学校の先生から見ても、生活に支障をきたす困りはなく、
お子さんからも「プログラミングがやりたい!」と希望があり、療育→プログラミング教室に通うことになりました。
生活の困りが解消され、お子さんの “好きなこと” に専念できるようになった事例になります。
うまくいかなかった事例
“ADHD” の小学1年生👩
集中力が限られていて、課題量の調節・自分に合った学習方法を頑張ってきた小学1年生のお子さん。
課題の量を調節、解き方の手順化、事前に見通しを説明、この3つの工夫をすることで、家庭でも学校の宿題ができるようになってきました。
その様子を見て、親御さんは安心され、療育を辞めて一般の学習塾へ。
ただ一般的な教え方では、お子さんが理解することが難しく、3年生の文章題や計算の応用問題についていけませんでした。
結果的に、授業や学習そのものを拒否するようになり、勉強に取り組むことが難しい状態になってしまいました。
失敗体験も多かったため、自己肯定感も下がっていて、
「もうやりたくない。何やってもできないんだよ」の発言が増え、療育に戻ってきたケースになります。
【合わせて読みたい記事】
【療育の後悔】受けないと、子どもの将来にどんな可能性が?事例を元に解説
療育を辞める「タイミング」

ここでは「療育をやめるタイミング」について、お伝えします。
『療育を辞めるタイミング』を間違えると、後からお子さんが困ってしまう為、とても大切な内容になります。
「療育を辞める」とは…
・療育先を “変える”
・療育先を “辞める“
のどちらかになります。
(当たり前ですが…)
1つずつ見ていきます。
療育先を「変える」タイミング
療育への行き渋りがある

お子さんの『療育への行き渋り』がある場合になります。
例えば、「○○先生ヤダ、○○は行かない」などの発言がある場合です。
療育先・ご家族が、療育を楽しめる工夫を最大限しても、お子さんが心底嫌がっている場合は、療育先を変えるタイミングになると思います。
何が嫌なのか探る
お子さんが話ができる場合は、嫌な理由を聞いてみるのも1つです。
もし、ご家族・療育の先生が工夫できる内容であれば、不安を取り除きます。
お子さんが話をするのが難しい場合は…
・指導が楽しめてるか
・先生/友達との相性はどうか
・先生/指導内容が変わったか
・ここ最近で嫌なことがあったか
・体調(睡眠、空腹、疲れ、風邪気味)
など、家族で振り返ってみることを、お勧めします。
子どもに変化がない

個人的な目安になりますが、
3ヶ月以上続けても、”成長を感じない” 場合は、1つのタイミングになります。
もしお子さんの成長をあまり感じない場合は、先生に今の指導の進捗を、詳しく聞いてみるのが良いでしょう。
お子さんの具体的な行動での説明など、療育先によっては、指導記録を使った説明などもあります。
そこで納得ができるなら、問題ありません。
先生との関係作りの時間は別
最初は先生との関係性作り、場や人に慣れる時間が必要になります。お子さんによっては1ヶ月以上必要な子もいます。
慣れるまでの時間は、成長というより、「成長するための土台作り」と捉えます。
お子さんが慣れてから、3ヶ月単位で成長を見ていけると安心です。
療育先を「やめる」タイミング
療育先に「辞めて大丈夫」と言われた

療育の専門家(療育指導員、児童発達管理責任者、心理士など)が
「療育辞めても大丈夫ですよ」などの発言があれば、辞めてもいい目安になります。
療育の専門の先生は、多くの発達障害のお子さんを見ています。
そして、お子さんが今後送る生活の状況も把握してます。
その先生からの発言は大きな意味を持ちます。
理想は、2名以上の専門家から聞けると良いです。理由は客観性が高まり。判断に信頼性が持てる為です。
懸念があれば『必要ない』と明言されることは、ほとんどないです。
困りの解消/対処法が実践できる状態

・「困りごと」が解消されてる
・お子さん自身で「対処法が実践できる」
この状態なら、1つの辞める目安になります。
ただ専門的な領域になりますので、療育先に相談できた方が安心です。
第3者の意見をきく
第3者とは、専門家のことになります。客観的な意見を聞いた上で、判断することをお勧めます。
専門家は、長期的な視点でお子さんの困りを想定できる為です。
どの年齢のお子さんが、何で困りやすいのか、など把握してます。
お子さんの特性・今後のライフステージとの間で、懸念点がないのか聞くことは、大切なことになります。
療育を「継続すべき」ケース

療育を「継続すべき」ケースは、2つのパターンあります。
①:「環境」が変わるとき
②:専門家に「継続」を勧められたとき
環境が変わるとき
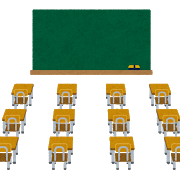
環境が変わる時は、お子さんへの負担が大きい為、慎重になる必要があります。
ここでいう「環境」とは…
・担任/クラス
・学校/園
・家庭
(引越し・家族が増える/減る)
になります。「療育をやめる」というのは、お子さんにとって、大きな環境の変化です。
環境の変化は、時期が重ならない様にすることで、お子さんの負担を軽くすることができます。
また、進学/進級で、生活そのものに大きな変化がある場合は、新生活に慣れるまでは、環境の変化は避けた方が良いです。
お子さんにもよりますが、具体的な期間は、3ヶ月前後は必要になると思います。
また慣れてきて、お子さんの普段の様子が出てきたと同時に、困りが出てくることも多いです。
緊張してることで、一時的にお子さんが無理をして頑張って、困りが出づらい場合も少なくありません。
慣れた状態で数ヶ月生活をしても、困りが出なければ、”卒業できる目安” になります。
✅環境の変化が大きい時期
個人的には、下記の時期は、療育をやめる時期としては、あまり勧められません。
・4~6月
・9~10月
4~6月は新年度の生活、9~10月は夏休み明けになります。
環境に対して、お子さんが頑張って慣れようとしている時期になります。
また2学期から、困りが表面化する場合もあります。
1学期は、緊張感もあり、無理して頑張れていたけど、それが2学期になり慣れと同時に、困りとして出る場合もあります。
専門家に継続を勧められたとき
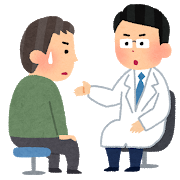
先ほどの説明と重なりますが、
・心理士
・療育先の指導員
・児童発達管理責任者
などの専門家の意見を聞いて、判断することが大切になります。
【合わせて読みたい記事】
【療育】掛け持ちはできる?~メリット/デメリット/療育の選び方~
療育を「卒業したあと」

ここでは、療育を「卒業したあと」について、触れていきます。
私が支援をしていて、療育を卒業されてから、再度相談にこられる親御さんがいます。
その方たちの共通点を考え、親御さんが2点準備しておけると良いものがあります。
お子さんによって個人差がありますので、必要ありそうな項目をご覧ください。
①:「環境」を作っておく
②:「学習サポート」の準備
環境を作っておく
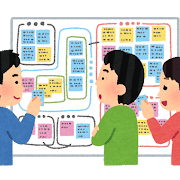
ここでいう「環境」とは、”お子さんの味方になってくれる人と繋がっておく” ということです。
療育で、お子さんが成長をしても、過ごす場所・人によっては、問題が解決しないことはあります。
よくあるのは、担任の先生の理解がなく、配慮どころか、叱責されたり、目の敵にされてしまうケースです。
最悪の想定をした上で、お子さんの味方になってくれる(理解者)人と、
いつでも相談できる状態を作っておくことが、大切になります。
例えば、下記の信頼できる先生と繋がっておけると、
学校で連携して、お子さんに合った環境が作りやすくなります。
・担任
・校長先生
・保健室の先生
・スクールカウンセラー
・通級の先生
まずは担任の先生にお話をし、理解が得られるか確認をします。
もし難しい場合は、校長先生やスクールカウンセラー(SC)との面談を申し込めると良いです。
先生への相談は、親御さんの心身の負担が大きく、とても大変なことだと思います。
ただ、お子さんに必要な環境を考えると、必要不可欠な点になります。
学習サポートの準備

学習面に不安がある子には、「学習面のサポート」を準備しておけると安心です。
発達障害の子に向けた学習支援ができる人は、まだまだ少ないです。
そういった背景から、今の義務教育の勉強だけでは、困ってしまう発達障害の子は、とても多いです。
学習の問題が表面化するのは、お子さんが小3~4年生の頃が多いです。
学校や授業を嫌がったり、テストが白紙になったり、お子さんの苦手意識が強まってきます。
それを避けるために、早めに、塾・家庭教師など、「学習のサポートの準備」が大切になってきます。
ただ、先ほども触れたように、専門的な方は限られているため、良い先生が見つからないかもしれません。
もし見つからない場合、私はタブレット学習を勧めています。
もちろん、お子さんに興味があったり、嫌がる様子がない、というのが前提になります。
お子さんが楽しく取り組めるゲーム性があったり、苦手な問題が自動抽出されるなど、
発達障害の特性に配慮された機能が、今は多くあります。
・今後サポートが必要になったときの為に、把握しておく
・学習の苦手意識が固まらない内に、子どもの成功体験を作っておく
目的に合わせて最初は、情報を集めるだけでも良いかと思います。
お子さんが学習で困ることが、予想できる場合は、
『こういう選択肢もあるんだ』と把握しておけると、いざという時、すぐに活用ができると思います。
発達障害の子の配慮では、下記の点が大事になってきます。
・失敗体験は「最小限」に
・「小さい成功体験」を増やす
・最初は「小さく始める」
・配慮は「なるべく早く」
タブレット学習のメリット、デメリットなど詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
学習の選択肢の1つとして、参考になれば幸いです。
【療育辞めてよかった!療育の辞め時】まとめ

記事のポイントになります。
✅療育を辞めてよかった事例
・日常生活の困りが解消された
・苦手な課題への取り組み方が学べた
・友達と会話ができるようになった
✅療育先を「変える」タイミング
・子どもの行き渋りがある
・子どもの変化がない
✅療育先を「辞める」タイミング
・専門家に「辞めても大丈夫」と言われる
・困りの解消/対処法が実践できる状態
✅療育を継続すべきケース
・環境が変わるとき
・専門家に「継続」を勧められたとき
✅療育を卒業したあと
・環境を作っておく
・本人の理解者と繋がっておく
・学習フォローの準備をしておく
・タブレット学習はハードルが低い
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】







































[…] 【療育辞めてよかった!】辞めるタイミングは4つ!事例/注意点 […]
障害支援相談員です。年々増加する障害児の療育サービスに疑問を感じています。 一度始めた療育サービスの卒業がかなり長期化しています。漫然とした療育? 預かり所?親の安心の為?
行政と一緒に考えていかねばならないと思っています。相談させて頂きたいです
ご相談ありがとうございます。
近年、疑問を感じるような支援が増えていること、私も感じています。
現在、ご相談希望の方には、
メール相談をさせていただいております。
ただ、基本的には親御さんを対象にしておりますので、
今回の相談内容に対して、お力になれないかもしれません。
せっかくご連絡頂いたのに
ご期待に添えず、申し訳ありません。