

通所受給者証について知りたい方「通所受給者証って、どんなデメリットがあるの?子どもの将来が不利になりそうで不安。通所受給者証について詳しく知りたい」
ネットで調べては見たものの、「色んな手帳があって、よくわからない!」
こんな思いをされた方も、少なくないのではないでしょうか?
本記事では、15年以上療育支援をしてる私が、「通所受給者証の押さえるべきポイント」をお伝えしたいと思います。
本記事がお役に立てば幸いです。
目次
通所受給者証の「デメリット」
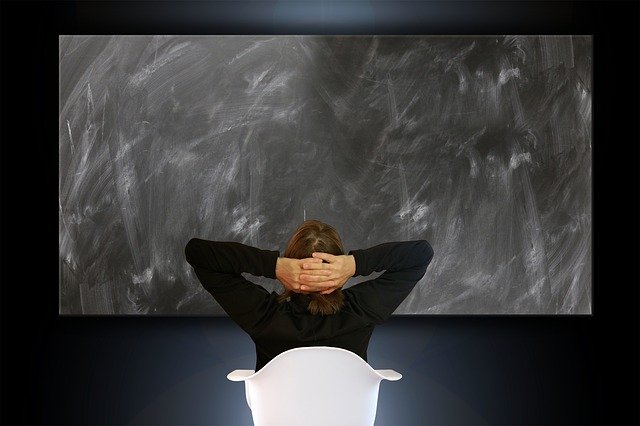
まず結論から言いますと、
『通所受給者証を取得すること』に、デメリットはありません。
ただ、私が支援してる親御さんからの声としていただいた、
「通所受給者証のデメリット」を3つお伝えします。
①:家族の「精神的な負担」
②:混み合ってる
③:手続きに「時間がかかる」
家族の気持ちの負担

これは人によりますが、「通所受給者証」をネガティブに捉えられる方は、精神的な負担になる場合があります。
「うちの子には障害がある」「レッテルが貼られそうで心配」など、不安に繋がる方がいます。
通所受給者証とは、お子さんに必要な支援が受けられる1つの方法になります。
ただ、お気持ちとして負担になる方は、一定数います。
混み合ってる

個人的には、ここが最大のデメリットだと思います。
後ほど詳しく説明しますが、利用料が安いので、その分かなり混み合っています。
数ヶ月~数年待たれる方も、珍しくありません。
すぐに支援を受けたい方は、民間療育など違う方法を並行して探すことも、お勧めします。
手続きに時間がかかる

自治体によりますが、私が知る限り、「時間がかかる」は、共通しています。
・取得までのステップが多い
・ステップ毎の間隔が1ヶ月ほど空く
このように、時間がかかってきます。
【合わせて読みたい記事】
通所受給者証の「メリット」

「通所受給者証を取得するメリット」は、3つあります。
①:利用料が「安い」
②:「個別~集団指導まで」経験できる
③:「ママ友」が作れる
利用料が安い
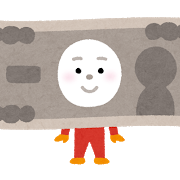
多くの方には、これが一番のメリットになると思います。
福祉サービスの為、国の助成金を受け、利用ができます。
1割の負担で利用ができ、所得に応じて負担額の上限(3パターン)が決まってます。
💰利用料(月の上限額)
| 非課税世帯 | 0円 |
| 世帯所得900万以下 | 4,600円 |
| 世帯所得900万以上 | 37,200円 |
1日あたり、10,000円弱の費用が、1,100円弱になります。
個別~集団指導まで経験できる

事業所や地域により異なりますが、個別・小集団(2~4名程度)・集団(5名以上)など、様々な指導があります。
お子さんに合わせて、『個別→小集団→集団』と、同じ場所でステップアップできます。
療育では、個別で身につけたことを、集団の場や友達に活かすことが、大切になります。
個別で身につけたスキルを実践する場として、集団指導は大切になります。
それが同じ場所で学べるのは、メリットの1つになります。
ママ友が作れる

ここは、「情報がほしい!」「話せるママ友がほしい」という方には、メリットになります。
逆に、「療育で、ママ友はいらないかな」という方は、読み飛ばしてください。
療育では、集団指導が多くあります。同じグループのママと席が隣になったり、お子さん同士が仲良しになって、話すこともあります。
ママ友ができて、情報交換や同じ境遇だからこそ話せることがあり、交流を活かしてる方も多くいます。
「似た境遇の人と繋がれると、気持ちが楽になる」という方は、実際に多いです。
✅「通所受給者証」と「療育手帳」は別物
端的にいいますと、通所受給者証より、更に手厚いサポートが受けられるのが「療育手帳」になります。
「対象の子」でいうと…
・通所受給者証:「知的障害ない子」も対象
・療育手帳:「知的障害ある」子が対象
もしお子さんに知的障害がある場合は、療育手帳の申請もあった方が良いでしょう。
手当や医療費の控除など、メリットがたくさんあります。
療育手帳については、【療育手帳の2つのデメリット】メリット/活用法 をご覧ください。
通所受給者証で「使えるサービス」

「通所受給者証」は、区の療育を受ける時に、必要になるものです。
利用できるサービスは、大きく2種類あります。
①:障害児通所支援
②:障害児入所支援
障害児通所支援の「児童発達支援・放課後デイ」は、利用される方が多いです。
障害児通所支援
児童発達支援
- 対象:未就学の児童(2才頃~年長)
- 形態:個別/集団指導あり
- 内容:SST/就学準備など
SSTの指導は、コミュニケーション・集団参加・切り替え・ルールの理解など、幅広くあります。
就学準備は、下記の内容など、様々あります。
・運筆
・文字/数字の学習
・机上課題(着席)
・挙手して意見を言う
放課後デイサービス
- 対象:就学以上の児童(小1~高3)
- 形態:個別/集団指導あり
- 内容:SST/学習など
児童発達支援との大きな違いは、対象年齢になります。
児童発達支援が終わったら、放課後デイを利用される子も、多くいらっしゃいます。
小学生以上ですと、SSTでは、感情のコントロール・他者の表情/気持ち理解・状況理解などがあります。
また、学習支援やお金・時間・物の管理の練習をする子も多いです。
保育所等訪問支援
- 対象:未就学の児童(2才頃~年長)
- 形態:訪問(園に)
- 内容:現状把握/情報共有/助言など
医療型発達支援
- 対象:身体機能の障害がある児童
- 内容:発達支援/治療
障害児入所支援
福祉型障害児入所施設
- 福祉サービス(介護)
医療型障害児入所施設
- 福祉サービス+医療サポート
【合わせて読みたい記事】
【落ちた人も多い?】特別児童扶養手当とは。金額/条件/申込方法
通所受給者証の「申請/取得/更新方法」

「通所受給者証の申請の流れ」は、大きく6つのステップになります。
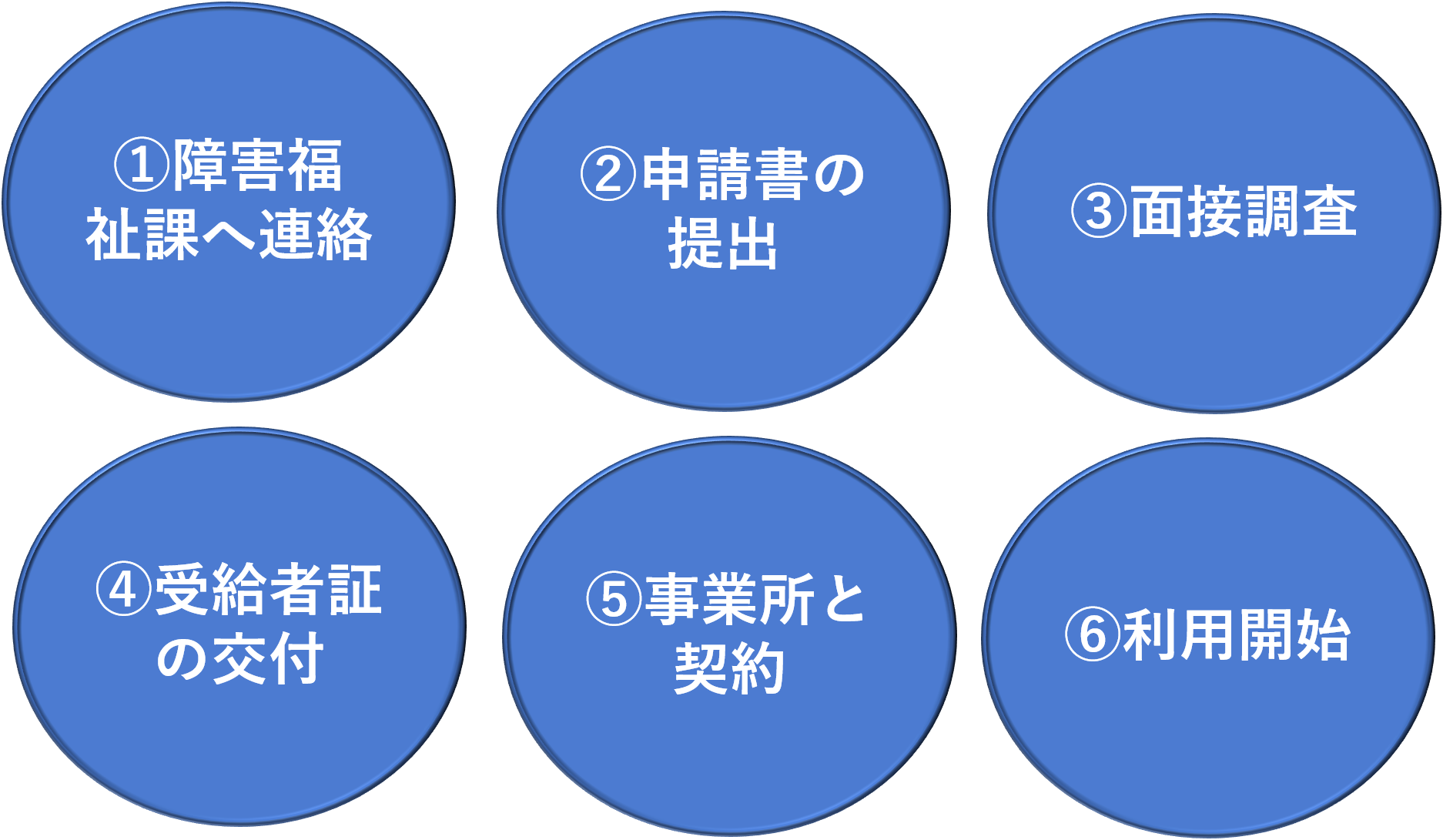
最初は、お住まいの区の障害福祉課へ連絡し、「通所受給者証(手帳)の手続きをしたい」ことを伝えれば、案内があります。
事業所を利用する前に、親御さんとお子さんで来所し、事業所の担当がヒアリング・お子さんの様子を見ることがあります。
お子さんの様子を見た上で、個別指導or集団指導なのか、判断しながらご案内を受ける形になります。
✅更新は1年ごと
自治体にもよりますが、基本的に1年毎に更新が多いです。「年度毎に更新するイメージ」になります。
必要な持ち物は…
・申請書
・印鑑
・本人確認書類
・通所受給者証
になります。
おすすめな「療育の選び方」

ここでは、おすすめな「療育の選び方」について、5つに分けてお伝えします。
一刻も早く困りを解消したい

- 民間の療育+民間のペアレントトレーニング
費用も労力かけられる場合は、民間の療育をおすすめします。
理由は「すぐに・お子さんに合った・質の高い」療育が受けられる為になります。
併行して、区の療育の申請も進め、療育の選択肢を増やしておけると安心です。
【合わせて読みたい記事】
多少制約があっても費用を抑えたい

- 区の療育
- 民間の療育
- 民間のペアレントトレーニング
- 独学(本・ネット)
まず、区の療育の手続きを進めましょう。ただ利用ができるまで、時間がかかります。
その間に、民間の療育で予算に見合う教室を探し、ペアレントトレーニングが受けられると、良いと思います。
親御さんの学習意欲・実践力が高い場合は、有効な方法になります。
緊急性の高い困りではないけど、お子さんの発達が気になる方は、下の記事をご覧ください。
【療育支援員がおすすめ】発達障害(グレーゾーン)が理解しやすい本11選
情報収集したい

- 民間療育の資料請求
- 発達障害関係の本
- 親の会(繋がりを広げたい方)
民間の療育の資料請求をしましょう。施設によってスタンスが違います。
どんなアプローチや施設があるのか、把握できると良いです。
具体的な関わりは、網羅的に学べる本が、手軽でおすすめになります。
おすすめの本は、下の記事でまとめています。必要な方は、ご覧ください。
【療育指導員が紹介】療育のおすすめ本!12選~目的別に紹介~
子どもの状態を知りたい

- 区の療育
- 発達検査を受ける
検査を受け、専門家の意見をもらうことをお勧めします。
どうすべきかわからない

- 区の相談窓口へ相談
お住まいの相談窓口(障害福祉課)への連絡をお勧めします。
「子どもの発達について相談したいです」とお伝え頂ければ、必要なご案内を受けることができます。
【関連記事】
【療育の後悔】受けないと、子どもの将来はどんな可能性が?事例を元に解説
【通所受給者証のデメリット】まとめ

記事のポイントになります。
✅通所受給者証の
「デメリット」
・家族の気持ちの負担
・混み合ってる
・手続きに時間がかかる
✅通所受給者証の
「メリット」
・利用料が安い
・個別~集団まで経験できる
・ママ友が作れる
✅通所受給者証で
「使えるサービス」
・障害児通所支援
・障害児入所支援
✅通所受給者証の
「申請/取得/更新方法」
・区の障害福祉課へ連絡
・申請書の提出
・面接調査
(家族へのヒアリング等)
・受給者証の交付
・事業との契約
・利用開始
✅オススメな療育の選び方
・急いでる:民間療育
・費用抑えたい:療育+民間ペアトレ
・情報収集した:資料請求/本
・子どもの状態が知りたい:検査予約
・判断迷う:地域の障害福祉課へ連絡
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】







































[…] 今日からわかる!ADHDの子供の4つの訓練方法 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】ADHDの子供の4つの療育 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】ADHDの子供の4つの療育 […]
[…] 【ADHDの子供の親向け】ADHDの子供の4つの療育 […]
[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]
[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]
[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]
[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]
[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]
[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]
[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]
[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]
[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]
[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]
[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]
[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]
[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]
[…] 細は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説しますをご覧ください。 […]
[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]
[…] 気になる方は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説しますをご覧ください。 […]
[…] お子さんの発達が気になる方は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説しますをご覧ください。 […]
[…] 療育について詳しく知りたい方は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法をご覧ください。 […]
[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法 […]
[…] 詳しくは、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]
[…] 【受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法 […]
[…] 詳しくは、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]
[…] 詳しい療育の流れは、【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]
[…] 詳しくは、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]
[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]
[…] 詳しく知りたい方は、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]
[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]
[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]
[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]
[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 […]
[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 […]