

子どもの不登校で悩まれてる方「保健室登校(別室)の場合、成績ってどうなるの?成績がつかなかったり、悪い評価になるのが心配。対策や事例が知りたい」
様々な理由で不登校になってるお子さんは、保健室登校(別室)をして、今の自分に合った通い方をしてる場合があります。
お子さんに合った通い方という意味では、必要なことですが、その反面、成績がどうなるのか..心配になる親御さんも多いと思います。
そこで本記事では、不登校の子の「保健室登校(別室)の成績/対策/事例」に関する情報をお伝えします。
この記事の執筆者の私は、不登校・療育支援を15年以上しています。
私が支援に携わってきた事例を通して、まとめてます。参考になれば幸いです。
目次
保健室登校(別室)の成績「よくある事例」

保健室登校(別室)の成績で「よくあるパターン(事例)」を2つお伝えします。
学校や地域によって変わってきますので、参考程度にご覧ください。
①:成績が「つかない」
(評定不能/オール1/全斜線)
②:「一部」成績がつく
(テストを受けてる科目のみ)
成績がつかない
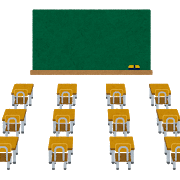
テストを受けていない為に、成績がつかないパターンになります。
テストで評価ができない以上、判断ができないという学校の考え方になります。
「評定不能/オール1/斜線」などで表現されることが多いです。
一部成績がつく

テストが1部受けている場合は、部分的に評価がつくことがあります。
テストを受けた特定の科目だけ、など限定的になります。
『保健室などの別室でテストを受けてOK』という学校もありますので、在籍校が可能なのか、相談できると良いと思います。
✅「評価の基準」は学校により違う
学校によっては「出席日数が全体の20%以下だと1になる」など、基準が違います。
また提出物が出せていれば、成績がつきやすい場合もあります。
早い段階で『評価の基準』を、学校の先生に確認できると安心です。
テストが受けられない時の「3つの対処法」

お子さんがテストが受けられない時の「対処法」は3つあります。
①:「学校での安心感」を確保する
②:本人に合う「テストの受け方」を考える
③:辛くなった時の「対処法」を決める
(テスト中など)
学校での安心感を確保する
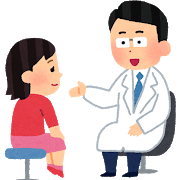
「テストを受ける」ということは、一定時間学校で過ごすことになります。
つまり、学校の中で本人が心理的に “安心できる要素” を作る必要があります。
例えば、
・信頼してる先生がいる
・個別でテストが受けられる
(別室で)
など、その子にとって安心できる要素が必要になります。
安心感があると、本人もチャンレジしやすくなり、結果的に上手く可能性も上がります。
私たちも同じで、緊張や不安な状態より、安心してリラックスした状態の方が、物事が進みやすいと思います。
不登校のお子さんは、この影響をより強く受ける様なイメージになります。
本人に合うテストの受け方を考える

お子さんによって、”何が安心で、何が不安か” は、変わってきます。
その子にとって、「安心感があって、不安が最小限になる様なテストの受け方」を見つけることが大切になります。
・お子さんの気持ち
(何が安心で何が不安か)
・学校で現実的にできる範囲
この2点を確認し、折り合いがつく方法を見つけていきます。
辛くなった時の「対処法」を決める
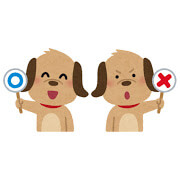
どんなに丁寧に環境や準備をしても、当日になって、お子さんが辛くなってしまうことはあります。
不登校の子は気持ちの波が大きく、コンディションは、その日にならないと分からないことが多いです。
コンディションの波を想定して「辛くなった時の対策」も決めておきます。
辛くなった時の対策の例としては、
・手を挙げる
・机にあるカードをめくる
・顔を伏せる
など、本人が実践しやすい方法を決めます。
そして学校にも話を通しておき、本人/家族/学校で共通認識をもっておきます。
このことを本人にも伝えておくと「何かあっても、◯◯すれば大丈夫。先生が助けてくれる」と安心感に繋がります。
保健室登校(別室)が安定しない時の「対策」

保健室登校(別室)が安定しない時の「対策」は2つあります。
①:「十分な休息」をとる
②:「学校の通い方」を見直す
十分な休息をとる

登校が安定しないよくある理由の1つに、”休息不足” があります。
不登校の子は十分な休息をとる必要があるのですが、それが足りていないと、登校が安定しないことがあります。
その場合は、まず休息を十分にとっていきます。
ちょっと回復したから大丈夫と思って登校して、少ししてまた休む..というパターンはとても多いので、
慎重に丁寧に本人とも相談しながら、決めていくことが大切になります。
判断はとても難しいのですが、本人と「◯◯の時は◯◯だったね」と過去を振り返りながら、確認するのが1つの方法としてあります。
具体的な休息中の過ごし方は、こちらの記事に詳しくまとめてます。
【関連記事】
【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン/関わり方/注意点
学校の通い方を見直す

“学校の通い方” と “本人の状態” が合っていない場合があります。
その場合は、まず通い方を見直していきます。
例えば、よくある通い方の選択肢は、
・好きな授業だけ参加
・保健室登校
・母子登校
・辛くなったら別室に移動
など様々な通い方があります。
お子さんの状態に合わせて、通い方を変えることが大切になります。
また通うペースも大切になります。こちらは一例になります。
・週2~3日通う
・苦手な科目がない日だけ登校
時間割を見て、本人と相談して通い方・ペースを決められるのが一番です。
ただ学校や担任の理解/協力は必要な為、連携は必須になります。
具体的な “学校とのやりとり” に関しては、こちらの記事をご覧下さい。
【合わせて読みたい記事】
成績がつかない時の「3つの選択肢」
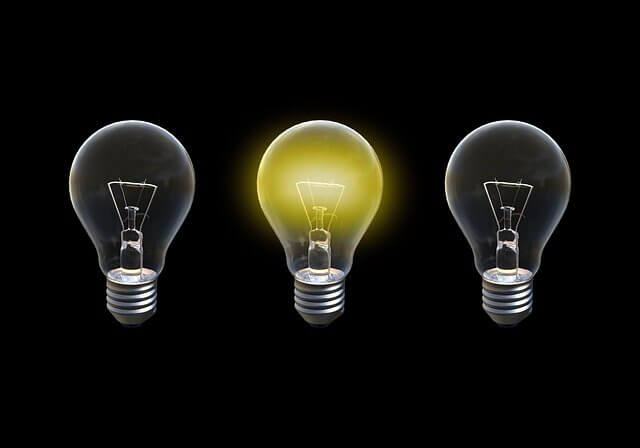
成績がつかない(低評価)時の「選択肢」は、3つあります。
①:私立高校
②:フリースクール
③:通信制の学校
④:ICT教材で出席扱い
私立高校

内申点の影響を受けない私立高校の受験になります。
公立高校は、内申点の影響がありますので、成績がつかなかったり、低評価ですと、厳しい場合が多いです。
フリースクール

似た境遇の子が通っていたり、通い方が選べたりと、様々なフリースクールがあります。
本人が安心できる学校の雰囲気、通い方など、見学・体験を通して選ぶことができます。
現在のオンラインスクールは、オンラインもあり、通学と交互にできる学校も多くあります。
通信制の学校
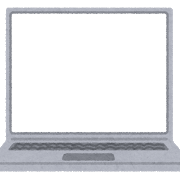
人に会ったり、集団の場に入ることが辛い子は、通信制も心強い選択肢の1つになります。
現在は、不登校の子の有力な選択肢の1つになっています。資料を取り寄せながら、本人と相談して情報を集めている方も多いです。
ICT教材で出席扱い
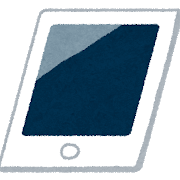
ICT教材とは、タブレット学習などの通信教材になります。
不登校で内申点の問題で進学先が減るのを避けるため、通信教材を使って出席扱いする方法があります。
在籍校によって適当になる場合とそうでない場合があります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
【保健室登校(別室)の成績】まとめ

記事のポイントになります。
✅保健室登校(別室)の成績
「よくある2つのパターン(事例)」
・成績がつかない
(評定不能/オール1/全斜線)
・一部成績がつく
(テストを受けてる科目のみ)
✅テストが受けられない時の
「3つの対処法」
・学校での安心感を確保する
・本人に合うテストの受け方を考える
・辛くなった時の対処法を決める
✅保健室登校(別室)が安定しない時
「2つの対処法」
・十分な休息をとる
・学校の通い方を見直す
✅成績がつかない(低評価)の時
「3つの選択肢」
・私立高校
・フリースクール
・通信制の学校
✅保健室登校(別室)してる子の
「学習対策」
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合った学習法
・レベルにあった問題の選択
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】







































