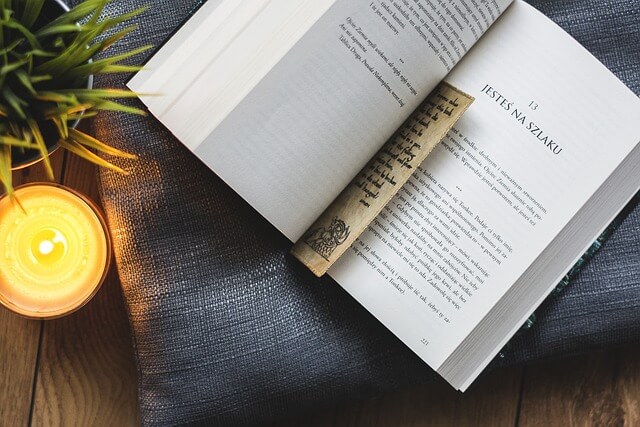

発達障害の子の宿題で悩まれてる方「もう中学生なのに宿題しない…。子どもが宿題する様になる方法が知りたい」
お子さんが中学生になると、進路や受験など、学習・宿題は重要になってきます。
それに伴い、お子さんが宿題をしないことに悩まれてる方も、少なくないと思います。
特に発達障害のお子さんの場合、様々な理由で宿題をすることが難しくなります。
“宿題をしない理由” によって、対応方法は変わる為、ご家庭での対策が難しいことも多いです。
そこで本記事では、
「発達障害の中学生の宿題」に関する情報を紹介したいと思います。
記事の執筆者の私は、お子さんの療育/学習支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その支援経験を元に、本記事をまとめてます。
参考になれば幸いです。
目次
発達障害の中学生が「宿題をしない理由」

発達障害の中学生が「宿題をしない理由」は、4つあります。
①:「宿題するメリット」を感じてない
(やる理由がない)
②:学習への「拒否感」がある
(やりたくない)
③:学習の「困難さ」がある
(やってるのに出来ない)
④:宿題以外の
「やりたいこと」に引っ張られてる
(他にやりたいことがある)
宿題するメリットを感じてない

お子さん自身に、”宿題する理由” がない場合になります。
親御さんからしたら「宿題はやるものでしょ。皆やってるんだから、理由も何もないでしょ」と思われるかもしれません。
ただ、お子さんの特性によっては、自分にとっても意味(メリット)が明確でないと、行動に移しづらい場合があります。
「皆がやってるから」
「学校でやると決まってるから」
など、お子さんにとって曖昧な理由ですと、宿題をする理由には繋がりづらいです。
学習への拒否感がある

学習への苦手意識があり、拒否してる状態になります。
完全に拒否してる子もいれば、苦手な科目の時だけ、拒否する子もいます。
個人差がありますが、共通して多いのは、学習の…
・”成功体験” が少ない
・”失敗体験” が多い
のいずれか、もしくは両方になります。
学習の困難さがある
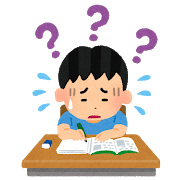
学習の困難さ(ex.読み・書き)がある場合です。
著しい困難さがある場合は、学習障害(LD)の診断を受ける子もいます。
お子さんは、一生懸命取り組んでるのに、定着が難しく、本人が自信を失ってる場合が多いです。
宿題以外のやりたいことに引っ張られてる

「やるべきコト」 よりも 『やりたいコト』 を優先してる場合になります。
例えば、ゲーム・動画・TVを見るなど、自分の好きなことを優先して、宿題を先延ばしにするパターンになります。
宿題をしない時の「5つの対策」
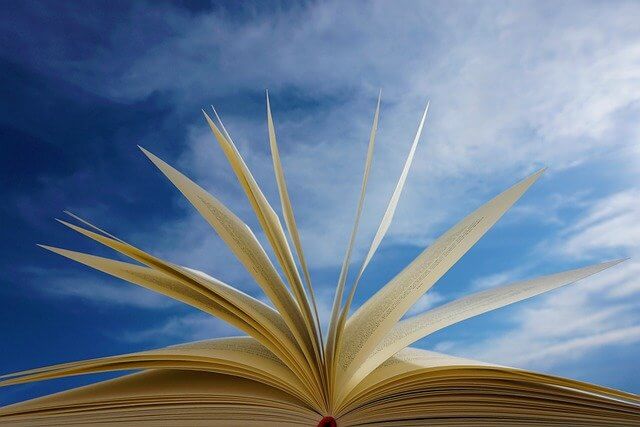
発達障害の中学生が、宿題をしない時の「対策」は、5つあります。
①:「宿題するメリット」を明確にする
②:「成功体験」を作る
③:学校に「相談」する
④:本人と「ルール」を決める
⑤:「タブレット学習」の導入
宿題するメリットを明確にする
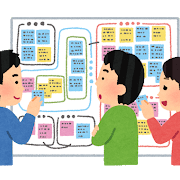
本人が認識できるように “宿題するメリット” を視覚的に示します。
例えば、お子さんが将来なりたいもの・やりたいことを聞きます。
例えば、それが作家だった場合(①→②→③の流れで話をする)、
「作家になる為には、何が必要?」
⇨①「語彙力、文章・ストーリー構成、表現力、色んな文章を読む経験が必要」⇨②「今の学習で繋がってることはある?」⇨③「国語の文章題、漢字で学べる!(作家に繋がるメリット)」
このように「本人のやりたいこと・興味関心」と「今の学習」を具体的につなげて、
本人が宿題するメリット(意味)を認識できるようにします。
紙に書き出したり、付箋でまとめるなど、一緒に整理できると丁寧だと思います。
成功体験を作る
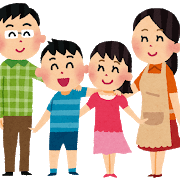
宿題(学習)の成功体験を作ります。
「この宿題ができた!」
「宿題が全部終わった!」
と本人が思える経験になります。
そのためには、大人が手伝ったり、宿題の量を減らすことも必要になります。
成功体験が積み重なってくると「ちょっと宿題やってみようかな(この前もできたし!)」
という意識ができ、行動に移っていきます。
学校に相談する
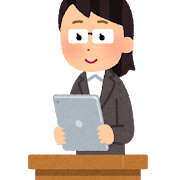
宿題の量や質が、明らかに本人に合ってない(大きな負担になってる)場合は、担任の先生に相談することも大切です。
先生次第にはなりますが、宿題が調節できれば過剰な負荷を避け、本人の成功体験が作りやすくなります。
それは、本人はもちろん、親御さんのストレス(負担)の軽減にも繋がります。
本人とルールを決める

“宿題に関するルール” を本人と決めます。
具体的には、宿題の量や時間などです。
ここで大切なことは、2点になります。
・本人の意思を聞く
・頭ごなしに否定しない
中学生にもなると、本人が自分で決めたり、選ぶ過程が大切になります。
ここが疎かになると「大人に勝手に決められた」「本当はやりたくないのに」という気持ちが、結果にそのまま出ます。
具体的には、宿題を適当に済ませたり、誤魔化したりする様になります。
本人の意見に明らかに無理がある場合は、大人側から選択肢を提示して選んでもらうのも1つです。
もしくは「○○は、この前難しかったと思うけど、どう思う?」など、
過去の事実(無理があった)を伝えつつ、正しく認識してもらった上で、本人の気持ちが聞けると良いです。
タブレット学習の導入
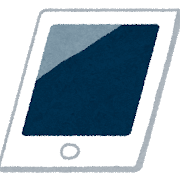
宿題をしたがらない理由で、勉強自体が分からないという場合は、周りからどんなに促しても、根本的な解決にはなりにくいです。
「どうせやってもできない」となれば、取り組んだとしても形だけで、理解には繋がりにくいです。
そしてその状態が続くことは、本人の今後の進路を考えると、将来の選択肢を狭めることに繋がります。
そのため、対策として「発達障害の子向けのタブレット学習」があります。
教科書、市販教材などで理解が難しかったり、机上課題やプリント学習自体が嫌な子には、効果が出やすいです。
詳しい説明は別記事でしていますが、お子さんの理解のしやすさ(特性)は、様々あり、その1つ1つの特性に配慮された学習PGMがタブレット学習にあります。
例えば、教科書にはない、アニメーション解説/音声解説が活用でき、動きや映像、読み上げ機能で理解を促してくれる特徴があります。
このように、発達障害など特性ある子向けのタブレット学習は、一般的な学習で効果が出なかった子にとっては、心強いツールになります。
詳しい情報は、こちらの記事をご覧ください。
特性のある子の、1つの学習方法として、参考になれば幸いです。
発達障害の中学生の宿題で「大切な視点」

発達障害の中学生の宿題で、「大切な視点」は、3つあります。
①:「本人の気持ち」を確認する
②:「宿題の量/質」が適切か確認する
③:本人が「選択できる機会」を作る
本人の気持ちを確認する
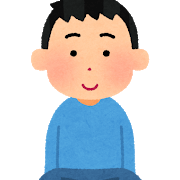
宿題に限らずですが、本人の気持ちが大切になります。
本人がどう思ってるのか、どう感じてるのか、大人側が丁寧に確認することが大切になります。
本人の気持ちがない行動は、形だけになり、エネルギー・時間を消耗する形になります。
逆にいうと、本人の気持ちある所には行動が起こり、結果が出る(宿題をする)ことにもなります。
宿題の量/質が適切か確認する
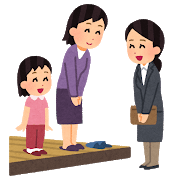
宿題が、親子のストレス・親子関係の悪化など、日常生活に支障を出してる場合は、
そもそもの宿題の質・量を見直す必要があります。
調整してもらえるかは、担任次第ですが、相談して調整できてる方は少なくありません。
もし、宿題の調整が難しい場合は、家庭の中で無理のない範囲の宿題の量を決めるのが良いと思います。
本人に無理をさせても、後から反動がきて、失敗体験になります。
失敗体験の積み重ねは、自己肯定感をさげ、お子さんの行動の活力を奪っていきます。
そうなると宿題の問題というより、生活全体の問題に発展していきます。
私が支援する中で、実際にそんなお子さん・ご家庭をたくさん見てきました。
本人が選択できる機会を作る

先ほどの①に、似ていますが、本人が選択できる機会を作ります。
宿題をどこまで頑張るのか、を本人に選んでもらう(考えてもらう)形にします。
自分で決められる機会を作ることで、反発心が生まれることを避けます。
自分で決めた方が頑張れますし、本人の自己決定スキル(自分で決める力)にも繋がる為です。
【発達障害の中学生 宿題対策】まとめ

記事のポイントになります。
✅発達障害の中学生が
「宿題をしない理由」
・宿題するメリットを感じてない
・学習への拒否感がある
・学習の困難さがある
・宿題以外のやりたいことにつられる
✅宿題をしない時の
「5つの対策」
・宿題するメリットを明確にする
・成功体験を作る
・学校に相談する
・本人とルールを決める
・タブレット学習の導入
✅発達障害の中学生の宿題で
「大切な視点」
・本人の気持ちを確認する
・宿題の量/質が適切か確認する
・本人が選択できる機会を作る
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】
【勉強できない中学生】ADHDの特性から考える~7つの勉強法~






































