

不安が強い子に悩まれてる方「子どもの不安が強くて、将来が心配。どう関わればいい?子どもの不安を減らせる方法が知りたい」
常に母親の近くにいたがる、一人でトイレに行くことを怖がる、夜に翌日のことを何度も確認してくる、など
不安が強い子の親御さんは、お子さんの将来が不安なってしまうものです。
この記事を執筆してる私は、療育/相談支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その中には、不安感が強いお子さんも少なくありませんでした。
その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不安が強い子どもの「2つの原因」

不安が強い子どもの「2つの原因」をお伝えします。
①:子ども自身の「特性」
②:子どもが過ごす「環境」
子ども自身の特性

お子さんが生まれ持った『気質に近いもの』になります。
性格に近いもので、本人の意思で変えようと思っても、変えられないものになります。
特性は、それ自体が良い悪いではなく、「活かし方」を考えることが、大切になってきます。
【合わせて読みたい記事】
【場面緘黙の子】緊張が強くて話さないのは甘え?5つの特徴/4つの接し方
子どもが過ごす環境

お子さんが過ごす「環境」で、
失敗体験を重ねたり、トラウマになる場合になります。
例えば…
・周囲が優等生ばかり
・失敗体験を重ねてきた
・親に叱責ばかりされてきた
・過去の出来事でトラウマを抱えてる
このように、育ってきた環境・経験が原因になることも、少なくありません。
✅鬱になると、「栄養素の欠如」が原因の場合も
不安が強まり、精神的に追い詰められると、鬱になる人がいます。
人は栄養素が足りないことで、不安を感じやすくなる場合があります。
✅「不安が強い子」は女の子に多い
これは、あくまで私の経験上ですが、生活に支障が出るぐらい不安が強い子は、女の子に多いです。
特に、思春期で自分を俯瞰してみれる年齢になると、
・友達関係
・自分と周りとの違い
・今後の生活
など、不安を感じやすい子が、増える傾向にあります。
【関連記事】
不安が強い子どもへの「8つの対処法」

不安が強い子どもへの「8つの対処法」をお伝えします。
①:子どもの特性を「受け入れる」
②:不安を一旦「受け止める」
③:不安を「視覚化」する
④:不安に「名前」をつける
⑤:不安なモノの「仕組み」を知る
⑥:「親子の時間」を作る
⑦:「大丈夫だった」気付きを与える
⑧:親の「助け」を減らしてく
子どもの特性を受け入れる

「特性=ありのままの子ども」と、受け止める視点になります。
特性は、気質に近いものです。変えるものではなく、付き合っていくものです。つまり、「活かし方」を考えることが、大切になります。
例えば、集中力が短い子の場合は…
・細かく褒める
・ゴールを決めておく
・TODOチェック表を使う
・1つずつの課題を短くする
・興味のあるものに結びつける
このように、『お子さんの特性を活かす方法』を考えていくことが、大切になります。
不安を一旦受け止める
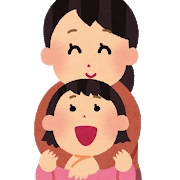
お子さんが不安を口にしたら、『○○なのが心配なんだね』と、一度受け止めます。
それが親からみて、「それの何が不安なの?」と思うことでも、一旦受け止めることが大切になります。
お子さんは一度受け止めてもらえると、安心します。
安心までいかない子でも、不安が更に強まることに、ブレーキをかけられます。
お子さんが “不安だと伝えてくれたら” 受容します。
不安を視覚化する

これは、心理学でもよくある方法ですが、不安に思っていることを、紙に書き出す方法です。
例えば、「明日の給食が不安」、「明日の習い事の先生が、どんな人か分からない」のように書き出します。
すると、気持ちが整理されたり、対策も考えやすくなります。
・明日の給食
⇨給食メニューで確認
・習い事の先生
⇨ホームページで顔を確認
このように、1つずつ整理をしていくことが、不安を減らす効果的に繋がります。
ちなみに大人の方にも、効果がある方法になります。
不安に名前をつける

お子さんに、「不安に名前をつけてもらう」ことも、方法の1つになります。
少しクスッとなるような名前をつけることで、いざ不安を感じる時でも、名前を呼んでみると、リラックスできる場合もあります。
不安なモノの仕組みを知る

不安に感じているモノの構造を理解すると、不安が減る場合があります。
例えば、初めていく場所に、不安を感じている場合です。
その場所の「室内の様子・中にいる人・どんなことをしてるのか」、などを画像や動画で確認する方法になります。
また…
・映画を怖がる
⇨撮影映像を見る
・初めての場所
⇨室内/人/内容を画像・動画で見る
・人を怖がってる
⇨その人が笑ってる所を見る
・着ぐるみを怖がる
⇨着てる人の休憩場面をみる
このように、怖がっているモノを別の角度で見ることで、不安が和らぐこともあります。
✅「日常生活に組み込む」のも1つ
日常生活の中で、不安なモノを見聞きする時間を作ることで、心理的に接触する頻度を増やし、不安を減らしていきます。
人は、接触する機会が多いほど、安心します。
例えば、小学校に不安がある就学前の子でしたら、年長さんの間に…
・散歩ルートを登校ルートと同じにする
・ユーチューブで小学校の動画を見る
などがあります。
お子さんが嫌がったら避けた方が良いですが、日常生活に自然に馴染んでいると、警戒心が解きやすくなります。
親子の時間を作る

ボストン大学の研究によると、不安感の強い8歳以下の子の親に玩具を集め、指示・質問・否定することを全くせず、100%子どもに向き合う指導をしました。
すると1日5分続けるだけでも、子どものが不安が軽減されたといいます。
このような「子どもの為の時間(子どもが自分の為の時間と思える)」が、大切になっていきます。
試しに1日5分から時間を作ってみるのは、いいかもしれません。
“大丈夫だった” 気付きを与える

不安を根本的に減らしてく為には、
お子さんの「結果的に大丈夫だった(不安だったけど)」という経験が、必要になります。
・試しにやってみたらできた
・不安を感じてたけど、やってみたら大丈夫だった
このような機会があったら、「○○をしたけど、大丈夫だったね」、「○○楽しかったね」など、
『不安だったけど、大丈夫だった』ということに、気づかせる声掛けをしましょう。
繰り返し声を掛けていくと、「ちょっと不安だけど、この前大丈夫だったからやってみようかな」
のように、次第にお子さんの行動に変化が出てきます。
親の助けを減らしてく

お子さんの自立を考えると、親の手助けを減らしていく必要があります。
少しずつ、親のフォローを減らしていきます。
減らすタイミングは、非常に難しいのですが、
例えば、「1ヶ月不安な言動がなく、チャレンジできたこと」は、フォローを減らすなど、
お子さんの不安感に合わせると、良いと思います。
【関連記事】
不安が強い子への「2つのNGな接し方」

不安が強い子への「2つのNGな接し方」をお伝えします。
①:不安を「否定」する
②:「罰」を与える・脅かす
不安を否定する

本記事の前半部分で、触れましたが、不安は受け止めることが、大切になります。
否定されれば、「誰も自分の気持ちを分かってくれない」など、ネガティブな気持ちが、強まってきてしまいます。
罰を与える/脅かす

罰や恐怖で押さえつけても、解決にはなりません。
むしろ、不安を抑え込むことで、感情が爆発したり、うつ傾向になったりと、逆効果になります。
この状態がひどくなると、二次障害になる場合があります。
詳しくは、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法 をご覧ください。
【不安が強い子供 8つの対処法】まとめ

記事のポイントになります。
✅不安が強い子どもの
「2つの原因」
・特性
・環境
✅不安が強い子どもへの
「8つの対処法」
・子どもの特性を理解する
・不安を一旦受け止める
・不安を視覚化する
・不安に名前をつける
・不安なモノの仕組みを知る
・親子の時間を作る
・大丈夫だった後に気付きを与える
・親の助けを減らしてく
✅不安が強い子への
「2つのNGな接し方」
・不安を否定する
・罰を与える/脅かす
以上になります。
本記事が参考になれば、幸いです。
【関連記事】
【すぐ泣く子供(小学生)】何が嫌なの?5つの原因/3つの接し方









































[…] 【不安が強い子供】今日から始められる!2つの原因と8つの対処法 […]
[…] 【不安が強い子供】今日から始められる!2つの原因と8つの対処法 […]
[…] 【不安が強い子供】今日から始められる!2つの原因と8つの対処法 […]
[…] 【不安が強い子供】今日から始められる!2つの原因と8つの対処法 […]
[…] 【不安が強い子供】今日から始められる!2つの原因と8つの対処法とは […]
[…] 【不安が強い子供】今日から始められる!2つの原因と8つの対処法をご覧ください。 […]
[…] 【不安が強い子供】2つの原因と8つの対処法 […]