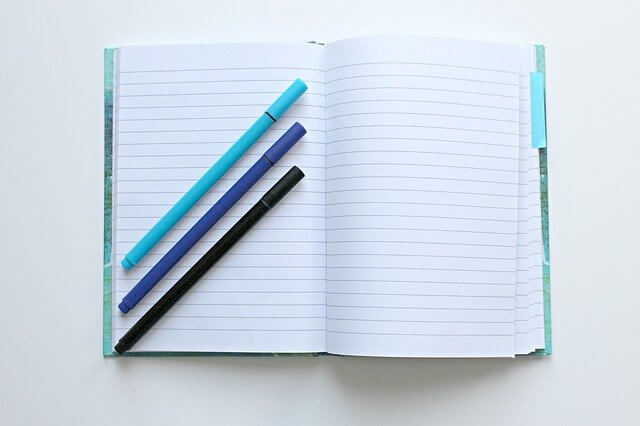

ADHDの子の勉強で悩まれてる方「うちの子、もう高校生なんだけど、勉強ができない。ADHDの子の勉強方法が知りたい」
「もう中/高校生なのに勉強できない…。やる気もなくて…進路が心配…」
「ADHDだから勉強できないの?子どもの特性に合った勉強法が知りたい」
お子さんの勉強で悩まれる方は多いですが、
特にADHDの特性を持つお子さんの場合、良い勉強法が見つからず、途方に暮れている方が少なくありません。
そこで本記事では、ADHDを3つの特性に分けて、
「ADHDの子(中/高校生)が勉強しやすくなる方法」をお伝えします。
困り事は、本人と環境との間で生じます。
そのため、本記事では、「本人の特性」と「環境」の2つの視点でまとめてます。
この記事を執筆してる私は、療育/学習支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その支援経験を元に、実際に上手くいった方法をまとめてます。
参考になれば幸いです。
目次
ADHDの中学生/高校生「勉強できない理由①」

ADHDの中/高校生が「勉強できない理由(本人の特性)」は、3つの特性からきます。
①:「多動性」がある
②:「衝動性」が高い
③:「不注意性」がある
多動性がある
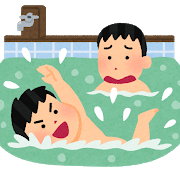
落ち着きがなく、何かに熱中している時以外は、常に体を動かしてるイメージになります。
座っていても体を揺らしたり、席を何度も立ったり、歩き回ったりします。
動きたくなる欲求(感覚探究)が強く、勉強に取り組める時間が限られてる為、
勉強に支障が出る場合が多いです。
衝動性が高い
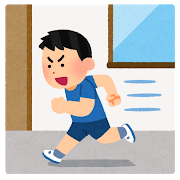
“何か気になるもの” があると、体が反応してしまう為、勉強以外に注意が向きます。
物や音、人の動きなど、お子さんの特性によって様々になります。
また、衝動的に問題を解くこともある為、問題文をあまり読まずに自分で解釈して解いたり、
できる計算問題でも、早く終えようと適当に解いてしまうこともあります。
問題を解くのは早いけど、ケアレスミスが多いなどの問題に繋がりやすいです。
不注意性がある

勉強に支障が出やすい「注意の特性」は、2種類あります。
注意が散りやすい(転動性が高い)
“他の刺激” に、注意が引かれやすい特徴になります。
個人差がありますが、下の様な刺激が多いです。
・音(聴覚)
(ex.テレビ・スマホ・人の声・外の音)
・視界に入るモノ(視覚)
(ex.人の動き・手先でイジれる物・好きな物)
本人にとって “気になるもの” になります。
注意が続かない(持続性)
“集中できる時間” が限られている特徴になります。
取り組める時間を設けても、集中力に上限がある為、十分な勉強が難しい場合が多いです。
✅注意を向けづらい不注意性 もある
優先順位が高いものに、注意が向けづらい特性(選択性)があります。
よくあるのは、授業中の先生の話よりも、周りの音・動き等が気になってしまい、
優先度が高い情報(先生の説明など)を聞き逃してしまうことです。
授業に参加していても、聞き漏れが多く、結果として勉強の遅れに繋がりやすくなります。
私たちは、色んな刺激(音・視界に入るもの)の中で、無意識に優先順位をつけて、意識(注意)を向けています。
例えば、部屋で人の話を聞いている時は、周囲の人、エアコンの音、外の車の音など、様々な刺激があります。
私たちは、無意識に話をしてる人に優先的に意識を向けています。
このコントロールの難しさが、”注意が向けづらい不注意性” と言われるものであり、
よく言われる “集中力が低い、先生の話を聞いてない子” に繋がっていきます。
ADHDの中学生/高校生「勉強できない理由②」

ADHDの中/高校生が「勉強できない理由(環境)」は、2つあります。
細かく言うと、たくさんありますが、
ここでは、”学習の場面でよくある2つ” をお伝えします。
①:「気になる刺激」が多い
②:「見通し」がない
気になる刺激が多い

本人にとって “気になるモノ” が多い環境になります。
気になるモノとは、本人を取り巻く全てのものになります。
例えば、人、物、音、場所、匂い、温度などあらゆるモノです。
勉強においては、人、物、音、場所の影響が高いです。
頭ではなく、体が反応してしまう “勉強中に思わず触ってしまうもの、気になってしまうもの” が多い状況になります。
見通しがない
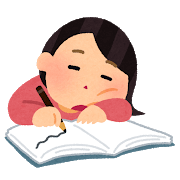
「何をどこまで解いたら終わりか」が分からない状態になります。
親御さんの中では、何となく「○○まで出来たら、終わりにしようかな」と考えていても、
本人が認識していなかったり、伝わっていない場合もあります。
この状態ですと、お子さんにとっては、ゴールのないマラソンをしてる様な状態になり、
モチベーションが下がり、勉強の成果が出づらくなっていきます。
✅「感覚が満たされてない」場合もある
「環境」ではありませんが、多動の子(常に動いてる子)には「動いて感覚を満たす」も大切になります。
例えば、「勉強の前に10分体を動かす」をするだけで、勉強の集中力が上がる(動きたくなる欲求が多少満たされる)子がいます。
席を立つこと、体を動かすことが減った分、勉強に向かえるようになります。
ADHDの中学生/高校生「特性を活かす勉強法」

ADHDの子の「特性から考える勉強法」は、7あります。
数が多いですが、該当する箇所だけを参考にする形で、問題ありません。
「多動性がある子」の勉強法
“多動性がある子” の勉強法は、3つあります。
ゴールを示す
勉強を始める前に、その日のゴール(終わり)を決めます。
例えば、「英語のプリント2枚」「数学の文章問題10問」など、誰が見ても分かる様な具体的なイメージになります。
多動の子は、ゴールが具体的ですと、集中力が高まりやすい(早く終えたい為)です。
事前に決めたゴールを本人とすり合わせしてから、その日の勉強を進めるのが理想になります。
中/高校生という年齢を考えると、本人に決めてもらい、
それが難しい場合は、一緒に決めていけると良いと思います。
思春期になると、お子さん自身の意思による影響が大きいこと、
そして自分で決めたことの方が、最後まで取り組める可能性が高い為になります。
細かく区切る
“1回の勉強時間” を細かく区切る方法になります。
ゴールが遠すぎると、早く終えようと適当に解いたり、
モチベーションが下がったままで、終えるまでに本来の何倍も時間が掛かることがあります。
そうならない為に、“本人の集中力できる時間” に合わせて、勉強時間を区切ると良いです。
例えば、15分が集中できる時間でしたら、
「最初の15分は数学の計算問題2P、1回休憩して、次の15分は漢字プリント2枚」
の様に、“課題” と “集中できる時間” を合わせながら区切るイメージになります。
サポートツールの活用
勉強への影響が大きい “座る” をサポートするツールになります。
ADHDの特性をもつ子の中には、姿勢の保持が難しかったり、疲れやすい子がいます。
姿勢が崩れる⇨集中が落ちる⇨勉強の質が落ちる
のように、負のサイクルに繋がりやすくなります。
参考例として、2つの “サポートツール” を紹介します。
✅ピントスクール
✅たーとるうぃず 重いひざかけ
「衝動性が高い子」の勉強法
“衝動性が高い子” の勉強法は、2つあります。
余計な刺激を減らす
勉強から気を逸らす原因になる “本人が気になるモノ” を片付けます。
ご家庭によっては、難しいこともあると思いますが、極力本人の視界に入らない様、工夫をします。
物が動かせない場合は、下のような工夫をする方法もあります。
・布をかぶせる
・パーテーションを立てる
・本人に壁に向いて座ってもらう
取り入れられる方法があれば、試してみるのも1つです。
【合わせて読みたい記事】
【療育指導員が紹介】ADHDの子が過ごしやすくなるグッズ8選
やることを1つに絞る
今やるべきことを “1つに絞り” 勉強します。
例えば「まず漢字を10個覚える」と決めたら、
それが終わるまでは、漢字の学習に使うモノ以外は、出しません。
他の科目などの本など、目につくモノがあると、注意が逸れる原因になる為、
今の勉強で使わないモノ以外は、視界に入らない環境にしておく、が大切になります。
「不注意性がある子」の勉強法
“不注意性がある子” の勉強法は、2つあります。
集中しやすい環境を作る
「集中しやすい」とは、“注意を逸らすモノがない環境” という意味になります。
ADHDの子にとって、勉強の妨げになる原因の多くは、視界に入る物・人・音などになります。
外からの刺激が少ない分、注意が逸れにくくなり、
勉強できる時間が増え、成果に繋がりやすくなります。
こちらは、”集中しやすい環境” の例になります。
・音が響きにくい部屋
・机は壁に向け設置
・勉強中は家族も静かに過ごす
・机は窓から離れた位置
(外の音を遠ざける)
一問一答で取り組む
余計な情報を最小限します。
例えば、プリントやドリルの問題を解く時に、そのまま解くのではなく、
・解く問題以外は、紙で隠す
(折って隠す)
など、“目の前の1問だけに集中できる状態”を作るのが効果的になります。
不注意性がある子は、他の問題に気を取られやすかったり、
どこから解けばいいか混乱したり、他の子より、体力・時間を消耗しやすいです。
そのため、解くべき問題以外は、視界に入らない様にした方が、集中力が落ちづらくなります。
【勉強できない中/高生 ADHD向け対策】まとめ

記事のポイントになります。
✅ADHDの中/高校生
「勉強できない理由」~特性~
・多動性がある
・衝動性が高い
・不注意性がある
✅ADHDの中/高校生
「勉強できない理由」~環境~
・気になる刺激が多い
・見通しがない
✅多動性がある子の
「勉強法」
・ゴールを決める
・短く区切る
・サポートツールを使う
✅衝動性が高い子の
「勉強法」
・余計なモノをなくす
・やることを1つに絞る
✅不注意性がある子の
「勉強法」
・集中しやすい環境を作る
・問題は1問ずつ出す
✅それでも
「勉強できない時の対策」
・特性に合う学び方
・刺激が少ない学習スタイル
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】
【すらら】発達障害の子の評判は?おすすめな子の特徴・理由・注意点








































