

ADHDの子の作文で悩まれてる方「子どもが作文が苦手で困ってる。作文が書ける様になる方法を教えてほしい」
「子どもの作文が文章にならない…一言で終わっちゃう……」
「どう教えればいいのか分からない…」
作文が苦手なADHDの子は、少なくありません。
ただ、家庭で教える様としても、なかなかうまく行かないことも多いかと思います。
そこで本記事では、「ADHDの子が書ける様になる6つの作文対策」をまとめました。
この記事を執筆してる私は、お子さんの療育/学習支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その支援経験を元に、実際に上手くいった方法を “短期的・長期的視点” でお伝えします。
参考になれば幸いです。
目次
ADHDの子の「作文が書けない理由」

ADHDの子の「作文が書けない理由」は、大きく2つあります。
①:「何を書いていいか」分からない
②:出来事を「忘れてる」
何を書いていいか分からない

私の経験上では、この理由が一番多いです。
そもそも何を書いていいか分からない、どう書いていいか分からない状態になります。
その為、「今日の楽しかったことを書いて」と言っても、書くことが難しいのです。
出来事を忘れてる
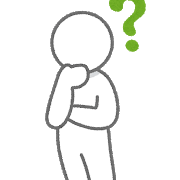
ADHDの特性の1つに、忘れやすい特性があります。
特に、多動・衝動性の高い子に多く、過ぎた出来事をあまり覚えてなかったり、
思い出したがらない場合もあります。
✅「苦手意識の強さ」も関係してる
ADHDの特性上、作文の苦手に繋がりやすい上に、失敗体験を重ね続けることで、作文への拒否感に、繋がることもあります。
もし拒否感が出てる場合、下のサイクルの練習が必要になります。
「本人に合った作文を書く方法を実践」⇨「上手く書けた(成功体験)⇨「本人の喜び(ex.ほめられる・達成感)」⇨「苦手意識が減る」⇨「作文に取り組める(自分から)」
数をこなすだけの「作文の練習」は、お子さんの苦手意識に繋がりやすいです。
ADHDの子の「作文対策~短期的~」

ADHDの子の「作文対策」は、3つあります。
ここでは、短期的な方法に絞って見ていきます(長期的な方法は後述します)。
①:作文の「基本的な型」を覚える
②:「基本的な型」を見ながら、自分で書く
③:「何も見ず」に自分で書く
作文の基本的な型を覚える
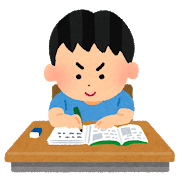
まず、作文は具体的にどう書くのか、フォーマット(型)を伝えます。
具体的には、5W1Hになります。
お子さんのレベルに合わせて、「誰が・何をした」など、最初は、答えられる情報量に留めます。
出来る様になってきたら「いつ・誰が・何をした」と、1つずつ情報量を増やしていきます。
最初に例文を見せて、それを真似してもらう形でも大丈夫です。
フォーマットを書いた紙を渡し、それを見ながら、○○を埋めてくイメージになります。
フォーマット(基本的な型)は、下の様なイメージになります。
「○○(誰)は、○○(何)しました」
「○○(いつ)、○○(誰)は、○○(何)しました」
もし、これでも難しい場合は、○○に実際に入れた例文を用意して、マーカーで〇〇に色を付けます。
マーカーがついてる箇所だけ、1つずつ考えてもらうのも、1つの方法になります。
✅”最初に” 書きやすいもの
お子さんによりますが、多くの子が最初に書きやすいのは、
・誰が
・どこで
・何した
になります。
答えが明確に決まってることが、多いからです。
逆に難しいのが…
・いつ
・なぜ
・どのように
です。時制(いつ)の理解が曖昧だったり、
文章で説明が必要なもの(なぜ・どのように)は、難しく感じる子が多いです。
基本的な型を見ながら、自分で書く

“フォーマット” を見ながら、○○が埋められる様になったら、
次はお手本を見ながら、一から文章を書いていきます。
最初は、1文ずつで大丈夫です。
これまでは、○○の部分だけ入れてましたが、ここでは、一から考えてもらいます。
お手本を見ながら、一から文が書けるようになりましたら、次のステップに進みます。
何も見ずに自分で書く

最後は、何も見ずに書きます。
覚えたフォーマットを思い出しながら、書いていきます。
もし、途中で難しい場面があれば、①で使った紙(フォーマット)を見て書いて大丈夫です。
また、1つの方法として、最初に自分で作文用紙の端っこに、
「いつ・誰が・どこで…」の5W1Hを書いて、始めるのもあります。
✅「作文が書けたこと」をほめる
作文が書けたら、ほめることも大切になります。
その時のポイントは「書けたこと」だけに焦点を当てて、ほめることです。
下の細かい部分は、一旦触れない方が良いです。
・字のきれいさ
・枠からはみ出ない
・細かい言葉の表現(語尾など)
先ほども触れましたが、作文が苦手なADHDの子には、
「作文が書けて嬉しかった」などのポジティブな経験が必要になります。
その為、最初から細かい箇所に触れてしまうと、作文へのモチベーションが下がってしまいます。
『作文が書けたら』ほめることが大切になります。
ADHDの子の「作文対策~長期的~」

ここでは、ADHDの子が “作文を書くベースの力” を身につける方法を見ていきます。
3つの方法になります。
①:「語彙力」を増やす
②:「よく使うフレーズ」を覚える
③:「1日感想」でアウトプットする
語彙力を増やす
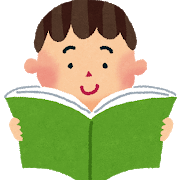
当たり前ですが、文章のほとんどは、単語で構成されてます。
語彙力が増えれば増えるほど、作文が書きやすくなります。
逆に語彙力が少なければ、作文を書くにも、その材料が限られた状態になってしまいます。
料理を作るにも材料がなければ、難しいのと同じですね。
まずは、作文の材料となる “語彙力を増やす” が大切になります。
【関連記事】
よく使うフレーズを覚える

先ほどの “語彙力” と、考え方は、同じになります。
作文でよく使うフレーズも、増やせると心強いです。
「楽しかった」
「嬉しかった」
「疲れた」
あくまで一例になりますが、お子さんが普段話すときに使ってるフレーズの中で、
作文で使えそうなものがあれば、教えていきましょう。
ある程度、語彙力がある子でしたら、使えるフレーズを増やす所から始めても大丈夫です。
1日感想でアウトプットする
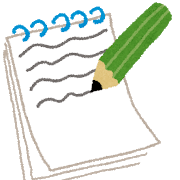
①・②で、語彙力やフレーズが増えてきたら、「1日感想」がお勧めです。
1日の終わりに大人から、今日の感想を一言聞いてみます。
「今日楽しかったこと1つ教えて」
「今日の○○はどうだった?」
など、お子さんが答えやすい質問だと、良いです。
ADHDなど、発達障害の子の中には、抽象的な質問が答えづらい場合があります。
具体的な質問ほど、答えてもらえる確率が上がります。
「今日どうだった?⇨今日の体育どうだった?」など、少し絞るイメージです。
必要があれば、お子さんに合わせて、”具体的な問いかけ” をしてみます。
それでも「作文が書けない」場合
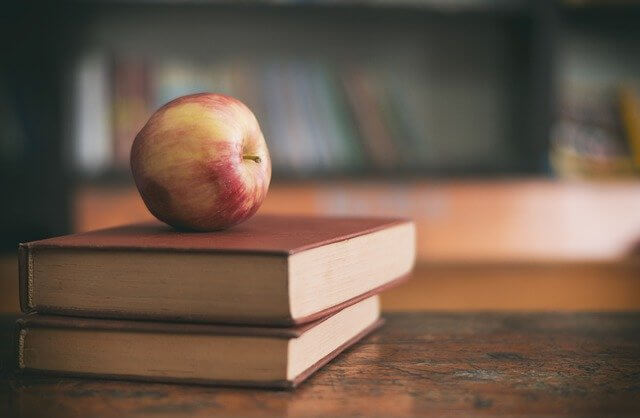
ここまでの内容を実践しても、作文がどうしても難しい場合もあります。
その場合は、“専門家・専門的なツール” に頼ることをお勧めします。
具体的な方法は、4つになります。
①:民間療育
②:家庭教師
③:タブレット学習
④:通信講座
民間療育

療育とは、発達支援の専門家が、指導を通して、お子さんの成長を作っていくものが中心になります。
福祉サービス、民間の2種類に分かれていますが、ここでは民間療育を中心にお伝えします。
理由は、福祉サービスは、通所受給者証が必要になり、手続きに時間がかかる上、かなり混みあっている為、利用までに数か月~数年かかることが多いです。
また福祉サービスは、集団指導が中心の為、本人の特性に合わせた個別指導が必要な作文には、十分なアプローチができない可能性が高くなります。
その点、民間療育は個別指導が多くある為、本人の特性に完全に合わせた作文対策の実施が実現可能になります。
個人的には、すぐに利用がしやすい民間療育がお勧めになります。
家庭で試行錯誤されても、状況に進展が見られない場合は、対策が本人の特性に合っていない可能性が高いです。
本人に合う方法を考える上で、まず本人の特性の把握が必要になり、そのためには専門の先生に、客観的に本人の様子を分析してもらうことが大切になります。
数値(結果)だけでしたら、病院の検査でも十分ですが、“日常の中でできる具体的な方法” までは教えてもらえない所がほとんどな為、民間療育に相談がするのが望ましいです。
今は民間療育の場所も増え、1回だけの指導でお子さんの特性を見てもらい、家でできる対策なども、具体的に教えてもらえます。
家庭だけで抱え込まず、専門の先生に一度アドバイスがもらえると、今後の学習面の対策が考えやすくなります。
特に作文は、学習だけでなく、文章で人に伝えるスキル、整理したり、要約したりと、今後生活する上で大切な要素がいくつもあります。
早い段階で、本人に合う作文を学ぶ方法を見つけたい所です。
家庭教師
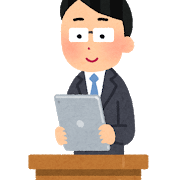
“発達障害を専門とした家庭教師” になります。
まだまだ数は少ないですが、ここ最近増えてます。
専門的な知識がある先生なら、お子様の特性に合わせて、教え方も工夫してくれます。
専門家の見極めポイントは、お子さんの特性に配慮した教え方・教材の工夫があるか、です。
一番避けた方が良いのは、決まった教材を、ただ問いてもらうだけの指導です。
もちろん、それを使う意図・妥当性があれば良いですが、それもなく、
ただ決まった問題を解くだけの先生でしたら、慎重に判断された方が良いと思います。
ここでは、私が知ってる家庭教師(発達障害の専門コース)を紹介します。
オンラインもありますので、ネット環境があれば、どこからでも受講可能になります。
実際の先生による無料体験も実施中になります。
タブレット学習
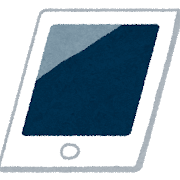
すぐに始められて、費用も抑えたいという方には、タブレット学習をお勧めします。
作文も、国語の他の問題と関連がありますので、学習全般を網羅できるタブレット学習は、効果的です。
教科書・参考書では、想像するのが難しい問題でも、
アニメーション・動画など、”発達障害の子が理解しやすい教え方” がいくつもあります。
メリット、デメリットなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【発達障害の子向け】タブレット学習~ADHD/自閉症の子に合う4つの特徴~
1つの選択肢として、参考になれば幸いです。
通信講座
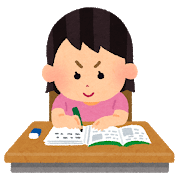
添削をしてもらい、学んでいくスタイルになります。一番気軽に取り組める方法になります。
詳しくは、ブンブンどりむ(小学生向け)をご覧ください。
【作文が苦手 ADHDの子向け対策】まとめ

記事のポイントになります。
✅ADHDの子の
「作文が書けない理由」
・何を書いていいか、分からない
・出来事を忘れてる
✅作文対策~短期~
・基本的な型を覚える
・お手本を見ながら、自分で書く
・何も見ずに、自分で書く
✅作文対策~長期~
・語彙力を増やす
・よく使うフレーズを覚える
・”1日感想” でアウトプットする
✅それでも
「作文が書けない」場合
・民間療育
・家庭教師
・タブレット学習
・通信講座
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】
【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法









































[…] 【作文が苦手】ADHDの子が書ける様になる!作文の6つの方法 […]
[…] 【作文が苦手】ADHDの子が書ける様になる!作文の6つの方法 […]