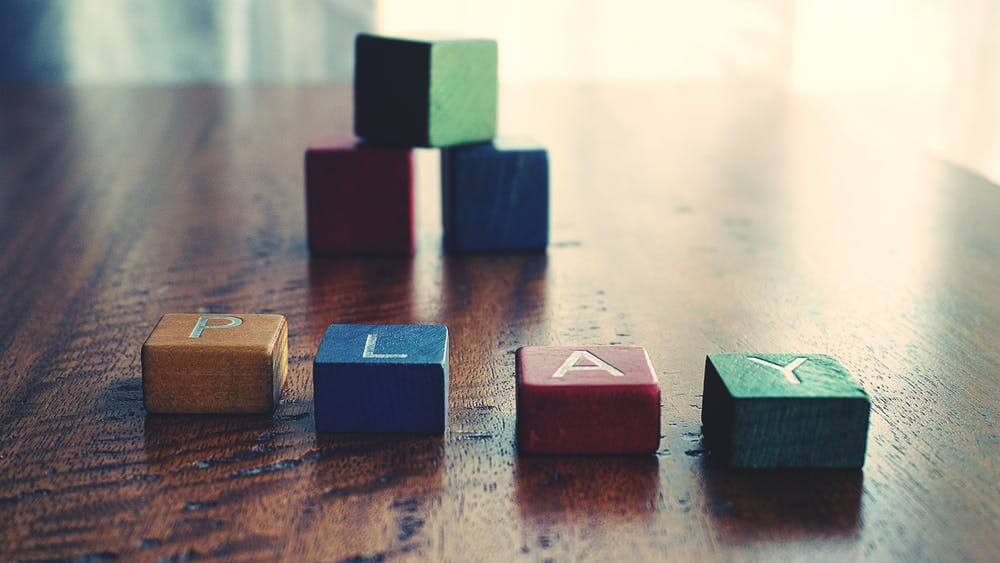

3歳の子の言葉の発達が心配な方「3歳の子のオウム返しは普通?それとも障害がある?言葉の発達が少し心配」
お子さんの言葉にオウム返しが多かったり、言葉の成長がゆっくりですと、心配になる方も多いと思います。
近年、お子さんの言葉の発達で悩まれている方が、増えています。
そこで本記事では「オウム返しが多い3歳の子への関わり方」をまとめてみました。
この記事の執筆者の私は、発達相談を15年以上しており、現在も言葉の発達相談に携わってます。
オウム返しは、自閉傾向がある子によく見られますが、3歳の健常児にも見られます。
そこを踏まえ、情報をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
オウム返しとは~3歳の健常児にもある~

「オウム返し」とは、言われた言葉を「そのまま真似して言い返す」ことです。
例えば、「おはよう」と言ったら「おはよう」と返してくれます。でも「ただいま」と言ったら「おかえりなさい」とは言いません(ただいま、と返します)。
真似をするだけで、会話自体は成立していません。この「オウム返し」は、自閉傾向のある子によくみられます。
ただ「オウム返しが出た=何か障害がある」というわけではありません。
ポイントは、「オウム返しばかりで、会話が成立していないか」になります。
オウム返しが多少多くても、会話自体が成立していれば、様子を見る形でも良いと思います。
✅オウム返しの「1つの原因」~自閉傾向がある子の場合~

自閉スペクトラム症の特徴が関係しています。その1つの特徴として、「目に見えないものを想像/理解する」の苦手さがあります。
会話とは、相手の質問の意図、気持ち/状況など、目に見えないものを考えて、伝えることです。
言葉の意図が理解しづらいと、聞いた言葉をオウム返ししやすくなったり、言葉の発達自体がゆっくりな傾向であったりします。
自閉スペクトラム症の詳しい特徴については、【自閉スペクトラム症】4つの特徴/7つの接し方をご覧ください。
✅オウム返しの「考え方」
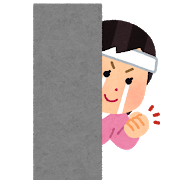
ここまで読むと、「オウム返し」は良くないんだ…と思われる方も多いかも知れません。
ただオウム返しは、立派な言葉の成長です。
オウム返しとは、言葉のマネ(模倣)です。言葉に限らずですが、学ぶことは全て『真似』から始まります。
真似ができなければ、何も学べません。オウム返しができる=言葉を覚える準備ができたということです。
お子さんの1つの成長として捉え、「得意なマネ」を活かし、会話に繋げる関わりをしていくことが大切になります。
言葉を増やす関わり方~オウム返しが多い3歳児~

オウム返しが多い、お子さんの言葉を増やすポイントは、2つあります。
①:オウム返しの前に、親が「正しい言葉」を言う
②:「視覚ヒント」「場面」と繋げて発する機会を作る
オウム返しの前に、親が正しい言葉を言う
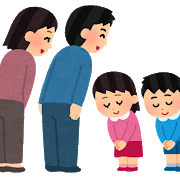
「オウム返し=マネが上手」ですので、この得意なマネを活かします。オウム返しは出る前に、「正しい言葉」を親が先に言うのです。
親が帰ってきた場面の、具体例で見ていきましょう。
~関わりを工夫しない例~
親:「ただいま」
↓
子:「ただいま」
~関わりを工夫した例~
親:「ただいま」
↓
親:「おかえりなさい(子供にオウム返しされる前に言う!)」
↓
子:「おかえりなさい」
もう1つ見ていきます。
~関わりを工夫しない例~
大人:「何才ですか?」
↓
子供:「何才ですか?」
~関わりを工夫した例~
大人:「何才ですか?」
↓
大人:「3歳です(子供にオウム返しされる前に言う!)」
↓
子供:「3歳です」
2つの具体例のように、お子さんのオウム返しが出る前に、親が正しい言葉を言うことが大切になります。
スピード勝負なので、事前に意識しておかないと、「先に子供に言われちゃった…(オウム返しを)」となってしまいます。
私も慣れないうちは、間に合わないことが何回もありました…。
ただお子さんの様子を観察していると、予想がつくようになりますので、回数をこなし慣れることをお勧めしています。
またお子さんが正しい言葉を言えたら、褒めましょう。正しい言葉が言えれば、自信になり、次第に自分から言えるようになっていきます。
視覚ヒント/場面と繋げ発する機会を作る
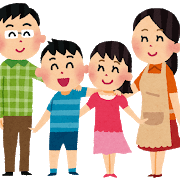
「視覚的ヒント」や「その場面」になった時に、言葉の促しをすることです。
具体例を見ていきましょう。
~例~
大人:「今日の朝は、なに食べたの?(直後に複数の絵カードを見せる)」
↓
子供:「クロワッサン(複数の絵カードから食べたものを選びながら)」
↓
大人:「クロワッサン食べたんだね!教えてくれてありがとう~!」
このように、今何を聞かれているのか分かるよう、絵カードなどの視覚的ヒントがあると、会話のキャッチボールに繋がりやすくなります。
また、視覚ヒントの代わりに、場面を活かす方法もあります。
例えば、外出先からお子さんと一緒に帰宅した時、「ただいま」と一緒に言うよう促しをすることです。
その場面になった瞬間、近くの大人が適切な言葉を発して見本を見せたり、一緒に言うよう促しをすると、場面と言葉が繋がり、日常会話に活かしやすくなります(帰宅する=ただいまと言う)。
こちらの関わりも、オウム返しが出る前にすることが、大切になります。
少し機械的な関わりに感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ自閉傾向のお子さんは、パターン化して覚えることが得意な場合が多いため、その子の良さを活かせる関わり方になります。
お子さんが日常生活で活かせるものを身につけていくことが、一番大切だと思います。
✅言い直しさせない/否定しない

オウム返しに関わらずですが、「言い直しさせる/否定する」は避けましょう。
理由は、言葉を発するモチベーションが下がり、発語自体の頻度が減ることに繋がるためです。
例えば、私達も新しく英会話を始めたときに、発音する度に「言い直し/否定」ばかりされたら、やる気がなくなってしまいますよね。
百歩譲って大人の私たちは、「失敗の繰り返しが身になる」など見通しがあるから、まだ割り切れるかもしれません。
ただ自閉スペクトラム症の子は別です。目の前のメリットが重要になります。
言葉が言えたことで、親が褒めてくれる/要求が通る、など嬉しいことがあるから、次の発語へと繋がるのです。
多くの方が、ここを間違って関わってしまうことが多いです。せっかく頑張っているのに、逆効果になってしまうのは、とても勿体ないです。
【関連記事】
【3歳のオウム返し 健常児にもある?】まとめ

記事のポイントになります。
✅オウム返しとは
・3歳健常児にもある
・会話への準備が整った状態
・言葉のマネが上手にできる状態
✅言葉を増やす関わり方
~オウム返しが多い3歳児~
・オウム返し前に正しい言葉を教える
・否定しない
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】









































[…] 自閉症スペクトラムの子供のオウム返しとは【会話に繋げる2つの方法】 […]
[…] 【健常児にもある?】子どものオウム返しとは。言葉を増やす2つの関わりとは […]
[…] […]
[…] 【健常児にもある?】子どものオウム返しとは。言葉を増やす2つの関わり方 […]