
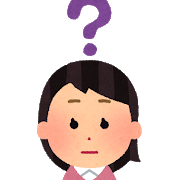
自閉症の子のおもちゃ選びで悩まれてる方「自閉症の子が好きなおもちゃってどんなもの?自閉症の子に人気なおもちゃが知りたい」
「子どもがおもちゃに興味がなくて、どんなおもちゃを選べばいいか分からない…」
「遊ぶだけじゃなくて、少しでも子どもの成長(発達を促す)になるおもちゃが知りたい…」
お子さんに合ったおもちゃ選びは、とっても難しいですよね。
この記事を執筆している私は、療育支援員を15年以上しており、発達障害のお子さん・親御さんの支援に携わってきました。
その支援経験を元にお伝えします。参考になれば幸いです。
※現在は、自閉症ではなく「自閉スペクトラム症(ASD)」と総称されています。本記事では、説明の都合で「自閉症」と表現しています
目次
- 1 自閉症の子に人気「夢中になるおもちゃ26選」
- 1.1 ①:感覚ストレスボール
- 1.2 ②:スクイーズ
- 1.3 ③:ストリング フィジェットトイ
- 1.4 ④:TANGLE
- 1.5 ⑤:知覚ウォータービーズ
- 1.6 ⑥:スパイキー フィジェットトイ
- 1.7 ⑦:マグネットボール
- 1.8 ⑧:粘土
- 1.9 ⑨:チューイー・チューブ
- 1.10 ⑩:スパイクボール
- 1.11 ⑪:3Dピンアート
- 1.12 ⑫:バランスボール
- 1.13 ⑬:液体オイル
- 1.14 ⑭:プッシュポップ
- 1.15 ⑮:ひもとおし1
- 1.16 ⑯:チップひもとおし2
- 1.17 ⑰:レインボー ボール
- 1.18 ⑱:円柱さし
- 1.19 ⑲:○×ピンポンブー
- 1.20 ⑳:シール
- 1.21 ㉑:すきなのどっち?
- 1.22 ㉒: マグネットブロック
- 1.23 ㉓:スパンコール
- 1.24 ㉔:バランスボール
- 1.25 ㉕: トランポリン
- 1.26 ㉖:バランスストーン
- 2 自閉症の子が夢中になる「おもちゃの選び方」
- 3 子どもの成長に繋がる「おもちゃの遊び方」
- 4 【自閉症の子が夢中 人気おもちゃ26選】まとめ
自閉症の子に人気「夢中になるおもちゃ26選」

自閉症の子に「おすすめおもちゃ」を、26種類お伝えします。
お子さんが興味をもちそうか、おもちゃの特徴も合わせて、一緒にご覧ください。
①:感覚ストレスボール
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚/固有受容覚) - ストレス発散になる
- 外で落ち着く時に使える
- 握る/ねじる/投げるの練習になる
※固有受容覚:筋力や力の加減を感じる感覚
②:スクイーズ
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚/固有受容覚) - ストレス発散になる
- 落ち着く時に使える
- 微細運動ができる
(握る/ねじる/投げる)
③:ストリング フィジェットトイ
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚) - ストレス発散になる
- 落ち着く時に使える
④:TANGLE
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚) - ストレス発散になる
- 落ち着く時に使える
⑤:知覚ウォータービーズ
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚/固有受容覚) - 外での待ち場面に使える
- ストレス/不安の軽減ができる
⑥:スパイキー フィジェットトイ
- 水洗いOK
- 感覚遊び(触覚)ができる
- 柔らかい素材で安全
- 握る/ねじる/投げる/踏む/さする/触るの練習になる
⑦:マグネットボール
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚/固有受容覚) - 誤飲ない子向け
⑧:粘土
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚/固有受容覚) - 色の概念理解が促せる
(混ぜるなど)
⑨:チューイー・チューブ
- 乳幼児向け
- 口まわりの筋力、舌の運動になる
- 口まわりの筋力が弱く、ヨダレが垂れやすい子向き
⑩:スパイクボール
- 口周りの運動(口腔運動)ができる
- 口周りの感覚遊びができる
(触覚/固有受容覚) - 口周りの筋力が弱く、ヨダレが垂れやすい子向き
⑪:3Dピンアート
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚/聴覚) - 独特の感触/音が楽しめる
⑫:バランスボール
- 感覚(視覚)遊びができる
- 落ち着いて過ごしやすい
⑬:液体オイル
- 感覚遊び(視覚)ができる
- 自閉傾向の子で好きな子が多い
⑭:プッシュポップ
- 不安を減らす効果
- パズルなど知育遊びもできる
- 押す/握る/ブロック遊びができる
⑮:ひもとおし1
- 目と手の協調運動ができる
- 名詞/カテゴリー概念が学べる
⑯:チップひもとおし2
- 微細運動の練習になる
(つまむ/穴に通す/ひっぱる) - 集中力がつく
(穴を注視する)
⑰:レインボー ボール
- 感覚遊びができる
(触覚/固有受容覚) - 外での待ち時間などで使える
- 感覚遊び(触覚)~10色以上の色のマッチングの練習ができる
⑱:円柱さし
- 感覚過敏の子も使いやすい
(手触りが滑らか) - 数、大/小の概念理解が促せる
- 手先が不器用な子向け
(掴みやすい作り)
⑲:○×ピンポンブー
- 感覚遊びができる
(聴覚/固有受容覚) - この音が好きな自閉症の子が多い
- 良い/悪いを伝える時に活用できる
⑳:シール
- 感覚遊びができる
(視覚/触覚/固有受容覚) - 微細運動の練習になる
(つまむ/はがす/つける) - 場所選ばずできる
(シール貼り)
㉑:すきなのどっち?
- 自己選択の練習になる
(選択する) - 自己決定の練習になる
(自分で決める) - 自己表出をの練習になる
(自分の意志を伝える)
【関連記事】
㉒: マグネットブロック
- 目で変化を楽しめる
(くっつく/外れる) - 微細運動になる
(つける/外す) - 組み立てやすい
(手先が不器用でも) - ブロック遊びの導入向き
(興味のキッカケになる)
㉓:スパンコール
- 手触り、目で見て楽しめる
㉔:バランスボール
- 平衡感覚が刺激できる
- 体幹が鍛えられる
㉕: トランポリン
- 体幹が鍛えられる
- 家庭でもストレス発散ができる
- 全身の感覚が満たせる(感覚探求)
- 家庭内で落ち着きやすくなる
※感覚が満たされる為
㉖:バランスストーン
- 感覚遊びができる
(触覚/固有受容覚/平衡感覚) - ソフト素材で安全
- バランス感覚が養える
- 色の概念理解も促せる
※平衡感覚=バランス感覚、体の傾きを感じる感覚
【合わせて読みたい記事】
自閉症の子が夢中になる「おもちゃの選び方」

ここでは、自閉症の子のおもちゃの「選び方」を見ていきたいと思います。
「選び方」を説明する理由は、この記事でおもちゃが把握できたとしても、それは一時的なことになるためです。
お子さんは成長し、「興味がある/必要になるおもちゃ」が変わっていきます。
そんなときにおもちゃの選び方を知らないと、先々親御さんもお子さんも困ってしまうためです。
選び方(本質)が理解できれば、今後のおもちゃで困ることは、かなり減るはずです。
自閉症の子には、特性があります。
この特性を理解しないとおもちゃを買っても「遊んでくれない!どのおもちゃが良いのか分からない!」という状態になりやすいです。
特性を把握して、お子さんに合う条件のおもちゃが見つけられたら良いと思います。
①:感覚が「満たせる」
②:「感覚で」楽しめる
(ex.見る・聞く・触る・揺れる)
③:「細かい操作」がない
④:よく触ってる「素材」
感覚が満たせる

自閉症の子は、感覚が過敏/鈍い子が多いです。療育では「感覚過敏/感覚鈍麻」といわれるものです。
感覚の過敏さがある子には、苦手な感覚(刺激)を極力避けることが大切になります。
おもちゃ選びにおいては、苦手なおもちゃを買わなければ問題ありません。
感覚の鈍さがあると、本来満たされるはずの感覚が、”鈍さ” ゆえに満たされにくい状態が多いです。
例えば、おもちゃの動く電車のタイヤをじっと見続けたり、グルグル回ったり、
常にウロウロして動き回ってる行動も、感覚を満たすための、典型的な行動の可能性が高いです。
この感覚が満たせるということが、自閉症の子の成長となり、その子の楽しみに繋がっていきます。
お子さんの『好きな感覚を満たせる』おもちゃを探すことが大切になります。
【関連記事】
感覚で楽しめる

特性上、目に見えない物を理解したり、関連付けたりすることが難しいです。
想像力が必要になる “見立て/ごっこ遊び” を前提にしたおもちゃ選びは、好む子が多くありません(お子さんが興味を示してるなら問題ありません)。
感覚的な遊びを楽しむ子でしたら
・動きを見る
・音を聞く
・触り心地
・体感
(ex.揺れ/回転/スピード)
などで楽しめるおもちゃが好まれやすいです。
細かい操作がない

自閉症の子は、手先が不器用・全身運動が苦手なことが多いです。
具体的には…
・ジャンプが苦手
・筆圧が弱い/強すぎる
・スプーン/フォーク/お箸が苦手
・走り方がぎこちない/よく転ぶ
・ボールをまっすぐ投げられない
など、様々あります。
細かい操作があるおもちゃですと、お子さんがおもちゃで楽しむことが難しくなりやすい為、シンプルに遊べるおもちゃが望ましいです。
もちろん、おもちゃの遊び方はそれぞれですので、結果的にお子さんが楽しめていれば、どんなおもちゃでも大丈夫です。
よく触ってる素材

お子さんが普段よく触ってるもの(素材)を確認します。
・ザラザラしたもの
・フワフワしたもの
・グニャグニャしたもの
など、お子さんが好む素材でできたおもちゃが良いです。
自宅、外、児童館、お店などで『お子さんがよく触るモノ見つける』が、おすすめになります。
【合わせて読みたい記事】
子どもの成長に繋がる「おもちゃの遊び方」

ここでは、成長に繋がるおもちゃの「活用法」を見ていきたいと思います。
親御さんがおもちゃを買うのは…
・子どもに楽しんでほしい
・子どもに成長してほしい
という想いからくるものが、ほとんどだと思います。
お子さんが楽しめるのはもちろん、遊びの中で、成長にも繋げていきたいですよね。
ここでは、私が実際に療育支援で使用して、効果的だった4つの活用法をお伝えします。
①:「感覚」をたくさん使う
②:「目で理解できる」遊びを増やす
③:「アイコンタクト」→おもちゃを渡す
④:「大人から」おもちゃを渡す
感覚をたくさん使う

自閉症の子は、個人差がありますが、発達がゆっくりな傾向があります。
特に感覚遊びを好む自閉症の子の場合、成長の後押しをする為には、『感覚遊び』が大切になってきます。
本来なら、時間をとって「感覚遊びの時間」が毎日とれるといいのですが、
育児/家事/仕事など…大忙しのママ/パパには、なかなか現実的ではありません。
生活全体のバランスを考えると、
『日常生活の中』に、いかに感覚遊びを入れられるかが、大切になります。
例えば、以下のような工夫方法があります。
・散歩は凹凸のある芝生、傾斜ある道でする
・おもちゃ以外の物に触れる機会を作る
・夏は水遊び、冬はお風呂で遊ぶ時間を作る
・公園の遊具で遊ぶ
(一人でできなくて可)
・家でボールプール、トランポリンを取り入れる
・粘土、スライム、お絵描きなど、感覚遊びを取り入れる
このように、日常生活の中で、『過ごす場所・使う物・遊び方』を工夫し、『感覚を使う』機会を、増やすことが大切になります。
【合わせて読みたい記事】
目で理解できる遊びを増やす

自閉症の子は、「目に見えないもの」を理解することが、苦手なことが多いです。
そのため、遊びも「目で変化を感じつつ楽しめるおもちゃ」が良いです。
例えば…
・くるくるチャイム
・自動販売機のおもちゃ
・ぺぐさしのおもちゃ
・積み木崩し(壊すことがメイン)
※プットイン=入れる
全て、自分の行動(物を入れる→物が入ったor違う物が出てきた)によって、結果が目で確認できるおもちゃです。
その子が行動を起こしたことで、「光る・音が出る・物が動く」など、変化を感じられるのがポイントになります。
アイコンタクト→おもちゃを渡す

ここでいう「アイコンタクト」とは、目を合わせるという意味です。
目を合わすことが難しい子は、おもちゃを使って、コミュニケーションスキルを上げられる可能性があります。
自閉症の子は、アイコンタクトをとることが、苦手な子が多いです。
大きな理由は、他者意識が低い・人への関心が薄いためです。アイコンタクトは、コミュニケーションの入口になります。
よく言葉が遅れている=発語の訓練、と思われがちですが、そもそもアイコンタクトがとれていないと、
言葉を覚えても、人に向けて使うことができません。つまり、コミュニケーションとして活かすことが、難しいです。
そのため療育の現場では、アイコンタクトが未定着の子は『アイコンタクトの獲得から始める』ことが多いです。
おもちゃを使って、アイコンタクトを促せると、お子さんのコミュニケーションスキルの土台を、作ることができます。
大好きなおもちゃであれば、お子さんからの要求がかなり出やすい為、コミュニケーションスキルを上げるチャンスです。
とは言っても、具体的に何をすればいいのか、難しいですよね。
ここからは、具体的なやりとりの流れを見ていきましょう。
親御さんがお子さんの好きなおもちゃを持って、お子さんの目の前にいる場面を作ります。
おもちゃを持っている(親)
↓
おもちゃを取ろうとする(子)
↓
おもちゃを親の顔に近づけ、子供と目が合うようにする(親)
↓
親の目を見る(子)
↓
おもちゃを渡す(親)
※一瞬でも目が合えば、おもちゃを渡してOKです。
あくまで参考例ですが、大事なことは「親御さんと目が合ったら、お子さんにおもちゃを渡す」を徹底することがポイントになります。
これを1日5~10回程度、毎日続けていければ、個人差はありますが、目が合う回数に変化が見えてくると思います。
もし増えない場合は、関わり方がズレているか、違う要因が考えられます。
大人からおもちゃを渡す

アイコンタクト同様に、ここでは、おもちゃを使って「他者意識」に繋げる関わりについて、お伝えします。
「他者意識」とは、人への興味です。『人への興味』は、コミュニケーションの原動力です。
“人に伝えたいという欲求” があって、初めてコミュニケーションは成り立ちます。
そのため、人と関わったことで、その子にとってのメリット(楽しかったと感じる)を作っていく必要があります。
メリット(人と関わったことで)が増えれば、少しずつ人への興味が湧きます。
自閉症の子は、一人遊びが好きな子が多いです。特性上、興味の幅がせまいため、おもちゃがあれば、ずっと一人で過ごせることも珍しくありません。
ただ、それですと、将来的にお子さんが困ってしまう可能性があります。大好きなおもちゃを使って、強い要求を活かせれば、他者意識を上げることができます。
ここでは、お子さんが自動販売機のおもちゃで遊ぶときの具体例でお伝えします。
親御さんは、「お子さんが持ってるコイン1枚以外」を全部持っている状態で始めます。
自動販売機(本体+コイン1枚だけ)を渡す(親)
↓
コイン1枚入れる(子)
↓
コインを1枚手渡しする(親)
↓
コイン1枚入れる(子)
↓
繰り返す
※コインがなくなったら、すぐに親が全部回収し、1枚ずつ渡す
※余裕がある場合は、1枚渡すときに、アイコンタクトを促す
1人で成立する遊びも、他者が入ることで、他者を意識せざるえない環境を作ります。
お子さんが流れを理解してきたら、親御さんは手の上でコインを置いて待ち、お子さんに取ってもらうのも良いでしょう。
また親御さんの手の位置をズラして、1回1回親御さんの手の位置を確認する機会を作ることで、効果が高まります。
✅「診断名=〇〇」ではない
自閉症(スペクトラム)と診断されたから、絶対○○ということはありません。
私は、これまで多くの発達障害の子を見てきましたが、同じ診断名でも、同じ特徴の子は1人もいませんでした。
例えば、自閉症(スペクトラム)と言っても、「こだわりがある・ない」や「言葉が出る/出ない」など、全く違います。
あくまで、お子さんに合った関わりを検討する、1つの材料だと思うことが大切になります。
【合わせて読みたい記事】
【自閉症の子が夢中 人気おもちゃ26選】まとめ

記事のポイントになります。
✅自閉症の子に人気
「夢中になるおもちゃ26選」
・感覚ストレスボール
・スクイーズ
・ストリング フィジェットトイ
・TANGLE
・知覚ウォータービーズ
・スパイキー フィジェットトイ
・マグネットボール
・粘土
・チューイー・チューブ
・スパイクボール
・3Dピンアート
・バランスボール
・液体オイル
・プッシュポップ
・ひもとおし1
・ひもとおし2
・レインボー ボール
・円柱さし
・○×ピンポンブー
・シール
・すきなのどっち?
・マグネットブロック
・スパンコール
・バランスボール
・トランポリン
・バランスストーン
✅自閉症の子が夢中になる
「おもちゃの選び方」
・感覚を満たせる
・感覚で楽しめる
(ex.見る/聞く/触る/揺れる)
・細かい操作がない
・よく触ってる素材
✅子どもの成長に繋がる
「おもちゃの遊び方」
・感覚をたくさん使う
・目で理解できる遊びを増やす
・アイコンタクト→おもちゃを渡す
・大人からおもちゃを渡す
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【合わせて読みたい記事】
【発達障害の子向け】タブレット学習~ADHD/自閉症の子に合う4つの特徴~









































[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選21選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選21選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選21選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選21選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】自閉症の子が遊べるおもちゃ【厳選23選】 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】自閉症の子が遊べるおもちゃ【厳選23選】 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】自閉症の子が遊べるおもちゃ【厳選26選】 […]
[…] 自閉症スペクトラムの子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】自閉症の子が遊べるおもちゃ 26選 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】自閉症の子が遊べるおもちゃ【厳選26選】 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】自閉症の子が遊べるおもちゃ【厳選26選】 […]
[…] 【療育支援員がおすすめ】自閉症の子が遊べるおもちゃ【厳選26選】 […]
[…] 自閉スペクトラム症の子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]
[…] 自閉スペクトラム症の子供にオススメなおもちゃ【厳選19選】 […]