

子どもの不登校で悩まれてる方「別室登校はいつでもするもの?別室登校してる子の今後はどうなるの?どんな進路に進むのか事例も知りたい」
別室登校をしてるお子さんがいると、
「いつまで別室登校すればいいんだろう…」
「学校に行けるようになるのかな…」
「進路はどうなるんだろう…」
など、お子さんはもちろん、親御さんも不安な気持ちで、いっぱいになりますよね。
そこで今回は、別室登校で大切なこと・別室登校の子で多い事例をお伝えしていきたいと思います。
この記事を執筆している私は、療育/相談支援を15年以上しています。不登校(完全不登校/別室登校)のお子さんの支援も数多くしてきました。
その支援経験を通して、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
※本記事はプロモーションを含みます
別室登校の「3つのパターン」

別室登校とは、教室以外の場所に通うことです。
お子さんにとっては、教室以外で “安心できる場所の確保” という意味合いになります。
別室登校には個人差があり、様々なパターンがあります。
ここでは、よくある3つのパターンをお伝えします。
①:「保健室(教室以外の部屋)」に登校
②:「放課後に」教室に登校
③:「課題を取りに」担任に会いにいく
お子さんによって、複数重なっていることもあります。
保健室(教室以外の場所)に登校

“教室以外の場所”に登校するパターンになります。
1番多いのは保健室ですが、他にも校長室や会議室の場合もあります。
ここは、学校・校長先生の意向によって、大きく変わる部分になります。
放課後に教室に登校

クラスメイトがいない放課後に、登校するパターンになります。
お子さん本人が「同級生に会いたくないけど、学校には行きたい」という場合が多いです。
教室で担任と話をするなどして、時間を過ごします(親御さんが付きそう形もあり)。
こちらは、担任の先生に相談し、協力を得る必要があります。
丁寧な先生は協力してくれますが、中には協力を得るのが難しい先生も少なくありません。
課題を取りに登校する
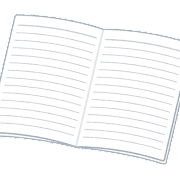
宿題や課題を取りに、登校するパターンになります。
放課後が1番多いですが、中には課題を受け取って、すぐ早退する子もいます。
「学校で過ごすことは難しいけど、学習が遅れないよう頑張りたい子」 に多いです。
別室登校で「3つの大事なこと」

お子さん本人にとって、別室登校で「大事な3つのこと」をお伝えします。
①:「本人のポジティブな経験」を目的にする
②:「本人のペース」に合わせる
③:「安心できる繋がり」を作る
本人のポジティブな経験を目的にする

不登校問題でよくあるのが「学校に行く」が目的になってしまうこと。
登校したその先に「本人が何を感じるのか」の視点がないと、
・数日登校できたけど、すぐ行けなくなった
・登校できたけど、本人が嫌な思いをした
(余計学校に行きたくなくなった)
など、ネガティブなことに繋がります。
大切なのは、学校で過ごす時間の中で本人が、
「○○が楽しかった」
「○○ができた」
「意外と、○○嫌じゃなかった」
とポジティブな気持ちを実感できることです。
この実感が、学校や他の場所に行くステップ(土台)となります。
(外と繋がりが持てる様になる)
本人のペースに合わせる

不登校の子は、気持ちの波が大きい子が多いです。
前日までは「学校に行く!」と言っていても、当日の朝になったら「学校行かない…」となったり、
数日or数週間学校に行けていて、このまま続くと思ったけど、次第に学校を休むようになったり…。
「昨日は、学校行くって言ってたのに」と思いたくなりますよね。
ただここで、本人のペース(コンディション)に合わせることで、
「行きたくなかったのに、やりたくなかったのに」という、本人の負の経験を減らすことに繋げられます。
負の経験は「あの時、嫌な思いをしたから、もうやらない」という、子ども本人の行動にブレーキをかけます。
負の経験を増やさない為にも、本人のペースに合わせることが大切になります。
安心できる繋がりを作る
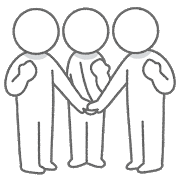
本人の “安心できる繋がり” を作ることが、大切になります。
例えば、
・家族と話す
・好きなことをする
・友達に会う
・好きな習い事に通う
など、本人が安心感を感じられる/心が満たされる繋がりを持つことです。
この繋がりが心を満たし、次第に本人の気持ちと行動が外へ向いていきます。
例えば、学校で過ごす時間が増えたり、家族以外の人と話す時間が増えたりなどの変化です。
【関連記事】
親がしてあげたい「3つのこと」

親がしてあげたい「3つのこと」をお伝えします。
①:「本人の意思」を尊重する
②:「本人のコンディション」を確認する
③:家庭と学校で「共通認識」をもつ
本人の意思を尊重する
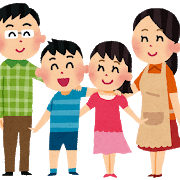
本人に選んでもらったり、意思を確認する機会を作っていきます。
本人に決めてもらうのが1番、本人の負の経験を増やしづらいためです。
本人が決めることが難しい時は、選択肢を伝えて、選んでもらう形でも大丈夫です。
本人のコンディションを確認する
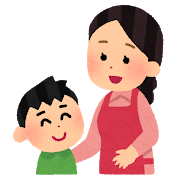
不登校の子は、無理をしたり、自分の体の状態に気付いていない場合が少なくありません。
登校をして、帰ってきたら疲れ切っている/些細なことで苛つく・翌日からしばらく学校を休む、など反動が出ることが多いです。
また明らかに負担が大きいことでも「大丈夫」と言うこともあります(家族に心配を掛けない為の本人の気遣いの場合もあります)。
そのため、本人に具体的な指標で、コンディションを教えてもらうことが大切になります。
例えば、10段階(10が1番調子が良い)で伝えてもらう方法になります。
「今日は2(調子が悪い)」「今日は8(調子が良い)」など、コンディションの把握ができれば、表現は自由です。
他にも、天気(晴れ/曇/雨など)で教えてもらう方法もあります。
本人も家族も把握しやすい指標があると、お互いコンディションが把握しやすくなり、
本人の調子に合った適切な判断ができるようになります。
家庭と学校で共通認識をもつ

家庭と学校で、本人にどう向き合うかの共通認識のすり合わせをします。
例えば、家庭では本人のペースに合わせる考えでも、
学校側が「とりあえず学校に来ましょう」という考えであると、本人が混乱したり、プレッシャーになってしまいます。
「本人が登校したいときに保健室登校する」「周りから学校に行くことを求めない」など、
“本人に向き合う上での軸” を固めていきます。
この軸があると、本人も安心し、負担も軽くなっていきます。
別室登校後の「3つの事例」

ここでは、別室登校後の「3つの事例」をお伝えします。
別室登校⇨登校
別室登校が安定してできるようになり、登校に繋がるパターンになります。
登校するのが、完全に安定するケースは多くないですが、
一定期間を別室登校することで、完全不登校を避けながら学校に繋がれる事例は、そこまで珍しくありません。
別室登校⇨そのまま卒業
別室登校しながら、そのまま卒業されるケースになります。
ただ学習面や進路など、事前に準備をしている(する必要がある)ケースが多いです。
自宅学習が上手くいったケースは、子ども本人が望む進路に、そのまま進める事例もあります。
自宅学習の詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください。
別室登校⇨フリースクール
フリースクールに繋がるケースも増えています。
フリースクールは数が少なく、現実的に通える子は限られているのですが、
最近では、オンラインで繋がれる学校も増えていて、選択肢が広がっています。
ここでは、参考程度に2つのフリースクールを紹介します。
SOZOWスクール
クラスジャパン小中学園
お子さんが興味を持つようでしたら、一緒にHPを見たり、資料を取り寄せることをお勧めします。
【別室登校は、いつまでするもの?】まとめ

記事のポイントになります。
✅別室登校の
「3つのパターン」
・保健室(教室以外の場所)に登校
・放課後に教室に登校
・課題を取りに登校
✅別室登校で
「3つの大事なこと」~本人にとって~
・本人のポジティブな経験
・本人のペースに合わせる
・安心できる繋がりを作る
✅親がしてあげたい
「3つのこと」
・本人の意思を尊重する
・本人のコンディションを確認する
・家庭と学校で共通認識をもつ
・学習フォローの機会を作る
✅別室登校後の
「3つの事例」
・別室登校⇨登校
・別室登校⇨そのまま卒業
・別室登校⇨フリースクールor療育
✅別室登校の子が
「備えたいコト」
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合う学習法
・レベルに合う学習単元
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【不登校の子は勉強追いつくの?】学習支援でも実践してる6つの勉強法
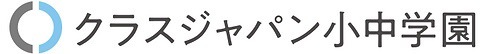









































[…] 【別室登校は、いつまでするもの?】大切な7つのポイント […]