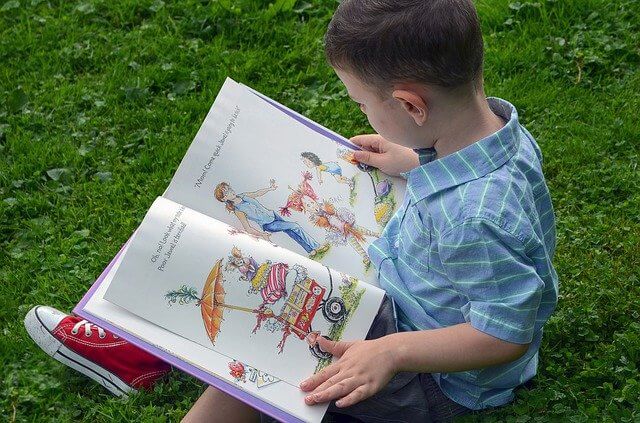

不登校の子の今後が心配な方「小学校低学年の子は、その後どうなるの?学校行ける様になる?受験や人間関係は大丈夫?他の子がその後どうなってるのか知りたい」
現在、不登校の数は増え続け、社会問題にも発展しています。
身近でも、不登校の子・学校を休みがちな子がいるのは、珍しくありません。
特に、小学校低学年の不登校の子は、見過ごされやすく、思春期に入ると引きこもりや鬱など、生活により大きな支障が出る可能性が高まります。
一方で、不登校の子のその後については、情報は少なく「うちの子は、これからどうなるの..」と不安になる方も多いと思います。
特に、小学校低学年の子は、周囲の大人の「気付き/対応」が遅れることも多く、事例自体、そこまでオープンにはなっていません。
そこで本記事では「不登校の低学年の事例/関わり方/注意点」に関する情報をお伝えしたいと思います。
私は、不登校・療育支援の相談/支援員を15年以上しており、
これまで不登校のお子さん、親御さんの支援に携わってきました。
支援をする中で大切だと感じた点を、事例を通してまとめてます。
本記事が、参考になれば幸いです。
目次
不登校低学年の子の「その後」~5つの事例~

不登校低学年の子の「その後」に関する5つの事例を紹介します。
私が支援する中で、実際に携わってきたケースになります。
①②が最も多く、次に③、そして④⑤と減っていきます。
①:学年/担任が変わり「復帰する」
②:不登校が続き「支援に繋がる」
③:「フリースクール」に通う
④:「引っ越し/転校」する
⑤:学校に通わず「中学受験」を目指す
学年/担任が変わり復帰する

不登校の原因が『担任の先生/特定のクラスメイト』など、はっきりしてる場合になります。
先生、クラスが変わることで、不登校の原因が解消され、復帰できる様になります。
「先生が怖い」
「先生に怒られてばかり」
「嫌なことしてくる子がいる」
などの発言がある子は、不登校の原因が明確なため、原因が取り除かれると、復帰に繋がりやすい傾向があります。
ただ、中には本人の特性が関係してる場合もあり、先生/クラスが変わったとしても、途中で不登校に戻る子もいます。
不登校が続き 支援に繋がる

原因が分からず、不登校の状態が続いてる子になります。
本人は、
「よく分かんないけど行きたくない」
「朝になると頭が痛くなる」
「学校にいくとドキドキする」
など、言葉にできない不安やストレスを抱えています。原因が分からない以上、家庭で対策が打てず、最終的に支援に繋がります。
不登校の支援とは、民間療育、NPO法人が多いです。学校の代わりとなる居場所、家族以外との交流、そして本人の今後について、一緒に考える機会になります。
支援先によっては「居場所を作る」が目的の場合もあれば、「本人の考え方/捉え方を広げる(本人が生きやすくなる為)」もあります。
本人が安心して楽しく過ごせて、信頼できる人がいる支援先が大切になります。
フリースクールに通う

学校(在籍校)に行く意思がない場合は、フリースクールの選択肢があります。
また、学校側の理解/協力が得られない場合も、フリースクールを選ぶ場合もあります。
最近はフリースクールの数も増え、お子さんの選択肢は増えてます。
数が多い分、内容、費用などそれぞれ違いますので、1つ1つ確認する必要があります。
引っ越し/転校する

数は少ないですが、引っ越し/転校する子もいます。
「本人の特性に理解を示す学校」、「通級/支援級がある学校」などを選ぶ(在籍校にない場合)場合があります。
学校に通わず 中学受験を目指す
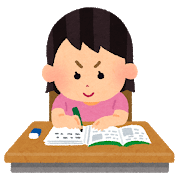
小学校高学年になると、「自宅学習+学習塾」で受験対策に注力する子がいます。
一律の教育ではなく、ある程度本人に合わせて指導してくれる様な、私立中学校を検討される方も少なくありません。
ただ、私立は学校によって、合う・合わないがハッキリ出やすい為、本人と一緒に見学する/本人の特性を学校に伝えておく必要があります。
実際に入学してから、本人に合わなかったというケースは少なくありません。
【関連記事】
【不登校の体験談】復帰した5つの事例~復帰に繋がった3つの共通点~
今、家族ができること~不登校低学年~

不登校低学年の子へ、「今」家族ができることは、5つあります。
①:「その子自身」を認める
②:「家=安心して過ごせる環境」にする
③:本人が「安心して楽しめるモノ」の確保
④:「今できてること」を見つける
(ほめる・共感する)
⑤:「支援先」に相談する
その子自身を認める

家族が、根底に持っておきたいスタンスになります。今の “その子自身” を受け止めることです。
不登校は、本人の特性と環境(学校)との間で、困りが生じています。本人に問題があるから、不登校というわけではありません。
『本人に問題がある』という視点ですと、本人の悪い所を “治す・改善する” という思考になり、本人にも伝わります。
本人の自己肯定感が下がり「どうせ自分なんて何もできない」と、自分の殻に閉じ籠もるようになります。状況は、悪化する一方になります。
「今の学校の環境は、本人にとっては辛いもの(辛く感じる子)なんだ」と、受け止めることが大切になります。
家=安心して過ごせる環境にする

不登校の子には、安心感が必要になります。安心と不安のバランスが崩れることで、不登校に繋がります。
不登校の多くの子は、学校での安心/不安のバランスが崩れてます。他の子と比べ、安心感が少なく、不安に感じてることが多いです。
そのため、まずは家を “安心できる場所” にする必要があります。すでに安心できる環境になってる家庭も多いと思います。
ただ、中には、『家族の関わり=ストレス』になってる場合もあります。
「明日は学校行くの?」
「何で学校行かないの?」
「学校行くって言ってたよね」
など、本人がストレス/プレッシャーを感じる機会が多いと、家で安心できず、心身を消耗していきます。
本人が安心して楽しめるモノの確保

本人が「これは好き!」「これやってると時間忘れちゃう!」のような、夢中になれるモノを見つけていきます。
アニメ、ゲーム、絵を描く、工作など、何でも大丈夫です。
大切なのは、本人が楽しめてる時間の確保になります。安心・楽しさを感じる機会がベースになり、不登校に向き合える状態に近づいていきます。
今できてることを見つける
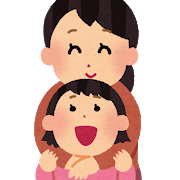
本人の “今できてること” を見つけ、声を掛けをします。
・部屋を片付けた
・朝◯時に起きた
・ドリルを1P解いた
・家の手伝いをした
また、本人の喜ぶポイントに合わせて、声かけを変えます。
・ほめる
(ex.◯◯できたね!すごい!)
・感謝を伝える
(ex.ありがとう、助かったよ)
・共感する
(ex.ドリル1P終わったんだね。これ難しいよね)
一般的には、高学年になるにつれ、感謝/共感の割合が高まる傾向があります。
支援先に相談する
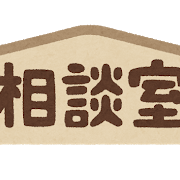
家での関わりに限界を感じたら、支援先に相談するのが良いです。
できれば限界を感じる前に、相談できるのが理想です。不登校の期間は、本人にとっては、自己肯定感が下がってる期間とも言えます。
不登校期間が短い方が、支援や家族の関わりの効果が出やすいです。支援先は、個別の民間療育で、本人に合わせて支援してくれる所が良いです。
放課後等デイサービスなどの福祉サービスもありますが、混み合っていたり、決まった先生が個別でずっとできるわけでない為、不登校の子には合いにくいことが多いと思います(先生が変わる、他の子がいるなど、本人の不安要素になる変化が多い⇨本人の負担になりやすい)
もし、居場所を作りたい!という場合は、不登校支援のNPO法人を探してみるのも、1つだと思います。
最終的には、本人が行きたいと思った所に繋がるのが、一番です。
「この先」家族ができること~不登校低学年~

不登校低学年の子へ「この先」家族ができることは、4つあります。
不登校の子は、状態によっては、しばらく休息が必要な場合もあります。
休息が必要かの判断基準は、【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点 をご覧ください。
もし、本人が自分以外に関心を示す様子があれば、こちらの関わりを参考にしていただければと思います。
①:「興味・関心を深める機会」を作る
②:「ポジティブ」に振り返る
③:「過去の自分と比較」の視点にする
④:「本人の特性」を言語化する
(周囲の理解を広げる為)
興味/関心を深める機会を作る

本人から「◯◯見てみた」「◯◯やってみようかな」などの発言があれば、興味が出たモノを知る機会を作ります。
例えば、
・資料請求してみる
・公式HPを一緒に見る
・道具を買う
・体験会に参加する
など、本人の興味が湧いたものに触れる機会を作ります。
発言がなくても、明らかに興味を示してる場合でも大丈夫です。
ポジティブに振り返る
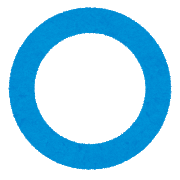
不登校の子は、周囲の出来事や人の言動に、敏感なことが多いです。
「◯◯で失敗した」
「人に◯◯と思われてる」
など、ネガティブな思考になりやすいです。
そこで、家族からポジティブに変換して、振り返っていきます。
・学校に行けなかった
⇨朝起きれた
⇨身支度できた
⇨校門までいけた
・問題10問解けなかった
⇨5問解けた
⇨分かる問題が解けた
⇨分からない問題を自分から聞けた
など、本人が失敗体験と捉えることを、ポジティブに変換(リフレーミング)していきます。
本人が納得しなくても、周りがポジティブな視点で、本人と向き合うことが大切になります。
また、最初に共感を入れた上でポジティブに変換することも、ポイントになります。
例えば「朝は眠いよね」「10問あると大変だよね」などの言葉を、最初の一言に添えるイメージになります。
過去の自分と比較の視点にする

不登校の子は、自分自身と同学年の子を比べやすいです。
「クラスの皆は、学校行ってるのに、自分は行けてない」と周囲と比べ、傷つきます。
大切なのは、過去の本人自身と比べ、ポジティブな変化を見ていく所です。
例えば、
・1ヶ月前は1日1ページのドリルだったものが、今は3ページできる様になってる
・朝12時に起きてたのが、9時に起きられる様になってる
などがあります。
本人の具体的な変化を伝えるイメージになります。回数と期間が必要になる為、日々の関わりの積み重ねになります。
「こんなことを褒めるの?」と感じる方もいるかもしれませんが、不登校の子は、それほど自信を失っている状態になります。
本人の特性を言語化する

本人が、学校や他の場所、人と関わる時に、周囲の理解は、必ず必要になります。
その為、親御さんが「本人の特性」を言語化できることが大切になります。
言語化できることは、周囲の理解に繋がり、本人が過ごしやすい環境作りに繋がります。
本人が得意、不得意な環境、必要な配慮などが伝えられると良いです。
【関連記事】
不登校低学年の子に「注意したいこと」

不登校低学年の子に向き合う時に、「注意したいこと」は、4つあります。
①:「親にとって」で考える
②:「周囲の子/兄弟姉妹」と比べる
③:「他の子と同じ」を求める
④:「親だけで」抱え込む
親にとって で考える

何かを、判断/考える時に、主語が「大人(親)」になっていないかです。
例えば、学校に行くのが辛い子に対して、学校のことを何回も聞くのは、本人にとってはネガティブに働きます。
これは、親御さんが安心したい、学校に行ってほしいという気持ちが、関わりに出ている場合が多いです。
大切なのは「その子にとって」で考えることです。家族としては、「もう少し頑張ってほしい」と思いたくなりますが、グッと押さえて、本人の気持ちを尊重することが必要になります。
周囲の子/兄弟姉妹と比べる

「上の子は、◯◯だった」
「下の子は、◯◯できる」
など、兄弟姉妹と比べることは避けたいです。
兄弟姉妹ですと、嫌でも本人は意識してしまいます。お子さんによっては、一人で比べて傷ついてる場合もあります。
ただ、少なくとも家族は「一人ひとり違うのが、当たり前」という認識で関わり続けることが大切になります。
他の子と同じ を求める

「みんなと同じコトができる様に」
「みんなに追いつく様に」
という視点も避けたいです。
この視点は、本人を否定する意味合いになります。
「その子なりのペースで」
「その子らしく過ごせる様に」
という視点が大切になります。
親だけで抱え込む
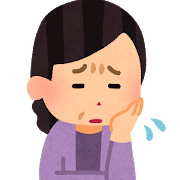
お子さんの不登校に関する悩みを、家庭内だけで抱え込まないことが大切です。
お子さんの不登校は、家族の心身の負担が大きいです。特に小学校低学年は、一人で留守番できないことも多く、フリースクールなども、年齢が対象外になる所が多いです。
また、家族全体の状況を俯瞰する視点も大切なため、家族以外で信頼できる人に相談するのも大事になります。
個人的には、不登校の支援先に相談するのが、一番だと思います。今の本人に必要な関わり・環境など、教えてもらえますし、逆に避けた方が良い関わりも知ることができ、学びになります。
【合わせて読みたい記事】
【不登校低学年のその後 事例紹介】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校低学年の子の「その後」
~5つの事例~
・学年、担任が変わり復帰する
・不登校が続き支援に繋がる
・フリースクールに通う
・引っ越し/転校する
・学校はいかず中学受験を目指す
✅「今」家族ができること
・その子自身を認める
・”家=安心して過ごせる環境” にする
・本人が安心して楽しめるモノの確保
・今できてることを見つける
・支援先に相談する
✅「この先」家族ができること
・興味・関心を深める機会を作る
・ポジティブに振り返る
・”過去の自分と比較” の視点にする
・本人の特性を言語化する
✅不登校低学年の子に
「注意したいこと」
・”親にとって” で考える
・周囲の子/兄弟姉妹と比べる
・”他の子と同じ” を求める
・親だけで抱え込む
✅不登校低学年の子が
「備えておきたいこと」
・学習の失敗体験の予防
・本人に合う学習方法の把握
・学習意欲の向上
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】







































[…] 【不登校低学年のその後は?】支援の事例紹介~今・この先、家族にできること~ […]