

子どもの不登校で悩まれてる方「うちの子、ゲームばかりで勉強しない。どう伝えれば勉強してくれるか…関わり方を教えてほしい」
不登校の我が子がゲームばかりしていると、「勉強しなさい!」と言いたくなりますよね。
我が子の将来を心配してのことですので、親として自然な気持ちだと思います。
ただ不登校のお子さんですと、どのように関わればいいのか、家でどのように過ごせばいいのか、悩まれてる方も多いと思います。
そこで今回は、ゲームばかりしてる不登校の子への関わり方をお伝えしていきたいと思います。
この記事を執筆している私は、療育・相談支援を15年以上しています。不登校のお子さんの支援も数多くしてきました。
その支援経験を通して、本記事をまとめてます。
参考になれば幸いです。
勉強しない不登校の子の「ゲームをする理由」

勉強しない不登校の子の「ゲームをする理由」は、大きく4つあります。
①:「ストレス発散の手段」が少ない
②:「自分の居場所/繋がり」を求めてる
③:「勉強嫌い/意味が見い出せない」
④:心身の「病気」
お子さんによって複数の理由が重なっていることもあります。
ストレス発散の手段が少ない

不登校の子は、大きなストレス、心に深い傷を負っていることが多いです。
そんな辛い状況の中で自分を保つために、ストレス発散や不安から離れる時間を作るための手段として、”ゲーム” をすることがあります。
今の自分を満たしたり、発散する方法が少なく、ゲームという方法でしか自分を保てない状態になります。
自分の居場所/繋がりを求めてる

①に近い内容ですが、自分を保つため、満たすために、安心・楽しめる居場所や繋がりを求めている場合になります。
ゲームですと、気軽に同じゲームが好きな、不特定多数の人と繋がることができます。
マイクで話をしたり、チャットで楽しむ子も少なくないです。
学校や身近な環境で居場所が持ちづらい子が、ネットゲームを通して、居場所を見つけることが増えています。
勉強が嫌い/やる意味が見い出せない
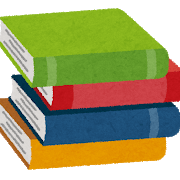
単純に勉強が嫌いだったり、嫌いではないけど勉強する意味が分からない(納得できない)ケースもあります。
勉強をする意味(自分にとってもメリット)に納得できず、勉強をしないor適当に済ませるケースも少なくありません。
子ども本人としては、自分にとって意味があるのか考えていて、やらない選択をしている場合もあります。
療育や家庭教師など、外部の力を借りないと、家庭内でのアプローチが難しいことも多いです。
家庭内でやるとしたら、勉強自体が楽しめる(少なくても、つまらなくない)工夫をする必要があります。
私がお勧めしているのは、タブレット学習です。気軽に楽しく学びに繋がりやすい方法になるためです。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
発達障害に関わらず、不登校の子にも参考になる内容になります。
心身の病気

日常生活に大きな支障がある場合は、”心身の病気” の可能性があります。
私はお医者さんではないので、医療分野の知識はありませんが、
病気の可能性を感じる場合は、
心療内科/児童精神科に相談されるのも、1つの方法になります。
かかりつけのクリニックがありましたら、まず担当の先生に相談されるのが良いと思います。
紹介してもらえる場合も多いです。もし本人が嫌がる場合は、まずは親御さんだけで相談でも良いと思います。
可能であれば、親御さんが感じられる心配を事前にお子さんの行動(症状)ベースで、
お伝えできると良いと思います(ex.ゲームがキッカケの癇癪が1日5回以上ある。落ち着くのに1時間以上かかる等)。
お医者さんが、状況の把握ができ、お子さんに必要なアドバイスを受けやすくなる為です。
不登校の子に関わる時に「大事なこと」

不登校の子に関わる時に「大事なこと」は、3つあります。
①:「本人のストレス軽減/親子関係」
②:「デッドライン」を決める+理由と一緒に事前に伝える
③:「否定・命令・質問攻め」はしない
本人のストレス軽減/親子関係が最優先
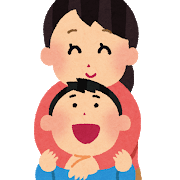
何よりも1番大切なのは、本人を満たす(ストレス軽減)、親子関係を壊さないことです。
「朝起きてほしい」「勉強してほしい」「ゲーム以外で過ごしてほしい」など、お気持ちはあると思います。
私も親なので、お気持ちはとてもわかります。ただ不登校の子には、回復してもらうこと(本人を満たす)がまず必要になります。
心に傷を負っていますので、まずは満たして回復ができないと、勉強や集団生活などは、難しいです。
また、ご家族が本人を支えるキーマン(本人にとっての心の拠り所)になりますので、関係性を壊さないことが重要になります。
勉強や家での過ごし方で、親子関係が悪くなると、二次障害(ひきこもり・鬱など)に繋がりかねません。
本人にとって安心できる場所がなくなるのは、二次障害のリスクを高めることと同じ意味になるためです。
まずは1番土台となる、“本人を満たす/親子関係” を大切にしていきましょう。
デッドラインは親が決める+理由を伝える
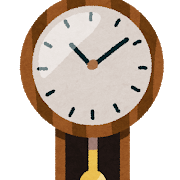
親御さんの中で、ゲームや動画などのデッドライン(終わりの時間)を決めておきましょう。
「ゲーム・動画は21:00まで」「ゲームは1日3時間」など、
親として、絶対に譲れないラインだけ具体的に決め、本人に事前に伝えましょう。
ここの基準がないと、日によって大人の対応が変わり、本人も時間を守りづらくなり、ご家族も困る状況になるためです。
【合わせて読みたい記事】
【不登校】子どもに暇と言われたら?「将来役に立つ」4つのやれると良いこと
否定/命令/質問攻めはしない

不登校の子は、ネガティブな言動に敏感なこともあります。
悪気がなくても、被害的に捉えたり、傷つくこともあります。
「○○できないの(否定)」
「○○しなさい(命令)」
「まだ終わってないの?何してたの?」
(質問攻め)
これらの言葉は、不登校の子にネガティブな影響を与えます。
ゲームばかりする不登校の子への「関わり方」

ゲームばかりする不登校の子への「関わり方」は、4つあります。
お子さん・ご家庭の状況によって様々になりますので、必要な部分をご覧ください。
①:話を最後まで聞き「共感」する
②:ルールは「子どもと一緒に」決める
③:親の基本スタンスは「見守る」
④:本人の意思を「形にする(サポート)」
話を聞き共感する
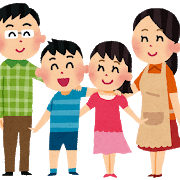
お子さんの話を、最後まで聞いて共感することです。
文字にすると簡単そうですが、実は意外と難しいです(私も日々の育児で苦労しています…)。
共感の仕方は、2つあります。
①:同じ言葉で、そのまま返す
(オウム返し)
②:お子さんの気持ちを代弁する
同じ言葉でそのまま返す
具体例を見ていきましょう。
お子さんが「この問題分かんない!イライラする!」と言ったら、
『分かんない問題はイライラするよね』と、同じ言葉で返すイメージになります。
「共感は苦手…」という方に、おすすめの方法になります。
お子さんの気持ちを代弁する
“お子さんの気持ち” を、親御さんが言葉にして伝える方法になります。
お子さんが「この問題分かんない!イライラする!」と言ったら、
『分かんない問題はイライラするよね。どう解けばいいんだよ!ってなるよね』と、お子さんの立場に立って、代弁するイメージになります。
同じ言葉を返す共感よりも難易度は高いですが、
その分「気持ちを受け止めてもらえた」という、お子さんの実感は強くなります。
ルールは子どもと一緒に決める
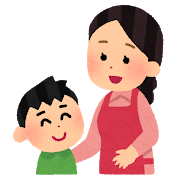
親御さんが決めたデッドラインの範囲の中で、お子さんと一緒にルールを決めていきます。
例えば、「プリント1枚終わったらゲーム1時間」「ゲームは1回1時間」などです。
大人が決めて伝えるのではなく、本人と一緒に決めて、納得してもらってから、ルールを実行する流れになります。
もし本人が納得しない場合は、親御さんから選択肢を伝えても良いと思います。
「例えば、○○と○○があるけど、どっちがいい?」など、事前に決めているデッドラインの中から、選んでもらう形でも問題ありません。
親の基本スタンスは見守る
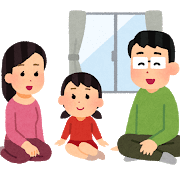
不登校の子と過ごす上で、ここが1番難しく感じる方が多いです。
実際に支援をしていても、ここが1番難しいと私も感じています。
基本的には、本人の意思が出るまで “見守る”。これがとても重要になります。
※明らかに危険な行動の場合は別になります(ex.SNSで見ず知らずの人に会いに行こうとする)
ここについては、別の記事で詳しくまとめてます。
詳しく知りたい方は、【不登校】元気なのに学校に行かない?3つの理由と接し方 をご覧ください。
本人の意思を形にする

本人の意思が出たら、なるべく早い段階で形(サポート)にしましょう。
例えば、こちらの様なイメージになります。
・ネットで一緒に調べる
・興味を持った場所に連れていく
・資料を取り寄せる
・興味あるものを購入し、家で触ってみる
お子さんから「○○見たいな」「○○してみようかな」などの発言があったら、本人に聞いてみてOKなら、行動していきましょう。
【ゲームばかり 勉強しない不登校の子】まとめ

記事のポイントになります。
✅勉強しない不登校の子
「ゲームする理由」
・ストレス発散の手段が少ない
・自分の居場所/繋がりを求めてる
・勉強が嫌い/意味が見い出せない
・心身の病気
✅不登校の子に関わる時に
「大事なこと」
・本人のストレス軽減/親子関係
・デッドラインは親が決める
・デッドラインは事前に理由と伝える
・否定/命令/質問攻めはしない
✅不登校の子「関わり方」
・話を最後まで聞き共感する
・ルールは子どもと一緒に決める
・親の基本スタンスは見守る
・本人の意思を形にする
(サポートする)
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【相談員が解説】すららで不登校を出席扱いにする方法!7つの条件







































[…] 【勉強しない不登校の子】ゲームばかりする3つの理由・対処法 […]
[…] 【勉強しない不登校の子】ゲームばかりする3つの理由・対処法 […]