

不登校の子に悩まれてる方「うちの子、全然勉強しない。何で勉強しないの?不登校の子の勉強対策を教えてほしい」
「学校に行かないなら、家で勉強してほしい…」
「このまま勉強しなかったらどうしよう…この先が心配…」
勉強をしない不登校の子で、悩まれてる親御さんは多いと思います。
「学校にいかない分、少しは勉強してほしい」と思うのが、親としての自然な気持ちだと思います。
そこで今回は、不登校の子が「勉強しない心理(理由)/対策/大切なこと」をお伝えします。
この記事を執筆してる私は、療育/相談支援を15年以上しています。不登校のお子さんの支援も数多くしてきました。
その支援経験を通して、本記事をまとめてます。
目次
不登校の子の「勉強しない心理」
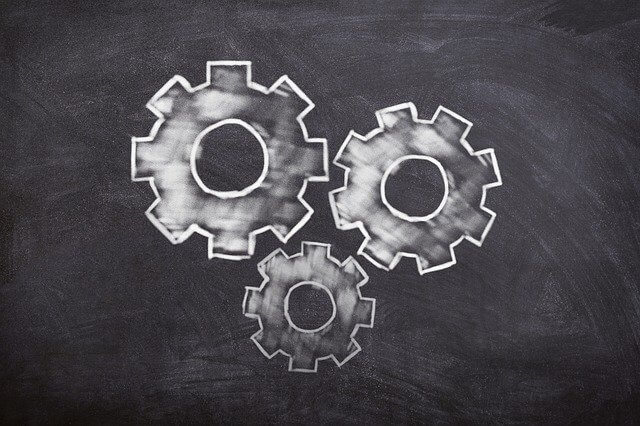
不登校の子の「勉強しない心理」は、大きく4つあります。
①:「心の余裕」がない
②:勉強への「拒否感」がある
③:勉強の「必要性」を感じてない
④:「勉強の仕方」が分からない
心の余裕がない

不登校の子は、大きなストレス、心に深い傷を負っていることが多いです。
そのため、”勉強する状態でない子” も少なくありません。
よく「回復期」と言われますが、まず心の休息が必要な時期になります。
本人の好きなことをして過ごし、心を休ませます。個人差がありますが、一定期間休むことで、心が回復してきます。
回復の1つのサインとしては、例えば、家族の手伝いをしたり、外出をしたりと、意識/行動が自分以外に向いてきます。
その段階に行くまでは、勉強は難しい状態の子が多いです。
勉強への拒否感がある

勉強への拒否感が強い場合になります。
「学校の授業についていけなかった」「勉強ができなくて怒られることが多かった」など、
“勉強の失敗体験の多さ” が主な理由です。
この状態の子は「勉強に取り組む(簡単な問題が解ける楽しさを実感)」ことが必要になります。
勉強の必要性を感じてない

勉強は嫌いじゃないけど、勉強する意味が分からない場合になります。
勉強する意味(=自分にとってのメリット)に納得できず、勉強しない or 適当に済ませる子がいます。
子ども本人としては「自分にとって意味があるのか」を考えていて、やらない選択をしてることもあります。
このタイプの子は、論理・合理的な思考が強いことが多いため、
「勉強が、その子の何に繋がるのか」を論理的に説明するのが効果的になります。
勉強の仕方が分からない

「やる気はあるけど、自分に合う方法が分からないから勉強しない」というケースになります。
一時期は頑張ったけど、上手くいかなかったから、それ以降勉強しない(できるイメージが湧かない)状態になります。
逆に言うと、自分に合った勉強の仕方がわかれば、勉強に踏み出しやすいともいえます。
不登校の子に関わる時に「大切なこと」

不登校の子に関わる時に「大切なこと」は、2つあります。
特に、「子どもに勉強してほしい!」と思われてる親御さんに向けた内容になります。
①:「主語」を子どもにする
②:勉強の「目的」を決める
③:「本人の意思」を尊重する
④:勉強後の「本人のメリット」を作る
主語を子どもにする
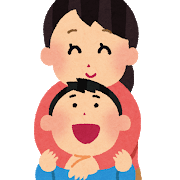
お子さんが不登校で、家で過ごす時間が長いと…
「○○は、頑張ってほしい」
「○○をしてほしい」
など、お子さんに求めたくなると思います。私も親なので、お気持ちはとっても分かります。
ただ不登校の子の場合、深く傷ついていたり、行動するのに膨大なエネルギーを必要とすることが多いです。
その場で出来たとしても、反動がきて、その後は、何も手が付かない状態になることもあります。
そういった背景を考えると、不登校の子に関わる大人側としては、
「その子にとって(その子自身の受け止め方)どうだろう?」と考えることが大切になります。
お子さんの将来を考えれば、勉強は必要になります。
ただお子さんの気持ち/コンディションを考えた時に、
「今は、心を休める時期かも」
「本人がどう思ってるか聞いてみよう」
「勉強の前に、どんな方法があるのか知ってもらおう」
と、違う関わりが見えてくるかもしれません。
勉強に関わらずですが、不登校の子と向き合う際は、「子どもを主語」にすることが大切になります。
勉強の目的を決める

勉強をする前に、“勉強する目的” が決められると理想です。
特に、勉強する意味が分からなくて、モチベーションが低い子には効果的になります。
お子さんの興味ある分野があれば、その方面に進学することを目的に、必要となる科目を確認していきます。
もしくは「○○学校に入学」のように、学校を目標にするのも1つです(学校がお子さんに合ってることが前提)。
興味あるものがなければ、ちょっとしたゲーム感覚でできる “タブレット学習” から始めるのも1つです。
まずは「勉強を楽しむ」「勉強の習慣化」を目的に、タブレットで楽しみながら進めるのも良い選択肢になります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
発達障害に関わらず、不登校の子にも共通する内容になっています。
本人の意思を尊重する
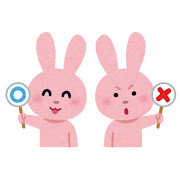
本人の気持ちを最優先にすることです(健康や安全面に支障がない範囲で)。
本人の納得感・必要性の実感がないと、勉強は形だけになってしまいます。時間と労力をかけたにも関わらず、成果が出ません…。
「こんなに頑張ったのに、ダメだった」
「本当は嫌だったのに、勝手に決められた」
このような子ども本人のネガティブな感情に繋がります。
また、大人のせいにして、良くない意味での逃げ道に走り、他責傾向に陥りこともあります。
そういった理由から「本人に決めてもらう」が大切になります。
✅「選んでもらう」も1つ
自分で考えることが難しい子には、大人が選択肢を出して、その中から選んでもらう形でも大丈夫です。
「○○と○○、どっちがいい?」など、複数の中から、選んでもらうイメージになります。
勉強後の本人のメリットを作る

勉強した後の、”本人にとっての嬉しいこと(メリット)” を作っていきます。
お子さんのタイプによって、喜び(メリット)は変わりますが、
例えば、こちらの様なイメージになります。
・ほめられる
・ゲームができる
・解ける問題が増えた
・点数が上がった
・勉強自体が楽しい
(タブレット学習)
勉強をした後に、嬉しいことがあれば、また勉強を頑張ろう!という気持ち/行動に繋がります。
逆にここがないと、余程の目的意識がない限り、長続きはしないものです。
【不登校の子 勉強しない心理】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の子の
「勉強しない心理」
・心の余裕がない
・勉強への拒否感がある
・勉強の必要性を感じてない
・勉強の仕方が分からない
✅不登校の子に関わる時に
「大切なこと」
・主語を子どもにする
・勉強の目的を決める
・本人の意思を尊重する
・勉強後の本人のメリットを作る
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【不登校の子】勉強しない心理とは?4つの理由・対処法 […]
[…] 【不登校の子】勉強しない心理とは?4つの理由・対処法 […]
[…] 【不登校の子】勉強しない心理とは?4つの理由・対処法 […]