

療育を辞めるべきか迷ってる方「療育をやめた方がいいか迷ってる。療育やめたら、子どもが将来困らないか不安。療育をやめても良い目安が知りたい」
療育に通ってお子さんが成長してくると、嬉しい反面、園・学校・他の習い事など、何を優先させるべきか、悩むことありますよね。
この記事の執筆者の私は、療育指導を15年以上しており、発達障害のお子さん・親御さんの支援をしてきました。
また私の息子は “言語発達遅滞・発達性協調運動障害”の診断を受け、2年ほど療育に通っていました。
その支援・育児経験を元に、「療育のやめどき・続けるべき目安・事例・やめた後のフォロー」を、まとめました。
参考になれば幸いです。
療育を「やめるタイミング」

「療育をやめる」を2パターンで見ていきます。
・療育先を変える
・辞める
療育先を「変える」タイミング
子どもが嫌がってる

お子さんが “療育の場所・先生を嫌がる” 場合です。
例えば、お子さんからの「○○先生ヤダ!○○行かない!」などの発言になります。
療育の先生・ご家族が、療育を楽しめる工夫を最大限しても、
お子さんが心底嫌がっている場合は、療育先を変えるタイミングといえるでしょう。
個人的な期間の目安としては、週1回のペースで通い、2ヶ月以上続いている場合になります。
子どもの成長を感じない

“3ヶ月以上通って、成長を全く感じない” 場合は、1つのタイミングになると思います。
お子さんにもよりますが、療育の指導内でも成長(些細な変化)が見られない場合は、
お子さんと療育先が合っていない可能性が高いからです。
お子さんの成長を感じない場合は、まず療育先に詳しく聞いてみるのが良いです。
成長の記録を見せてもらったり、説明を聞いて、納得できる場合は、継続した方が良いと思います。
次の療育先の利用の確定後
今の療育先が、余程良くない場合を除いて、
新しい療育先の利用が確定(見学or体験をして)している状態になってから、今の療育先をやめることをお勧めします。
今の療育先をやめて、新しい療育先探しても、見つからない(もしくは時間がかかる)場合、
療育が全くない期間ができてしまう為、それは避けられた方が良いです。
療育先を「やめる」タイミング
療育先に「問題ない」と言われた

療育の専門家は、多くのお子さんを見ています。そして、お子さんが今後送る生活も把握しています。
もし懸念があれば『必要ない』と言われることは、ありません。
もし親御さんに小さな心配事がある場合は、「○○のときは○○の配慮をしましょう」など、
具体的な対処法が聞いておけると安心です。
困りの解消/対処法が実践できる状態
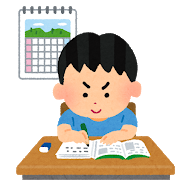
療育に通うキッカケになった “困りごと” が解消されていたり、
“お子さん自身で” 対処法が実践できる状態なら、1つのタイミングになります。
ただここは、専門的な部分になりますので、療育先に相談することをお勧めます。
✅「親の判断だけ」で決めない
専門家の客観的な意見を聞いた上で、判断することをお勧めます。
理由は、専門家はお子さんの「未来」の困りを想定しやすい為です。
多くのケースを見てきて、どういう特性の子が・どの年齢で・何に困りやすいか等、ある程度把握しています。
お子さんの特性・今後のライフステージを考慮して、懸念があるのか聞くことは、とても大切なことです。
親御さんだけの判断ですと、「今」に焦点がいきやすかったり、未来の困りが想像しづらいことが多いです。
後から「やっぱり辞めなければ良かった…」だけは、避けたい所です。
私が支援してきた方で、療育を辞めて後悔された方も一定数いらっしゃいます。
こちらの記事に事例をまとめてますので、興味のある方はご覧ください。
【療育の後悔】受けないと、子どもの将来にどんな可能性が?事例を元に解説
療育を「続けた方がいい」ケース

療育を「続けた方が良いケース」は、大きく2パターンあります。
①:「環境が変わる」とき
②:専門家に「継続」を勧められたとき
環境が変わるとき
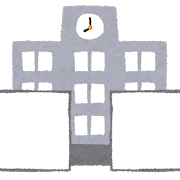
ここでいう「環境」とは…
・担任/クラス
・学校/園
・家庭
(引越し・同居する人数の変動)
になります。「療育をやめる」というのは、私たち大人の想像以上に、お子さんにとって大きな環境の変化になります。
環境の変化は、時期をズラすことでお子さんの負担を軽くすることができます。
また、進学・進級で、生活そのものに大きな変化がある場合は、その生活に慣れるまでは、環境の変化は避けた方が良いです。
お子さんにもよりますが、新しい環境に慣れる目安として、2~3ヶ月ぐらいあると良いと思います。
また、慣れるのと同時に、困りが出るパターンも多いです。
緊張してることで、一時的にお子さんが無理をして頑張って、困りが出づらいことも多いです。
新しい環境に慣れた状態で生活をした上で、
困りがでなければ “安心して卒業できる目安” になります。
環境の変化が大きい時期
個人的には、4~6月、9~10月は、
『今の生活に子どもの困りがないか』を見極める、大切な期間になります。
よく年度末に療育をやめる方がいらっしゃいますが、
正直、あまり勧められません(やめざる得ない場合は、どうしようもないのですが…)。
個人的には、新生活に慣れて、お子さんが大きな問題なく過ごせるのを確認してから、やめることをお勧めしています。
年度末でやめるか迷われてる方は、可能であれば6月末までの様子を見て、判断できるのが一番安心です。
【合わせて読みたい記事】
【どんな基準で判定される?】通級を徹底解説!通う目安と注意点
専門家に継続を勧められたとき
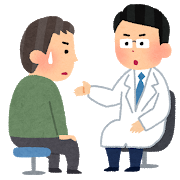
専門家とは、療育先の指導員・児童発達管理責任者・心理士・言語聴覚士などになります。
できれば2名以上が理想でして、その理由は、より客観性が増すためです。
なぜやめない方がいいのか
“お子さんがどんな場面で具体的に困る可能性があるのか” を、聞いてみます。
そこが納得できるものであれば、続けられる方が良いと思います。
【関連記事】
療育をやめた「事例」

ここでは、療育をやめて “成功した事例と失敗した事例”を、1つずつお伝えします。
私が実際に支援してきたお子さんの事例になります。
「うまくいった」事例
“自閉スペクトラム症” の年長さん👦
療育で見通しがある状態で、着席・課題への取り組み・順番を守ることができるようになった年長さん。
小学校でも、見通しを事前に伝えることを学校側にお願いしたことで、スムーズに。
事前の見通しがないと、課題拒否が出ますが、お子さんの療育で身につけた集団参加・周囲に合わせる力(協調性)、
そして、親御さん・学校側の連携が上手くいった事例になります。
「失敗体験」になった事例
“ADHD” の小2👩
集中力が限られていて、課題量の調節・療育先にお子さんに合った学習への取り組み方で頑張ってきました。
課題の量を調節した上で、「解き方の手順化+事前説明」をすることで、療育先でも学校の宿題ができていました。
その様子を見て、親御さんが療育やめたのですが、
小学3年生で文章題・計算の応用問題についていけず、学習そのものを拒否する状態になりました。
自己肯定感も下がり、「どうせ上手くいかない、何やってもできない」の発言が増え、療育に戻ってきたケースになります。
療育を「やめた後」

ここでは、療育を「やめた後」について、触れていきます。
療育をやめた後に、親御さんが “準備しておきたいこと” が2つあります。
お子さんによって変わりますので、必要性を確認しながらご覧ください。
①:本人が「安心できる環境」を作っておく
②:本人に合う「学習サポート」の準備
本人が安心できる環境を作っておく
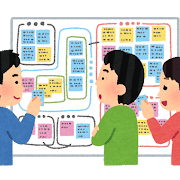
発達障害の子は、不安が強かったり、安心感が得にくい場合があります。
そのため、お子さんが「安心できる環境」は、とても大切になります。
療育でお子さんが成長しても、”一緒に過ごす人・場所” によっては、お子さんが辛い思いをすることもあります。
よくあるのは、学校の理解がなく、叱責ばかり続くケースです。
望まない環境になった時に、
お子さんの理解者となる人と、”相談できる関係性を作っておく” ことが、大切になります。
例えば、下記の信頼できる先生と繋がっておけると、
学校と一緒に、お子さんが “安心できる環境” が作りやすくなります。
・担任
・校長先生
・保健室の先生
・通級の先生
・スクールカウンセラー
まずは、担任の先生に相談をしてみます。
もし理解が得られない場合は、校長先生やスクールカウンセラー(SC)との面談をお勧めします。
先生への相談は、親御さんの心身の負担がとても大きくて、大変なことです。
親御さんが無理のない範囲で、進めていけると良いです。
【関連記事】
【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント・対処法
本人に合う「学習サポート」の準備

学習面に不安がある子は、「学習面のサポート」を準備が大切になります。
発達障害の子に向けた学習支援は、特別支援教育(配慮が必要な子への教育)ですら、まだ発展途上です。
今の義務教育でしたら、発達障害の子に合った学習は、十分でない可能性が高いです。
“学習の問題が表面化” しやすいのは、お子さんが小3~4年生になる頃です。
学校や授業を嫌がったり、テストが白紙になったり、お子さんの苦手意識が強まってきて、様々な場面で影響が出てきます。
完全な拒否反応が出る前に、塾・家庭教師など、お子さんに合う『学習のサポートの準備』が大切になってきます。
塾や家庭教師など、良い先生が見つかれば一番です。ただ人の相性の問題があるので、お子さんに合う先生が見つからない場合もあります。
【療育のやめどき 4つのタイミング】まとめ

記事のポイントになります。
✅療育先を「変える」タイミング
・子どもが嫌がっている
・子どもの成長が見られない
✅療育先を「やめる」タイミング
・専門家に「必要ない」と言われた
・困りの解消/対処法が実践できる状態
✅療育を続けた方がいいケース
・環境が変わるとき
・専門家に「継続」を勧められたとき
✅療育をやめた後
・安心できる環境を作っておく
・本人の理解者と繋がっておく
・本人に合う学習フォローの準備
・タブレット学習は始めやすい
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【療育のやめどきは、いつ?】4つのタイミングとは。事例/注意点あり […]
[…] 【療育のやめどきは、いつ?】4つのタイミングとは。事例/注意点あり […]
[…] 【療育のやめどきは、いつ?】4つのタイミングとは。事例/注意点あり […]