

子どもの進学で悩まれてる方「特別支援学級から普通高校に行く子はいるの?何ができれば行けるの?」
特別支援学級の子の進学先で、悩まれる親御さんは、とても多いです。
お子さんの特性を考えると、普通高校が良いのか、通信学校など他の選択肢が良いのか、など難しい問題にぶつかります。
その中でも「普通高校」を進学先として検討される方も、少なくありません。
ただ「特別支援学級から普通高校に行けるの?行けても困らない?何ができると良いの?」など、不安に感じられる方も多いです。
そこで本記事では、
「普通高校に行く(過ごす)上で大切なこと/注意点」をお伝えしたいと思います。
私は、発達支援の相談/支援員を15年以上しており、これまで進路のご相談も受けてきました。
この支援経験を元に、私が現場で見て感じてきたことを、お伝えしていきます。
参考になれば幸いです。
目次
特別支援学級から普通高校に行く「5ポイント」

特別支援学級から普通高校に行く為の「ポイント」は、5つあります。
ここでお伝えするのは、学力以外のポイントになります。
本人が普通高校での生活を、自分らしく楽しく過ごす為に大切な点になります。
「行く」だけでなく「行って楽しく過ごせる」為のポイントになります。
①:本人の「自己選択」
②:「自己認知」と「対処法」
③:信頼できる「繋がり/居場所」
④:本人の「捉え方」
⑤:「周りに頼る」スキル
本人の自己選択

普通高校という選択肢を、最終的には本人に選んでもらう形をとります。
複数ある選択肢(進学先)のそれぞれのメリット/デメリットを伝え、本人に選んもらう機会を作ることが大切になります。
各選択肢については、学校の先生など詳しい先生から情報を集めます。
自己認知と対処法
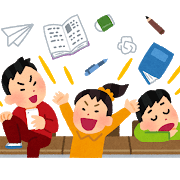
本人が、自身の特性を知り、対処法を実践できる状態が必要になります。
例えば、記憶が苦手な特性をもつ子でしたら、机でメモ用の付箋を貼っておき、いつでもすぐにメモできる状態を作るようにします。
このように自分の特性を理解し、その対処法が実践できれば、生活の困りを減らすことができます。
自身の特性・対処法を言葉で人に伝えることができ、対処法が自分で実践できる状態が理想的になります。
また、普通高校に進むということは、特別支援学級のクラスメイトと違い、”自分と周囲との違い” を実感する場面が増えます。
「自分は◯◯が得意、◯◯は苦手。周りと◯◯が違う」など、自分と周りとの違いを正しく認識することも大切になります。
信頼できる繋がり/居場所

特別支援学級に在籍してた子が、普通高校に行くのは、多くの子にとって不安があるものです。
今まで受けていた配慮がなかったり、周りが理解してくれている状況とも違ってきます。
そんな不安がある環境の中で、大切なのは、本人が “信頼できる人/場所との繋がり” を持つことになります。
家族や友人、療育先の先生など、安心して話せる存在になります。
・自分を理解してくれる人の存在
・心を許して話せる時間
これらは、本人の安心感に繋がります。
安心感は、生活する上での土台になる為、進学前にしっかり作っておく必要があります。
本人の捉え方
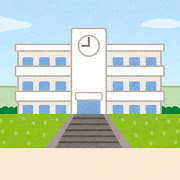
普通高校に行くことで、今まで当たり前に受けていた配慮(周囲の理解)は、得にくくなります。
そんな環境ですと、本人の中で、
「上手くいかなかったこと」
(他の子と同じ様にできなかった)
「自分と周りの子との違い」
などを感じやすくなります。
ただ、違いは誰にでもあって、その違いが、特別支援学級に通う子は、特に大きいことが多いです。
「自分は自分」「人は人」と分けて考えられるかは、本人自身を守る上で、大切な要素になります。
「自分はダメだ」「周りの子よりできない」など、ネガティブに捉える子ですと、高校生活が辛くなり、二次障害などに繋がる恐れがあります。
周りに頼るスキル
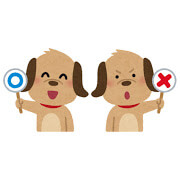
誰でも少なからず、高校生活やこの先の生活で困ることはあります。
そんな時に、一人で抱え込まず、周りの人に頼れる力(ヘルプ要求)が大切になります。
・困ってることを人に伝えられる
・人に手伝ってもらう
・人に教えてもらう
このように、周りに頼るスキルは、高校生活に限らず、生きてく上で、ずっと必要になるスキルになります。
特別支援学級の子「高校受験の注意点」

特別支援学級の子が「高校受験する時の注意点」をお伝えします。
注意点は、公立の普通高校の受験が厳しくなる点になります。
特別支援学級の多くは、内申点がつかない(低い)です。その為、内申点の影響を受ける公立高校の受験が難しくなります。
ただ、学校や地域によって変わる可能性がある為、在籍校に確認することが一番になります。
【特別支援学級から普通高校に行く】まとめ

記事のポイントになります。
✅特別支援学級から普通高校に行く為の
「5つのポイント」
・本人の自己選択
・自己認知と対処法
・信頼できる繋がり/居場所
・本人の捉え方
・周りに頼るスキル
✅特別支援学級の子が
「高校受験する時の注意点」
・公立高校の受験が厳しい
・在籍校に確認する
✅普通高校に行く為に
「必要な学習対策」
・特性の把握
・特性に合う学習方法
・学習意欲を高める
・学習の成功体験を積む
・学習単元の流れに沿う
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】




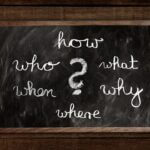




































[…] 【特別支援学級から普通高校に行くには何が必要?】5つのポイント・注意点 […]
[…] 【特別支援学級から普通高校に行くには何が必要?】5つのポイント・注意点 […]
[…] 【特別支援学級から普通高校に行くには何が必要?】5つのポイント・注意点 […]
[…] 【特別支援学級から普通高校に行くには何が必要?】5つのポイント・注意点 […]