

通級(判定など)について知りたい方「通級ってどんな基準で判定されるの?うちの子が判定されるのか知りたい。通級が必要な目安、注意点も知りたい」
我が子にとって、どの学級が合っているのか、悩む親御さんも多いと思います。
本記事では、通級の判定基準含め、通級に関する基礎的な情報をお伝えします。
私は、発達支援の相談/指導員を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
通級の判定基準

結論からお伝えすると、通級の判定基準は、明確にはありません。
強いて言うなら、最終的には「親の判断」に委ねられています。
ただ支援している親御さん方を見ていると、「普通学級の受け入れ拒否された」と学校側に、遠回しに断られてしまうことも、少なくありません(結果として通級/支援級を利用するケースが多いです)。
ここで大切なのは、『お子さんにとって「通級」という場所が必要なのか?』、ということになります。
と言っても、通級が必要になる具体的な目安がないと、分からないですよね。
次の内容で、通級が必要になる目安の部分を、説明をしていきたいと思います。
通級自体の詳しい説明については、こちらの記事をご覧ください。
通級が必要になる目安

通級が必要になる目安は、3つあります。
①:「普通学級」で本人が困ってる
②:本人が「通級」を望んでる
③:第3者(特に学校)から「通級」を勧められてる
普通学級で本人が困ってる
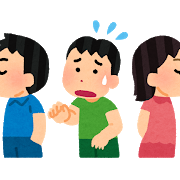
お子さんが普通学級の生活(就学前の子は、園の生活)で、困っている場面があれば、そこのサポートを通級で受けられると良いことがあります。
例えば、友達への言い方がキツくなってしまいトラブルになるという場合は、
「相手の気持ちを考える/友達への伝え方などを学ぶ指導」を受けられると良いと思います。
本人が通級を望んでる

お子さん自身から、実際に困っていることを個別でゆっくり教えてほしい、など希望がある場合は、通級が必要な一つの目安になります。
普通学級の中で工夫をしても、状況が変わらなければ、通級を学校に相談するのが良いと思います。
第3者から通級を勧められてる
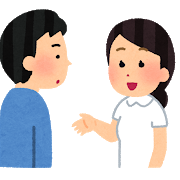
第3者から、通級を勧められた場合も目安になります。
特に学校側から提案などあった場合は、学校生活を見て判断されているので、お子さんに必要な場合が多いです。
【関連記事】
【通級を勧められた時】利用すべき?3つの判断基準~事例も紹介~
通級の入り方

通級への入り方は、「就学前」、「就学後」の2つに分けられます。
就学前

教育委員会に、就学相談をすることができます。地域によって呼び方/手順が変わります。
『お住まいの地域の就学相談』については、お住まいの自治体・学校に問い合わせるのが、一番良いです。
✅就学相談
就学相談(7~9月が多い)とは、専門の就学相談員と保護者との面談を通してお子さんにとって、最適な就学先を決めます。
お子さんの状態を把握するための検査が行われたり、相談員がお子さんの在籍園・在籍校に赴いて、お子さんの様子を確認することもあります。
お子さんの様子、保護者/専門家の意見、学校や地域の状況などの総合的な情報をふまえ、就学指導委員会が、お子さんに一番良いと思われる就学先を決定します。
この決定に保護者の方が同意をすれば就学先が決定します。もし同意できない場合は、その旨を教育委員会に申し立て、再度就学相談を受けることもできます。最終的には、保護者の方の意向が尊重されます。
就学相談では、お子さんの状態を正確にしっかりと伝えることが大切です。医療機関で受けた診断書・療育手帳・検査結果などがあれば、持参することをお勧めします。
✅注意点:私立/認可外の園は、情報が回らない場合もある
私立や認可外の保育園/幼稚園は、教育委員会の管轄外なので、就学関連の情報が回ってこない可能性があります。
その場合は、ご自身で市区町村の教育委員会に問い合わせをして、就学相談を受けることが良いでしょう。
就学後
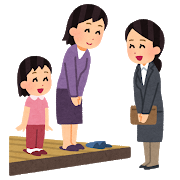
小学校入学時は、普通学級に在籍してた子が、そのあと通級が必要になることもあります。
その場合、まずは担任の先生に相談されるのが良いでしょう。担任⇨校長や校内委員会が動いてくれます。
校内委員会
校内委員会とは、子どもの状態に早期に気付き、適切な支援を行うために小・中学校に設置されたものです。
主な役割は6つになります。
・支援が必要な子の早期の把握
・支援計画書の作成
・保護者相談の窓口
・担任の指導のサポート
・全教職員の共通理解を図る(研修など)
・専門家に判断を求めるかどうかの検討
万が一、担任に言っても動いてくれる様子がなければ、管理職(校長、教頭など)かコーディネーターに、相談することをお勧めします。
通級を嫌がってる子の「学習対策」

ここでは、学習面に心配があるものの、通級を嫌がってる子の学習対策について、お伝えします。
本人が通級を嫌がってる場合、通級を利用するのは難しいです。
仮に行けたとしても、途中で行かなくなったり、本人の中で「何で自分だけ皆と離れないといけないの?」という不満が溜まります。
お子さんによっては、不登校のキッカケになる場合もあります。
とはいえ、学習面の心配がある子が、そのまま普通学級の授業を受けて学習の遅れが解消されるかというと、難しい場合もあります。
ここで避けたいのは、学習の遅れはもちろんですが、それ以上に学習の失敗体験による、自己肯定感の低下、学習の拒否感が強まることです。
その為には、学習の失敗体験を予防すると同時に、小さな成功体験を積み重ねる必要があります。
お子さんの「できた!」「次もやろう!」を作り、学習のポジティブな経験を作ることが大事になります。
ここでは、具体的な学習方法の1つとして、家庭で自分のペースでできる “タブレット学習” をお伝えします。
学習サポートはタブレット学習
学校の授業では、理解が難しい場合、いくつもの理由がありますが、私が支援してきた中で特に多かった理由をまとめてみました。
いずれの場合でも、タブレット学習だと、アプローチがしやすいです。
・理解自体が難しい
⇨アニメーション/音声学習
(ペーパー教材が合わない子向け)
・ペースが早すぎる
⇨自分でペースが決められる
(ボタンを押して次に進む)
・学習の苦手意識
⇨ゲーム要素があり、勉強感が薄い
(学習の取り組みやすくなる)
・情報が多すぎて、優先順位がつけられない
⇨1画面で1つの課題のみ提示
(注意散漫な子向け)
他にも、タブレット学習が合う子、合わない子の特徴がありますので、詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
発達障害あるなしに関わらず、学習の困りを抱えてる子向けの内容になります。
1つの学習方法として、参考になれば幸いです。
【どんな基準で判定?通級に通う目安】まとめ

記事のポイントになります。
✅通級の「判定基準」
・明確な基準はない
・親の最終判断
✅通級が必要になる「目安」
・子どもが「普通学級」で困ってる
・子どもが望んでる
・第3者から勧められてる
✅通級の「入り方」
・就学相談(就学前)
・担任に相談(就学後)
✅通級を嫌がってる子の
「学習対策」
・失敗体験の予防をする
・小さな成功体験を重ねる
・本人が理解しやすい学習法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】









































[…] 【どんな基準で判定される?】通級を徹底解説!通う目安と注意点まで […]
[…] 【どんな基準で判定される?】通級を徹底解説!通う目安と注意点 […]
[…] 【どんな基準で判定される?】通級を徹底解説!通う目安と注意点 […]