

癇癪持ちの夫で悩まれている方「夫の癇癪に疲れた。このまま我慢するのも限界。夫にどう接していけばいいか教えてほしい」
癇癪はご本人だけではなく、家族にも大きなストレスを与えます。
たた癇癪は、コントロールが簡単にはできないものになります。では家族はどのように向き合っていくべきなのでしょうか。
この記事を執筆している私は、発達支援/家族支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
私が実際に家族支援をして、ご家族の負担が軽くなった事例を元に、癇癪持ちの夫の原因/接し方/付き合い方をまとめました。
参考になれば幸いです。
目次
癇癪持ちの原因
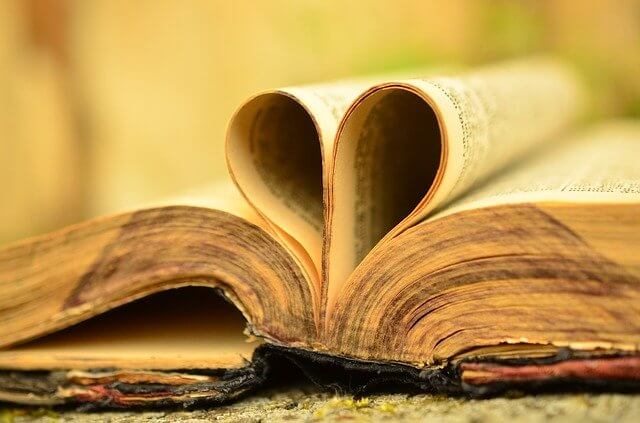
癇癪持ちの原因は、大きく4つに分けられます。
①:発達障害
②:病気
③:トラウマ
④:セロトニン不足
発達障害
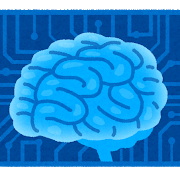
発達障害とは、生まれつきもっている「気質的に近いもの」です。
癇癪持ちに繋がりやすい発達障害は、代表的なものでは2つあります。
簡単に、特徴をまとめていますので、該当するか参考程度にご覧ください。
ちなみに私が相談支援してきた方の中では、自閉スペクトラム症傾向の方が、多かったです。
✅自閉スペクトラム症(ASD)
□言葉を表面的に捉えやすい
□こだわりが強く、自分のやり方を曲げない
□急な変更、日々のルーティンから外れることが苦手
□相手の気持ちを想像することが苦手
✅ADHD(注意欠陥多動性)
□細かいミスが多い
□突発的な言動が多い
□忘れものが非常に多い
□時間/物/お金など管理が苦手
病気
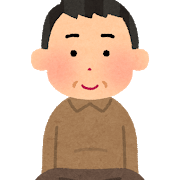
仕事などの社会との関係、家族との関係で、うつ病などの病気にかかることがあります。
感情を安定させるのが難しく、親しい人の前で怒りの気持ちを表し、癇癪持ちのような状態になることもあるでしょう。
このような場合は、脳に異常が生じて怒りをコントロールさせることが難しいこともあり、医療的なサポートが必要になることがあります。
心療内科などにかかって、カウンセリングや投薬治療など、医療機関に相談をすることが、1つの方法になります。
トラウマ
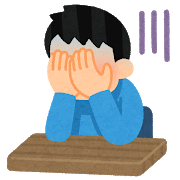
過去の辛い経験から、トラウマを抱えている場合です。相手のちょっとした行動や言動を、過敏にネガティブに捉えてしまうことがあります。
自分が否定されていると感じてしまうため、周囲が気付かないことも、本人にとってはストレスになります。
セロトニン不足

癇癪持ちの人には、セロトニンという神経伝達物質が不足していることがあります。
セロトニンは脳内で作られ、ストレスを軽くするような、精神安定剤のような働きがあります。
セロトニンを増やすためには、
・適度な運動
・感情を動かす
・十分な睡眠
これらを日常的にすることで、できます。
「感情を動かす」とは、様々な経験や見聞きして、感動したり、笑ったりすることです。
映画鑑賞や読書、人と合うなど、ご本人の感情が動きやすいものが、良いです。
✅一時的な癇癪の場合(短期間)

一時的な癇癪の場合は、2~3ヶ月様子を見て、それでも状況が変わらない場合は、本記事の対処法が必要になると思います。
一時的な癇癪とは、下記のような生活自体に、大きな環境の変化が原因の場合になります。
・勤務先の異動
・家族が増えた
・在宅ワークになった
・住む場所が変わった
環境の変化があった時期と癇癪が出始めた時期が、一致していたら可能性があると思います。
癇癪持ちになりやすい人の特徴
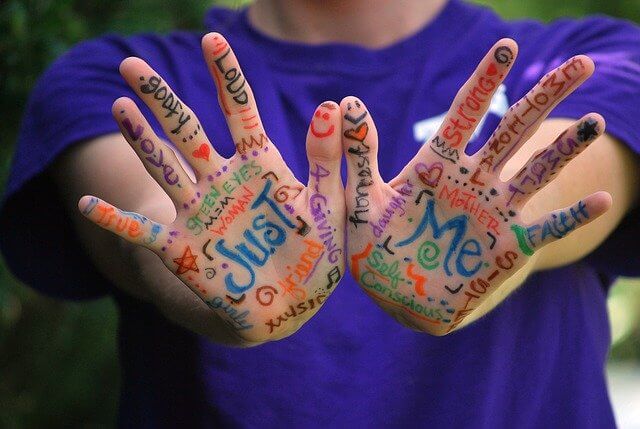
癇癪持ちになりやすい人の特徴は、主に2つあります。
あくまで、1つの傾向になります。
①:まじめ
②:完璧主義者
まじめ
癇癪持ちの人は、まじめな方が多いです。普段から規則を守った生活をしています。
少しでも自分が正しいと思うルールから外れた言動をとる人を見ると、怒りの気持ちが湧きやすくなります。
完璧主義者
癇癪持ちの人は、『○○しなければいけない』という、独自の強い考えがあります。
自分の予定した通りに進まないと、自分自身に対しても、周囲の人に対しても怒りの気持ちを爆発させ、癇癪を起こすことがあります。
癇癪持ちの夫への対処法
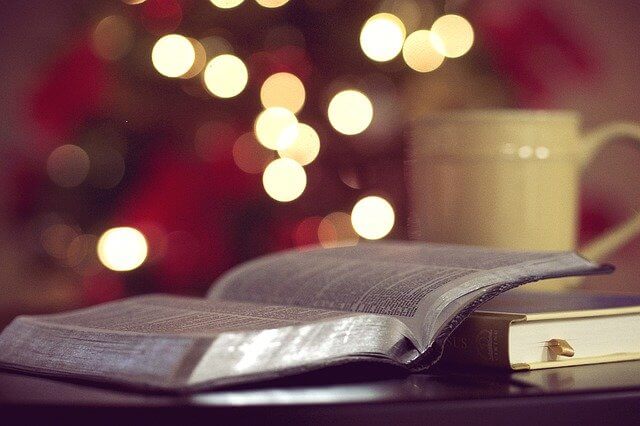
夫の癇癪持ちの原因によりますが、対処法は5つあります。
原因別に、1つずつ見ていきます。
①:夫の特性を理解する
②:夫婦カウンセリング
③:別居
④:離婚
⑤:専門機関に相談
夫の特性を理解する
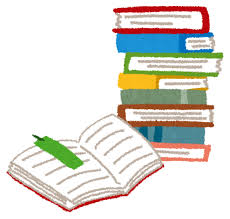
癇癪持ちの原因が、発達障害の可能性がある場合になります。
発達障害の可能性がある場合、「ご家族が当人の特性の理解をする」ことが大切になります。
当人の得意/苦手なことを把握し、なぜその言動をとるのか?を知ることから始まります。
本来は、ご本人も一緒に理解することが理想ですが、大人の場合、難しいことが多いです。(社会にある程度適応できている場合が多いため、受け入れ拒否の可能性がある)
そして、夫の特性を知った上で、具体的にどう対処すればいいのか、を考えることです。
例えば…
①ルーティン(※)がある夫
→買い物を頼む時、旦那さんがいつも通る道沿いの店にあるものを頼む
※自分の通る道を変えたくない
②急にやることが増えるのが苦手な旦那さん
→役割を決め、やることをメモでまとめ、見れるようにリビングに貼っておく
②は、やることをいつでも確認できる状態にし、事前に伝えておくことで、旦那さんのルーティンに入れ込んでもらうようにします。
このように、『旦那さんが不快に感じることを避ける方法』を考えることが、大切になります。
先ほどの例ですと、
①:いつも通る道以外の道を通ること
②:予定外のことをお願いされること
感情論ですと、終わりが見えないですが、このように原因に対して、具体的な方法ですと今よりもお互いストレスを減らすことができます。
旦那さんがどんな気質(ADHD?自閉スペクトラム症?)があるのか、本記事で絞られてきたら、本を読んで理解を深め、対処法を知りましょう。
「どの気質があるのか分からない」という方は、それを判断するために、本を読むのも良いと思います。
参考程度に、私のオススメの本を載せておきますね。
私の夫は発達障害?
夫婦カウンセリング

夫婦で一緒にカウンセリングを受けることです。(市/県の社会保険サービス機関に相談)
年々、日本でも夫婦カウンセリングは一般的になりつつあります。
別居

ここでいう別居とは、物理的/心理的距離を一時的に置き、ストレスを減らすためのものになります。
別居というと、ネガティブな印象を持たれる方が多いかもしれません。
ただ、心も体も安定した状態を作ることで、今後について冷静に考えることができる、有効な1つの選択肢になります。
離婚

ここまでの方法を夫が拒否し、進展が見られない状態のときは、離婚も1つの方法です。
「今の生活の状態が続く=家族みんなが幸せ」が考えられないなら、検討することをオススメします。
専門機関に相談

夫が発達障害の傾向があり、家族内で解決が難しい場合は、第3者の介入が必要になります。
相談先は、2つになります。
①:精神科(発達障害専門外来)
②:発達障害者支援センター
理想は、ご本人(夫)と家族で受診に行くことです。理由は、より良いアドバイスをもらうためです。
一人ですと、主観が入りがちで、専門家のアドバイスも実態(事実)とズレる恐れもあるためになります。
またご本人の理解が得られない場合は、家族だけでも良いです。客観的な意見がもらえるので、何ヶ月も一人で抱えて悩むより、負担も軽くすることができます。
解決につながらなくても、ご家族が話を聞いてもらえる人と繋がりが持てるのは、精神的な安定に繋がることができます。
「一人で抱え込まない状態を作る」が大切になります。
✅受診/診断を強要しない
大人の発達障害の場合、社会にある程度適応していることも少なくありません。当人が気付いていない場合も多いです。
そういった場合、無理に受診などを勧めることは、傷ついたり関係性の悪化に繋がることもあるので、注意が必要です。
夫の癇癪を「我慢し続けるリスク」

我慢し続ける方は、少なくないです。確かに我慢さえしてしまえば、一番丸く収まりやすいと考えやすいですよね。
ただ我慢し続けても、事態は悪化していきます。ここでは、我慢し続けることで、どんな悪影響なことがあるのか、解説していきますね。
①:カサンドラ症候群
②:子どもの二次障害
カサンドラ症候群
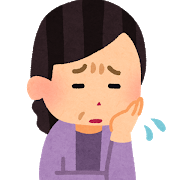
- 家族がなる二次障害
- 抑うつ※
- 体重の増減
- 無気力
※鬱に近い状態
ご家族の二次障害(カサンドラ症候群)です。我慢し続けた結果、家族が精神的に追い詰められ、鬱に近い状態になります。
子どもの二次障害

- 過度な緊張から敏感になる
- 叱責が続き、自己肯定感が下がる
- 親の発達障害→子供の二次障害の原因になる場合あり
子どもの二次障害は、いくつも種類があります。不登校、引きこもり、スマホ依存症等様々です。
詳しくは、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法をご覧ください。
✅カサンドラ症候群になりやすい人
- 真面目
- 几帳面
- 完璧主義
- 面倒見が良い
【癇癪持ちの夫 原因/接し方】まとめ

記事のポイントになります。
✅癇癪持ちの原因
・発達障害
・病気
・トラウマ
・セロトニン不足
✅癇癪持ちになりやすい人の特徴
・まじめ
・完璧主義者
✅癇癪持ちの夫への対処法
・夫の特性を理解する
・夫婦カウンセリング
・別居
・離婚
・専門機関に相談
✅夫の癇癪を「我慢し続けるリスク」
・精神科(発達障害専門外来)
・発達障害者支援センター
✅旦那さんの癇癪を我慢する悪影響
・カサンドラ症候群
・子どもの二次障害
以上になります。
本記事が、お役に立てれば幸いです。
【関連記事】
【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法








































[…] 【癇癪持ちの夫】我慢は解決方法ではない!4つの原因と妻の接し方とは […]
[…] 【癇癪持ちの夫】我慢は解決方法ではない!4つの原因と妻の接し方とは […]
[…] 【癇癪持ちの夫】我慢は解決方法ではない!4つの原因と妻の接し方とは […]
[…] 【癇癪持ちの夫】我慢は解決方法ではない!4つの原因と妻の接し方とは […]
[…] 【癇癪持ちの夫】我慢は解決方法ではない!4つの原因と妻の接し方 […]
[…] 【癇癪持ちの夫】我慢は解決方法ではない!4つの原因と妻の接し方 […]