

不登校の子で悩まれている方「不登校の子どもが母親に依存して困ってる。このままでいいのか不安。子どもにどう関わっていくべきか分からない」
お子さんが不登校ですと、「学校には行かせるべき?」「無理させないべき?」など、どうしてあげるべきか、分からなくなりますよね。
不登校のお子さんの中には、母親に依存している場合があり、接し方で悩まれる親御さんがとても多いです。
そこで本記事では、「母親に依存する不登校の2つの原因/接し方」についてお伝えします。
この記事を執筆している私は、育児/相談支援を15年以上してます。不登校のお子さんの支援も多くしてきました。
その経験を通して、必要な視点と具体的な関わり方をまとめています。
参考になれば幸いです。
目次
不登校の子が「母親に依存する原因」

原因の前に、「母親に依存する」とは、具体的にどういうものなのか、見ていきます。
・家の中でも常に母の近くにいる
・母が外出しようとすると不安がる
・母が家族と話していても、常に話しかける
これは一例ですが、母親に接している時間/近い距離感を求める言動が、共通して見られます。
次は、母親に依存する不登校の「原因」2つについてお伝えします。
①:生活の中で「安心/楽しい」が極端に少ない
②:生活の中で「不安/ストレス」が極端に多い
生活の中で安心/楽しいが極端に少ない

日常生活の中で、お子さんが感じる『安心/楽しい』が、極端に少ない場合になります。
人は、「安心」がベースにあって、生きていけるものです。
あの有名なマズローの5大欲求でも、食事や睡眠などの次に、大事と言われています。
母親に依存してしまう不登校のお子さんは、この「安心/楽しい」が極端に少ないことが多いです。
例えば…
・家族との関係性
・家族とのコミュニケーション
・家庭環境(家にいて安心できる)
お子さんの安心になる要素が極端に少ないと、「母親に依存する」「不登校になる」など、お子さんの言動に影響が出てきます。
また「楽しい」も同じで、お子さんの原動力になるため、必須になります。
生活の中で不安/ストレスが極端に多い
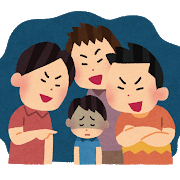
日常生活の中で、お子さんが感じる『不安/ストレス』が、極端に多い場合になります。
多くの人は、「不安」を抱えながら、生きていきます。
ただその不安が「極端に多い」「極端に強い」場合は、生活に支障が出てきます。
母親に依存する不登校の子でいうと、以下の内容が「不安の元」になっていることが、多いです。
・授業についていけない
・学校の担任が嫌い
・友人関係
・行きたくない習い事
これらの不安が強いと、不安を減らすため(自分を守る)に、「常に母親にベタベタする」など、お子さんの言動に出てきます。
✅不登校の原因は「家庭環境」が最も多い
不登校の原因というと、「いじめ」などをイメージされる方が、多いかもしれません。
でも実際は “いじめ” よりも、「家庭環境」が理由で、不登校になってる子が多いです。
母親に依存する「不登校の子の接し方」

母親に依存する「不登校の子の接し方」 は、2つあります。
不登校のお子さんにおいては、例外なく必要になります。
①:生活の中で「安心/楽しい」を増やす
②:生活の中で「不安/ストレス」を減らす
生活の中で安心/楽しいを増やす

お子さんの『安心/楽しい』を増やしていきます。
まず最初に、お子さんが、”何に対して”、安心を感じているのか、箇条書きしてみます。
例えば…
・家族にほめられる
・絵を描く
・公園で遊ぶ
・一緒に料理をする
・祖父母の家に行く
このように箇条書きにして、どれなら現実的に、頻度や時間を増やすことができるのか、確認をします。
お子さんをほめる回数を増やしたり、月に1回行っていた祖父母の家に行くのを、月に2回にしたりするイメージになります。
「お子さんの安心」を書き出し、増やせるものを決めていきます。
生活の中で不安/ストレスを減らす
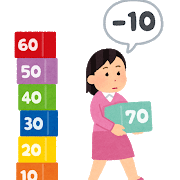
お子さんの『不安/ストレス』を減らしていきます。
先ほどを同じ様に、お子さんが何に対して不安を感じているのか、箇条書きしてみましょう。
例えば…
・学校に行く
・宿題
・担任
・学校の行事
・親に怒られる
現実的に、量や質を調整できるか、確認をしていきます。
例えばよくあるのは、宿題の量を減らしてもらったり、学校の行事は休む、などです。
あとは、親御さんが意識をして、怒る回数を減らすことも効果的です。
学校関係は、担任の先生に相談が一番になります。
もし相談できない場合は、校長先生などの管理職か、学校のスクールカウンセラーに相談するのが、良いと思います。
また「学校にいく」がストレスになっている場合は、”学校の何が”、不安なのか、お子さんに具体的に確認できると良いでしょう。
「国語の授業」「給食」など、具体的に出れば、その時間帯だけ欠席したり、
保健室で過ごして避けるなど、工夫できることがあります。
学校に無理に行かせることは、逆効果
お子さんが「行きたくない」と行っている状態で、学校に行かせることは、逆効果になります。
学校での失敗体験から自信を失ったり、疲弊して途中から学校にいけなくなることがあります。
不登校の子は、一見元気そうに見えますが、強い不安やストレスを抱えています。
この不安やストレスを『お子さん一人で抱え込まない様に、支えていくこと』が、大切になります。
ストレスを把握する方法
ストレスを数字にして、教えてもらう方法があります。
例えば、ストレスを5段階で、1が1番低く、5が1番高い、とします。
「学校の宿題は4、給食が2」など、具体的にして、親子で一緒にストレス値を確認し、
把握・工夫できる箇所を見つけていくことが、効果的です。
言語化が難しいお子さんには、数字は共通認識が持ちやすいです。
【不登校の子の母親への依存】まとめ

記事のポイントになります。
✅母親に依存する
「不登校の子の特徴」
・家の中でも常に母の近くにいる
・母が外出しようとすると不安がる
・母が家族と話していても、常に話しかける
✅不登校の子が
「母親に依存する原因」
・生活の中で “安心” が極端に少ない
・生活の中で “不安” が極端に多い
✅母親に依存する
「不登校の子の接し方」
・生活の中での “安心” を増やす
・生活の中での “不安” を減らす
・”安心/不安” を具体的に出す
・現実的に工夫できるものをやる
✅不登校の子の将来に向けて
「備えたいコト」
・取り組みやすい学習スタイル
・学習の成功体験
・特性に合う学習法
・レベルに合う学習内容
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【不登校の子は勉強追いつくの?】学習支援でも実践してる6つの勉強法








































