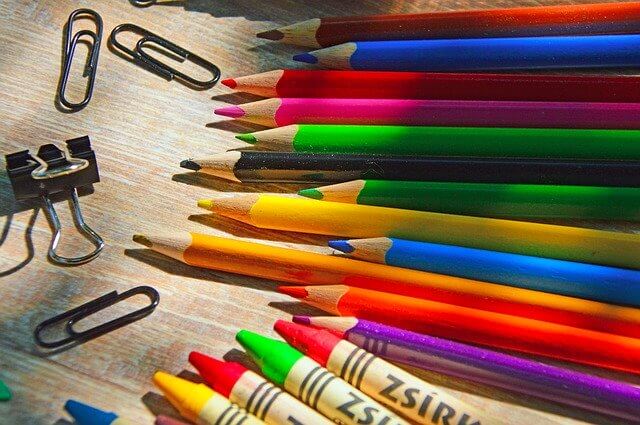

子どもの学級で悩まれてる方「特別支援学級から普通学級に転籍はできるの?転籍する基準、タイミング、注意点が知りたい」
お子さんが支援学級に通っていると「普通学級へ転籍」を考えられる方も少なくないと思います。
「普通学級でもついていけるんじゃないか」
「将来のことを考えると、通常学級に在籍してた方が良いんじゃないか」
と思われる方もいらっしゃると思います。一方で、通常学級への転籍はできるのか、どんなケースができるのか、疑問に思われる方も多いと思います。
そこで本記事では「支援学級から通常学級へ転籍する子の3つの事例/共通点」をお伝えしたいと思います。
この記事を執筆してる私は、療育/発達支援を15年以上していて、現在も支援に携わってます。
その支援経験の中で、支援学級から通常学級へ転籍する際に、大切だと感じたことをまとめました。
参考になれば幸いです
目次
特別支援学級⇨普通学級「転籍する目安」

支援学級から普通学級へ「転籍する目安」は、4つあります。
①:「本人の意思」がある
②:「学校側が了承」してる
③:今の支援学級で「大きな困りがないor対処できてる」
④:「支援学級に在籍した理由(本人の特性・困り)」が
「通常学級で対処できるイメージ」が持ててる
本人の意思がある

本人の気持ちになります。どんなに客観的に見て、通常学級の方が本人に合っていたとしても、本人も気持ちがなければ、それまでになります。
通常学級は、支援学級とは環境が変わります。
関わる人、授業のスピード、レベルなど、変わってきます。
そういった支援学級との違いを理解した上で、本人が「通常学級へ転籍したい」という意思があるかを確認することが重要になります。
学校側が了承してる
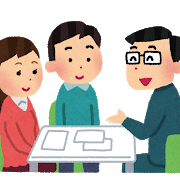
学校側として「通常学級でも良い」という見立てがあるかです。
当たり前ですが、学校の様子は学校の先生が一番把握してます。学校での様子、学校の環境を踏まえ、本人が通常学級で過ごしやすいか、の判断はとても重要になります。
最終的な判断は、親御さんになりますが、判断材料の1つとして学校の見立ても大事になります。
支援学級で困りがない or 対処できてる

支援学級で、本人が大きな困り事なく、過ごせていることになります。
配慮や理解がある支援学級で困り事がある場合は、通常学級へ転籍して上手くいくことは、ほとんどありません(勿論、先生との相性など、細かくいうと、言い切れないケースも1部あります)
配慮や理解がある支援学級の中で、大きな問題なく過ごせているのは、最低条件として必要になります。
通常学級で過ごせるイメージが持ててる

客観的に見て、本人の特性・困りになりそうな場面に対して、通常学級という環境で対処できる(折り合いがつけられる)イメージが持てているかになります。
例えば、通常学級はクラスメイトが多いので、ザワザワした音などが本人の集中力を落とすことに繋がる場合は、課題に取り組む時は、イヤーマフをつけて気になる音を減らす工夫をするなどです。
また、周囲のクラスメイトの言動が気になって、指示を聞き漏れがある子でしたら、席を一番前にしてもらい、他の子の様子が視界に入らないように調整をします。
先生の工夫という視点でしたら「一度クラスを静かにさせてから(他の音がない環境を作る)、説明を始める」ですと、聴覚過敏の子も、指示の聞き漏れが少なくなります。
このように、先生の配慮、環境作りを通して、本人が大きく困らない状態を作れるかが大切なポイントになります。
✅中学生は「高校受験」の選択肢が広がる
お子さんが中学生の場合、普通学級に在籍することで、受験できる高校の選択肢が増えます。
残念ながら、現在のほとんどの特別支援学級では、内申点が「つかないor低評価(5段階で1など)」になります。
つまり、内申点の影響が高い『公立の高校受験』が、かなり厳しくなります。
ただ、普通学級に転籍をして内申点が得られれば、公立の高校受験も選択肢に入ることになります。
詳しくは、【特別支援学級だと内申点は出ない?】普通学級との違い をご覧ください。
特別支援学級⇨普通学級「転籍時の注意点」

支援学級から普通学級への「転籍時の注意点」は、2つあります。
①:本人に「事前に伝えておく」
②:「学校・地域の差」がある
本人に事前に伝えておく
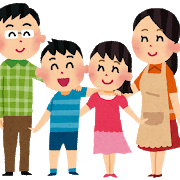
今まで過ごしてきた支援学級、転籍する通常学級との違いを伝えておきます。
本人の中で「思ってたのと違った。嫌な気持ちになった」とならないように、事前に違いについて把握してもらいます。
違いについては、人数、流れ、場所、授業のレベルなど要点をお伝えしつつ、本人が困る可能性がある場面での対処法も伝えます。
例えば、支援学級では、先生がこまめに時間をとって「分からない所ある?」と聞いてくれていたが、通常学級では、その時間がないこと、また困ったときは、挙手をして先生に伝えるなど、支援学級との違いで困りそうな場面に対して、予め対処法を具体的に伝えていきます。
通常学級の担任にも伝え、協力を得られる状態があると理想的です。
学校/地域の差がある

学校や地域差、同じ学校でも年度ごとによって、学級の状況は変わってきます。
学校によっては、支援学級から通常学級へ転籍することがハードルが高い場合もありますし、逆に学校が後押しをしてくれ、転籍できるケースがいくつもある場合もあります。
また校長先生が変わることで、良くも悪くも変わるため、情報収集はとても大切になります。
私の経験上、特に多い理由は、下記になります。
①在籍校に特別支援学級がない
(もしくは空きがない)
②支援学級の生徒数の先生のバランス
③発達検査や知能検査の結果が必要
(且つ、知的な遅れ等、支援の必要性が記されていること)
①の場合は、近隣の学校まで通う形になります。
送迎は、親御さんがしなければならない場合もあります。
②は、表には出ない学校側の事情になります。学級運営をする為の生徒数のバランス・先生の人員体制の事情があります。
先輩ママ、担任やスクールカウンセラーを通して、支援学級の先生から情報を集めておけると良いと思います。
【関連記事】
【支援学級の子は高校進学できない?】7つの進路先~進路選びの3つのポイント~
✅二次障害になるリスクを避けたい
二次障害とは、お子さんの障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)がキッカケで、叱責や失敗体験を重ね続け、
不登校や引きこもり、鬱などになることをいいます。
お子さんにとって、が普通学級という環境で「○○ができなかった」「○○が嫌だ」など、ネガティブな経験が重なり続けるよ、二次障害に繋がる恐れがあります。
【合わせて読みたい記事】
特別支援学級⇨普通学級「転籍した3つの事例」
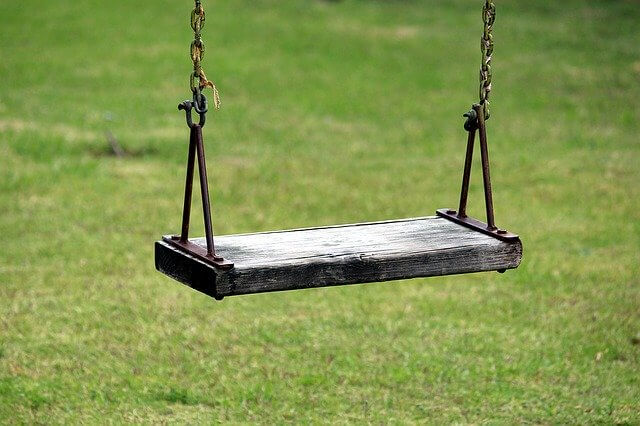
支援学級⇨普通学級へ「転籍した3つの事例」をお伝えします。
私が支援に携わったケースになります。
✅小3女子(ADHD 不注意タイプ)
就学時健診で、支援学級を勧められ、親御さんが「学校が嫌にならない様に」という心配もあり、小1から支援学級で通学されていました。ADHDで不注意性が高く、注意が散りやすい為、指示を聞いて行動に移したり、集団行動に1~2テンポ遅れる様子がややありました。支援学級では、5名ほどのクラスで、学校に楽しく通えていました。支援学級の中では、大きな困りもなく、知的な遅れもない為、環境(気になるモノが少ない)が整っていれば、大きな問題もありませんでした。そんな中、小2の秋の担任の先生との面談で「通常学級でも良いのでは」というお話がありました。スクールカウンセラーなどの意見も聞きながら、小3~通常学級に転籍することになりました。学校側の理解もあり、担任の先生には、本人の特性も伝わっていました。学校側も本人の特性に合わせて関わるスタンスであった為、個別の声かけも工夫してくれました。例えば、机の上にモノがある状態で次の指示を出すのではなく、一旦机の上のモノを片付ける指示を出し、そこができたら、次の指示を出していました(注意が逸れる刺激を減らす為)。こういった配慮があるコトで、通常学級でも大きく遅れて困ることはありませんでした。また手伝ってくれるクラスメイトを本人の近くの席にするなど、環境的な配慮もありました。多少周りと比べて、1テンポ遅れたり、先生の指示の聞き逃しもありますが、大きな困りまでいかず、楽しく学校生活を送っていました。
✅小5男子(ASD/自閉スペクトラム症)
小2~支援学級で通っていました。思ったことをすぐ口にしたり、ルールを守らない子に怒ってトラブルになったり、人の気持ち・状況を理解することが難しい特性がありました。トラブルが続いたこともあり、支援学級に転籍し、SS(ソーシャルスキル)のサポートも受けながら、少人数のクラスで過ごしていました。ただ交流級で通常学級の子との関われる機会もあった為、給食や体育などの時間は通常学級の子と一緒に参加していました。チクチク言葉、フワフワ言葉など、人の気持ち、伝え方のフォローも受けながら、また療育では、感情の温度計(自分の気持ち理解)、相手の気持ち・状況理解の支援も受けていた為、人とのやりとりも大きなトラブルを回避できるぐらいスムーズになり、小5~通常学級への転籍が決まりました。事前に担任の先生から、クラスメイトに本人の特性(気になったことを言葉に出しやすい、言葉が強くなることがあるけど、悪気はない等)を伝えてくれたこともあり、通常学級で大きなトラブルがあることなく、過ごすことができました。
✅中2男子(ASD/自閉スペクトラム症)
小学校で支援学級に在籍していた為、中学校も支援学級でスタートしました。人への関心が薄く、相手の立場で考えることが得意でない為、時々、失礼な言動をとってしまうことがありました。親御さんがいじめなどの心配もしていて、小学校からの支援学級の良さを知っていたこともあり、支援学級のまま、過ごしていました。ただ、中学校生活で大きな困りがないこと(友達がいなく、一人が過ごすことが多かったが、本人は気にしていない)、高校進学の選択肢が狭まることを考え、通常学級へ転籍することを決めました。担任の先生とも、進路・就職を見据えて、転籍することになりました。高校では、公立の普通高校に進学した為、支援学級在籍ですと公立高校の受験は厳しかった為(内申点)、結果として、転籍は、良い判断になりました。
【関連記事】
【発達障害だけど普通学級で貫き通します】事例の紹介~学級選びのポイント
通常学級へ転籍する前に「押さえたいこと」

支援学級⇨通常学級へ転籍する前に「押さえておきたいこと」を3つお伝えします。
この3つは、親御さんだけで出来る手立てになります。
先輩ママから情報を集める
『同じ境遇のママ友にお話を聞く』ことです。
学級の転籍は、学校側とのやりとりもあります。
学校側のリアルなスタンスが事前に分かっていると、今後の転籍を検討する上で、スムーズになります。
時々あるのは、学校側が曖昧な返事をし続け、親御さんが療育もせず半年以上も待つ…
結果、今も入れないまま時間だけが過ぎた…という、勿体ないケースです。
その学校や学級に転籍したママ友と繋がることができる場合は、とても有効な方法になります。
もし、難しければ、違う学校でも結構ですので、学級の転籍を経験されたママ友に聞くのも1つです。
ただ、経験しているママ友を見つけるのは難しいですし、
こういった相談をするのも勇気がいると思うので、ハードルが高い方もいらっしゃると思います。
ただ、「お子さんのため」という観点でいくと、一番リアルな情報を集められると思い、ここで紹介させていただきました。
通級の検討
普通学級と支援学級の間に、「通級」という学級があります。
普段は普通学級で過ごすのですが、特定の科目だけ、別室で個別指導(少人数指導)を受けられる制度になります。
特別支援学級と通級の違いについて知りたい方は、下の記事をご覧ください。
学習対策
学習に不安がある子には、学校の授業以外の学習サポートがあると安心です。
授業についていけず、学校への行き渋りに繋がるケースはありますので、事前に学習対策ができていると良いです。
支援学級から転籍する子の中で、授業の難易度ペースの違いで、戸惑う子もいますので、失敗体験に繋がる前に、サポートしていきたい点になります。
今は、タブレット学習は、在籍校の教科書に準拠されている為、授業の予習・復習ができ、学校の授業の補填ができます。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
発達障害に関わらず、グレーゾーン、発達ゆっくりな子など、学習に困りを抱えてる子に関する内容になります。
学習方法の1つとして、参考になれば幸いです。
【特別支援学級から普通学級に転籍】まとめ

記事のポイントになります。
✅支援学級⇨普通学級
「転籍する目安」
・本人の意思がある
・学校側が了承してる
・今の支援学級で大きな困りがないor対処できてる
・”支援学級に在籍した理由(本人の特性/困り)” が
”通常学級で対処できるイメージ” が持ててる
✅支援学級⇨普通学級
「転籍時の注意点」
・本人に事前に伝えておく
・学校、地域の差がある
・二次障害のリスクがある
✅支援学級⇨普通学級
「3つの事例」
・小3女子(ADHD 不注意タイプ)
・小5男子(自閉スペクトラム症)
・中2男子(自閉スペクトラム症)
✅普通学級へ転籍する前に
「押さえておきたいこと」~親ができること~
・先輩ママからの情報
・通級の検討
以上になります。
本記事が、お役に立てれば幸いです。
【関連記事】







































