

子どもの不登校で悩まれてる方「不登校の子が再登校する時の注意点が知りたい。復帰する時のポイントも教えてほしい」
不登校のお子さんにとって「再登校」は、不安や緊張を感じやすい場面になります。
実際に再登校が上手くいかず、辛い思いをされるお子さんは少なくありません。
ご家族として、どのようにサポートすればいいのか、とても難しい問題になります。
そこで本記事では不登校の子の「再登校の注意点/大切なポイント」に関する情報をまとめました。
この記事を執筆してる私は、不登校・療育支援を15年以上しています。
現場で支援をしてきて感じたことを、事例を通してまとめてます。
本記事の後半では、不登校の子が中長期的に備えておきたいこともお伝えします。
参考になれば幸いです。
目次
再登校する時「4つの注意点」~失敗しない為に
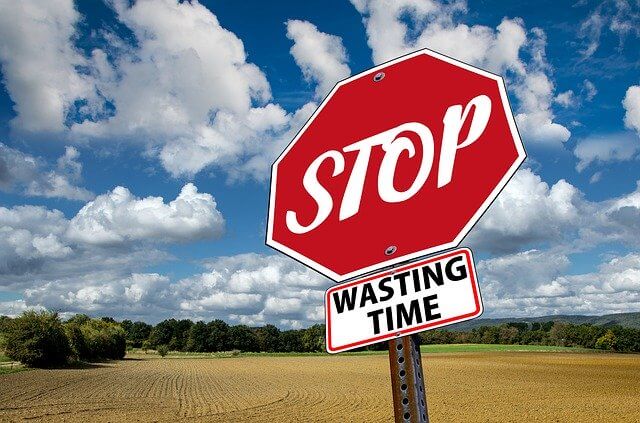
不登校の子が、再登校する時の「注意点」は4つあります。
①:「再登校=解決」と思わない
②:周りが「過剰反応」しない
③:「過度な期待/プレッシャー」をかけない
④:本人に「再登校しなきゃ」と思わせない
再登校=解決 と思わない

「数日登校できた」
「1週間休まず登校できた」
お子さんが望んで出来たことであれば、喜ばしいことですが、「登校できた=不登校が解決」ということにはなりません。
不登校問題で大切なことは、本人が抱える困り(不安)の原因に対して、本人が対処できる状態(周りのサポートを受けながら)を作っていくことです。
私が知る限りでは、何の心配もなく、不登校問題が完全に解決したと言えるケースは、多くありません。
学校に登校できてる期間があっても、実際のところは、本人の一時的な頑張り(無理をして)だったり、
担任やクラスメイトの理解/協力があるなどの環境要因だったりと、長期的に保証できるものではない場合もあります(もちろん、環境との折り合いがついて、登校が安定するケースもあります)。
環境(担任やクラス)が変わったタイミングで、不登校に戻る子も珍しくありません。
目の前の環境に対して、本人が過ごしやすくなる様に、本人や学校と相談しながら進めていくことが大切になります。
周りが過剰反応しない
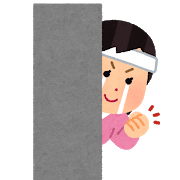
周囲の大人が、本人の1つ1つの言動/変化に、過剰に反応しないことになります。
例えば、これらの言動があります。
・登校できた
・学校に行くと発言した
・学校の準備を始めた
・勉強を始めた
ご家族、担任の先生など、大人の方からしたら、本人のポジティブな言動(再登校に対する)は嬉しいですし、応援したいものです。
ただ過剰に反応することで、本人はプレッシャーを感じて「期待を裏切れない、失敗できない」と気を張って、自分を追い詰めてしまいます。
無理を続けて反動がきて、不登校に戻る場合もあります。
再登校の失敗は、本人の自己肯定感を著しく低下させる為、予防に最善を尽くしたい点になります。
過度な期待/プレッシャーをかけない
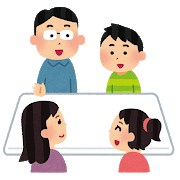
先ほどの過剰反応に似ていますが、なるべく期待/プレッシャーを感じさせない様にします。
不登校の子は、自己肯定感が下がっていて、周りの反応に敏感なことが多いです。
周りの大人の応援を期待と捉え、自分を追い込んでしまうこともあります。
「登校できたね、明日も頑張ろう」
「少しでも学校行けるといいね」
「先生が待ってるよって言ってたよ」
など、一見本人を支える言葉のようなものが、本人にとっては負担になる場合が多いです。
本人に”再登校しなきゃ”と思わせない

「再登校しないといけない」と本人に思われない様にします。
本人が「再登校以外許されない」という認識をもつと、精神的に追い詰められ、状況は良くない方向に進みます。
「◯◯しなきゃ」
「◯◯すべき」
これらは、不登校の子と関わる上では、特に “避けたい考え方” になります。
再登校で失敗に繋がりやすい「4つの原因」

再登校の「失敗に繋がりやすい原因」は、4つあります。
①:「休息不足」になってる
②:「本人の状態」「通い方」が合ってない
③:本人との「すり合わせ不足」
④:「学校の環境」が悪い
休息不足になってる
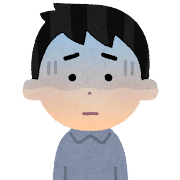
個人差がありますが、不登校の子には、最初は「休息」が必要な場合が多いです。
心身ともに疲弊していたり、ストレス過多になってます。
そんな状態をリセットするために、ある程度休む必要があります。
休息が足りてないと、心が折れやすくなり、再登校の失敗に繋がります。
再登校の失敗要因の1つとして、とても多いものになります。
本人の状態と通い方が合ってない
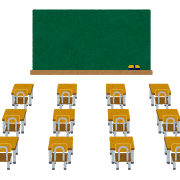
本人の状態と学校の通い方が、合ってない場合になります。
明らかに休息が必要な子が、週5日フルで登校していたり、苦手で嫌な授業にも無理して参加していたり…
本人が無理をしてる状態が続くと、再登校の失敗の確率は、確実に上がります。
本人とのすり合わせ不足

登校することの意味、通い方、ペースなど、本人とのすり合わせが不十分な場合になります。
本人が選択できる機会が少なかったり、大人が話を進めてしまう流れが強いと、
再登校しても、途中で休むことに繋がりやすくなります。
学校の環境が悪い

明らかに、学校の環境が本人に合っていない場合になります。
本人には、個別配慮が必要にも関わらず、
・担任の理解がない
・個別対応は不可
(学校や先生のスタンス)
このような環境ですと、お子さんのコンディションが整っていても、環境的な問題で難しいことが多いです。
また嫌がらせをしてくるクラスメイトが嫌、という場合もあります。
クラスメイトの問題は、先生が介入することで、改善することもあります。
【関連記事】
再登校する時の「6つのポイント」

再登校する時の「ポイント」は、6つあります。
①:本人の「気持ち」
②:目的は「本人のポジティブな実感」
③:本人に必要な「配慮/環境」があるか
④:再登校は「1つの選択肢」と考える
⑤:「再登校以外の選択肢」も用意する
⑥:家族は「いつも通り過ごす(淡々と)」
本人の気持ち
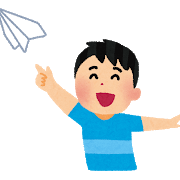
本人の気持ちが全ての土台になります。
本人の気持ちとは、本人が感じる「納得感/必要性」になります。
・なんで学校に行くの?
・自分にとって何か意味あるの?
(登校するメリット)
この2点を本人がどこまで感じられるか、が大事になってきます。
例えば、
・友達と話したいから、午前中だけ登校する
・将来建築関係の学校に行きたいから、受験に必要な科目の授業だけ受ける
“本人が望むこと” と “登校すること” の重なる部分を見つけることが重要になります。
目的は 本人のポジティブな実感

「学校に行く」を目的にするのではなく、
「学校に行って、楽しかった!」
「思ってたより嫌じゃなかった!」
と実感できることを目的にするイメージになります。
「学校に行く」は、あくまで手段になります。ここが目的になってしまうと「学校に行けたけど、本人は辛い思いをして、学校への苦手意識が強まった」になります。
不登校問題で、とても多いパターンになります。
どの時間帯に、どのような通い方で参加することで、本人が「学校に行って良かった」「学校で◯◯ができた」と実感できるのか、そこを探すことが大切になります。
本人に必要な配慮/環境があるか

本人が「学校に行って良かった(嫌じゃなかった)」と思える為の「本人への配慮・環境」はあるのか…になります。
ここがないのに学校に行っても、本人の失敗体験を重ねるだけになってしまいます。
【合わせて読みたい記事】
再登校は1つの選択肢と考える
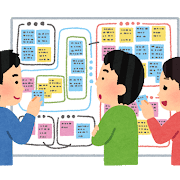
「登校しないといけない」
「学校を休むのは良くないこと」
周囲の大人がこのような認識を持つと、
本人のストレスが溜まる⇨コンディションが悪くなる⇨学校を休む⇨自己肯定感が下がる⇨不登校が強まる
このような負のサイクルに陥ります。本人もご家族も辛い状況に追い詰められます。
それよりも、
『登校も、休むのも。同じ選択肢の1つ』
と周りの大人が、言葉や態度で示し続けることで、本人の過度なストレスが避けられる為、本来必要な自分に向き合う時間、家族で向き合う時間がとりやすくなります。
過度なストレスがあると、正常なコンディションでない為、本人や家族が本当の意味で問題解決する為のコミュニケーション/アクションをとることが難しくなります。
本人自身の気持ち、本当に望んでいること、苦手なこと(配慮や工夫が必要な)等が見えづらくなり、問題が長期化する可能性が高まります。
再登校以外の選択肢も用意する
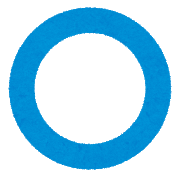
再登校以外の選択肢がないと、再登校できなかった時に、本人の自己肯定感が下がる可能性が高まります。
休んだ時の過ごし方を事前に決めておけると、同じ「学校を休んだ日」でも、充実度や本人の気持ちは違ってきます。
本人と一緒にどんな過ごし方ができるのか、一緒に考えることが大切になります。
具体的な過ごし方については、こちらの記事をご覧ください。
✅「小学生の子の過ごし方」について
✅「中学生以上の子の過ごし方」について
家族はいつも通り過ごす
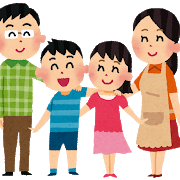
不登校の子は、気持ちの波が大きいことが多いです。
学校に行けたり、行けなかったり、イライラしてたり、落ち込んだり..お子さんによって様々になります。
お子さんがどんな状態の時にも、良い意味で変わらず見守る(本人が困っていれば助ける)スタンスが大切になります。
“過剰反応” に近い考え方ですが、周りの大人の反応次第で、
本人のネガティブな気持ちを減らすことができます(少なくとも増やすことを予防できる)。
【関連記事】
【別室登校の過ごし方】メリット/デメリット/教室へ復帰する5つのポイント
再登校で失敗した時の「3つの対処法」

再登校で失敗した時の「対処法」は、3つあります。
①:「十分な休息」をとる
②:「学校の通い方」を見直す
③:「学校以外の選択肢」を考える
十分な休息をとる

足りてない休息を、しっかりとります。
好きなことをして過ごしてもらい、心身ともに休んでもらいます。
休息をとってる時の注意点は、2つあります。
・本人が頑張りすぎてないか
(休息になっていない)
・周りが登校の促しをしてる
(本人が無理してしまう)
お子さんの様子を見ながら休息できているか、見守っていきます。
特に、下の特徴がある子は、注意が必要になります。
・完璧主義(0or100思考)
・真面目で力を抜くのが苦手
・妥協ができない
本人の表情、声のトーン、家族とのやりとりの様子など、変化を見ていきます。
【関連記事】
【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン/関わり方/注意点
学校の通い方を見直す
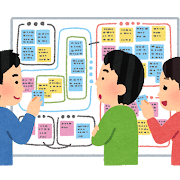
本人の状態に合わせるため、通い方を見直していきます。
例えば、通い方なら、
・授業の部分参加
・保健室登校
・辛くなったら別室に移動
など様々な方法があります。
お子さんの状態に合わせて、通い方のハードルを下げることが大切になります。
通うペースも同様になります。
・週3日に減らす
・好きな授業だけ参加
(1日に受ける授業数の調整)
通い方やペースは、学校や担任の理解/協力が必要なため、連携は必須になります。
具体的な “学校とのやりとり” に関しては、こちらの記事をご覧下さい。
学校以外の選択肢を考える

「本人の状態」と「学校の環境」の組み合わせ次第では、環境を変える方が良い場合もあります。
特に、学校の理解が得られず、本人が辛い思いをしてる場合は、検討する余地はあると思います。
こちらは、選択肢の例になります。
・フリースクール
・通信
・習い事
・転校
・自宅学習
(担任が変わるまでの期間)
習い事に関しては、こちらの記事をご覧下さい。
それでも「再登校が難しい時」~その場の対応

本記事の内容を実践されても「再登校が難しい時の原因/対応」を、3つお伝えします。
あくまで、その場での対応になります(根本的な対応は、後述します)。
原因は、複数重なっていることもよくあります。
①:「休息」が足りてない
②:本人が感じる「安心要素」が少ない
③:本人が感じる「不安要素」が多い
休息が足りてない

不登校の子は、精神的に疲弊している状態のことが多いです。
取り組む気力がなかったり、心を閉ざす様子がある子は、休息が必要になります。
心と体を十分に休ますことが、不登校の子のサポートの最初の1歩になります。
休息の具体的な取り方は、こちらの記事をご覧ください。
【関連記事】
本人が感じる 安心要素 が少ない

本人が生活の中で感じる「安心感」が足りていない場合になります。
不登校問題の場合は、学校での安心感になります。信頼できる先生、友達、場所など、本人が安心できる要素が足りていない場合が多いです。
本人にとって、何があると安心できるのか、聞きながら、可能な範囲で作って行くことが大切になります。
よくある例ですと、これらの要素があります。
・信頼できる先生の存在
・好きな先生と話す時間
・友達との交流
・辛くなったら保健室に行ける
(教室以外で過ごせる場所)
本人が感じる 不安要素 が多い

先ほどの「安心要素」と考え方は、同じになります。
本人が感じる不安要素を聞いて、可能な範囲で減らしてくイメージになります。
よくある例は、こちらになります。
・怖い先生
・苦手なクラスメイト
・嫌いな授業
クラスメイトですと、席を離す、嫌いな授業だけは休む、などの方法があります。
現実的に難しいことも多いですが、可能な範囲で工夫していくことが大切になります。
【不登校の再登校 復帰時の注意点】まとめ

記事のポイントになります。
✅再登校する時の
「4つの注意点」
・”再登校=解決” と思わない
・周りが過剰反応しない
・過度な期待/プレッシャーをかけない
・本人に “再登校しなきゃ” と思わせない
✅再登校の失敗に繋がりやすい
「4つの原因」
・休息不足になってる
・”本人の状態” と “通い方” が合ってない
・本人とのすり合わせ不足
・学校の環境が悪い
✅再登校する時の
「6つのポイント」
・本人の気持ち
・目的は本人のポジティブな実感
・本人に必要な配慮/環境があるか
・再登校は1つの選択肢と考える
・再登校以外の選択肢も用意する
・家族はいつも通り過ごす(淡々と)
✅再登校で失敗した時の
「3つの対処法」
・十分な休息をとる
・学校の通い方を見直す
・学校以外の選択肢を考える
✅それでも
「再登校が難しい時」~その場の対応~
・十分な休息をとる
・本人が感じる “安心要素” を増やす
・本人が感じる “不安要素” を減らす
✅それでも
「再登校が難しい時」~今後の備え~
・学習の苦手意識の払拭
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】









































[…] 【不登校の再登校】復帰する時の6つのポイント […]
[…] 【不登校の再登校】復帰する時の6つのポイント・4つの注意点 […]