

場面緘黙の子の育児で悩まれている方「家では普通に話せるのに、外で話さないのは甘えなの?どう接すればいいか知りたい」
「家では普通にしゃべるのに、外で話さないのは甘え…?」
「話さない原因が、甘えなのか分からない…良い接し方が分からない…」
家では普通に話をするのに、家を出た途端話をしなくなる..「何で??」と不思議に思ったり、どう接していいか困ってしまいますよね。
この記事を執筆してる私は、お子さんの療育指導/相談支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
これまで、場面緘黙の子への支援もしてきました。
その経験を元に、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
場面緘黙とは
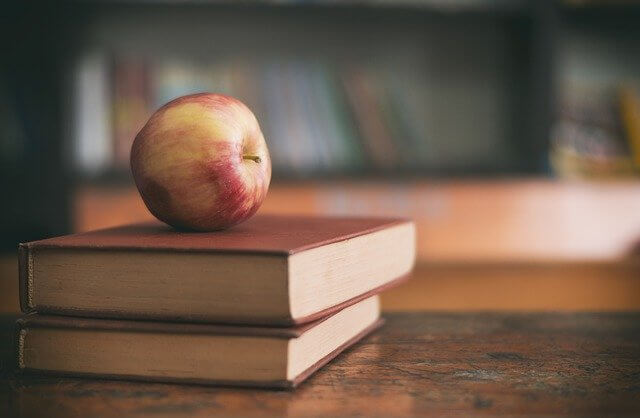
場面緘黙(かんもく)とは、特定の場面で、話をすることが難しい状態をいいます(家ではごく普通に話せるのに)。
例えば、幼稚園・保育園・学校・習い事などの場所で人と話せない状態が、1ヶ月以上続くなどです。
場面緘黙の原因
原因は、医学的にはっきりしてません。ただ原因として、扁桃体(不安/恐怖を司る脳の一部)の過敏性が指摘されています。
扁桃体(へんとうたい)とは、身の危険が迫ると対処法(戦うor逃げる)を一瞬で判断する、脳の一部になります。
この扁桃体の過敏さから「話さなきゃ」と分かっていても、強い不安にかられ、話すことが難しくなると、言われています。
場面緘黙の割合
0,2~0,5%になります。学校に、数名はいる計算になります。
人見知りとの違い
程度の違いになります。社会生活に大きな支障が出る場合は、場面緘黙として継続的なサポートが必要になります。
場面緘黙の診断基準
□特定の場面(保育園/幼稚園/学校など)で一貫して話せない
□話せないことにより、社会生活/成長に大きな影響が出ている
□1ヵ月以上続いている(入園/入学時など特定の期間ではない)
□話せない理由が言葉の遅れによるものではない
□コニュニケーション障害/発達障害とは違う
場面緘黙の子の「5つの特徴」

場面緘黙のお子さんの困りは『能力が発揮できず、社会生活に支障が出る』ことになります。
場面緘黙のお子さんは、緊張する場面になると、これらの様子が見られます。
①:固まる
②:無表情
③:反応がない
④:声を出さない
⑤:常に緊張してる
①~⑤の状態になることで、伝えたいことが伝えられない、誤解を受け辛い思いをすることが増えます。
「話せない」ことで失敗体験が増えてくると、二次障害(鬱など)に発展し、困りが強まる場合もあります。周囲の理解が、大切になってきます。
【関連記事】
場面緘黙の子の「4つの接し方」

場面緘黙のお子さんへの接し方は、大きく4つあります。
基本的には、お子さんの安心できる人・場所・活動・時間を、作ることになります。
これから説明する4つの内容は、全てお子さんの「安心」が、前提のものになります。
①:「家/家族以外で」楽しかった経験を増やす
②:「夢中になれるもの/場所」を増やす
③:「好きな習い事」をする
④:1~3の楽しめたことを「振り返る」
家/家族以外で楽しかった経験を増やす

『家/家族以外の人と関わって楽しかった』という経験を作ることが、大切です。
この成功体験が積み重なってくると、人と関わることも楽しみが増え、緊張も和らいでいきます。
緊張/不安を減らす方法も大切ですが、それ以上にお子さんの「楽しかった!」の経験を積むことが、必要になります。
夢中になれるもの/場所を増やす

お子さんの『夢中になれるもの/それができる場所』を、増やすことです。
これが増えてくると、人と関わる手段が増えます。言葉で交わす以外にも、一緒に何かを作ったり、ゲームをしたり、スポーツをするなどがあります。
言葉だと緊張しても、話すことが求められず楽しめる方法なら、関わりやすいです。
好きな習い事をする
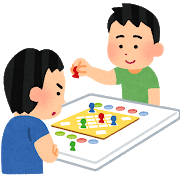
お子さんの『好き!楽しい!』が詰まった習い事をします。
先ほどの夢中になれるものを、一定の時間や場所を得ることで、
お子さんの成功体験や自己肯定感が上がる機会が保つことができます。
1~3の楽しめたことを「振り返る」
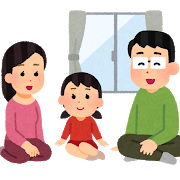
1~3で楽しめた経験を家族(お子さんが安心して話せる人)で話題として話して、楽しく振り返ります。
お子さんが1~3の経験を「少し緊張するけど、楽しいし、またやりたい」と思ってもらうことが、大切になります。
そのために、家で楽しかったことを振り返ることは、とても良いことです。
場面緘黙の子に避けたい「3つの関わり方」

場面緘黙の子に避けたい「関わり方」を3つお伝えします。
話をさせようとする

場面緘黙のお子さんに、「声を出す、話をしてもらう」ことを求めるのは、避ける必要があります。
分かっていても、できないのが困りなので、「求められる→話せない→失敗体験→自己肯定感下がる→一層話せなくなる」
このような流れに、陥りやすいです。場面緘黙のお子さんは、周囲の変化に敏感です。
大人の「話をさせよう」という意図も感じ取り、構えてしまったり、緊張が強まり、拒否感が強まっていきます。
場面緘黙のお子さんに話をするよう促したり、練習させようとするのは、最も避けるべき関わりになります。
否定する

「話せない」ことを否定することは避けるべきです。「話せないとダメだよ」はもちろんですが、
・今後は頑張って声出してみよう
・今日、先生に挨拶できた方がよかったね
このようなお子さんからしたら、否定されたと捉えられる表現も、避けられた方が良いです。
「やっぱり自分はダメだったんだ」と思い、自信を失い、ふさぎ込んでしまいます。
「話せない」を連想させる声掛けも、避けていきたい所です。
人前で話せたことを褒める

場面緘黙のお子さんは、人に注目されることが負担になります。
・人に注目される
・話すことそのものに触れる
これらも避けられる方が、良いです。話せても自然にしていて、やりとりを楽しめれば、十分です。
もし、お子さんの気持ちを確認されたい場合は、家など、お子さんが安心して気持ちが言える空間をお勧めします。
お子さんの気持ちに寄り添った日々の関わりが、大切になります。
✅「学習場面」が負荷になることも
勉強を教わる場面で、
・分からない箇所が聞けない
・分からない所が伝えられない
など、学習面で膨大なエネルギーを使ったり、ストレスを感じる子もいます。
特に小学校中学年以上ですと、親御さんが教えることも難しくなってくる為、塾や家庭教師が必要になってきます。
ただ場面緘黙の子の場合、それが難しい場合も多いです(形でできても、本人が無理をしてるケースがある為)。
お子さんの学習の場面で負荷がかかっていそう(かかりそう)でしたら、タブレット学習をお勧めします。
タブレット学習では、アニメーション・音声で解説をしてくれ、分からない箇所は何度も確認することができます。
「伝えられない・聞けない・分からなかったらどうしよう」という不要な緊張/ストレスを避けることができます。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
発達障害の子向けの記事になりますが、場面緘黙のお子さんにも参考になる内容になってます。
1つの学習サポートの方法として、参考になれば幸いです。
【場面緘黙の子 話さないのは甘え?】まとめ

記事のポイントになります。
✅「場面緘黙」とは
(原因、割合、基準など)
・特定の場面で話すことが難しい状態
✅場面緘黙の子の
「5つの特徴」
・医学的にはっきりしていない
・一説では:脳の扁桃体の過敏さ
✅場面緘黙の子が
「挨拶が苦手な理由」
・注目が集まりやすい
・失敗体験の積み重ね
・自分から発するハードルの高さ
✅場面緘黙の子の
「4つの接し方」
・家族以外で関われる人を増やす
・楽しめるもの/場所を増やす
・「話さなくてもいい」活動に参加
・習い事をする
・1~4の楽しめたことを話す
✅場面緘黙の子に避けたい
「3つの関わり方」
・話をさせようとする
・否定する
・人前で話せたことをほめる
以上になります。
不安が強い子には、「今のままでも大丈夫だよ」という、
“ありのままのお子さん ” を認める姿勢が、大切になります。
お子さんの安心に繋がるキッカケになれば、幸いです。
【関連記事】
【不安が強い子供】今日から始められる!2つの原因/8つの対処法









































[…] 【場面緘黙の子】緊張が強くて話さないのは甘え?5つの特徴と4つの接し方 […]
[…] 【場面緘黙の子供】話さないのは甘え?5つの特徴と4つの接し方とは。NGな接し方も紹介 […]