

特別支援学級の担任に不安がある方「特別支援学級の担任にはずれが多いって本当?担任がはずれの場合、どうすればいい?」
お子さんが支援学級に在籍中、もしくは、これから通うことを検討されている方にとって、
「支援学級の担任」の存在は、重要ですよね。色んな噂話もあるので、実際に不安を感じる方も多いかと思います。
私は、発達支援の相談/指導員を15年以上しており、現在も特別支援学級についての相談を多くいただいてます。
その支援経験を元に、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
特別支援学級の はずれの「担任の特徴」

どの学校にも、残念ながら一定数の「はずれ」担任は、存在します。
「はずれ」担任の特徴をまとめてみました。
・子どもを頭ごなしに怒る
・子どもの気持ちに寄り添わない
・子どもや親を否定する
・話を聞かない/協力しない
・子どもに変化することを求める
このような担任教師に当たってしまうと、お子さんや親御さんは、本当に苦労をします。
実際に、私も支援する中で、苦労してきた方を多く見てきました。
【関連記事】
【現場でよくある事例】支援級(情緒級)を選んで後悔する3つのパターン
特別支援学級の はずれの「担任が増える背景」

特別支援学級の先生の特徴は、2つあります。
①特別支援をやりたい人
②特別支援をやらざる得なかった人
当然ながら、②の場合が問題に繋がりやすいです。
その背景は大きく2つあります。あくまで、私の知る範囲での内容になりますので、参考程度にご覧ください。
普通学級を担当できない先生の配置
なぜ特別支援学級に、このような先生が配置されるのか。それは、学校を運営するための人事(+先生の技術)事情があります。
普通学級の担任は、30~40名の集団をまとめるスキルが、必要になります。
教員の専門技術の一つの「集団統率力」になります。
数十人の子ども達の集団に対し、信頼関係をベースに、自分の指示を通し、集団を牽引しつつ、同時にクラス内の最低限の秩序を作り上げる技術のことです。
日本の学校教育の基本は、一斉指導のため、教員にとって必須の技術になります。
これができない先生が、よく言われる「はずれ担任」となり、特別支援学級に配置されることがあります。
少人数のため、普通学級よりも見やすいと思われている学校が、多いのかもしれません。
また特別支援学級は、数名のクラスになるため、年度の途中で普通学級に移ったり、転校することもあります。
クラスが年度途中で、なくなることもある為、途中で教員を退職することをしやすいなどの事情もあります。
詳しく知りたい方は、【特別支援学級の担任】専門性がない人もいるって本当?実情を解説 をご覧ください。
実際は、指導技術が乏しい先生に、特別支援学級を運営することはできないのですが..。
特別支援学級のお子さんは、人の言動に敏感な子が多く、より繊細で丁寧な関わりが必要になります。そういった技術は、高い指導力を元に発揮されるものです。
全国学力学習状況調査の平均点の維持
もう一つの背景は、学校の評価です。「はずれ担任」は、効果的な授業を成立させることが難しいです。そのため、その学級の学力は落ちることが多いです。
現在、教育委員会/学校の管理職の方達が最も恐れているのが、「全国学力学習状況調査」の点数です。
普通学級のお子さんは、6年生になればその調査を受けます。そしてこの調査は、過去の全ての学年で学んだ力が試されるため、どこかの学年での学習内容の学びが浅いと、調査の点数に大きく影響します。
今の小学校は、全国学力学習状況調査を軸に回っています。これが学校の評判や運営に大きな影響を与えるためです。
そのため、指導力のない先生は、調査の対象外である特別支援学級に配置されることが多いです。
はずれの担任への「対策」

「はずれ」担任に当たってしまった時の、家庭/学校内でできる対策を、4つお伝えします。
①:担任と「話をする機会」を作る
②:「管理職の先生」に相談する
③:子どもに「不安を伝えない」
④:特性に合う「学習対策」をする
担任と「話をする機会」を作る

担任と直接話をして、上手くいくことが一番良いです。相手も大人ですので、こちらの言い分は聞いてくれるとは思います。
3つのポイントを1つずつ見ていきます。
あくまで相談のスタンス
親御さんが一方的に要望を言ったり、先生の指導の指摘などをしないことです。先生がネガティブに捉えられたら、協力してもらうことは難しくなるためです。
子どもの気持ち、困りの事実を伝える
「○○と思う」という、親御さんの主観ではなく、事実として「子どもが○○と言っている」など、事実ベースで伝えることが大切です。
主観ですと、先生としても「本当にそうなのかな?」と疑問が生まれ、協力を得られづらくなるためです。
理解してもらえない場合は、すぐ引く
③は、話をしても、合わない場合は、時間を掛けても意味がありません。逆に関係性が悪化し、逆効果になることもあります。
その場合は、この後ご紹介する対策をお勧めします。
管理職の先生に相談

学校の管理職(校長、教頭 or 副校長)に、担任教師の不安な点を伝えます。
担任がその学級を担当することは、校長の権限で決定されます。そのため、校長に相談することは、筋が通っています。
よほどでない限り、校長も、それぞれの担任の特性は、把握しています。何か解決策が出てくるかもしれません。
学校側でも、先生の指導力は、おおよそ把握しています。指導力が乏しい先生の何らかのトラブルは、管理職からすれば想定の範囲内です。
例えば、対策の1つとして、ベテラン教師と一緒に組ませる、サポートの教員を付けるなど、できる範囲内で対策をしているものです。
このような「担任以外の望み」を親御さんが把握し、頼ることが大切になります。
また、校長からすると「自分が命じた」責任がありますので、その事に何かご意見が出れば、真剣に対応します。
管理職から担任への指導も期待出来ますので、まずは管理職に相談する機会をもつことが良いです。
「クレーム」ではなく、「相談」というスタンスは変えず、その責任感に期待して、不安な点は全て伝えた方が良いです。
子どもに不安を伝えない

親御さんが担任に不安を感じていることを、言葉に出してお子さんに伝えるのは、避けた方が良いです。
お子さんとしては、固定観念が入り、先生の全てを悪く見る可能性があり、担任との関係性の悪化に繋がる恐れがあるためです。
もし、お子さんが担任に不安/不満を感じている場合は、「○○って思ったんだね」とお子さんの気持ちを代弁し、受け止められると良いです。
ここで注意が必要なのは、同調しすぎないことです。お子さんの中で、「やっぱり先生は悪いんだ!」いう、先生への嫌悪感が増すことに繋がる為になります。。
年度の途中で先生は変えられないので、不必要にネガティブな感情を助長し、関係悪化は避けられる方が良いです。
⚠注意点
校長(教頭or副校長先生)に、相談する前に教育委員会に相談することは、避けたい所です。理由は、校長先生との関係性を悪化させる可能性があるためです。
教育委員会とは、「学校の人事責任がある校長」に指導できる立場にありますが、校長としては、自分に相談される前に、教育委員会に相談され、指導を受けたら、良い気持ちはしません。
まずは校長に相談し、どうしても難しい場合は、教育委員会に相談ができると良いです。
特性に合う学習対策をする
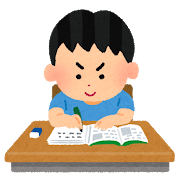
担任の理解や配慮が得にくいとなると、学校での学習を進めることも難しくなってきます。
本人と担任との関係性、担任の教え方など、学習の困難な要因はいくつもあります。
また、お子さんの様子や学級によっては、「本人のレベルと学習レベルが合わない」という場合があります。
知的な遅れがない子(情緒面に特性ある)には、そもそもの学習レベルが合っていないこともある為、個別の学習対策が必要になります。
学習対策:タブレット学習
特性ある子にとって、学ぶ上では、工夫が必要になります。
・口頭の説明だけでは、理解にしくい
・情報量が多いと、注意が散る
・処理に時間がかかる
・聞く、書くなどの動作が同時にできない
・苦手意識が強い
など、お子さんの特性、状況によって、学習の困難さがどこから来るのか、様々になります。
これらの困難さにアプローチできるのが、タブレット学習になります。
アニメーション解説があり、必要最小限の情報のみで、自分のペースで繰り返し学習ができます。
また、本人の回答結果から、課題分析し、必要な問題を自動抽出してくれ、効率的に進められます。
プリント学習などで理解しにくい子には、心強い学習ツールになります。
その他メリット、デメリットなど詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
発達障害に関わらず、学習で困ってる子にとって、参考になる内容になります。
1つの学習方法として、参考になれば幸いです。
【特別支援学級の担任 はずれが多い?】まとめ

記事のポイントになります。
✅特別支援学級の
「はずれの担任の特徴」
・子どもを頭ごなしに怒る
・子どもの気持ちに寄り添わない
・子どもや親を否定する
・話を聞かない/協力しない
・子どもに変化することを求める
✅はずれの担任が
「増える背景」
・学校の体制/仕組み
・学校の評判/運営のため
✅はずれの担任への
「対策」~家庭/学校内でできること~
・担任と話をする機会を作る
・管理職の先生に相談する
・子どもに不安を伝えない
・学習対策をする
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】
【支援学級の子は高校進学できない?】7つの進路先~進路選びの3つのポイント~









































[…] 【特別支援学級の担任】はずれが多いって本当?3つの対策を紹介します […]
[…] 【特別支援学級の担任】はずれが多いって本当?3つの対策とは […]