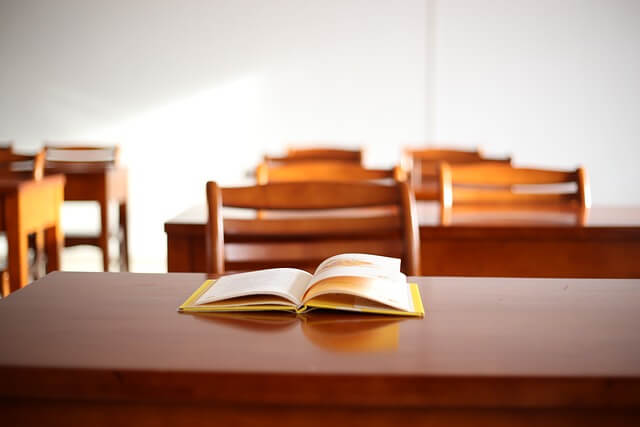

支援学級について知りたい方「情緒学級、知的学級は何が違うの?それぞれの特徴、注意点が知りたい」
支援が必要な子の学級を検討される際、多くの方が検討される「支援学級」。
以前より耳にすることは増えましたが、情緒学級、知的学級など種類があり、イマイチ違いが分からないという方も、少なくないと思います。
そこで本記事では、支援学級の情緒・知的学級の違い、注意したい点をお伝えしたいと思います。
本記事の執筆者の私は、療育/相談支援を15年以上してます。
支援をする中で、学級を検討される際に事前に把握した方が良い点をまとめてます。
参考になれば幸いです。
※私が支援してきた範囲の情報になります。参考程度にご覧ください(詳細は地域の学校の確認をお勧めします)。
目次
「情緒学級」と「知的学級」の違い

「情緒学級」と「知的学級」の違いは、一言でいうと、“知的な遅れ” があるかどうかになります。
検査で、軽度知的障害(IQ50~69)の診断がつく子は、知的学級に在籍することが多いです。
次の項では、情緒、知的学級のそれぞれの特徴をお伝えします。
「情緒学級」の特徴
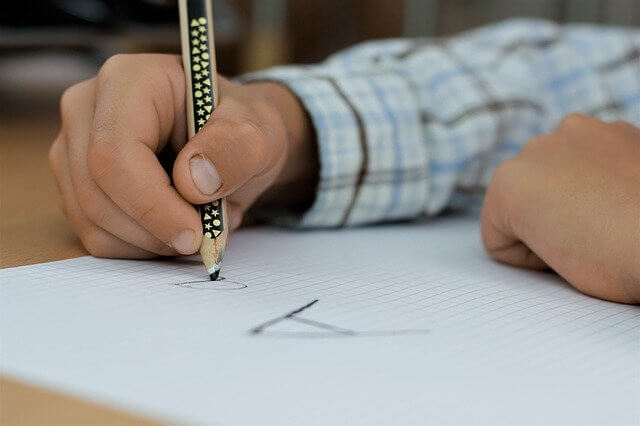
「情緒学級」の特徴を、3つの視点でお伝えします。
学校・地域によって変わりますので、参考程度にご覧ください。
在籍する子
行動・情緒面に特性がある子になります。具体的には、知的な遅れがないことに加えて、
・ADHD
(注意欠陥多動性障害)
・ASD
(自閉スペクトラム症)
・LD
(学習障害)
などの診断がある子がいます(複数ある子もいます)。
また、明確な診断がなくとも、周りに影響が出る行動が出やすい、気持ちの波が大きく、集団行動が難しいなどの特徴もあります。
具体的な様子としては、
・離席、奇声
・他害、暴言、癇癪
・著しい学習の困難さ
・その他影響が大きい行動
(ex.物を壊す、投げる)
のような、本人はもちろん、周囲やクラスに大きな影響を与える行動をする子は、情緒学級の対象になり得ます。
支援内容
8名以下の学級で、個別の特性に合った指導が受けられます。
“個別の特性に合った” とは、例えば、
・視覚的に見通しを伝える
(今日のゴール・何をすべきか)
・指示は短く、ゆっくり、具体的に伝える
・気になる刺激を最小限にしてる
(気になるモノ、音など)
・落ち着くスペース、時間が設けられてる
・本人に合った学習課題
(学年じゃなく本人のレベルに合わせる)
このような、お子さんが「安心して、参加しやすく、成功体験を積みやすくなる」為に、特性に配慮された指導が行われます。
進学/今後
基本的に高校には支援学級がない為、進学先で悩まれる方が多いです。
多くの方は、以下の選択肢で検討されます。
・普通高校
・特性に配慮された高校
(特性がある子が多く通ってる)
・通信制高校
・支援学校
私が支援してきた中ですと、特性に配慮された高校を第一に考えられる方が多いです。
次に、普通高校を検討される方が多かったです。
【関連記事】
【特別支援学級から普通高校に行くには何が必要?】5つのポイント/注意点
「知的学級」の特徴

「知的学級」の特徴(支援学級)を、3つの視点でお伝えします。
在籍する子
知的な遅れがある子になります。
私が支援してきた中では、軽度知的障害(IQ50~69)のお子さんがほとんどになります。
パッと見た感じでは分からないことも多いですが、会話をしていると、認識のズレ(言葉の裏側の意味・ニュアンスなど)などを感じる部分があります。
支援内容
8名以下の学級で、個別の特性に合った指導が受けられます。
障害者手帳を取得している子も多く、支援内容は日常生活に直接結びつくものが中心になります。
お金や時間などの自己管理など、自立する上で基盤になる部分になります。
進学/今後
支援学校の高等部を目指す子が多いです。就労を見据えて、作業所や一般企業の障害者枠で就職するなどになります。
障害者枠は、以前と比べ、就職数自体は増えていますが、まだまだ少ないのが現状の上、お給料も生活するには足りないぐらい、少額なのが現状になります。
✅境界知能の子は、支援が届きにくい
境界知能とは、IQが70~85を指し、知的障害では該当しないものの、平均IQ(90~109)より下回ります。
つまり、他の子と同じことが求められ苦労が多い中、知的障害ではない為、支援がなく辛い状況に追い込まれやすいです。
学級に関しても「診断名がないと支援学級は難しい」と言う学校もあり、在籍する学級が合わないという子も少なくありません。
支援学級の「注意点」

支援学級の「注意点」は、3つあります。
①:「学校/年度によって」学級状況は違う
②:「専門知識/スキルがない」先生がいる
③:支援学級は「高校にはない」
(情緒学級の子は特に注意が必要)
学校/年度によって学級状況は違う
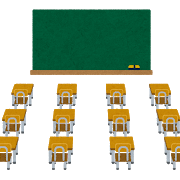
学校や年度によって、支援学級の状況は大きく変わります。
・情緒学級、知的学級に別れてない
(分ける程の人数がいない等)
・該当の学年に支援学級がない
・在籍校に支援学級がない
(支援学級がある近くの学校に通う)
・校長が変わって支援学級の対応が変わった
(校長の特別支援に対する考え方による)
前年度までの支援学級の情報を、ママ友に聞けるのが、一番になります。
それが難しい場合は、担任の先生を通して、支援学級の先生のお話を聞くか、SC(スクールカウンセラー)に相談するのが良いです。
専門知識/スキルがない先生がいる

支援学級の先生は、普通学級の先生と資格/経験など、基本的に同じになります。
「支援学級だから専門性がある」というわけではありません。
中には、普通学級でクラスを担当できず(技量的、精神的に)、支援学級を担当するケースもあります。
先生によってかなり変わる為、蓋を開けてみないと分かりませんが、まず先生が頼れる存在なのか、確認する必要があります。
支援学級の先生に関して、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
【合わせて読みたい記事】
支援学級は高校にはない

繰り返しになりますが、基本的に支援学級に高校はありません。
その為、高校の受験先で悩まれる方が多いです。発達障害などの特性がある子が多く在籍する高校も増えています。
通える範囲で該当する高校があるのか、あるとすれば、本人と見学・体験にいき、雰囲気が見れると良いです。
【合わせて読みたい記事】
【現場でよくある事例】支援学級を選んで後悔する3つのパターン/対策
【支援学級の違い 情緒学級/知的学級】まとめ

記事のポイントになります。
✅「情緒学級」と「知的学級」の違い
・知的な遅れの有無
✅「情緒学級」の特徴
・在籍する子
⇨行動/情緒面の特性がある子
(ex.離席、癇癪、他害、学習の困難さ)
・支援内容
⇨安心、参加しやすい、成功体験に繋がる
(ex.見通しを伝える、指示が簡潔・具体的)
・進学/今後
⇨特性に配慮がある高校、普通高校が多い
✅「知的学級」の特徴
・在籍する子
⇨軽度知的障害(IQ50~69)の子が多い
・支援内容
⇨生活に直結する内容が多い
・進学/今後
⇨作業所、一般企業の障害者枠
⇨数は増えてるが、給与面など課題は多い
✅支援学級の「注意点」
・学校、年度によって学級状況は違う
・専門知識、スキルがない先生がいる
・支援学級は高校にはない
(情緒学級の子は特に注意が必要)
✅支援学級を検討する子に
「必要なこと」
・本人の特性の把握
・必要な配慮/環境の把握
・学校側への相談
(本人の特性を把握した後)
✅支援学級を検討する子の
「学習対策」
・学習の失敗体験の予防
・本人の特性に合う学習法の把握
・学習の意欲を高める
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【支援学級にいじめはある?】100名以上の子から見える”現状”
【子どもに「特別支援学級」って何?と聞かれたら】説明の仕方、注意点








































[…] 【同じ支援学級でも違う?】情緒学級・知的学級の3つの違い […]
[…] 【同じ支援学級でも違う?】情緒学級・知的学級の3つの違い […]