

子どもの進路について悩まれてる方「支援学校か、支援学級に行くべきか、迷ってる。うちの子に合ってる進路を選びたい。選ぶ基準が知りたい」
特性ある子の進学先の判断は、多くの親御さんが悩まれる難しい問題だと思います。
以前と比べ「支援学級」「支援学校」は、増え、お子さんの選択肢は増えました。
一方で、
「うちの子はどっちが合ってるの?」
「選ぶ基準が分からない」
と悩まれてる方が多いのも、事実になります。
そこで本記事では、お子さんの進学先を選ぶ際に関わる「支援学校/支援学級」に関する情報をお伝えします。
私は、療育・発達支援員を15年以上しており、これまで特性ある子の支援に携わってきました。
その支援経験を元に、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
支援学校or支援学級「どっちがいい?」
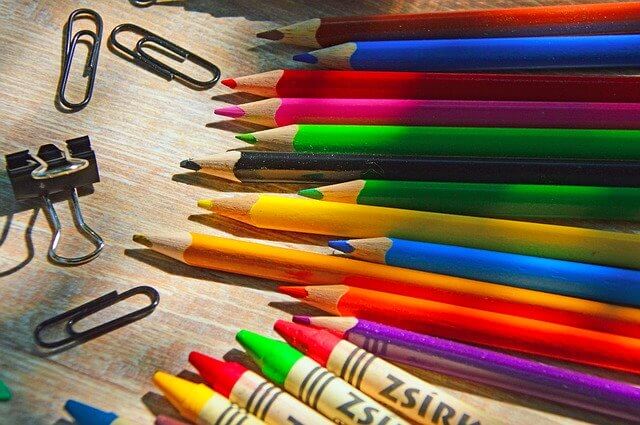
支援学校と支援学級は、お子さんによって、どっちが良いのか、変わってきます。
進学先に何を求めるのかによっても、違ってきます。
ただ、支援学校の方が支援の厚さがあり、その分、生活面での困り度が大きい子が通う場所になります(詳しくは後述します)。
そこを踏まえ、具体的にどんな視点で、選んだ方が良いのかお伝えします。
支援学校 or 支援学級「選ぶ時の4つの手順」
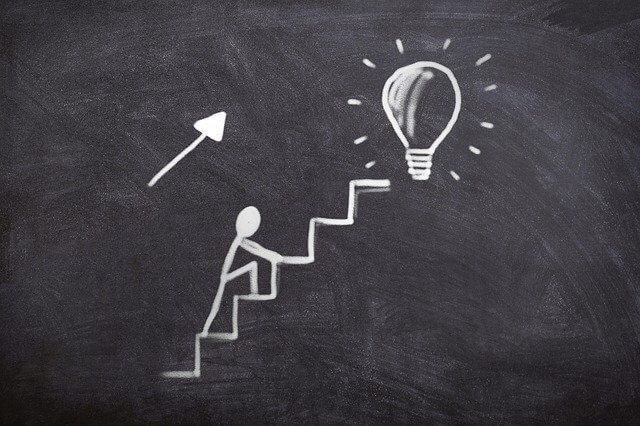
支援学校or支援学級を「選ぶ時の手順」は、4つあります。
こちらの順で進められるのが、一番スムーズになります。
①:支援学校、支援学級の「違い」を知る
②:「発達のバランス/知能レベル」の把握
③:「通学圏内の支援学校/支援学級」の把握
④:検討中の支援学校/支援学級に見学にいく
支援学校、支援学級の違いを知る

当たり前になりますが、まず最初に、支援学校と支援学級の違いを把握します。
対象となる児童、支援内容、卒業後の進学先、支援をする先生を把握した上で、メリット/デメリットを確認します。
支援学校と支援学級の違いについては、後ほど、図でお伝えします。
発達のバランス/知能レベルの把握

お子さんの発達のバランス(得意/不得意/凸凹)、知能レベルを把握します。
代表的なのは、WISCなどの検査を受け、書面で残す形が望ましいです。
WISCの場合ですと、「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」の4つの領域から、客観的に数値化されます。
お子さんの得意、不得意、生活上で想定される困りなど、心理士の所見から確認することができます。
注意点は、
「口頭で言われてだけで書面は残ってない」
「何を言われたか覚えてない」
など、勿体ないケースもありますので、検査前に書面が残るのか、事前に確認することをお勧めします。
かかりつけの小児科、クリニックなどで実施するか、実施していない場合は、実施可能な病院などを紹介してもらえます。
お近くのクリニック、児童精神科、教育支援センターなどに問い合わせをするのが一番良いです。3~6か月待ちぐらいは当たり前になるぐらい、混み合ってる所が多いです。
もし、3か月以上待つ場合は、民間療育の リタリコジュニア でも心理検査を実施しています。
2か月以内で受けられる場合が多いので、早めに受けたい方向けになります。
心理検査を受けたい旨をお伝えすれば、その後ご案内があります。
通学圏内の支援学校/支援学級の把握
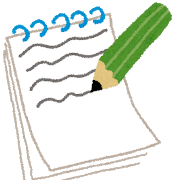
現実的に、通学できる支援学校/支援学級を把握します。
お住まいの地域によっては、そもそも選択肢が少ない場合も考えられます。
検討中の支援学校/支援学級に見学にいく
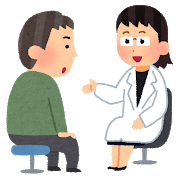
支援学校、支援学級の違い、お子さんの発達バランス/知能レベルが把握できたら、通学可能な支援学校、支援学級に見学に行きます。
見学の際に、こちらの2点があるのか、聞けると安心です。
・本人に似た特性の子の受け入れ実績
・本人が通った場合に得られる配慮
例えば、予定外のことが起こるとパニックになる特性の子に対しては、クールダウンできる部屋が設けらてる等です。
また、本人の様子を伝え、見学先の先生の意見を聞くのも重要です。
先生から見て、
「配慮があれば、通えそうです」
「うちの学校だと、難しいかもしれません」
など反応があると、参考材料になる為です。
支援学校と支援学級の「違い」
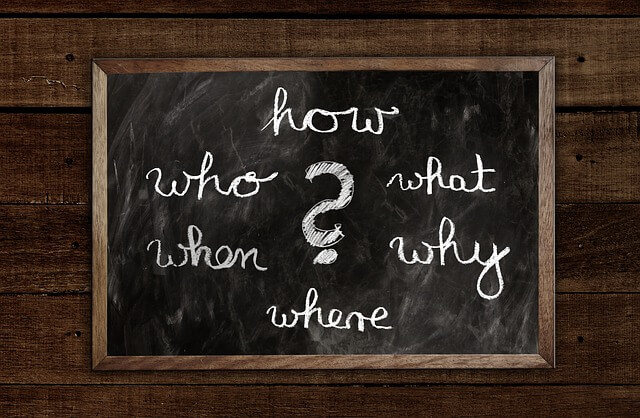
支援学校と支援学級の「違い」になります。
| 項目 | 特別支援学校 | 特別支援学級 |
| 呼び方 | 支援学校(2007年まで:ろう学校、盲学校、養護学校) | 支援級、なかよし学級など |
| 人数 | 3~8名 | 8名以下 |
| 内容 | 自立と社会参加 (ex.社会ルールの遵守、道具の使い方、時間理解) | 個別の支援計画に基づいた授業 |
| メリット | 支援が手厚い・自立に直結しやすい | 個々の特性に応じた指導が受けられる |
| デメリット | 関わる人・経験できることが限定されやすい | ・専門的な先生とは限らない ・内申点がほとんどつかない ※中学 |
支援学校と支援学級のメリット、デメリットは、こちらになります。
支援学校のメリット
・専門性が高い支援
・知識、スキルが高い先生
(全員が特別支援学校教諭免許状あり)
・進学や就職の相談ができる
(通常の学校より情報が集まる)
支援学校のデメリット
・手続きが複雑
・本人が嫌がる場合がある
・関わる人が限られる
支援学級のメリット
・発達/特性に合う指導が受けられる
・自己肯定感を保ちやすい
・普通級と交流が持てる場合がある
支援学級のデメリット
・在籍基準があいまい
・担任の質の違いが大きい
・学校、地域差が大きい
・子どもが拒否することがある
・高校は、ほとんど支援級がない
・近くの学校に通う必要がある
(学区内に支援級がない場合)
【関連記事】
【現場でよくある事例】支援級(情緒級)を選んで後悔する3つのパターン/対策
支援学校が合いやすい子の「特徴」

支援学校が合いやすい子の「特徴」になります。
あくまで、支援してきた中で、個人的に感じた点になります。
・知的障害がある
・社会での自立に力を入れたい
(生活に直結するスキル)
・苦手な環境が多く、パニックになりやすい
(環境の変化が著しく苦手)
あとは、本人が支援学校の雰囲気・どんな場所なのか知った上で、安心して過ごせるかになります。
支援学級が合いやすい子の「特徴」

支援学級が合いやすい子の「特徴」になります。
こちらも、支援する中で感じられた点になります。
・集団が非常に疲弊しやすい
・集団行動に常に遅れがある
・困っても誰にも助けを求められない
・他害、癇癪など周りに大きな影響が出る
・知的な遅れがある
(境界域~軽度まで)
※境界域:IQ71~84 軽度:IQ51~70
こちらも、本人がメリット、デメリットを把握した上で、本人が納得していることが大切になります。
【どっちがいい?支援学校 or 支援学級】まとめ

記事のポイントになります。
✅支援学校or支援学級
「どっちがいい?」
・学習の進度が一般的
・多くのクラスメイトと交流が持てる
✅支援学校or支援学級
「選ぶ時の4つの手順」
・支援学校、支援学級の違いを知る
・発達のバランス/知能レベルの把握
・通学圏内の支援学校/支援学級の把握
・検討中の支援学校/支援学級へ見学
✅支援学校のメリット
・専門性が高い支援
・知識、スキルが高い先生
(特別支援学校教諭免許状)
・進学や就職の相談ができる
✅支援学校のデメリット
・手続きが複雑
・本人が嫌がる場合がある
・関わる人が限られる
✅支援学級のメリット
・発達/特性に合う指導が受けられる
・自己肯定感を保ちやすい
・普通級と交流が持てる場合がある
✅支援学級のデメリット
・在籍基準があいまい
・理解ない先生もいる
・学校、地域差が大きい
・子どもが拒否することがある
・高校は、ほとんど支援級がない
・近くの学校に通う必要がある
✅支援学校が合いやすい子の
「特徴」
・知的障害がある
・社会での自立に力を入れたい
・苦手な環境が多く、パニックになりやすい
✅支援学級が合いやすい子の
「特徴」
・集団が非常に疲弊しやすい
・集団行動に常に遅れがある
・困っても助けを求められない
・他害、癇癪など周りに大きな影響が出る
・知的な遅れがある
✅支援学級を選ぶ子が
「備えたいこと」
・学校以外での学習対策
・特性に合う学習方法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】







































