

学習障害の子で悩まれてる方「学習障害の子に何をしてあげればいい?親ができることが知りたい」
学習障害の子は、知的な遅れがないにも関わらず読み書きが難しかったりと、目に見えづらい特性を抱えています。
そのため、本人が自身の特性を受け入れなかったり、配慮されることを拒むこともあります。
家族として、どう関わるべきか、何をしてあげられるのか..とても難しい問題だと思います。
そこで本記事では「学習障害の子に、親御さんができること」についてお伝えしたいと思います。
この記事の執筆者の私は、発達障害のお子さんの療育/学習支援を15年以上しており、現在も学習障害で悩まれてるお子さん、親御さんの支援に携わってます。
その支援経験を元にしてます。参考になれば幸いです。
目次
親が家庭でできる「4つのコト」~学習障害~

学習障害の子へ、親が「家庭でできるコト」を、4つお伝えします。
①:「学習障害」を学ぶ
②:「本人の自己肯定感」を守る
③:今できてることを「認める/ほめる」
④:「家族の認識」を揃える
学習障害を学ぶ

「学習障害」に関する知識をつけます。
まず本人の特性を知り、
「どこが頑張りポイントなのか」
「何ができないのか(本人に求めるべきじゃないのか)」
の点を把握する必要があります。
この点が分からないと、本人にしてあげられることを考えることが難しくなります。
本人の自己肯定感を守る

学習障害は、自己肯定感が下がりやすいです。
読み書きなど、特定のこと以外は、他の子と同様にできる分、
「何で自分にはできない」
「どうせ頑張っても上手くいかない」
と傷つきます。失敗体験が多くなると、周りの意見を聞かず、配慮されることも嫌がり、相談・支援先に行くことも拒否する様になります。
ここまでの状態になると、本人の困り感を減らしていくことが困難になります。
今できてることを認める/ほめる
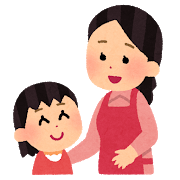
学習障害となると、読めない、書けないなど、できない所に目がいきがちです。
ただ、本当に大切なのは、本人の “今できてること” に目を向け認めることです。
例えば、読むのに人より時間がかかっても、ゆっくりであれば読めています。
枠から字がはみ出ても、読める字で書けています。
このように、本人が今できてる所を見つけ、周りが認めていくことが大切になります。
本人が嫌じゃなければ、「最後まで読めたね!」「5問も漢字書けてすごい!」など、ほめるのも効果的です。
思春期の子ですと、嫌がる場合が多いと思うので、「〇〇の字が少し崩れてるよ」「〇〇が枠からはみ出てるよ」など、細かい指摘は控えるだけでも十分です。
家族の認識を揃える
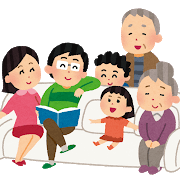
本人の特性、できること、できないこと(本人に求めないこと)などを、家族間で共通認識を持つことが重要になります。
学習障害のケースでよくあるのが、家族からの声掛けが本人のストレスになり、学習拒否に繋がることです。
本人が難しいことを、親御さんが一般的な基準で求め続け、本人の自己肯定感を下げていることが多いです。
親が外でできる「2つのコト」~学習障害~

親が「外できるコト」を、2つお伝えします。
①:「学校の理解・協力」を得る
(合理的配慮)
②:「支援先」に頼る
(療育・家庭教師)
学校の理解・協力」を得る
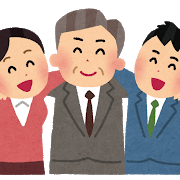
学校側の理解と協力を得るために、相談をします。
本人の特性を伝え、配慮してもらえないか相談をします。近年ですと「合理的配慮」という言葉もありますが、本人の特性に応じて、学校側に配慮してもらえるケースが増えています。
こちらは、合理的配慮の一例になります。
・テストは別室で受ける
(周囲が気になり集中できない子)
・テストの文字の拡大化
(読みが苦手な子)
・課題の文字にルビをつける
(漢字の読みが苦手な子)
※ルビ=ふりがな
学校の先生に相談し、できることがないか、確認できると良いです。
支援先に頼る

療育、発達障害専門の家庭教師など、プロの力に頼ることです。
参考例として、1つご覧ください。
プロの力に頼ることが一番確実ではありますが、時間や費用、お子さんに合う先生が見つかるかなど、デメリットがあるのも事実です。
もし、時間や費用的な問題、もしくは「そこまでじゃないけど、家でできることはしてあげたい」という方には、タブレット学習をお勧めします。
家でできる:タブレット学習
タブレット学習は、お子さんの発達特性に合わせて、
①:特性に配慮された学習PGM
(発達障害の専門家監修)
②:無学年式
(学年を遡って学べる)
③:課題の分析/選定/提示
(解答結果から自動分析⇨選定)
④:ゲーム性豊富な学習PGM
(苦手意識がある子でも取り組みやすい)
などがあります。
特性ある子が学習でつまづくポイントに対して、上記の①~④でアプローチしてくれるのが、タブレット学習になります。
お子さんへの学習サポートの情報を集めてる方、我が子に合う学習サポートがまだ定まってない方は、こちらの記事をご覧ください。
タブレット学習の、より詳しい情報をまとめてます。
診断名に関わらず、学習に困りがある子にとって、1つの学習方法として、参考になると思います。
卒業まで時間がほとんどないなどでない限りは、まずは家庭内でフォローができるのか試した後、難しければ専門家に頼るなど、他の方法を検討する形をお勧めします。
【学習障害 親ができること】まとめ
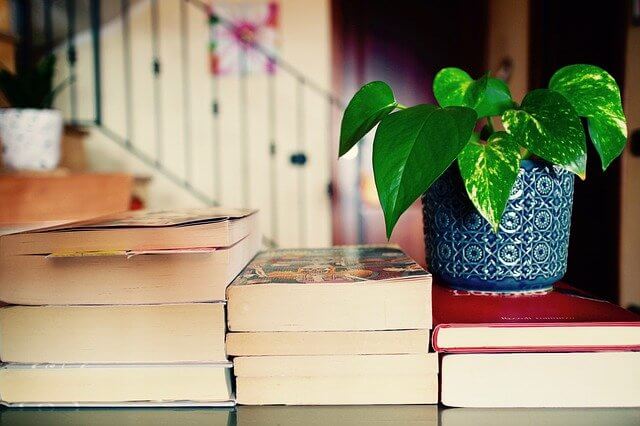
記事のポイントになります。
~学習障害の子へ~
✅親が家庭でできる
「4つのコト」
・学習障害を学ぶ
・本人の自己肯定感を守る
・今できてることを認め、ほめる
・家族の認識を揃える
✅親が外でできる
「2つのコト」
・学校の理解・協力を得る
(合理的配慮)
・支援先に頼る
(療育/家庭教師)
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【学習障害】親ができること~家庭できる4つのコト・外でできる2つのコト […]
[…] 【学習障害】親ができること~外でできる2つのコト […]