

子どもの癇癪が通報されそうで不安な方「子どもの癇癪の泣き声で近所に通報されそうで不安。実際に通報され、また通報されてしまいそうで心配。できることがあれば知りたい」
お子さんの癇癪は、親御さんのエネルギーを消耗しますし
大きな泣き声は、虐待疑いの通報をされてしまうのでは…と不安になる方も、以前に比べ増えています。
この記事の執筆者の私は、虐待児を預かる児童福祉施設や、発達障害や家庭問題を抱えたお子さんの相談支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。
その中には、家庭でのお子さんの癇癪や通報されるのでは…と悩まれている方も、多くいらっしゃいました。
その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
子どもの癇癪で通報されやすい「2つの原因」

子どもの癇癪で通報されやすい「2つの原因」をお伝えします。
①:子どもの激しい泣き声
②:近所との関係性の薄さ
子どもの激しい泣き声

これは当たり前ですよね。
更に原因を深堀りしていくと、お子さんの癇癪を起こすキッカケが、生活の中で作られているからです。
よくあるキッカケが以下の2つになります。
・自分(自分)の要求が通らなかった
・やりたくないことがある
ただ、生活の中では、お子さんの要求が通せなかったり、お子さんがやりたがらないことを、やってもらう必要がありますよね。
ここの具体的な対策については、次の章で説明します。
近所との関係性の薄さ

現代は、近所との関係も、希薄な傾向になります。
この「近所関係の希薄さ」が、通報されやすい原因になるには、次の理由があります。
人は未知のものに対して、強気不安や恐れを抱く性質のためです。
例えば、次の2つのうち、どちらの方が、通報される確率は高いでしょうか?
①普段から挨拶をして、どんな人柄や家庭かイメージが湧いている
②挨拶もしないので、どんな家庭なのか、全く分からない
答えは②です。明確ですよね。全く同じ状況で、お子さんの泣き声が聞こえた時、近所との関係性によって、通報される確率は変わってきます。
人は「自分が把握しているかどうか」で、不安度が全く異なります。
虐待の通報は、国民の義務(児童福祉法第25条)です。
自分が通報をしなかったことで、万が一事件があったことを考えられると、虐待の可能性を感じた時点で通報する方もいるでしょう。
地域で虐待が把握しやすいという点では、良いと思いますが、虐待ではなく必死に癇癪に対応した結果に通報されてしまうのでは、その親御さんにとって、あまりにも辛いです。
そんな方のために、できる方法・使える資源を、次の章で説明したいと思います。
通報されない為の「3つの対策」

本当は虐待ではないのに、通報をされてしまう…ということを避ける方法は、3つあります。
①:「癇癪の原因」を特定し、対応する
②:近所と最低限の「関係性を作る」
③:「地域の支援機関」へ相談
癇癪の原因を特定し、対応する
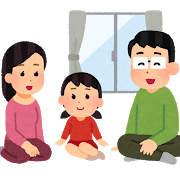
一番の理想は、癇癪がなくなることですよね。
癇癪をなくすためには、癇癪の原因を特定する必要があります。
例えば、同じ癇癪でも「欲しいお菓子がもらえない」、「お風呂に入るのはイヤ」など原因で、対応するためには、原因毎にアプローチを変える必要があります。
例えば、「欲しいお菓子がもらえない」なら、お菓子を上げてしまうと、癇癪をすればお菓子がもれえるという誤った学習になり、癇癪がひどくなります。
そのため、癇癪に対して要求に応えない関わりが必要になります。
「お風呂に入るのがイヤ」の場合は、お風呂に入ったら何ができるのかを事前に伝えたり、お風呂が楽しくなるよう、お風呂の中で楽しめるオモチャ・遊びを考える方法もあります。
このように原因によって、関わり方が全く違います。日々激しい癇癪が続いているということは、お子さんの癇癪の原因と関わり方がマッチしていないのかもしれません。
もし家庭でできることを、まずしたいという方は、【癇癪】今日からできるクールダウン 3つの対処法をご覧ください。
「癇癪の原因別の関わり方」を、図で簡単に理解できるように、まとめてます。
近所と最低限の関係性を作る
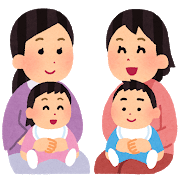
先ほども説明しましたが、近所の方が、知らないことで不安が募り、通報されるケースが多いです。
逆にいうと、知ってもらっていることで、通報の可能性を減らすことができます。
誰にでもすぐできる方法としては、
・笑顔で挨拶をする
「え?そんなこと?」と思われるかもしれませんが、とても大切です。
顔を合わせれば、お互い笑顔で挨拶できる関係性になりましたら、「いつも騒がしくてすみません」と、一言言えると理想的です。
近所の方としては、「育児を頑張ってるんだな」「悪い人じゃないんだ」と思ってもらえます。
人によっては、ただでさえ子育てで大変なのに、何で近所にそこまで言わないとなの?と思われるかもしれません。
ただ、通報される不安・実際にされたときのストレスは、非常に大きいものです。
それを考えたときに、日常の中でできる一言は、やる価値のあることだと、私は思います。
地域の支援機関へ相談

さきほどの①②を実践しても、難しい場合は、専門家の力を借りた方が良いです。
・地域の障害福祉課
・児童相談所
いずれも、お住まいの区役所のHPで確認することができます。
【関連記事】
【子供の癇癪 通報の不安対策】まとめ

記事のポイントになります。
✅子どもの癇癪で通報されやすい
「2つの原因」
・子どもの激しい泣き声
・近所との関係性の薄さ
✅通報されない為の
「3つの対策」
・癇癪の原因を特定し、対応する
・近所と最低限の関係性を作る
・地域の支援機関へ相談
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】
【発達障害の子の育児をやめたい】親の負担を軽くする4つの方法








































[…] 【子供の癇癪】通報されそうで不安。通報される2つの原因と対策とは。 […]
[…] 【子供の癇癪】通報されそうで不安。通報される2つの原因と対策 […]