

子どもの不登校で悩まれてる方「不登校になってから全然運動しない。運動不足が心配。不登校の子におすすめな運動、継続できるコツが知りたい」
不登校のお子さんは、外出の機会が減ったり、家で過ごす時間が増える為、運動不足に繋がりやすいです。
同級生や近所の目が気になったり、単純に面倒くさかったり、家でゲームをしてる方が楽しいなど、運動不足(外に出たくない)になる理由は、様々になります。
運動に誘っても、工夫して声を掛けても、なかなか難しいという方も多いと思います。
そこで本記事では、運動不足を解消する為に大事なこと/方法をお伝えします。
この記事を執筆してる私は、不登校・療育支援を15年以上しています。
実際に支援する中で、大切だと感じたことをまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不登校の子の運動「継続する時の3ポイント」

不登校の子の「運動を継続するポイント」は、3つあります。
①:「本人のメリット」から考える
②:「運動=手段」と考える
③:「義務感」を無くす
本人のメリットから考える

本人の “運動するメリット” を考えることが大切になります。
例えば、ダイエットは続かないことが多いと思います。
その理由の1つとして、本人にとってメリットがない(弱い)ことが考えられます。
・着れる服が増える
・周りから褒められる
・痩せた体を鏡で見るのが楽しい
など、ダイエット自体に考えられるメリットはありますが、本人にとって “運動する面倒くささ” の方が強ければ、それはダイエットが続かない理由になります(本人がメリット自体を感じない場合もある)。
お子さんが運動しないのも同じです。運動したことで得られる喜び、楽しさがない(弱い)と、運動が続かないのは自然なことだと言えます。
こういった背景から、本人の運動するメリットはある?メリットは作れる?を、まず考えることが大切になります。
運動=手段 と考える

運動不足の問題があると「どんな運動なら出来るんだろう?」と考える方が多いと思います。
ただ、大事なのは本人のメリットになりますので、メリットから、運動(手段)を考える方が効果的です。
例えば、お菓子を買ってもらうのが嬉しい!という子でしたら、近くのコンビニまで散歩にいき、自分でお菓子を選んで買う機会を作る、などです。
運動そのものが楽しめる子でない場合は、メリットから考えると、自ずと運動(今回で言うと散歩)が考えやすくなります。
義務感を無くす

「全然動いてないから、運動するよ」
「運動するって約束したでしょ」
このような関わりですと、運動が苦痛になり、作業的になります。
運動することで得られるもの(本人のメリット)がないと、義務感だけになり、それは苦痛、ストレスに繋がりかねません。
【関連記事】
不登校の子「運動不足解消の4つの方法」

不登校の子「運動不足を解消する方法」は、4つあります。
繰り返しになりますが、大切なのは本人にとってのメリットになります。
ここで紹介するのは、不登校の子達が運動をする意義を感じやすかった方法になります。
お子さんによって、合う合わないありますので、参考例として、ご覧ください。
①:「室内」での運動
②:近所のお店までの「散歩」
(買い物)
③:家の手伝い
(家事)
④:運動の習い事
(オンライン)
室内での運動

外出することに抵抗感がある子には、室内運動も1つになります。
道具が必要になりますが、室内でできる運動を紹介します。
・トランポリン
・バランスボール
・卓球
・縄跳び
・室内ゲーム
(ex.Wii Fit、リングフィット、Nintendo Switch Sports)
お子さんが楽しめる運動でしたら、どんな運動でも構いません。
室内ゲームがイメージが湧きづらい方もいらっしゃると思いますので、参考程度に、こちらをご覧ください。
✅Nintendo Switch Sports
✅ファミリートレーナー
近所のお店までの散歩
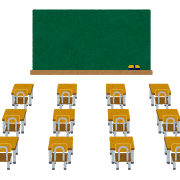
歩いて行ける範囲の中で、スーパーやコンビニに行って、家族と散歩します。
好きなお菓子を買う、好きなモノを見に行くなど、本人の楽しみを目的に散歩します。
他にも、電車が好きで自転車で見に行ったり、電車のスタンプラリーを貯める為に電車で移動するなど、色んな楽しみを目的に体を動かす子がいます。
散歩は、家族とコミュニケーションできる機会にもなるので、個人的にはお勧めになります。
家の手伝い

洗濯、お風呂掃除、ゴミ捨て、買い物など、本人ができる家事になります。
体を動かす以外にも、家族に感謝され、人の役に立てたという実感に繋がるメリットがあります。
本人の役割にもなり、自己肯定感の低下を止める要素にもなる為、不登校の子には、特にお勧めになります。
運動の習い事

自宅でできるオンライン上の運動の習い事になります。
オンライン上で先生と関わること、家族を間に入れて(本人と先生の)やりとりをすることが嫌じゃない子でしたら、1つの選択肢になります。
【不登校 運動不足と4つの対策】まとめ

記事のまとめになります。
✅不登校の子が運動を
「継続する時の3つのポイント」
・本人のメリットから考える
・運動=手段と考える
・義務感を無くす
✅不登校の子の
「運動不足解消の4つの方法」
・室内での運動
・近所のお店までの散歩+買い物
・家の手伝い
・運動の習い事
(オンライン)
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【不登校】運動不足はどうする?継続できる3つのポイント […]