

子どもの不登校で悩まれてる方「修学旅行は行かせた方がいいの?不登校の子は修学旅行はどうしてるの?」
不登校のお子さん/親御さんにとって、悩みの1つになるのが学校行事。
その中でも、修学旅行は大きな行事のため、参加すべきかどうか、悩まれる方が多いです。
行かせるべきか..無理をさせないべきか..その判断はとても難しいと思います。
そこで本記事では、不登校の子の “修学旅行” に関する情報をまとめました。
私は、療育・相談支援を15年以上しており、不登校/発達障害の子、その親御さんの支援に携わってきました。
修学旅行に関する相談もたくさん受けてきました。その支援経験を元に、本記事をまとめてます。
参考になれば幸いです。
目次
不登校の子の修学旅行で「大切なこと」

“不登校の子の修学旅行” で、大切なことは、3つあります。
①:本人の「意思」
②:修学旅行で得る「本人の感情/経験」
③:学校側の「スタンス」
本人の意思

一番最初に確認することが “本人の意思” になります。
修学旅行に関わらずですが、不登校問題は、本人の意思を前提にして、あらゆるコトの判断をする必要があります。
本人の意思がなければ、どんなに条件が良くても、良い結果に繋げるのは難しくなる為です。
修学旅行で得る「本人の感情/経験」

本人が修学旅行に参加して、”ポジティブな感情・経験を積めるか?” という点になります。
本人にとって、明らかにハードルが高い場合、参加できたとしても、辛い思い(失敗体験)をして終わってしまいます。
“修学旅行に参加する” が目的にならないことが重要になります。
その為には、本人が「修学旅行楽しかった、参加できて良かった」と思える経験が必要になります。
学校側のスタンス

学校側のスタンスを、事前に確認する必要があります。
「親の送り迎えがあるなら、大丈夫ですよ」
「皆と同じ様に参加する必要があります」
「初日だけ参加できる様、調整をしますね」
など、学校によって様々です。
「本人の気持ち」「学校が現実的にできるライン」を確認して、
本人にとってポジティブな経験に繋がりそうなら、修学旅行の参加は前向きに進めて良いと思います。
✅”もしもの時” の対策
修学旅行の途中で、本人がどうしても辛くなった時の対策を、”本人/ご家族/学校で決めておける” と安心です。
・何かあれば、家族が迎えに来てくれる
・一人で落ち着ける場所に移動できる
など、本人が「何かあっても○○があるから大丈夫」と思えることが、本人の安心感に繋がります。
【関連記事】
【欠席理由はどう伝える?】不登校の欠席連絡・電話が辛い時の対策
不登校の修学旅行「避けたいこと」
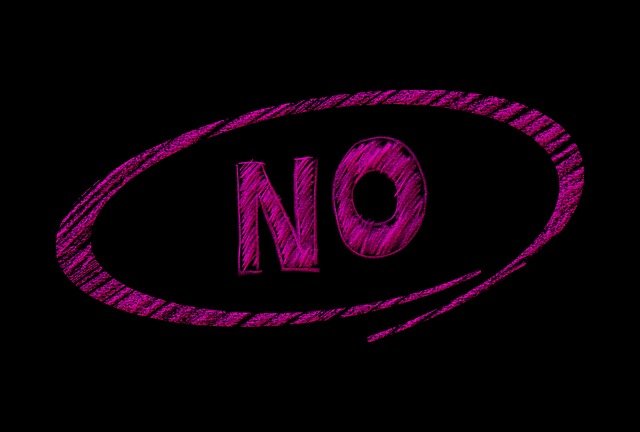
“不登校の修学旅行” に関する注意点は、3つになります。
お子さんに対する、避けたい対応になります。
①:本人の不安を「軽視」する
②:本人に「プレッシャー」を与える
③:「学校の意向」を軽んじる
本人の不安を軽視する

本人が不安がっていたり、答えが出せず悩んでる様子を、軽く捉えることです。
不登校の子は、頭で分かっていても、行動が追いつかず、その葛藤で苦しんでることが多いです。
そのため、些細なことで不安になったり、その不安を上手く言葉にできないこともあります。
本人の不安を聞きながら、紙に書き出して一緒に整理したり、
考える時間を空けるなど、丁寧に関わる必要があります。
本人にプレッシャーを与える

意図がなくても、周囲の大人の言葉/態度が、本人にプレッシャーを与えてることは多いです。
「修学旅行は行けるの?どうするの?」
「とりあえず行ってみたら?」
など、我が子を想っての発言でも、本人の捉え方は、”プレッシャー” になりやすいです。
学校の意向を軽んじる
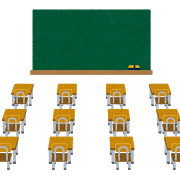
学校側が慎重な姿勢の場合は、その理由を確認した上で、話を進めるのが一番です。
・個別フォローが十分にできない
・学校側と親の認識の相違
(本人の状態に対して)
【関連記事】
【不登校の子の修学旅行 大切な点】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の子の修学旅行で
「大切なこと」
・本人の「意思」
・修学旅行で得る「本人の感情/経験」
・学校側の「スタンス」
✅不登校の修学旅行~注意点~
「避けたいこと」
・本人の不安を「軽視」する
・本人に「プレッシャー」を与える
・「学校の意向」を軽んじる
✅注意点
・本人の意思だけで判断しない
・対処法も一緒に考えておく
・学校側に対処法も共有しておく
✅不登校の子が
「準備しておきたいこと」
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合う学習法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】









































[…] 【不登校】修学旅行は行くべき?大切な3つのポイント・注意点 […]
[…] 【不登校】修学旅行は行くべき?大切な3つのポイント・注意点 […]
[…] ・障害を持つ中学生の修学旅行(mamasta | ママスタ)・【不登校】修学旅行は行かせて平気?大切な3つのポイント・注意点とは(… […]
[…] ・障害を持つ中学生の修学旅行(mamasta | ママスタ)・【不登校】修学旅行は行かせて平気?大切な3つのポイント・注意点とは(… […]