

不登校の本を探してる方「不登校について学べる本が知りたい。子どもへの関わり方、経験者の体験談など、読みやすい本を教えてほしい」
「子どもが学校に行かない..この先が不安」
「不登校の子にどう関わっていいか分からない」
「子どもが不登校になった時はどうすればいい?」
不登校の子をもつ親御さんは、様々な不安や悩みがあります。
そこで本記事では「不登校がよく理解できる本」をお伝えしたいと思います。
・不登校の基礎知識を得る
・親の関わり方を学ぶ
・経験者の体験談が聞きたい
など、目的に合わせて本をまとめています。
この記事の執筆者の私は、療育支援員を15年以上しており、
不登校、発達障害のお子さん・親御さんの支援に携わってきました。
その支援経験を元に、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不登校の本「おすすめ7選」
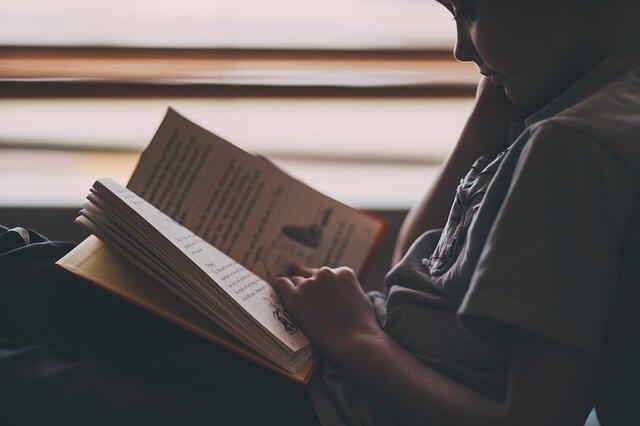
不登校の「おすすめの本」を7冊お伝えします。
それぞれの本の特徴と目的(どんな方向けか)をお伝えします。
①:不登校になったら最初に読む本
- 最初に読みたい1冊
- 不登校の基礎知識が得られる
②:子どもが不登校になったら読む本
- 不登校の子の育児の経験談
- 特に母親におすすめな本
③:子どもが不登校になっちゃった!
- 不登校の全体像が把握できる(段階)
- 不登校について細かく理解できる
④:学校に行けない子の気持ちがわかる本
- 子どもの心情が理解できる
- 親として大事な視点が学べる
⑤:不登校、頼ってみるのもいいものだ
- 親の視点と関わり方が学べる
⑥:不登校ー親子のための教科書
- 経験者や支援者からの事例が把握できる
- 不登校のよくある疑問が解消されやすい
⑦:学校は行かなくてもいい
- 不登校経験者の体験談
- 不登校の子の気持ちが分かる
- 不登校問題で大切な視点が学べる
【関連記事】
【不登校の小学生】家での過ごし方は何が大事?4つのポイント・注意点
不登校の本「活用する時のポイント」

ここでは、本の知識を活用する時のポイント について触れていきます。
①:本の知識は「参考程度」にする
(考え方の全体像として捉える)
②:「子ども・家庭に合わせて」変える
(本の知識をベースに)
本の知識は参考程度にする
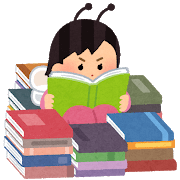
本の知識は、あくまで基本的な視点・考え方として捉えます。
不登校の基本的な知識、共通したNGな関わりなど、お子さんと関わる上でベースを作る材料にします。
本の知識を、そのまま実践しても、お子さんのタイプ・家庭の状況によっては、ネガティブに作用することもあります。
お子さんと関わる上で、判断する材料として、本の知識を活かしたい所です。
子ども/家庭に合わせて変える
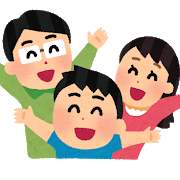
本で基本的な知識を得たら、お子さん・家庭に合わせて、関わりに活かしていきます。
何が正解か分からない場合は、可能なら支援者や信頼できる学校の先生など、相談するのが良いです。
もし周りに頼れない状況でしたら、1回試しにお子さんに関わり、反応を見るのも1つです。
そこで反応が良ければ、続けていくのも良いです。お子さん本人と話せる関係でしたら、「◯◯するのはどう?」など、本人に聞くのも良いと思います。
一番良いのは、支援者に相談し、お子さんの特性を知った上で、本の知識を関わりに活かすことです。
【関連記事】
【不登校の本7選】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の本
「おすすめ 7選」
・不登校になったら最初に読む本
・子どもが不登校になったら読む本
・子どもが不登校になっちゃった!
・学校に行けない子どもの気持ちがわかる本
・不登校、頼ってみるのもいいものだ
・不登校ー親子のための教科書
・学校は行かなくてもいい
✅不登校の本
「活用する時のポイント」
・本の知識は「参考程度」にする
・「子ども・家庭に合わせて」変える
・本人の特性を把握した上で、本の知識を関わりで活かす
(支援者に相談)
✅不登校の子が
「備えておきたいこと」
・最低限必要な学力
・本人希望の進路に必要な学力
・学習習慣の定着
・学習の成功体験
・特性に合う学習法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【不登校】学校とのやりとりで大切な3つのポイント・2つの注意点








































