

子どもの不登校で悩まれてる方「授業は受けてないけど行事だけ参加させるのは良い?尊重した方がいいのか、止めた方がいいのか分からない」
不登校には、完全不登校、別室登校、1部の授業だけ参加、行事だけ参加など様々な形があります。
その中でも、普段は学校を休んでるけど「行事だけ参加したい」という子がいます。
親御さんとしては「学校にちょっとでも関われるのは良いこと..でも授業に出席してないのに、本人が好きな行事だけ参加させるのは問題ないの?」
と、判断に迷われる方も少なくないと思います。
結論からお伝えすると、本人の意思があるのなら、本人にとってポジティブな経験になるのであれば『行事だけ参加する』は良いことです。
ただ、事前に押さえたい点や注意点がありますので、本記事では、1つ1つ詳しくお伝えしていきたいと思います。
この記事を執筆してる私は、不登校・療育支援を15年以上しています。
これまでの支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不登校の子が「行事だけ参加することの意味」

不登校の子が「行事だけ参加することの意味」とは、本人の成功体験になる、ということです。
成功体験とは、行事に参加したことで、
「◯◯の行事に参加して良かった」
「◯◯ができて嬉しかった」
「自分が心配してたより、案外平気だった」
「次の行事も行ってみようかな」
など、本人にとってポジティブな気持ちが持てる経験のことです。
「成功体験を積む」ということは、自己肯定感が上がり、物事へチャレンジする意欲が高まります。
自己肯定感は、お子さんが行動する上での原動力ですので、とても大切な土台になります。
逆に行事だけ参加して、ネガティブな気持ちになるようでしたら、参加する時期を検討したり、参加する方法を見直すなど、工夫が必要になります。
行事に参加する前に「守りたい4つのポイント」

行事に参加する前に「押さえたいポイント」は、4つあります。
①:「本人の気持ち」を確認する
②:具体的な「参加の仕方」を決める
③:「途中で辛くなった時の対策」を決める
④:学校と「共通認識」をとる
本人の気持ちを確認する

『本人の気持ち』とは、本人の「◯◯したい」という希望と、「◯◯が怖い」などの不安を聞くことです。
基本的には、本人の気持ちを尊重することが大切ですが、不登校の子は、無理をしてしまって後から反動が来る子も少なくない為、ポジティブな気持ち、ネガティブな気持ちの両方が聞けると良いです。
不安な気持ちが出たら、その不安に対する対策などを事前に一緒に考え、本人の不安がクリアになれば(過度な不安が避けられる状態)、参加する方向で進めるのが良いと思います(詳細は後述します)。
具体的な参加の仕方を決める
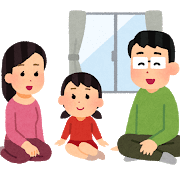
「行事に参加したい」という本人の気持ちが確認できたら、今の本人に合った参加の形を決めます。
・本人が了承してる
・本人の不安に対して対策が決まってる
・本人への負荷が重すぎない
このような点を意識した上で、参加の形を決めていきます。
私が今まで支援してきた中ですと、
・見学で参加
・特定の活動だけ参加
・先生の手伝い役として参加
このような参加の形がありました。
お子さんの成功体験になる様な “参加の形” を見つけることが大切になります。
途中で辛くなった時の対策を決める

どんなに事前に丁寧に準備していても、本人が行事の途中で辛くなってしまうこともあります。
不登校の子のコンディションは、不安定なため、完全には読めません。
「事前に辛くなった時の対策」を本人と決めておくことが大切になります。
例えば、本人が辛くなったら、
・◯◯の先生に伝える
(本人が信頼してる先生)
・保健室に移動
・早退する
などの対策があります。
本人が納得していて「辛くなっても◯◯すれば大丈夫」と思えているのが理想的になります。
学校と共通認識をとる

本人の気持ち、参加の仕方、辛くなった時の対策、などを学校に共有します。
特に、参加の形や途中で辛くなった時の対策は、学校の理解・協力も必要になります。
学校として、どこまで協力してもらえるか、現実的にサポートできるかは、様々になります。
・在籍校で現実的にできるライン
・本人に必要な参加の形
・辛くなった時の対策
などのすり合わせしておけると安心です。
また、学校が理解してること、協力してることは、本人の安心感に繋がりやすいです。
本人の不安を少しでも減らす為には、環境作りも大切になってきます。
【関連記事】
行事の参加に関する「3つの注意点」

行事の参加に関する時の「注意点」は、3つあります。
①:本人への期待値を「上げ過ぎない」
②:「ネガティブな声掛け」はしない
③:「何度も」聞かない
本人への期待値を上げ過ぎない
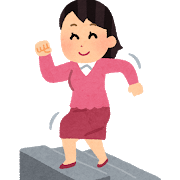
大人側からの “本人への期待値” を上げ過ぎないことです。
行事に参加できることは、不登校の子にとっては大きいことですし、ご家族としても嬉しく応援したくなるものです。
「行事に参加できるなら、授業も参加できるかも..」と期待される気持ちが出るのも、自然なことだと思います。
ただ、不登校の子は気持ちやコンディションに波があり、1つの場面だけでは判断ができません。
仮に行事に参加できても、その後学校に登校できる日数が増えるとは限りません。
過剰に反応せず、いつも通りの様子で「行事楽しかったんだね。良かったね」と終えるぐらいの方が良いです。
逆に、行事に出たことで、周りから「学校もう少し頑張ってみる??」など言われると、”行事に参加したこと=ネガティブな経験” に繋がりかねません。
ネガティブな声掛けはしない

行事に参加したことで、細かい所が気になる場合があるかもしれません。
例えば、
・先生に挨拶してない
・挨拶の声が小さい
・行動が周りに遅れてる
など、ご家族として「◯◯した方が良いと思うよ」「◯◯だともっと良かったね」などの声掛けをしたくなる時があるかもしれません。
ただ、ネガティブ(もしくは本人にとってポジティブではない)な声掛けは避けたい所です。
理由は、行事に参加したことで指摘されれば、自己肯定感も下がり、行事に参加する意欲が失われる為です。
何度も聞かない

「行事楽しかった?」
「学校どうだった?これからどうする?」
「先生や友達と話せた?何話したの?」
本人が快く答えてくれたり、本人から話をしてくれる場合を除き、
ご家族から、何度も質問したりすることは避けたいです。
もし本人にとって行事への参加が良いものでなかったら、嫌なことを思い出させるキッカケになってしまいます。
ご家族として気になる所ですし、聞きたい所ですが、気持ちを押さえて見守っていきたい点になります。
【関連記事】
行事に参加した後に「守りたい3つのポイント」

行事に参加した後に「押さえたいポイント」は3つあります。
①:しっかり「休む」
②:「本人の感想」を聞く
③:「ポジティブな振り返り」をする
しっかり休む

たとえ短い時間でも、行事に参加することは、本人にとって大きな負荷がかかるものです。
周りから見て変わりない様に見えても、精神的に消耗していたり、家に帰ってから反動が出ることもあります。
本人のペースで十分に休んでもらい、休息を最優先にします。
また、周囲の大人からも「休むこと(休んで良いこと)」をメッセージとして伝えるのも大切です。
お子さんによっては、同学年の子を見て焦ったり、もっと頑張らなきゃと力が入る子もいます。
ただ、本人に合ったペースで進めないと、反動が来て、裏目に出ることが多いです。
本人の感想を聞く
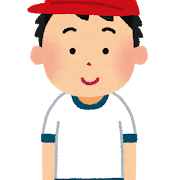
休息がとれたら、何気ない会話の時などに、感想が聞けると良いです。
テーブルを挟んで面と向かって聞くより、普段の雑談の中で、話の流れの中で聞けると良いです。
本人がどう感じたかによって、今後の学校との向き合い方など、考える材料が増える為、参考になります。
明らかに、本人が嫌がることが想像できたり、そもそもそういった話をする関係性でない場合は、聞かない形で問題ありません。
ポジティブな振り返りをする
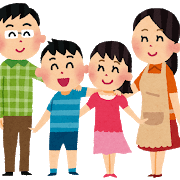
本人が対話できる状態でしたら、行事に参加して、どうだったか振り返りができると良いです。
「友達とアニメの話ができたんだね」
「行事で◯◯が出来たんだ!凄いじゃん!」
「行事の中で特に◯◯が楽しかったんだね」
など、本人が行事に参加した中でポジティブな要素を拾って言葉にして返すことで、本人としても…
「行事に参加して良かった」
「言われてみれば◯◯楽しかったな」
など、本人が自身のポジティブな気持ちを再度感じられたり、新たな気付きを与えるコミュニケーションの機会に繋がります。
【関連記事】
【別室登校の過ごし方】メリット/デメリット/教室へ復帰する5つのポイント
【不登校 行事だけ来るのはいい?】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の子が
「行事だけ参加することの意味」
・成功体験を積む
・自己肯定感の向上
・次の行動への意欲に繋がる
✅行事に参加する前に
「押さえたい4つのポイント」
・本人の気持ちを確認する
・具体的な参加の仕方を決める
・途中で辛くなった時の対策を決める
・学校と共通認識をとる
✅行事の参加に関する
「3つの注意点」
・本人への期待値を上げ過ぎない
・ネガティブな声掛けはしない
・何度も聞かない
✅行事に参加した後に
「押さえたい3つのポイント」
・しっかり休む
・本人の感想を聞く
・ポジティブな振り返りをする
✅不登校の子に
「必要な備え」
・必要最低限の学力
・本人が望む進路に必要な学力
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合う学習方法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】







































