

不登校の子の担任がしつこくて困っている方「学校の先生が登校するよう連絡がしつこい。登校させるべき?でも子どもは登校を嫌がっているし…。親としてどうすべきか分からない」
お子さんが不登校ですと、先生との「登校するのか、休むのか、これからどうしていくのか」等の、やりとりが出てきます。
このやりとりで悩まれている方が、今増えています。
この記事を執筆してる私は、発達/相談支援を15年以上しています。不登校のお子さんの支援も多くしてきました。
その支援経験を元に、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
先生がしつこい「2つの理由」
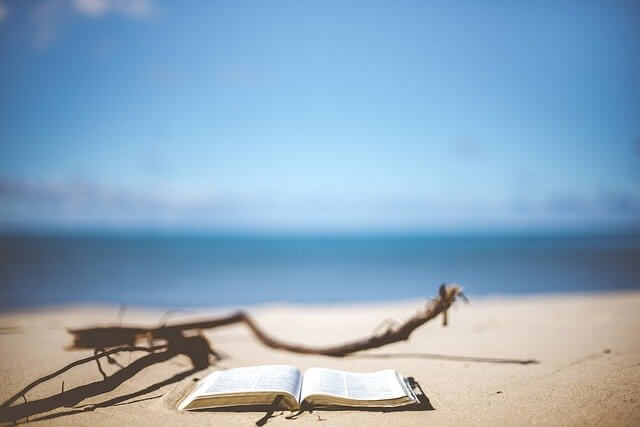
不登校の子に対して、先生がしつこい理由は、主に2つあります。
①:専門知識がなく、熱心なため
②:学校の評価を気にしているため
専門知識がなく、熱心なため
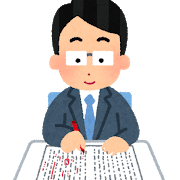
不登校のお子さんに対する専門的な知識があまりなく、熱意でお子さんに関わっているタイプの先生の場合になります。
先生の特徴として多いのは…
・経験が浅め
・子ども想い
・「とりあえず学校に来ちゃえば大丈夫です」等の発言がある
などの様子が見られ、経験や知識を持ち合わせていない場合が多いです。
✅無理解な先生の場合もある
最近はだいぶ減ってきましたが、「不登校は甘えだ!親の育て方が甘い!」というスタンスの先生です。
他の視点を受け入れず、登校を強めに求める先生です。支援をしていると、先生だけではなく、親御さんの中にもこのタイプの方がいらっしゃいます。
学校の評価を気にしてる為

学校は、不登校児童を出した場合、外部機関にその数や理由など報告する必要があります。
不登校には、欠席日数が何日以上などの基準があり、この不登校児童の数が多いと、学校の信用に関わってきます。
ここを気にしているのは、主に学校の管理職(校長や教頭先生)になりますが、
管理職の指導で担任の先生が学校の評判を守るため、登校するよう必死に電話をしてくる、ということが、残念ながらあります。
✅「登校する=不登校の解決」と思っている先生
登校することが、不登校の解決と思っている先生は、悪気なく子どもを登校させようとします。
先生にとっては「登校する=解決のゴール」になっているためです。
もし担任がこのタイプの先生でしたら、注意が必要です。次の項目で対策を解説しますので、お子さんの為にも、一緒に見ていきましょう。
しつこい先生の「3つの対策」
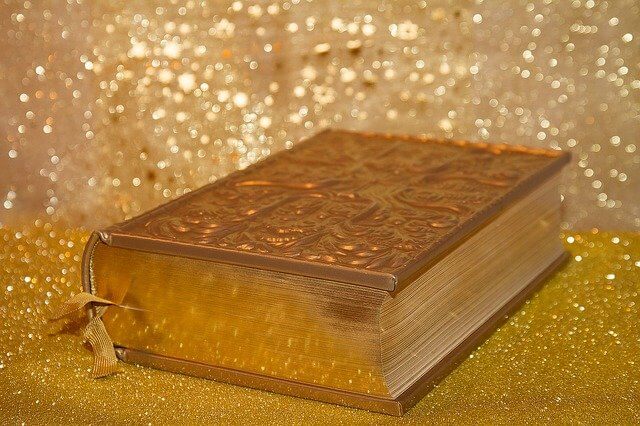
「しつこい先生の対策」は、3つあります。
私が実際に支援してきて、効果的だった方法になります。
①:登校は、「子どもと家族」で決める
②:先生との「連絡のタイミング、頻度」を決める
③:学校側で「信用できる先生」と繋がる
登校は、子どもと家族で決める
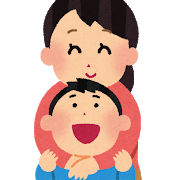
先生の連絡がしつこいと、プレッシャーを感じ、「子どもは嫌がっているけど、学校に行かせたほうがいいかな…」と、心が揺れる方がいます。
ただ不登校で大切なのは、「本人の意思の尊重」です。
先生がしつこいからという理由で学校に行っても、お子さんが辛い思いをし逆効果になります。
登校するかどうかは、「本人と家族で話をして一緒に決める」ということを、軸に置くことが必要になります。
そして、このスタンスを先生に明確に伝えることが大切になります。『登校は、子どもと親で相談して決めたいと思います』と、伝えるイメージになります。
不登校のお子さんだけでも、神経を使うなか、先生がしつこいと、本当に疲弊されると思います。
ただお子さんのことを考えると、ここの軸を持つことは、とても大切なことになります。
【合わせて読みたい記事】
先生との連絡のタイミング、頻度を決める

「完全不登校の子の毎日連絡」や「不登校ぎみで当日の朝まで休むか分からない場合の連絡」は、親御さんの大きな心身の負担になります。
仕事をされている親御さんの場合は、朝は尚更忙しいため、朝の電話連絡が大変です。
そこで、担任の先生と事前に『連絡をとるタイミング、頻度を決めておく』ことが、対策としてあります。
例えば…
・登校するときだけ連絡する
(完全不登校)
・毎週月曜と金曜の朝だけ先生に連絡する
(不登校ぎみ)
このように、お子さんの状態に合わせて、先生と相談し、決めておけると毎朝の「今日の連絡は…」というストレスが減らせます。
減らせる負担は工夫し、お子さんに向き合える時間を作っていくことが、大切になります。
学校側で信用できる先生と繋がっておく

残念ながら、担任の先生が信用できるとは限りません。
こちらがどんなに工夫しても、向き合ってくれなかったり、信用できない先生はいます。
ただその状態ですと、お子さんが、いざ「学校に行きたい」といったときに、お子さんが安心して登校する環境を作ることは、難しいです。
そのために、学校側の「信用できる先生」が必要になります。
例えば、
・校長先生
・教頭先生
・スクールカウンセラー
・通級の先生
などになります。特にスクールカウンセラーの先生は、学校と親御さんの中立の立場に当たる方になります。
学校側に伝えにくいことなども相談し、どうすべきか、助言をもらうことができます。
このような「学校との繋がり」を早めに作っておくことが、大切になります。
先生がしつこい時の「2つの注意点」

先生がしつこい時に、やりがちな注意点が2つあります。
ここが避けられるだけでも、現状を悪化させる可能性を下げることができます。
①:焦らせて登校させない
②:先生に謝らない
焦らせて登校させない

先ほどの説明を重なりますが、先生のプレッシャーに押されて、登校させるのは逆効果になります。
「無理やり行かされた」「誰も自分の気持ちを分かってない」「やっぱり学校は嫌だ」となります。
お子さんの気持ちに合わせて、進めていくことが必要になります。
とは言っても「勉強についていけなくなる…子どもの将来が心配…」という方も、いらっしゃると思います。
不登校の子の学習で悩まれている方は、【不登校の子は勉強追いつくの?】学習支援でも実践してる6つの勉強法 をご覧ください。
先生に謝らない

欠席の電話をするとき、「今日は欠席させて頂きます。すみません…」と伝えることが多いと思います。
ただ欠席の連絡は、お子さんが近くにいるときは、注意が必要です。
自分が学校休んで、自分の親が電話で先生に、「すみません」と言っていたら、
お子さんとしては「学校休むことはそんなに悪いことなんだ」「家族にも先生にも迷惑掛けちゃってる」と、自己肯定感が下がったり、罪悪感が強まります。
そういったことを避けるために、「すみません⇨ありがとうございました」にすることで、ある程度解消ができます。
こちらが参考例になります。
「今日は欠席させて頂きます。すみません」
⇩
「今日は欠席させて頂きます。電話のお時間ありがとうございました。」
お子さんの状況や先生のタイプに合わせて、参考にしてみてください。
それでも、「先生に迷惑は掛けているから、お詫びの一言は伝えたい..」という方は、
可能な範囲で、お子さんのいない所で、電話ができると良いと思います。
【不登校 しつこい先生への対応】まとめ

記事のポイントになります。
✅先生がしつこい
「2つの理由」
・専門知識がないが熱心
・学校の評価を気にしてる
✅しつこい先生の
「3つの対策」
・登校は「本人の意思」で決める
・先生との連絡のタイミング、頻度を決める
・信用できる先生と繋がる
✅先生がしつこい時の
「2つの注意点」
・焦らせて登校させない
・先生に謝らない
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】
【不登校の親】ノイローゼになる前に。親のメンタルを守る為に大切なこと







































[…] 【不登校】しつこい先生にはどう対応すべき?3つの対策 […]
[…] 【不登校】しつこい先生にはどう対応すべき?3つの対策 […]