

子どもの不登校で悩まれてる方「学校は休んでるのに、遊びには行く..止めた方がいい?どう関わるべきか分からない」
不登校は、完全不登校、別室登校、特定の授業だけ参加、行事だけ参加など..お子さんによって様々な形があります。
その中には「学校は休んでるけど、遊びには行く」というお子さんもいらっしゃる為、
ご家族として、尊重すべきか止めるべきか、判断に悩まれてる方も多いです。
結論からお伝えすると、本人が望んでいることでしたら、尊重して問題ありません(危険などが伴わない範囲で)
とはいえ、学校を休んでる状態で本人に遊びに行かせるだけでは、
「本当にこのままで大丈夫?好きなことだけやって、不登校が悪化するんじゃないの」とご家族は不安になると思います。
そこで本記事では、”遊びには行く不登校の子” に関わる上で「ご家族が認識しておきたいこと/関わる時のポイント」をお伝えしたいと思います。
この記事を執筆してる私は、不登校・療育支援を15年以上しています。
これまで不登校の子、親御さんの支援に携わる中で、効果があった内容をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不登校の子が「“遊びには行く” が良い理由」

不登校の子が「“遊びに行く” が良い理由」は、4つあります。
家族の皆さんが把握したい点にもなります。
①:不登校の子は「疲弊/消耗」してる
②:「安心/楽しい/
家族以外との繋がり」が大事
③:「自己選択/自己決定」の機会が必要
④:「一方的な管理/制限」は逆効果
不登校の子は疲弊/消耗してる

不登校の子は、心身が疲弊してる場合が多いです。
強い不安や緊張を抱えていたり、プレッシャーを感じて常に気を張っていたり、心と体のエネルギーを消耗しています。
特に、精神的に疲れてることが多く「自分は何をやってもダメ」と自己肯定感が下がってる場合も多いです。
・ストレス過多
・落ち込んでる
・自信がない
・不安で辛い
・気持ちの波が大きい
・無気力
など、お子さんによって、様子は変わってきます。
いずれにしても、不登校の子には、まず休息が必要になります。学校が辛い場合は、一旦学校のことを忘れて、心身を休める必要があります。
「遊びに行く」というのは、本人にとって休息・楽しい時間になるポジティブな要素ですので、尊重したい点になります。
不登校の子の休息の取り方・休息のタイミングなどの詳細は、こちらの記事をご覧ください。
【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン・関わり方・注意点
安心/楽しい/家族以外との繋がり が大事
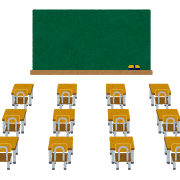
不登校の子が、これからの生活や学校に向き合ってく為には、欠かせないモノがあります。
それは…
・信頼できる人
(話を聞いてくれる/理解してくれる)
・安心できる場所
(リラックスして過ごせる/所属感)
※所属感=「ここにいても良いんだ」と思えるポジティブな気持ち
本人にとって、安心・信頼できる繋がり(人/場所)が大切になります。
「自分には味方がいる」
「分かってくれる人がいる」
「ここに行くと楽しい、また来たい」
このようなポジティブな気持ちになる機会が、不登校の子を守る要素になります。
冒頭でもお伝えしましたが「遊びに行く」が本人にとって「楽しい!また遊びたい!」などポジティブな気持ちに繋がるのであれば、尊重したい貴重な機会になります。
自己選択/自己決定 の機会が必要

生活をする中で年齢が上がるほど、自分で選んで決める機会が増えてきます。
私たちの感覚としては「自分で決める」は、当たり前に感じられるかもしれませんが、不登校の子の場合は別になります。
不登校の子の中には、自分で決めることが極端に苦手だったり、母親に全部委ねて依存する子もいます。
本人自身に決める機会がないまま、ご家族が決め続けると、本人の中で「自分で選ぶ、決める」という選択肢がなくなっていきます。
決断できなかったり、周りの後押しがないと選べない子もいますので、小さい機会から選ぶ・決める機会を作ることが大切になります。
一方的な管理/制限 は逆効果

不登校の子は、ゲーム、スマートフォン、動画などで過ごす時間が多くなりやすいです。
ご家族として、
「依存症になるんじゃないか」
「自分の殻に閉じこもる様になる…」
「好きなことばかりじゃ、頑張る力が身につかなくなる…」
など、ご心配が尽きないかと思います。そのため、ご家族が禁止・制限・管理する場面が多くなりやすいです(必要な部分もあります)
実際に不登校支援をする中で、本人の日中での過ごし方のご相談は多いです。
ただ、大人の視点だけで、
「ゲームは◯時間」
「勉強30分したら、動画10分見ていいよ」
「◯◯をしたら、外に遊びに行って良いよ」
など、一方的な管理は、逆効果になる場合が多いです。
本人の不満が溜まったり、長続きしなかったり、癇癪になってご家族と衝突したり、親子関係が悪化したり、ネガティブなことに繋がりやすいです。
そのため、本人との対話を通して、一緒に決めることが大切になります。
お子さんの年齢によっては難しい部分もありますが「遊びに行く」も相手や場所、時間によって変わってくると思いますので、時間や場所など、本人とルールなどを決められると良いと思います。
本人と決める具体的な方法は、次でお伝えします。
【関連記事】
遊びには行く子に関わる時の「5つのポイント」

遊びには行く子に関わる時の「ポイント」は、5つあります。
①:本人が「楽しめてる時間」を増やす
②:本人の気持ちを「尊重する」
③:本人の「選ぶ・決める機会」を作る
④:「生活リズム」を守る
⑤:「家での役割」を渡す
本人が楽しめてる時間を増やす

繰り返しになりますが、不登校の子にとって「遊びに行く」は良いことです。
一緒に楽しめる人、場所、時間があることは、本人の活力になります。
家でも外でも、家族でも友達でも、習い事でも、本人が楽しめる時間であれば、それは多い方が良いです。
本人が興味を持てることを、ご家族も一緒に探したり、見学や体験に行くのも1つです。
本人に好きなモノが見つかると、これからの生活、学校と向き合うエネルギーに繋がりやすくなります。
【関連記事】
本人の気持ちを尊重する

基本的には、本人の気持ちを尊重することが大切になります。
・どう思ってるか
(感じたこと)
・どうしていきたいか
(希望や不安)
お子さんによっては、言葉にするのが難しい場合もありますので、落ち着いた環境で丁寧に伝えて、考える時間を作るのも良いと思います。
もし、療育や習い事など、ご家族以外の大人の方と繋がれていて、本人も信頼してる場合は、ご家族以外の方から気持ちを聞くのも1つです。
本人が、一番気持ち話しやすい人/環境を選ぶことが大切になります。
本人の選ぶ/決める機会を作る
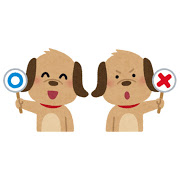
生活の中で、どんなに小さなことでも良いですので、本人が「自分で選ぶ、自分で決める」機会を作ることが大切になります。
自分で考えることが難しい子の場合は、ご家族が選択肢を提示したり、選択肢のメリット・デメリットをお伝えし、選んでもらうのも1つです。
お子さんによっては、紙や小さいWボードなどに書き出して整理をし、視覚的に整理するのも効果的です。
生活リズムを守る

遊びに行くと、お子さんによっては、生活リズムが乱れる場合もあります。
そのため、生活リズムを乱さない範囲の中で「遊びに行く」を尊重する必要があります。
特に大切になるのが、起床時間になります。遊びに行った日の夜は遅くまで起きてる、興奮して眠れない、などの理由で起床時間が大きくズレると、生活リズムの乱れに繋がる恐れがあります。
家での役割を渡す

「遊びに行く」は良いことですが、それ以外でも、できることが増えると良いですよね。
本人と話をして、決める必要はありますが、例えば、家の役割を担ってもらうのも1つです。
・ゴミ捨て
・洗濯物をたたむ
・お風呂掃除
・買い物
など、本人が取り組みやすいモノなら、内容はどんな形でも大丈夫です。
そして、ご家族にも感謝される機会になる為、本人としても自己肯定感が上がる機会に繋がりやすいです。
お子さんによっては短い時間、学習をするのも1つです。お子さんが取り組みやすく続きやすい内容ですと良いです。
【関連記事】
【不登校だけど遊びには行く子】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の子の
「“遊びには行く” が良い理由」
・不登校の子は疲弊\消耗してる
・安心、楽しい、信頼できる人の存在が大事
・自己選択/自己決定の機会が必要
・一方的な管理/制限は逆効果
✅遊びには行く子に関わる時の
「5つのポイント」
・本人が楽しめてる時間を増やす
・本人の気持ちを尊重する
・本人の選ぶ/決める機会を作る
・生活リズムを守る
・家での役割を渡す
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】


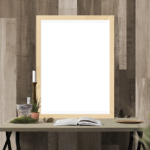





































[…] 【不登校だけど遊びには行く子】関わる時に大切な5つのポイント […]