

ADHDの子の学級で悩まれてる方「うちの子は普通学級で大丈夫かな。ついていけるか心配。学級選びのポイントや事例が知りたい」
「子どもに合った環境(学級)を選んであげたい」
どんな親御さんも、我が子の過ごしやすさ・将来の為に、学級選びを考えられると思います。
一方で、普通学級?通級?支援学級?など、うちの子に合った学級はどこなんだろう?と、
疑問に思われる方も、少なくないと思います。
ADHDの特性がある子でしたら、学級選びは、より丁寧に進める必要があります。
そこで、本記事では、「ADHDの子の学級に関する事例・学級選びのポイント」をまとめました。
私は、療育/相談支援を15年以上しており、これまで、学級選びの相談も多く受けてきました。
この支援経験を元に、情報をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
ADHDの子は「普通学級に行ける?」

支援をする中で、よく聞かれる質問になります。
「ADHDの子は、普通学級に行けるんでしょうか?うちの子は大丈夫でしょうか?」という内容です。
学級選び自体は、親御さんの判断で決められます。
ただ、お子さんにその学級が合ってるかは、ケースバイケースになります。
少なくとも、「ADHDだから普通学級は合わない」ということは、ありません。
ADHDの子が普通学級で過ごした「成功事例」

ここでは、ADHDの子の普通学級の「成功事例」を2つお伝えします。
私が実際に、支援をした事例になります。
成功の基準は、人によって様々ですが、ここでは、2つの基準で見ていきたいと思います。
・子ども本人が学校生活を楽しめてる
・学校生活に、大きな問題がない状態
では、1つずつ見ていきます。
環境が作れた「衝動タイプ」の小1👧
ADHDの「衝動性が高い」タイプのお子さんになります。
嫌なことがあると「離席する」「プリントを破る(授業に参加しない)」がありました。
授業が本格化する5月頃~本人の困った言動が、目立つようになってきました。
担任の先生との面談で指摘され、親御さんはショックを受けていました。
ただ、担任の先生は、協力して下さるスタンスで、「必要な関わり方があれば、教えて下さい」とお話もありました。
そこで、教室の後ろの隅に「休憩スペース(椅子)」を作り、何かあれば、そこで休憩して良いことになりました。
担任の先生からクラスメイトに、事前に説明してもらい、
本人が安心できる環境(休憩場所)を、作ることになりました。
そこから1ヶ月ほどで、離席する・プリントを破る様子は、ほとんど無くなりました。
休憩スペースを利用することで、困った行動は減っていきました。
本人は「何かあれば休憩スペースに行ける」という安心感があり、
結果として、授業に参加できる時間も増えていきました。
「不注意型」の小5👧
ADHDの「不注意タイプ」のお子さんになります。
物の管理が苦手で、忘れ物が多かったり、提出物の漏れが多く、本人も親御さんも困っていました。
低学年の内は、親御さんが全部用意をする形で、乗り切ってました。
ただ、このままだと本人が困ってしまう為、「帰る前のチェックリスト」を使うことにしました。
具体的には、チェックリストをランドセルに貼っておき、下校前にチェックリストを確認できる様にしました。
ランドセルを開けると、チェックリストが視界に入る様になってます。
担任の先生にも事情を説明し、最初の内は、個別で声を掛けてもらいました。
最終的には、家に持ち帰るものを、自分で確認できる様になり、
忘れ物で、日常的に困ることは無くなりました。
【関連記事】
【ADHDの子】うちの子は何タイプ?3つのタイプ/7つの接し方
ADHDの子が普通学級で過ごした「失敗事例」

ここでは、ADHDの子の普通学級の「失敗事例」を2つお伝えします。
こちらも、私が実際に支援した事例になります。
離席が多い「多動タイプ」の小2👦
多動性があり、授業中に席を立ち、フラフラする様子があるお子さんです。
指示が理解できなかったり、課題が分からないと、席を立つことがありました。
先生は、度々声を掛け、一旦席に戻れるものの、時間が立つと、再び席を離れる繰り返しでした。
多動性に加えて、一斉指示の理解が難しい様子もあった為、
30人以上の集団ですと、どうしてもついていけない場面がありました。
次第に、先生に注意される回数が増え続け、
本人は「自分はダメな子」と発言する様になり、自己肯定感が下がっていきました。
3年生~は支援級に移れたのですが、本人にとって2年生で過ごした時間は、辛いものになってしまいました。
手が出る「衝動性タイプ」の小3👦
衝動性が高く、思い通りにいかないと癇癪が出るお子さんです。
授業中に問題が解けないと、イライラして「もうできない!」と叫んだり、
友達に言われた些細なことで怒り、衝動的に手が出ることがありました。
特に、友達とのトラブルが多く、怪我をさせてしまう場面もありました。
親御さんは、謝罪の対応に追われ、学校からも責められ、疲弊されてました。
普通学級という大人数の環境ですと、刺激が多く、本人の怒りに繋がるキッカケが多かったです。
本人も、悪いことは分かってるのに、繰り返してしまう自分に嫌気が差してました。
途中からは、親御さんが学校に付き添い、授業中も教室の後ろで、本人のサポートをする形になりました。
【関連記事】
学級選びで「大切なこと」

学級選びで「大切なこと」は、3つあります。
①:本人の「気持ち」
②:「必要な配慮・環境」があるか
③:第3者から「どの学級を」勧められてるか
※特に学校
本人の気持ち

本人の気持ちが一番大切になります。
ただ、実際に学級選びとなると「親御さん・学校で話を進める」ことも多いです。
本人の意思がないと、上手くいかないことが多いです。
“本人の納得感・選択” が大切になります。
例えば、「大人数で皆と同じ授業を受けるのと、少人数で自分のペースで進む授業なら、どっちの方がいい?」
など、本人の気持ちが聞けると理想的です。
大人から見て、通級や支援級の必要性があっても、
本人が『皆と同じがいい。恥ずかしいからヤダ』などの気持ちがあれば、
特別支援の環境も、活きづらくなってしまいます。
【合わせて読みたい記事】
【子どもに「特別支援学級」って何?と聞かれたら】説明の仕方/注意点
必要な配慮/環境があるか

お子さんに特性あり、学校生活の中で困りがあるなら、
『お子さんに合わせた配慮・環境』は、必要になります。
例えば、一斉指示の理解は苦手だから、個別でゆっくり説明が必要」であれば、
“その配慮が得られる学級” を選びます。
お子さんに必要な配慮・環境は何だろう?
⇨その配慮・環境は、普通学級?通級?支援学級?どの学級が一番得られるだろう
と考えるイメージになります。
ただ、専門的な内容になりますので、療育に通われてる場合は、支援員の先生に。
通われてなければ、学校の先生に相談できると良いと思います。
【合わせて読みたい記事】
第3者からどの学級を勧められてるか

第3者(特に学校)から、どの学級を勧められているか、も大切な点になります。
特に『学校側の考え』は、実際の本人の様子を見て判断してる為、
検討する際の “大切な情報” になります。
療育に通ってる方は、可能なら学校に訪問してもらい、専門の先生にアドバイスをもらうのも1つです。
もし、療育に通われていない場合は、
学校に配属されてるスクールカウンセラーに相談し、様子を見てもらうこともできます。
地域差がありますので、『在籍校に確認』してみます。
✅「先入観・世間体」で学級選びをしない
「ダメな子がいく所だから」や「周りから変な目で見られる」などの理由で、学級を選んでしまうことは避けましょう。
「お子さんにとって」の学級選びでないと、その後の学校生活で辛い思いをして、
最悪の場合、不登校・引きこもりなど、二次障害になることもあります。
二次障害は、適切な環境があれば防げます。
二次障害について、詳しく知りたい方は、下の記事をご覧ください。
学級選びに不安がある時「備えたいこと」

ここでは、学級選びに不安がある時に、3つの「備えておきたいこと」をお伝えします。
事前に準備をしておき、何かあったときに
“すぐ動ける状態を作っておく” が大切になります。
必要に応じて、参考にして下さい。
①:学校内で「相談できる人」と繋がる
②:「通級/支援級の情報」を集める
③:「学習面」のサポート
学校内で相談できる人と繋がる
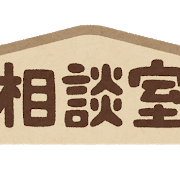
学校内で、信頼して相談できる人と繋がっておくのが、大切になります。
よくあるのは、担任の先生の理解がなく、お子さんが辛い思いをしてるケースです。
いざ問題が起こった時に、お子さんの味方になってくれる(理解者)先生と繋がっておけると、
問題の解決に向けて、協力を得られやすく安心です。
学校内で相談できる先生は、下の先生が多いです。
・担任
・校長/教頭先生
・保健室の先生
・スクールカウンセラー
・通級・支援級の先生
・支援コーディネーター
信頼できる・話がしやすい先生は、人によって様々だと思います。
まずは、面談など時間をとって、信頼できる先生を見つけておけると安心です。
【関連記事】
【発達障害の子と担任が合わない時】3つの大切なポイント/対処法
通級/支援級の情報を集める
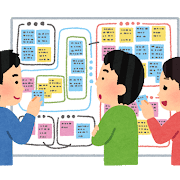
在籍校に、通級/支援級があるか
⇨あるなら、何クラスで何名なのか
⇨ないなら、、どこの学校に通うのか
のように、事前に情報を集めておけると安心です。
あと、可能でしたら、先輩ママに聞くのも1つです。
表面的な情報だけでなく、実情も掴みやすいのでお勧めになります。
【合わせて読みたい記事】
学習面のサポート
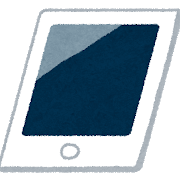
学習面が心配な方は、「学習面のサポートの準備」をしていきます。
例えば、ADHDの子でよくあるのは、
・授業参加できなくて、勉強が遅れてる
・集中力低くて、学力がついてない
・そもそも勉強やりたがらない
などの、学習の困りが出やすいです。
学習面で困る場合、最も多い時期は、小3~4になる頃です。
実際に支援していて、学習に関する相談では、最も多い学年になります。
授業についていけなくなり、点数が低くて、お子さんの拒否感が次第に強まってきます。
授業を嫌がったり、宿題でイライラが爆発したり、勉強をしなくなったり…。
そうならない為の「学習のサポートの準備」になります。
学習サポートの準備の1つとして、私はタブレット学習を勧めています。
もちろん、「お子さんが興味を持てたり、取り組むのが嫌じゃない」、というのが前提になります。
タブレット学習には、家庭内で気軽に取り組めるのはもちろん、
お子さんの苦手な問題が自動抽出されるなど、学習サポートが充実した機能が、多いです。
・今の課題/今後必要な学習内容の把握
・小さい成功体験積み、自信をつける
(学習が嫌にならない様に)
目的に合わせて、情報を集めるだけでも良いと思います。
タブレット学習については、下の記事にまとめてます。
お子さんの学習に不安がある方は、ご覧ください。
【発達障害の子向け】タブレット学習~ADHD/自閉症の子に合う4つの特徴~
【ADHDの子は普通学級は避けるべき?】まとめ

記事のポイントになります。
✅ADHDの子は
「普通学級に行ける?」
・ケースバイケース
・”ADHD=普通学級はダメ” ではない
✅ADHDの子が普通級で過ごす
「成功事例」
・必要な環境が作れた事例
・不注意型の子の事例
✅ADHDの子が普通級で過ごす
「失敗事例」
・離席が多い/多動タイプの事例
・突発的な言動が多い/衝動性タイプの事例
✅学級選びで
「大切なこと」
・本人の気持ち
・必要な配慮/環境があるか
・第3者からどの学級を勧められてるか
✅学級選びに不安がある時
「やるべきこと」
・学校内で相談できる人と繋がる
・通級/支援級の情報を集める
・学習面のサポート
以上になります。
本記事がお役に立てれば幸いです。
【関連記事】







































