

子どもの学級で悩まれてる方「小学校の先生から支援学級を勧められた。普通学級と支援学級、どっちがいいの?学級選びのポイントが知りたい」
お子さんの学級選びは、多くの親御さんが悩まれるとても難しい問題です。
先生に支援学級を勧められた。でもすぐに決断できるという方は、少ないと思います。
そこで、本記事では、「支援学級を勧められた時、押さえておきたい3点」をまとめました。
私は、発達支援の相談/指導員を15年以上しており、これまで学級選びの相談も多く受けてきました。
現在も支援に携わってる経験を元に、私が特に大事だと思う3点について、お伝えしていきます。
その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
支援学級を勧められた時「しておきたいこと」

支援学級を勧められた時に「しておきたいこと」は、3つあります。
①:子どもの「具体的な言動」を聞く
(支援学級を勧める理由)
②:支援学級の「情報収集」をする
③:子ども本人の「気持ち」を聞く
子どもの具体的な言動を聞く

学校が支援学級を進めるのには、当然理由があります。
学校の先生が、お子さんの何かしらの言動を見て、「支援学級を勧める」という判断をしています。
そのため、支援学級を勧める理由(根拠)を、お子さんの具体的な言動で聞くことが大切になります。
よくある支援学級を勧められる理由(お子さんの言動)は、下の内容が多いです。
・授業中の離席
・他児へのちょっかい
・友達とトラブルが頻発
・学習の遅れが著しい
これらの理由を具体的な場面で聞けると、”学級を変える必要性の有無” や “本人に合う学級選び” の参考になります。
支援学級の情報収集をする
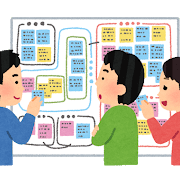
支援学級の情報を、できるだけ集めます。
学校によって、かなり変わってくる為、事前の情報はとても重要になります。
支援学級といっても、先生の理解がなかったり、学級内が荒れていたり様々です(年度によっても変わります)。
理想の情報収集は、支援学級を経験した先輩ママに聞くことです(難しいことですが…)。
把握しておきたい情報は…
・クラス編成
・先生の人員体制
・先生/子どもの様子
・普通級との交流頻度
・転籍の有無
(支援学級⇄普通学級)
になります。
事前に把握しておけると、学級選びの判断材料になります。
子ども本人の気持ちを聞く
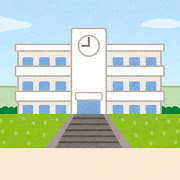
子ども本人が今の学級(普通学級)で過ごすことをどう思ってるのか、を聞きます。
先生から見て困っていても、本人は困っていない場合もあります。中には、友達が多く楽しんでる子もいます。
学級選びは、本人の気持ちが最も重要になります。
早い段階で聞いておけると、今後の学級選びの方向性が見えて進めやすくなります。
小学校で支援学級を勧められた「2つの事例」

私が実際に支援に携わってきたケースになります。
【普通学級を選んだ】小2 ADHD傾向あり👦
学校から授業の遅れを理由に、支援学級を勧められました。
ただ、在籍校の支援学級は落ち着かない環境で、先生も配慮がないという情報を、ママ友から聞いていました。
クラスの様子としても、同じ学年の支援学級の子は、飛び出しや他害など、トラブルが頻発していました。
そのため支援学級は選択せず、学習の遅れに関しては、家庭でタブレット学習を導入することにしました。
導入後も、学習の遅れはあったものの、授業が全く分からなくて嫌になるということもなく、普通学級で楽しく過ごすことができました。
【支援学級を選んだ】小3 ASD(自閉スペクトラム症)傾向あり👧
板書が間に合わず、授業の内容理解にも遅れがありました。
本人の気持ちとして「ゆっくり教わりたい」「分からない時にすぐ質問したい」という希望もあり、支援学級に進むことになりました。
支援学級に移ってからは、板書のペースや質問できる時間が本人に合っていた為、授業が理解できない状態は避けられる様になりました。
以前は、学習に自信がなく、授業の緊張した様子でしたが、今は成功体験も積めるようになり、自分から学習に取り組む姿勢が見られるようになりました。
【合わせて読みたい記事】
【現場でよくある事例】支援級を選んで後悔する3つのパターン/対策
普通級から「支援級へ移る目安」

普通級から「支援級へ移る目安」は、4つあります。
①:本人が「困ってるか」
②:本人の「気持ち(必要性/納得感)」
③:本人の「過ごしやすさ」が作れるか
(支援級で)
④:学校側の「考え」
本人が困ってるか

本人が今の学級(普通級)で困りを感じてるのか、が大切になります。
周りから見て、困ってるように見えても、本人が困りを感じてない(気にしてない)場合もあります。
まずは、本人が日常生活をどう感じてるのか、確認してくことが大切になります。
本人の気持ち

本人の、支援級に移ることへの「必要性や納得感」になります。
本人が困りを感じていた場合は、その困りを減らす為に学級を変える選択肢を伝えていきます。
例えば、人の声やザワザワした音が気になって疲れる、という子でしたら、
少人数の支援級ですることで、苦手な人の多さ、音を避けることができます。
本人の困りを軽減するために支援級が利用できるなら、それも1つの選択肢になります。
このように本人の困りに繋がるモノがあれば、必要性や納得感が出やすいです。
✅本人が困りを感じてない場合
本人が困りを感じてない場合は、本人の希望(望み)を聞く場合もあります。
例えば「自分に合った勉強がしたい。個別でゆっくり教わりたい」などの気持ちがあれば、支援級が選択肢に入ります。
このように、支援級という環境が本人の希望(望み)に、少しでも形にできる可能性があるなら、転籍の検討ができます。
【関連記事】
【子どもに「特別支援学級」って何?と聞かれたら】説明の仕方/注意点
本人の過ごしやす」が作れるか
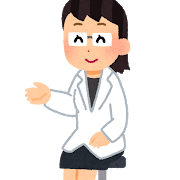
例えば、環境の変化が苦手で、見通しがないと不安でしょうがない子がいた場合です。
そんな不安を感じやすい子に対して、検討する支援級が、毎年先生が何人も変わっていて、不安定な状況だったら、変化が苦手なお子さんには合っていません。
このように、本人の特性と検討する学級との相性を見ておく必要があります。
学校側の考え
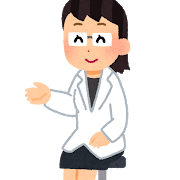
担任やSC(スクールカウンセラー)がどう考えているのか、聞きます。
・支援級に移る必要性があるのか?
(普通級でできることはないのか)
など、学校の先生の見立てを伺ってみます。
学校の先生ですと、支援級の状況なども把握してもらえる為(確認してもらえる)、お子さんの状況と合っているのか、相談もしやすいです。
診断名は考える材料の1つと捉える
学校によっては、診断がないと、支援級に移ることができない場合があります。
学校の方針として、手続き上の問題では仕方ないですが、
お子さんと向き合う上で本当に大切なのは、診断名はお子さんの1つの見方」と考えることです。
「その子に必要な配慮や環境は何があるんだろう?」と考える為の材料に過ぎません。
説得<選択肢を知ってもらう
親の立場としては「できれば普通学級に」「すぐに支援学級に」など、色んなお考えがあると思います。
お考えが明確になるほど、本人に伝わってほしくて、中には説得や誘導をしたくなる時もあるかもしれません。
ただここでは、”本人を説得” というよりも、“それぞれの学級(普通学級・支援学級)のメリット・デメリットを伝える” ことが、まず必要になります。
必要な情報を把握してもらった上で、本人が選ぶことが重要になります。
自分で決めないと「本当は行きたくなかった」「勝手に決められたから」と頑張る力が削がれる恐れがある為です。
普通級から支援級へ「4パターン(事例)」
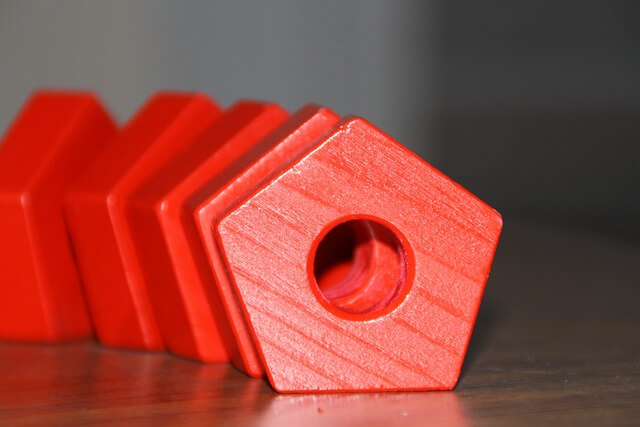
私が、現場でよく見てきたケースになります。
①:小1/小2の子(グレーゾーン)
⇨集団に1~2テンポ遅れる
②:小1~小4の子(診断あり/傾向あり)
⇨他害・癇癪・離席等が増える
③:親の意向で普通級にチャレンジ
⇨参加してるけど、授業理解してない
④:小3/4の子
⇨授業の遅れが目立つ
小1/小2の子⇨集団に1~2テンポ遅れる

幼少期から、何となく変わった子だなぁと感じていたけど、生活上で困ることはなく、就学まで進んでいたケースになります。
幼稚園や保育園では、自由保育が主体で、先生もお子さんを尊重する方針で、お子さんの様子が目立つことはありませんでした。
ただ就学して、30~40名の大きな集団になり、先生の個別の声掛けがあまりない環境にあると、集団への遅れが目立ってきました。
集団の動きに対して、1~2テンポ遅れる様子が出てきました。
担任の先生との面談で指摘されるパターンが多く、親御さん自身驚かれることもあります。
時期でいうと、GW明けの5~6月頃に目立ってきて、相談に来られる方が多いです。
小1~小4の子⇨他害・癇癪・離席が増える

診断名があったり「ADHD傾向あり」など、特性がある子になります。
カッとなって手を出したり、注意されたことで癇癪を起こしたり、授業中に離席するなどになります。
他の子や授業に大きな影響を与える行動の為、学校側から支援級を進められるパターンも少なくありません。
親の意向で普通級にチャレンジ⇨参加してるけど、授業理解してない

本来、支援級に行っても良いお子さんですが、親御さんの意向で普通級で様子を見る判断をしたケースになります。
検査結果から、知的障害までつかないですが、ボーダーラインの子で、一見他の子と変わらないように見るタイプの子になります。
学校では、他害や離席など、周囲に大きな影響を与える行動がない為、普通級で過ごすのも問題ないように見えます。
先生によっては「良い子ですよ」と見過ごされることもあります。
ただ、本人は授業に参加はしてるけど、内容を理解が難しく学びになっていない場合があります。
本人が全く気にしないタイプでしたら、過ごすことだけならできますが、次第に授業が苦痛になったり、学習への拒否感に繋がる子も一定数います。
本人や親御さんの気持ちを確認しながら、今の学級が最適なのか、学校や支援先を相談が必要なケースになります。
小3/4の子⇨授業の遅れが目立つ

学習の苦手さは、以前から見られていたものの、小1/2では何となく過ごしてきたケースになります。
小学3、4年生になり、文章題が増えたり、計算が複雑になる中で、苦手さが顕著に出ます。
授業だけでは理解が追いつかず、家庭で親御さんが教えても、なかなか定着しづらいケースになります。
学習しても成果が出ず、次第に本人の学習の拒否感が出てきて、学力以前に、学習の取り組みの問題に発展してきます。
客観的に見て支援級の方が合ってる子は多いですが、
本人自身が「自分はバカじゃない」「何で皆と違う所に行かないと行けないの?」
と拒否する場合が少なくありません。
【小学校で支援学級を勧められた時】まとめ

記事のポイントになります。
✅支援学級を勧められた時に
「したいこと」
・子供の具体的な言動(勧める理由)を聞く
・支援学級の情報収集をする
・本人の気持ちを聞く
✅支援学級を勧められた
「事例紹介」
・【普通学級】小2 ADHDケース
・【支援学級】小3 ASDケース
✅普通級から
「支援級へ移る目安」
・本人が困ってるか
・本人の気持ち(必要性/納得感)
・本人の過ごしやすさが作れるか
・学校側の考え
✅普通級から支援級へ移った
「4パターン(事例)」
・小1/小2の子(グレーゾーン)
⇨集団に1~2テンポ遅れる
・小1~小4の子(診断あり/傾向あり)
⇨他害・癇癪・離席等が増える
・親の意向で普通級にチャレンジ
⇨参加してるけど、授業理解してない
・小3/4の子
⇨授業の遅れが目立つ
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【小学校で支援学級を勧められた時】学級選びの3つのポイント […]
[…] 【小学校で支援学級を勧められた時】学級選びの3つのポイント・事例紹介 […]
[…] 【小学校で支援学級を勧められた時】学級選びの3つのポイント・事例紹介 […]
[…] 【小学校で支援学級を勧められた時】学級選びの3つのポイント・事例紹介 […]
[…] 【小学校で支援学級を勧められた時】学級選びの3つのポイント・事例紹介 […]