

療育について知りたい方「療育にデメリットはあるの?注意点があれば知りたい」
困りを抱えてる子の支援になる “療育” 。
保育園で勧められたり、保健師から発達の指摘を受けたり、学校の担任から療育を紹介されたり..
今、様々な場面で「療育」という言葉を知る方が増えています。
子どもに必要性があるかも..と思っても、聞き慣れない「療育」という言葉。
「どんなデメリットがあるの?」
「将来不利にならないの?」
と不安に思われる方も少なくないと思います。
そこで本記事では、
「療育のデメリット・注意点」に関する情報をまとめました。
本記事の執筆者の私は、発達・療育の支援を15年以上しており、現在も療育に携わってます。
現場での支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
療育の「デメリット」

療育を受けること自体に「デメリット」はありません。
強いて言えば、注意点に近いものが、3つあります。
①:家族の「精神的な負担」
②:「空き枠」が少ない
③:手続きに「時間/労力」が必要
家族の精神的な負担
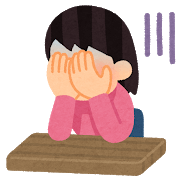
個人差がありますが、
「通所受給者証(療育に必要な手帳)」をネガティブに捉える方には、精神的な負担になる場合があります。
「うちの子に障害はない」
(手帳は必要ない)
「将来不利になりそうで心配」
と感じる方が一定数いらっしゃいます。
通所受給者証とは、福祉サービス(児童発達支援・放課後デイ)を受ける為に必要な手続きの一部になります。
『障害の有無を判断する』
『将来不利になる』というものではありません。
空き枠が少ない

療育をする事業所は、混み合ってる所が多いです。
理由の1つとして、受け皿と必要とする子の数が合っていない点があります。
特に福祉サービスの療育は、地域によっては、数年待ちというもの珍しくありません。
費用の負担の違いもあり、民間療育の方が空き枠が多い傾向があります。
手続きに 時間/労力が必要
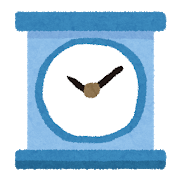
療育(福祉サービス)を受けるには、お住まいの役所の窓口で、手続きが必要になります。
複数の窓口を行き来して、問診や検査など、何回も実施します。1回ごとに数ヶ月空くこともありますので、時間やエネルギーを使います。
療育を始める方の多くが「手続きが本当に大変だった..」とお話されるぐらいです。私も息子が療育に通ってましたが、始める前の手続きだけで疲れていたのを覚えてます。
療育の「メリット」

療育の「メリット」は、3つあります。
①:「本人の過ごしやすさ」が作れる
②:自己肯定感 低下の「予防」ができる
③:子どもとの関わり方を「親が学べる」
本人/家族 の過ごしやすさが作れる

お子さん、ご家族の困りを減らし、過ごしやすさに繋げることができます。
困りとは、
「今の困り」
「今後出る可能性がある困り」
の2種類になります。
この困りは、お子さん自身がスキルを身につけること、
そしてご家族がお子さんを理解し、関わり方を学ぶことで、軽減したり解消することができます。
自己肯定感低下の予防ができる
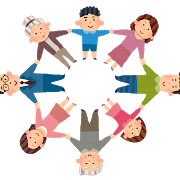
「早期療育」が勧められる理由の1つにもなります。
支援を受けずに、困った状態が続けば、お子さんは日常生活の中で、
「◯◯ができなかった」
「また先生に怒られた」
「自分だけ、皆よりできない」
と感じる機会が増え続けます。
失敗体験が重なると、自信を失い、活力が失われます。
自己肯定感が下がった子は、社会から離れる or 離れる問題行動をとります。
そうなる前に、予防的に療育を利用することが大切になります。
子どもとの関わり方を親が学べる

お子さん自身が自分の特性を知ったり、対処法が学べると、生活が格段にしやすくなります。
また、家族が学ぶことで、お子さんとコミュニケーションがとりやすくなり、理解が深まります。
療育はお子さんだけじゃなく、家族も一緒に参加することが重要になります。
療育で大切な「心構え」

療育で大切な「心構え」は、3つあります。
①:目的は、「本人の過ごしやすさ」を作る
②:「子どもだけ」が変わるものではない
③:療育に「正解はない」
本人(家族)の過ごしやすさを作る

療育は、定型発達の子に追いつく為でも、皆と同じことができる様になる為のものでもありません。
その子が自分らしく、過ごしやすくなる為のスキル・経験を積む為のものです。
そしてご家族が、お子さんを理解しサポートできる状態にしていく為のものになります。
子どもだけが変わるものではない
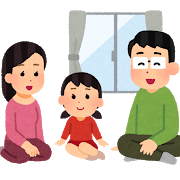
療育は、お子さんがスキルを身につける点と、ご家族がお子さんの特性・関わり方を学ぶ場になります。
療育の先生がどんな意図で関わっているのか、家では具体的にどんな配慮が声掛けが必要なのか、
ご家族も学びながら通うことが、大切になります。
正解はない
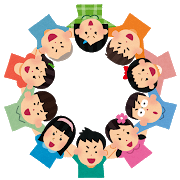
療育や教育に、正解はありません。
1ヶ月前に効果的だった関わりが、今は合わないということもあります。
お子さんの状態、過ごす環境、時期など、様々な要因から、お子さんに必要なものは変わってきます。
ただ、それを専門の方でない方が調整したり、判断することは難しいです。
それを踏まえ、療育などの専門機関に繋がっておくことが、長期的な観点でも大切になります。
【関連記事】
【療育の後悔】受けないと、子どもの将来はどんな可能性が?事例を元に解説
療育を「選ぶポイント」
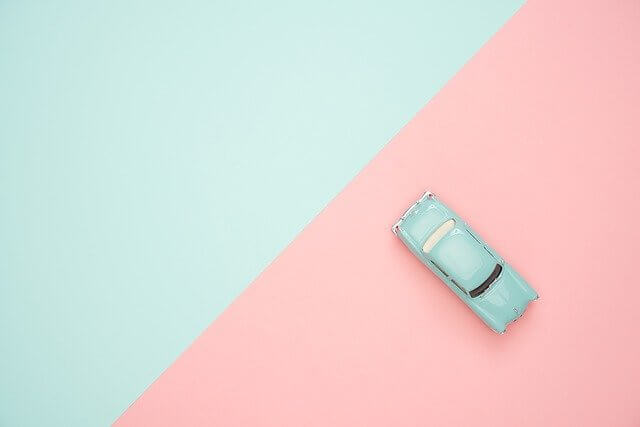
ここでは、療育を「選ぶポイント」を3つお伝えします。
①:本人が「楽しめてるか」
②:家族が「信頼できるか」
③:「子どもの課題」と
「療育のタイプ」が合ってるか
本人が楽しめてるか

大前提は、お子さんが楽しめていて、また来たい!と思えているか、です。
中には慣れるまで、しばらく通わないと行けない子もいます。
あくまで個人的な目安ですが、2ヶ月(週1回)通っても、慣れる様子が全く感じられない場合は、
他の療育を検討されても良いかもしれません。
家族が信頼できるか
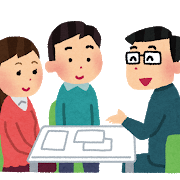
ご家族が、療育の先生を信頼できるか、相談しやすいか、の観点で選ぶことも大切になります。
当たり前ですが、お子さんを連れて実際に通われるのは、親御さんです。
人間的な相性もですが、親身になって話を聞いてくれるか、共感してくれるか、アドバイスは具体的かなど、
相談できる専門家として信頼できるか…を見ていけると良いと思います。
子どもの課題と療育の形態が合ってるか

お子さんが学ぶ必要があること(課題)と療育の形態(目的)が合っているかも重要になります。
例えば、発語(意思疎通)がなく、人に全く関心がない(マネ・目を合わせる様子がない)子に、
集団の療育だけでは、発語(意思疎通)には繋がりづらいです。
個別で人に伝えるメリット(意味)を理解する必要があるため、集団の環境だけでは、不十分なためです。
このように、お子さんが学ぶ必要があるスキルと療育のタイプが合っているかは、とても重要なポイントになります。
「福祉サービスの療育が空いたから、とりあえず集団療育に通ってます」という方の中には、
お子さんの状態(その子の療育の目的)と合っていないというケースが少なくありません。
【療育のデメリット 3つの注意点】まとめ

記事のポイントになります。
✅療育の「デメリット」
・家族の精神的な負担
・空き枠が少ない
・手続きの負担が大きい
✅療育の「メリット」
・本人(家族)の過ごしやすさが作れる
・自己肯定感 低下の予防ができる
・子どもとの関わり方を親が学べる
✅療育で大切な「心構え」
・療育の目的は、
本人の過ごしやすさを作ること
・療育≠子どもだけが変わるもの
・療育に正解はない
✅療育を「選ぶポイント」
・本人が楽しめてるか
・家族が信頼できるか
・”子どもの課題” と “療育のタイプ” の相性
✅療育を選ぶ前に
「家庭でできること」~学習面~
・特性に合う学習方法
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【療育で追いついた?】療育で成果が出るポイント、成功・失敗事例を紹介






































[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び方 […]
[…] 【療育のデメリット】3つの注意点・メリット・心構え・療育の選び […]