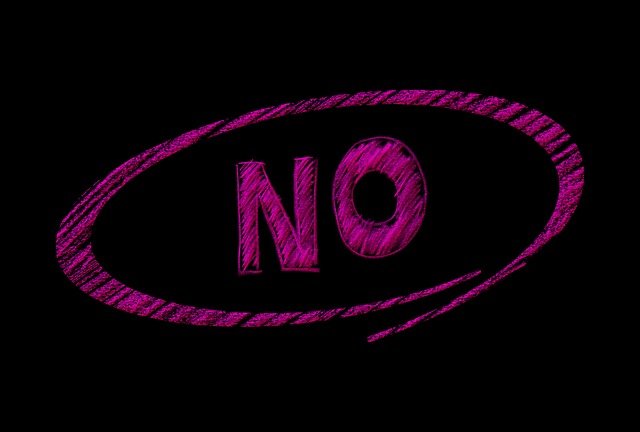

授業参観に行きたくない方「うちの子(発達障害)は、周りに迷惑をかけてるかもしれない。子どもに目立つ言動があり、他の親に引け目がある。授業参観を乗り切る方法が知りたい」
我が子の学校生活が見れるのは楽しみ、という反面、
「授業参観には行きたくない…」と、感じている方も、少なくありません。
この記事の執筆者の私は、育児相談/支援を、15年以上しています。私自身2児の親でもあります。
支援をしていく中で、授業参観を苦痛に感じてる方が、少なくないことを初めて知りました。
そこで、私の支援/育児経験を元に、「授業参観を嫌な思いをしない方法」を中心に、お伝えしたいと思います。
参考になれば幸いです。
目次
発達障害の子の授業参観行きたくない「理由」

授業参観に行きたくない理由は、3つあります。
①::他の親に「引け目」がある
※子どもに問題行動があり
②:「ママ友との付き合い」が苦手
③「一人ぼっち」で居心地が悪い
他の親に引け目がある

「我が子に問題行動があり、周囲に迷惑を掛けるから、参観日などの行事に出たくない」という理由になります。
よくあるお子さんの言動としては、
・離席
・暴言/暴力
・突発的な発言
・周囲へのちょっかい
など様々です。
このような言動が多いお子さんですと「◯◯さんのお母さんは、どう考えてるの?」という感じで、
学校にご意見を言ったり、言わずとも冷たい視線を送ったり、過敏に距離をとろうとする方がいます。
そんな中、授業参観に行ったら、他の保護者に何か陰口を言われるのでは…
と不安があり、参観に行きたくても行けない親御さんもいます。
ママ友との付き合いが苦手

『ママ友同士の付き合い』が、苦手な場合になります。
ママ友によっては、グループがあるので、
グループ内の会話に、合わせたりすることが、疲れてしまう方が多いです(私もこのタイプです…)。
また、お子さんのことを否定したり、干渉してくる方もいるため、表面的なやりとりだけでも、疲れることが多いです。
✅”懇親会” が嫌な場合もある
「懇親会が疲れる」という方も、少なくありません。
特に新年度の最初の保護者会は、これから子どもがお世話になる先生に、挨拶という意味もあって、参加をすることが多いです。
懇親会によっては、一人ずつ順番に自己紹介の時間がある場合があります。
私はこれが苦手で、懇親会にあまり良い思い出がありません…。
一人ぼっちで居心地が悪い

「学校の中で一人ぼっちになりたくない」
「孤立している様子を、子どもに見られたくない」
という心配が、ある場合になります。
ママ友がいない親御さんですと、授業参観に行った時、話し相手が誰もいないため、一人ぼっちの状態に、なりやすいです。
社交性の高い方ですと、近くの人と話ができたりするのですが、これが苦手な方は、辛くなりやすいです。
お子さんの年齢によっては、子どもの目が気になるので、
親が孤立している様子を見られたくないと思われる方も、少なくありません。
授業参観に行かない「2つのメリット」

「授業参観に行かないメリット」を2つお伝えします。
①:他の親と「顔を合わせなくて済む」
②:「傷つかなくて」済む
他の親と顔を合わせなくて済む
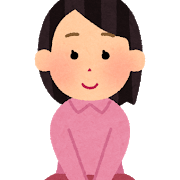
当たり前ですが、参観日に学校に行かなければ、「他の保護者と顔を合わせなくて済む」というメリットがあります。
ママ友同士の付き合いで、面倒なトラブルに巻き込まれることもないため、距離をおけることに、安心される方も多いです。
傷つかなくて済む

学校の中で、一人ぼっちになるのが辛いという親御さんですと、
授業参観に行かないことで、「孤独感を感じずにすむ」というメリットもあります。
授業参観に行かない「3つのデメリット」

「授業参観に行かないデメリット」を3つお伝えします。
①:「学校生活の様子」が見れない
②:子どもが「残念がる」
③:本人の「困り」を見落とす可能性がある
学校生活の様子が見れない

『学校生活の様子が見られない』という、デメリットがあります。
普段、親御さんは、学校生活を見る機会はありません。お子さんからの話を聞いていても、実際に見るのとでは、違います。
そういう意味で授業参観は、学校生活の様子が直接見られる、貴重な機会になります。
・我が子が学校を楽しめているのか
・授業についていけているか
・クラスメイトと上手く関われているか
など、様々な心配事や疑問を解消する為にも、参加しておくことは、安心になります。
子どもが残念がる

多くの子にとって授業参観は、お母さんやお父さんが見に来てくれる、楽しみな日です。
周りの子の親が来ている中、自分の親がいないとなると、残念な気持ちになります。
授業参観が、寂しかった思い出になる可能性があります。親としては、避けたい所ではあります。
本人の困りを見落とす可能性がある

学校生活には、担任の先生・本人も気付いていない、困りがある場合があります。
先生の場合は、30~40名の集団を見ているので、お子さんの細かい部分までは、把握が難しいです。
よくある例は、
・困ったときに助けを求められない
・授業態度は良いけど内容が理解できてない
など、周囲のフォローが入るのが、遅れてしまうことがあります。
お子さん自身は困りと感じていなかったり、言葉で親御さんに説明することが難しい場合もあるため、
周囲が気づくことが、遅れる場合があります。
【関連記事】
授業参観で嫌な思いをしない「3つの方法」

「授業参観で嫌な思いをしない方法」を3つお伝えします。
①:授業参観が「始まってから」教室に入る
②:授業参観が「終わる前に」教室を出る
③:「家族・親族」に協力してもらう
授業参観が始まってから教室に入る

『授業参観が始まってから』教室へ入ります。
話をしているママはいないので、気まずい思いをしなくて済みます。
シンプルですが、効果は抜群になります。
授業参観が終わる前に教室を出る

授業が終わる前に、教室を出ます。
また、学校によってはアンケート(感想)があるので、記入する時間を計算して、教室を出ましょう。
個人的には、『教室に入る前に、アンケートを持っておき、参観中に書いておく』ことが、お勧めになります。
✅①②について子どもに「事前に伝えておく」
お子さんに、『途中から教室に入ること・出ること』を伝えておきます。
お子さんによっては、授業開始時に親御さんがいないと、途中で親御さんが入ってきても、そのまま気づかない場合もあります。
それですと、お子さんが寂しい思いをするので、事前に伝えて置けると安心です。
家族/親族の協力を得る

どうしても一人が辛いという方は、奥の手として、
旦那さんやお母さん(おばあちゃん)、親族と一緒に行く方法があります。
心許せる人と話ができれば、時間はあっという間に過ぎますので…。
私が今まで参加した授業参観ですと、クラスに1,2組ぐらい見かけます。
数は少ないですが、一人の孤独感の方が辛いという方には、良い方法だと思います。
もし、頼れる方がいない場合は、
・スマホをいじる
・学校からの手紙を読む
・廊下や壁に貼ってある作品を眺める
などの方法があります。
(私はよく、1つずつ作品をじっくり見てます)
【関連記事】
【授業参観の感想の例文】たった1つ!書き方のコツとは?注意点もあり
【発達障害の子の授業参観に行きたくない時】まとめ

記事のポイントになります。
✅授業参観に行きたくない
「3つの理由」
・親同士の人付き合いが苦手
・一人ぼっちで居心地が悪い
・他の親に引け目がある
✅授業参観に行かない
「2つのメリット」
・他の親と顔を合わせなくて済む
・傷つかなくて済む
✅授業参観に行かない
「3つのデメリット」
・学校生活の様子が見れない
・子どもが残念がる
・本人の困りを見落とす可能性がある
✅授業参観で嫌な思いをしない
「3つの方法」
・授業参観が始まってから教室に入る
・授業参観が終わる前に教室を出る
・家族・親族の協力を得る
✅授業参観で
「子どもの学習面が気になった時」
・学習の苦手意識をつけない
・小さい成功体験を作る
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考になれば、幸いです。
【合わせて読みたい記事】









































[…] 【授業参観に行きたくない】参観で嫌な思いをしない!3つの方法 […]
[…] 【授業参観に行きたくない】参観で嫌な思いをしない!3つの方法をご覧ください。 […]