

子どもの接し方で悩まれている方「子どもがくるくる回るのは自閉症だから?いつからやるもの?止めた方がいいのか、対応方法が知りたい」
よく自閉症(スペクトラム)の子に見られることが多い「くるくる回る」。
お子さんがしていたら、「自閉症なの?」と心配になったり、他の子と同じように遊ばない様子も、気になる方も少なくないと思います。
この記事の執筆者の私は、療育指導を15年以上しています。
その経験を元に本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
※現在、自閉症は「自閉スペクトラム症(ASD)」と総称されています。本記事では、説明の都合上「自閉症」と表現してます
目次
自閉症の子の「くるくる回る行動」とは

自閉症の子の「くるくる回る」は、常同行動ともいいます。
常同行動とは『一見意味のない同じ動きを繰り返している』ことをいいます。
例えば、
・ぐるぐる回る
・手をヒラヒラさせる
・物を振り続ける
などになります。どんな行動で出るかは、お子さんによって様々です。
『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版 テキスト改訂版)にも、常同行動の診断の条件が明記されています。
要点だけまとめると、こちらのイメージになります。
①:3才以下で表れる
②:社会生活で支障出るor自傷がある
③:医学的に説明できない
※薬の副作用や病気の症状など
常同行動自体は、問題ではないのですが、これが社会生活に支障が出る場合は、介入が必要です。
詳しくは、後述しますね。
自閉症の子のくるくる回る行動の「3つの原因」

自閉症の子のくるくる回る行動の「3つの原因」をお伝えします。
①:不安/緊張がある
②:満たされない感覚がある
③:不快感がある
不安/緊張がある

自閉スペクトラム症の子は、感覚の偏り(過敏)があります。多くの人が気にならない音や人の気配など、強いストレスを感じやすいです。
そういったストレスから、自分を守る/安心感を得るため(回避するため)に、くるくる回るなどの行動をとる場合があります。
満たされない感覚がある

こちらも感覚の偏り(鈍さ)のため、満たれない感覚を満たすために、行動する(感覚探求)ことです。
自閉スペクトラム症の子は、「こんなに回って目がまわらないの?」と思うぐらい、頻繁にくるくる回っている子がいます。
これも感覚の鈍さから、人より感覚を欲する特性があるのです。感覚遊びは、お子さんの遊びの中でも、一番土台となる遊びです。
全体的な発達傾向がゆっくりな子は、3才を過ぎても、この感覚遊びを好む傾向にあります。
不快感がある

何か不快感を感じているときに、出ることがあります。
例えば、治りかけのかさぶたの痒い、室温が合わない(暑い/寒い)、肌着の素材が合わず気になるなどです。
✅くるくる回る行動が多い子の特徴
3才以下の知的、発達障害の子が多いです。知的、発達障害の5~15%前後の子に確認されることが多いです。
定型発達の子にも、「くるくる回る」などの常同行動は、ありますが、全体の4%前後で自然に消えていきます。
【合わせて読みたい記事】
くるくる回る行動の「3つの問題」

くるくる回る行動は、お子さんにとって必要な行動です。基本的には止めずに、尊重することが望ましいです。
ただし、表現の仕方/場面/その子自身、周囲への影響によっては、介入する必要があります。
くるくる回る行動(常同行動)が問題になる時は、大きく3つあります。
①:自分や周囲の人を傷つける
②:子供自身の社会生活に支障が出る
③:周囲の社会生活に支障が出る
自分や周囲の人を傷つける

自他を傷つける危険行動がある場合は、最優先で介入が必要になります。
くるくる回る行動では、人や壁にぶつかる、外では車や自転車にぶつかりそうになる様子があれば、介入すべきです。
個人的には、すぐ専門機関へ相談することをお勧めします。
子供自身の社会生活に支障が出る

園や学校などの集団生活に参加できない、支障がある場合です。
離席するorその場にいるけど話を聞いていなく授業についていけないなどになります。
周囲の社会生活に支障が出る

家族や担任、周囲のクラスメイトなど周囲の人が困ってしまう場合です。
自閉スペクトラム症の子は、興味の幅の狭さ/感覚の偏りから、「困る」ということを感じにくい場合があります。
ただ本人が困っていなくても、周りが困っていることも少なくありません。必ず周囲の人の声にも耳を傾けることが大切になります。
【合わせて読みたい記事】
くるくる回る行動への「3つの関わり方」

くるくる回る行動への「3つの関わり方」をお伝えします。
①:やることを与える(指示)
②:無害な行動へ促す(代替)
③:場所を限定する(条件)
やることを与える(指示)
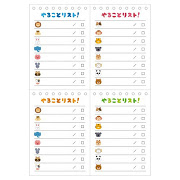
やることがなく、くるくる回っている場合があります。そういうときは、やることを与えましょう。
「このパズルやってみようか」とお子さんの好きなものを通して伝えましょう。
『違う過ごし方をしている方が楽しい(くるくる回るより)』ということを、実感してもらえる関わりが、大切になります。
無害な行動へ促す(代替)

問題が出ている場合に、なるべく影響が少ない行動に変えることです。
例えば、くるくる回って、周りの子にぶつかりそうになる場合は、万華鏡を使って、その場で楽しめる形に変えることです。
硬い物を繰り返し投げる子は、柔らかいボールを投げてもらう、机を叩く子は音の出るオモチャを叩いてもらう、など工夫ができます。
物/場所を限定する(条件)

くるくる回っても問題ない場所に限定することです。外出時は、事故など危険があるため、家だけに限定するなどです。
事前に家だけでするよう、約束をすることが大切です。そして、外で我慢できた分、家では自由にしてもらいましょう(危険がない限り)。
お子さんによっては、物を限定する方法もあります。
例えば、口に入れて噛み続けるなどです。そういった場合は、噛み続けても問題がない、柔らかい物だけで限定するなどと調整をしましょう。
具体的なオモチャを知りたい方は、自閉スペクトラム症の子供にオススメなおもちゃ【26選】をご覧ください。
✅くるくる回る行動の治療法
行動療法と薬物療法があります。
行動療法は、主に療育になります。
スキルを身に着け対処したり、周りの人が関わり方を工夫し、お互いの歩み寄りをすることです。
具体的には、さきほどの「くるくる回る行動の対応方法」で解説した内容になります。これを専門家に指導してもらえるのが療育といわれるものです。
薬物療法は、医療になりますので、小児科や精神科などの医療機関に相談されるのが、良いです。
【自閉症のくるくる回る、いつから?】まとめ

記事のポイントになります。
✅自閉症の子の
「くるくる回る行動」とは
・一見意味のない動きを繰り返す行動
・常同行動という
✅くるくる回る行動の
「3つの原因」
・不安/緊張がある
・満たされない感覚がある
・不快/不満がある
✅くるくる回る行動の
「3つの問題」
・自他を傷つけるとき
・自他の生活に支障がでるとき
✅くるくる回る行動への
「3つの関わり方」
・やることを与える
・無害な行動へ促す
・物/場所を限定する
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
【関連記事】








































[…] くるくる回る原因とは【自閉症スペクトラムの子供の対応方法】 […]
[…] くるくる回る原因とは【自閉症スペクトラムの子供の対応方法】 […]
[…] くるくる回る原因とは【自閉症スペクトラムの子供の対応方法】 […]