

子どもの不登校で悩まれてる方「子ども(中学生)が復帰を怖がってる。どうすれば怖がらずに登校できるの?再登校する為の方法が知りたい」
現在、不登校のお子さんは増えています。
不登校問題の1つとして、よくあるのが「本人が復帰を怖がる」です。
ご家族からしたら、
「何がそこまで怖いんだろう..」
「背中を押すべきか、無理させない方がいいのか、分からない..」
と疑問や悩みを持たれることも、多いと思います。
そこで本記事では「不登校の復帰/再登校」に関する情報をまとめました。
この記事を執筆してる私は、不登校・療育支援を15年以上しています。
私が実際に携わってきた事例を通して、本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
不登校の中学生「復帰が怖い理由」

不登校の中学生の「復帰が怖い理由」は、3つあります。
不登校の状態から、復帰することは、心理的に怖いものです。
緊張感や不安感があるのは、自然なことです。そこを前提に、3点触れていきたいと思います。
①:本人の「特性」
②:「学校内に明確な原因」がある
(ex.担任、特定のクラスメイト)
③:学校での「失敗体験」が多い
本人の特性

本人の特性(生まれつきの気質に近い)になります。
あくまで一例ですが、私が支援する中で、多かったのは、以下になります。
1️⃣周囲の状況に敏感(HSP気質)
2️⃣感覚過敏
3️⃣不安の強さ
4️⃣学習の困難さ(LD傾向)
5️⃣ADHD、自閉スペクトラム症
もちろん、これ以外にもありますし、複数重なっているお子さんもいます。
今回は、明確な診断が付きづらく、不登校に多い、①~③に触れていきたいと思います。
周囲の状況に敏感
周りの言葉や出来事をダイレクトに受けやすく、本人が過度な不安や緊張をしたり、疲れやすくなります。
例えば、先生がクラス全体や特定の子を叱っているにも関わらず、自分が叱られてる様に感じてしまい、辛くなってしまうなどです。
他にも、周りの子に気を遣いすぎて、疲れてしまうこともあります。
感覚過敏
ザワザワした音(聴覚)や給食の匂い(嗅覚)など、過敏さが理由で、過ごしづらさに繋がっています。
感覚の問題ですので、不快な刺激をなるべく避けたり、グッズを使って軽減する工夫が必要になります。
不安の強さ
漠然とした不安の強さから、学校が怖くなる場合になります。
「周りの子が、自分の悪口を言ってる」
「クラスメイトが睨んでくる」
「どう思われてるか不安でしょうがない」
など、本人が不安に駆られ、思い込んでる場合があります。
学校内に明確な原因がある

復帰が怖くなる理由が、学校内にある場合になります。
例えば、以下のような理由があります。
・担任の理解がない
・陰湿なクラスメイト
・学校側の配慮がない
(個別対応を認めない)
このような環境ですと、お子さんのコンディションが整っていても、環境的な問題で難しいことが多いです。
学校での失敗体験が多い

失敗体験を積み重ねすぎて、学校という場所に対してネガティブな印象しかない場合になります。
お子さんによっては、トラウマに近い場合もあります。
中には、嫌だった経験がフラッシュバックして、苦しむ子もいます。
復帰する為の「4つの方法」

不登校の中学生が、復帰する為の「方法」は、4つあります。
①:本人の「意思」
②:「学校の通い方」のすり合わせ
③:辛くなった時の「逃げ道」を決めておく
④:「休んでも良い」ことを伝えておく
本人の意思

一番大切なのは、本人の意思になります。本人の意思がなければ、難しいです。
本人の意思とは、本人が感じる「納得感/必要性」になります。
・登校する理由
・学校で過ごすことの意味
(自分にとって)
この2点を本人がどこまで感じられるか、が大事になってきます。
家族との話で、ここを確認することが大事ですが、
「話ができる状態じゃない、本人の拒絶が強い」などの場合は、本人の休養が必要な可能性が高いです。
該当する方は、こちらの記事をご覧下さい。
学校の通い方のすり合わせ

本人と一緒に「通い方/ペース」を、
具体的に決めていきます。
通い方の例
よくある通い方の例になります。
・保健室登校
・放課後に課題だけ取りに行く
・好きな授業だけ参加
・オンラインで参加
本人、家庭、学校の状況に合わせて、選ぶことが大切になります。
ペースの例
よくあるペースは、以下になります。
・週◯日登校
・好きな授業だけ参加
・給食~参加
・本人が疲れたら、1日休む
(翌日~登校)
学校や担任の理解も必要なため、連携が必要になります。
【合わせて読みたい記事】
辛くなった時の逃げ道を決めておく
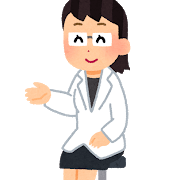
本人が「どうしても辛い」状態になった時の、逃げ道(登校以外の方法)を決めておきます。
「本人ができる」「学校の許可を得てる」、この2点を押さえる必要があります。
例えば、以下のような方法があります。
・特定の授業だけ参加
・オンラインで参加
・保健室登校
(ex.空いてる会議室、校長室なども)
本人に選んでもらい、その日の過ごし方を決めてもらいます。
選択肢自体は、事前に本人と決めておけると、当日スムーズになります。
【関連記事】
【別室登校の過ごし方】メリット/デメリット/教室へ復帰する5つのポイント
✅『共通認識が持てる目安』を決めておく(学校を休む基準)
不登校の子は、前日の夜まで学校に行くと言っていても、
当日の朝に「やっぱり今日は休む」と言うことがよくあります。
本人は、学校に行くのが本当に辛いのですが、
家族としては「昨日は行くって言ってたじゃん..」と思われることもあると思います。
そこで、本人のコンディションを、数値やマークで表現し、学校を休む基準に結びつけておきます。
例えば、以下の様な基準(表現)があります。
・10段階中、2以下なら休み
(数字が大きくなる程、調子が良い)
・◯、△、☓で、☓なら休み
共通認識が持てる具体的な表現ですと、自他共にコンディションが把握しやすくなります。
【関連記事】
【不登校中学生の一日のスケジュール】時間管理の4つのポイント
休んでも良いことを伝えておく

「学校に登校しないといけない」
「学校を休むのはダメ」
周囲がこのような認識を持つと、本人は無理をしたり、過度なプレッシャーを感じ、コンディションが悪くなってきます。
それよりも、
『辛かったら休んでも良い』
『登校は選択肢の中の1つ』
と周りが言葉や態度で示し続けることで、本人も「行けたら行く」という気持ちにゆとりができる為、
結果として安定に繋がりやすくなります(少なくとも悪化は避けられる)。
復帰する時の「3つの注意点」

不登校の中学生が、復帰する時の「注意点」は、3つあります。
①:「復帰できた=不登校解決」ではない
②:周りが「過剰反応」しない
③:本人が辛い時は「すぐ休ませる」
復帰できた=不登校解決 ではない

「1回登校(復帰)できた」
「1週間休まず登校できた」
これらは、不登校が解決したことにはなりません。
不登校問題の解決は、不安の原因に対して、本人や周りが対処できる状態、折り合いがついてる状態を指します。
私が知る限りでは、不登校問題が完全に解決したケースは、多くはありません。
学校に通い続けられていても、それは、本人の一時的な頑張り(無理をした)だったり、担任やクラスメイトの協力があったりと、長期的に保証があるものではない為です。
担任次第で、不登校に戻るケースも多いです。
不登校に関して、完全解決というよりも、
“本人と学校の環境が折り合いがつく様に、サポートし続ける” 視点が重要になります。
周りが過剰反応しない
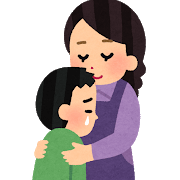
本人の1つ1つの言動/変化に、過剰に反応しないことになります。
ご家族としては、本人のポジティブな言動/発言は嬉しいものです。
ただそれは、不登校に関しては、一時的である場合が多いです。
例えば、これらの様な言動になります。
・「学校に行く」と発言した
・前日に学校の用意をした
・数日登校できた
不登校の子は、気持ちの振り幅が大きいため、一挙一動に反応するのは、本人やご家族にとって、良いことだとは言えません。
特に、周囲の大人の過剰反応は、本人にプレッシャーを与え、無理をさせたり、
周囲の期待に応えられないことで、本人の自己肯定感の低下に繋がります。
本人が辛い時はすぐ休ませる
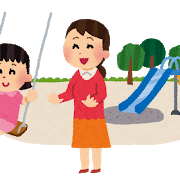
本人が辛いことを教えてくれたり、様子として明らかに辛そうな場合は「すぐ休む」が大事になります。
無理をすれば、必ず反動がきます。反動の出方(ex.イライラ、疲労感、欠席)は一人ひとり違いますが、少なくともポジティブに作用することはありません。
本人が無理をしてる自覚がない場合は、先ほど触れた「学校を休む基準」を決めておく対策が、効果的になります。
それでも復帰が難しい時の「3つの原因」

不登校の中学生が、復帰できない「原因」は、3つあります。
ご家族が、認識しておきたい点になります。
①:「休息」が足りてない
②:「本人の特性」と「学校の環境」の
ミスマッチ
③:「学校の通い方」が本人に合ってない
休息が足りてない
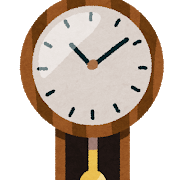
休息が足りてなくて復帰が難しいパターンになります。
周囲が登校する様に何度も促してることも、原因の1つになります。
本人に好きなことをして過ごしてもらい、十分な休息をとってもらいます。
休息が足りなかった理由で多いのが、こちらの2つになります
・本人が頑張りすぎてる
(気持ちに体が追いついてない)
・周りが登校の促しをしてる
(本人に無理をさせてる)
お子さんの “休息の必要性の目安” は、こちらの記事を参考にご覧ください。
【関連記事】
【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン/関わり方/注意点
本人の特性と学校の環境がミスマッチ

本人の特性と学校の環境が合っていない場合になります。
例えば、周囲の状況に引っ張られやすい特性(HSP気質)がある子と、大きい声で叱る担任の組み合わせです。
担任の先生がクラス全体に大声で叱る機会が、本人は辛くなってしまいます。
先生はスタンスを変えるつもりはなく、本人の特性も変わるものではない為、問題解決の進展が見られないケースになります。
学校の通い方が本人に合ってない

本人の状態と学校の通い方が合ってない場合になります。
例えば、完全登校できる状態でない子に対して、他の子と同じ様に登校させてる場合になります。
お子さんに合わせて、細かくステップを分けられると、上手くいきやすいです。
・ペースを減らす
・授業を受ける時間数を調節する
・過ごす場所を教室以外にする
お子さんに合わせた「通い方(ハードルの下げ方)」を見つけることが大切になります。
【復帰が怖い 不登校の中学生の再登校】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の中学生
「復帰が怖い理由」
・本人の特性
・学校での失敗体験が多い
・学校内に明確な原因がある
(ex.担任、特定のクラスメイト)
✅復帰する為の
「4つの方法」
・本人の意思
・学校の通い方のすり合わせ
・辛くなった時の逃げ道を決めておく
・休んでも良いことを伝えておく
✅復帰する時の
「3つの注意点」
・復帰できた=不登校解決ではない
・周りが過剰反応しない
・本人が辛い時はすぐ休ませる
✅それでも復帰が難しい時の
「3つの原因」
・休息が足りてない
・本人の特性と学校の環境がミスマッチ
・学校の通い方が本人に合ってない
✅不登校の中学生が
「備えたいこと」
・学習の成功体験
・学習習慣の定着
・特性に合う学習方法
・レベルに合った問題の選択
・タブレット学習
以上になります。
本記事が参考なれば幸いです。
【関連記事】







































[…] 【復帰が怖い】不登校の中学生が再登校する時の4つのポイント […]
[…] 【復帰が怖い】不登校の中学生が再登校する時の4つのポイント […]
[…] 【復帰が怖い】不登校の中学生が再登校する時の4つのポイント […]
[…] 【復帰が怖い】不登校の中学生が再登校する時の4つのポイント […]
[…] 【復帰が怖い】不登校の中学生が再登校する時の4つのポイント […]