

子どもの不登校で悩まれてる方「うちの子、不登校でずっと寝てる。親として、どうしてあげたらいい?対応の仕方を教えてほしい」
お子さんの不登校で悩まれてる方は、今増えています。
その中でも「家で寝てるだけ」という、過ごし方で困っている方も多いです。
家での過ごし方は、親としても「何かできることはないかな…」と悩みのポイントになるかと思います。
この記事を執筆している私は、療育・相談支援を15年以上しています。不登校のお子さんの支援も多くしてきました。
その支援経験を元に本記事をまとめてます。参考になれば幸いです。
目次
不登校の子「ずっと寝てる原因」

不登校の子「ずっと寝てる原因」は、大きく3つあります。
①:「起きたくない」気持ち
②:「生活リズム」の乱れ
③:心身の「病気」
起きたくない気持ち

お子さん本人が、“何かしら” が嫌で「起きたくない」と思っている場合になります。
何が嫌かは、お子さんそれぞれですが、よくあるのは…
・担任の先生が嫌い
・苦手な友達がいる
・とにかく学校が嫌
・学校の授業が分からない
などが、あります。
お子さんによっては、何が嫌か分からなかったり、言葉にすることが難しいこともあります。
生活リズムの乱れ
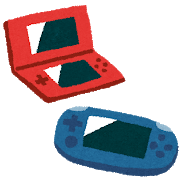
何かしらの原因で「生活リズム」が乱れている場合になります。
生活リズムが乱れると、睡眠不足/昼夜逆転に繋がる可能性があります。
生活リズムが乱れる、よくある原因は、以下になります。
・夜更かし
・強い緊張/不安
(眠れない/寝付きが悪い)
本人として頑張ってても、生活リズムが乱れてしまう場合もあります。
心身の病気

日常生活に大きな支障がある場合は、”心身の病気” の可能性があります。
私はお医者さんではないので、医療的な専門知識はありませんが、
親御さんが少しでも、病気の可能性を感じる場合は、
心療内科/児童精神科に相談されるのも、1つだと思います。
かかりつけのクリニックがありましたら、まず担当の先生に相談されるのが良いと思います。
もしお子さんが思春期で足を運ぶのを嫌がる場合は、親御さんだけでも相談できないか、事前に電話で相談してみましょう。
【合わせて読みたい記事】
昼夜逆転を治す為に「できること」~本人~

昼夜逆転を治す為に「本人ができること」は、3つあります。
お子さん・ご家庭の状況によって様々ですので、
できそうなイメージが湧くものがあれば、参考にご覧ください。
①:「決まった時間」に起きる
②:起きる「動機」を作る
③:「日中」に活動する
決まった時間に起きる

凄くシンプルですが、一番効果的な方法になります。
昼夜逆転の子に対して、支援の現場でもよく使われる方法になります。
私たち大人も、連休があると生活リズムが乱れ、寝すぎて寝付きが悪くなったり、朝起きづらいことがあると思います。
ただ、いざ仕事が始まると、最初は朝が眠くても、次第に生活リズムが戻ります。
これは「朝の決まった時間に起きてる」からです。
昼夜逆転の子も基本的には、これと同じ考え方になります。
起きる動機を作る

「決まった時間に起きる」という方法が分かっても、お子さんにその気がなければ、難しいですよね。
お子さん本人の “朝起きる動機(メリット)” を作ることが、必要になります。
例えば、朝の時間・日中時間だけ、いつもより “好きなことができる時間を増やす” などです。
本人が好きなことを、既に自由にできている状況だと難しいですが、
そうでなければ、
「夜は、好きなことできる時間が少ないけど、朝/日中なら長い時間できる」
という形なら、朝起きるメリットができます。
このように、本人の朝起きるメリットが作れると、最初のステップはバッチリです。
【合わせて読みたい記事】
【不登校】子どもに暇と言われたら?「将来役に立つ」4つのやれると良いこと
日中に活動する

朝起きるリズムができてきたら、日中の活動をしていきます。
当たり前ですが、社会生活は日中の活動が中心になります。
社会生活を想定して、日中に活動できる時間/活動の種類(過ごし方)を作ることが大切になります。
お子さんによって、日中の活動は様々です。
ここでは、私が実際に支援していた子の例を紹介します。
お子さんが拒否しない範囲のもので、本人が選べることが大切になります。
・散歩
・読書
・買い物
・家の手伝い
(掃除/洗濯など)
・学習
(プリント/タブレット学習など)
・習い事
(オンライン可/本人の好きなこと)
具体的な不登校の子向けの習い事は、こちらの記事をご覧ください。
1つの選択肢として、参考になれば幸いです。
昼夜逆転を治す為に「できること」~親~

昼夜逆転を治す為に「親ができること」は、3つあります。
お子さん/ご家庭の状況によって様々になりますので、
イメージの湧くものがあれば、参考にご覧ください。
①:話を聞き「共感」する
②:本人の意思が出るまで「見守る」
③:「環境作り・サポート」をする
話を聞き共感する
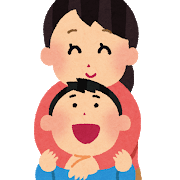
お子さんの話を、最後まで聞いて共感することです。
具体的には、2つの関わり方になります。
①:同じ言葉で、そのまま返す
(オウム返し)
②:お子さんの気持ちを代弁する
同じ言葉でそのまま返す
お子さんが「宿題めんどくさい!」と言ったら、
『宿題めんどくさいよね』と、同じ言葉で返すイメージになります。
「共感が苦手…」という方に、おすすめの方法になります。
お子さんの気持ちを代弁する
“お子さんの気持ち” を、親御さんが言葉にして伝える方法になります。
「宿題めんどくさい!」でしたら、
『宿題多いから、全部やるの大変だよね』と、お子さんの立場に立ち、気持ちに寄り添うイメージになります。
こちらの方が難易度は高めですが、
オウム返しの共感よりも「気持ちを受け止めてもらえた」と、お子さん自身が実感しやすくなります。
本人の意思が出るまで見守る
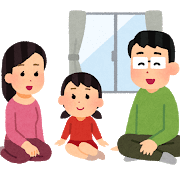
恐らくここが、親として一番むずかしい部分だと思います。
本人の意思が出るまで “見守る”、これがとても大切になります。
「そんなことしてたら、いつまでも外に出れないままだよ…」という方も、いると思います。
ここについては、【不登校】元気なのに学校に行かない?3つの理由と接し方 で詳しく解説しています。
⚠「プレッシャー・叱責」は、不登校問題を長期化させる
親御さんや先生など、周囲の大人からの関わり方次第で、不登校が長くなることもあります。
我が子の将来が不安になる親の気持ちは、とても分かります…ただ不登校の子には、「見守る」が必要になります。
環境作り/サポートをする

不登校は、本人の意思が出るまでの期間(充電期間)に、環境を作っておくことが、大切になります。
意思が出たとき(興味・関心)に、すぐ行動に移せるよう準備しておきます。
例えば、こちらの様な環境作り/サポートがあります。
・興味を持った学校/場所につれていく
・新しいことに挑戦できる機会を作る
・ネットで一緒に調べる
・資料を取り寄せる
・興味あるものを購入し、家でやってみる
お子さんの希望に合わせて、選んでいけると良いです。
【合わせて読みたい記事】
【不登校の子ども】何が正解なの?望ましい声かけ/避けたい声かけ
昼夜逆転を治すときの「注意点」
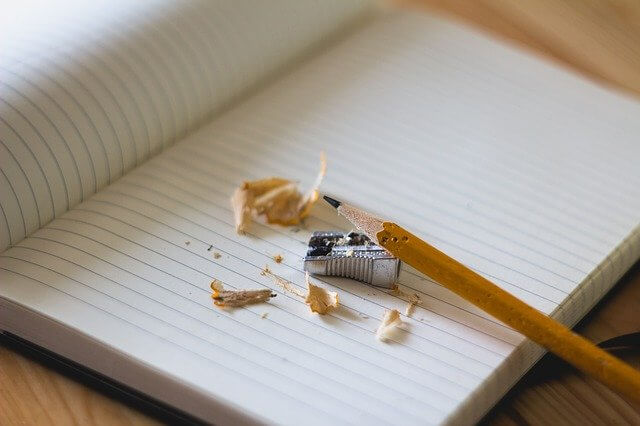
昼夜逆転を治すときの「注意点」は、3つあります。
①:「強制」しない
②:本人を「責めない」
③:「プレッシャー」を与えない
強制しない

本人の意思を無視して、強制するのは避けたい点になります。
その場で出来たとしても、本人の中では
「やりたくなかったのに。もうやらない!」とネガティブな経験になってしまいます。
学校に登校したり、違う環境に進むときに、本人の意欲が低下していきます。
長期的に見て、逆効果になってしまいます。
本人を責めない

不登校であること・ずっと寝ていることを、責めないことです。
この「責めない」というのは、言葉だけでなく、声のトーンなども含まれます。
例えば、「○○やった?」というのも、”何気ない質問” の時もあれば、”疑うように確認する” トーンもあります。
本人が『責められてる』と、感じる可能性がある関わりは、避けた方が良いです。
責められてると思うと「やっぱり自分だダメなんだ。何をやっても上手くいかない」と、
自分の殻に、閉じこもるようになります。
プレッシャーを与えない

先ほどの「責めない」に似ていますが、誰でも無意識にやりがちな関わりになります。
「明日は学校行けそう?」
「今日学校の先生と電話で話したよ」
「明日は学校で○○やるんだって」
親御さんとしては、ただ伝えているつもりでも、
お子さん本人からしたら、プレッシャーになっていることが多いです。
「じゃあどう声掛けしていいか分からないよ…」という方は、
【不登校の子ども】何が正解なの?望ましい声かけ/避けたい声かけ をご覧ください。
朝、夕方、夜など場面に分けて使える、具体的な声かけをまとめてます。
【不登校ですっと寝てる子】まとめ

記事のポイントになります。
✅不登校の子
「ずっと寝てる原因」
・起きたくない気持ち
・生活リズムの乱れ
・心身の病気
✅昼夜逆転を治す為に
「できること」 ~本人~
・決まった時間に起きる
・起きる動機を作る
・日中に活動する
✅昼夜逆転を治す為に
「できること」 ~親~
・話を聞き共感する
・本人の意思が出るまで見守る
・環境作り/サポートをする
✅昼夜逆転を治す時の
「注意点」
・強制しない
・本人を責めない
・プレッシャーを与えない
✅不登校の子に
「今後必要な備え」
・学習習慣の定着
・学習の成功体験
・学習意欲の向上
・特性に合う学習法
・レベルに合う学習単元
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、参考になれば幸いです。
【関連記事】
【不登校の子は勉強追いつくの?】学習支援でも実践してる6つの勉強法








































[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因・対処法を解説。3つの注意点あり […]
[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因・対処法を解説。3つの注意点あり […]
[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因・対処法を解説。3つの注意点あり […]
[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因・対処法を解説。3つの注意点あり […]
[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因・対処法 […]
[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因・対処法 […]
[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因・対処・注意点 […]
[…] 【不登校ですっと寝てる子】3つの原因/対処法タブレット学習は、自宅でできる学習ツールです。 […]