

子どもの学級で悩まれてる方「支援学級はどんな子が通うの?支援学級に通わせた方がいいのか迷ってる。支援級のメリット/デメリットが知りたい」
このようなお悩みに、お応えします。
発達障害やグレーゾーンと言われる子の学級選びは、多くの親御さんにとって、判断が難しい問題になります。
学級の1つの選択肢として「支援学級」を検討される方も多いです。
ただ「支援学級はどんな子が通ってるの?うちの子に合うのかな..」と疑問に感じる方も多く、情報収集にも限界があるのが現状になります。
そこで本記事では「支援学級に通う子の特徴/支援学級のメリット/デメリット」をお伝えしたいと思います。
私は、発達支援の相談/支援員を15年以上しており、これまで学級選びのご相談も受けてきました。
この支援経験を元に、私が現場で感じてきたことをお伝えします。
参考になれば幸いです。
目次
支援学級に通う子の「2つの特徴」

支援学級に通う子の「2つの特徴」になります。
もちろん他にも特徴はありますが、支援の場で特に多いと感じる特徴を中心にお伝えます。
①:「授業に支障を出す行動」が出る子
②:授業に「全くついていけてない」子
授業に支障を出す行動が出る子

授業を止めてしまったり、他の子に影響を出してしまう行動をする子です。
具体的な行動は、
・離席する
・他害、暴言
・飛び出し
・他児へのちょっかい
・大声を出す
などになります。授業の進行、クラスの子の学校生活に大きな影響を与える行動になります。
学校としても、最優先で対応したいお子さんの行動になります。
授業に全くついていけない子
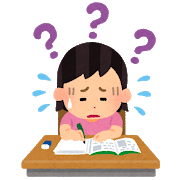
授業には参加していて、授業を妨害することはないので、一見問題なさそうに見えます。
ただ、本人としては、授業の内容理解が難しく、お子さんによっては「ただ座って空間にいるだけ」に近い場合もあります。
お子さんによっては、平気で過ごしていて困ってない場合もあれば、学習や授業が嫌になって、拒否感が出てくる場合もあります。
【関連記事】
【小学校で支援学級を勧められた時】学級選びの3つのポイント/事例紹介
支援学級に通う「3つのメリット」

支援学級に通う「メリット」は、3つあります。
①:「本人の特性に合った」指導、環境
②:「居場所(安心/自己肯定感)」になる
③:普通学級の子と「交流」できる
本人の特性に合った指導、環境
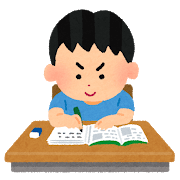
当たり前のお話ですが、普通学級よりも “特性に配慮された指導” が受けやすいです。
“特性に配慮された指導” の例としては、
・指示に視覚情報を取り入れる
・少人数で刺激が少ない環境
・個々に合った課題の難易度
など、普通学級では配慮が得にくいサポートが受けやすいです。
居場所(安心/自己肯定感)になる

本人の安心感・自己肯定感を作りやすいです。
合わない環境で過ごすということは、本人からしたら不安ですし、失敗体験を重ねることで自己肯定感が下がるリスクがあります。
逆に本人が過ごしやすい環境(支援学級)ですと、安心し、成功体験を積める為、自己肯定感を高めることにも繋がります。
普通学級の子と交流できる

学校によっては、普通学級の子と交流できる(交流級)機会があります。
例えば、給食や体育の時間は、一緒に授業を受けるなどです。
お子さんによって、交流級で受ける授業が変わる場合もあります。
支援学級に通う「5つのデメリット」

支援学級に通う「デメリット」は、5つあります。
厳密にいうと、本人や学校、学級の状況次第で、デメリットになり得る可能性があるものになります。
お子さん本人、学校、地域によって、変わりますので、参考程度にご覧ください。
学級を選ぶ段階で、こちらのデメリット(可能性)を認識することが大切になります。
①:本人が「ネガティブに捉える」
②:学級の状況が「本人に合わない」
③:先生に「専門スキルがない」
④:在籍校に「支援学級がない」
⑤:「受験の選択肢」が減る
本人がネガティブに捉える

「皆と違うクラスにいく」
「自分だけ違う教室で授業を受ける」
これらの事実をネガテイブに捉えることがあります。
普通学級⇨支援学級に移る場合は、特にネガティブな反応が増えやすいです。
実際に「みんなと離れたくない」「自分はバカじゃない」と言う子も少なくありません。
学級の状況が本人に合わない
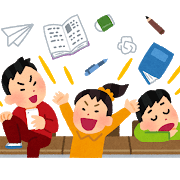
支援学級のはずが、中身は特別支援教育から離れた内容になっている場合です。
よくあるのは、学習が簡単すぎて、本人には合ってない(プリントを渡されて終わり)、落ち着かない子がいて、学級自体が騒がしいなどです。
学級の状況によっては、個々に合わせた指導を受けることが難しい場合があります。
【関連記事】
【現場でよくある事例】支援級(情緒級)を選んで後悔する3つのパターン
先生に専門スキルがない

「支援学級の先生」いっても、先生に専門的な知識やスキルがあるとは限りません。
中には、発達障害や特性への理解がなく、叱責や指摘を中心とした指導をする先生もいます(以前よりは減りましたが)。
支援学級に入ったのに、担任の誤った認識/指導で、辛い思いをしてるお子さんや親御さんは、少なくありません。
【合わせて読みたい記事】
在籍校に支援学級がない
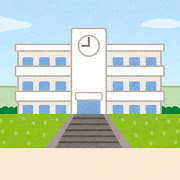
学校によっては、支援学級自体がない場合があります。
その場合は、近隣の学校まで通う必要があります。
法の改正もあり、以前と比べ支援学級や通級が設置されてる学校は増えましたが、まだまだ環境が整っていない学校が存在しているのが、現状です。
受験の選択肢が減る
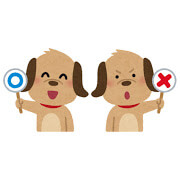
支援学級に在籍するということは、内申点がつかないことが多いです。
つまり、内申点が影響する公立高校の受験は厳しくなるということです。
私立高校の受験や通信制の学校など、選択肢が一部減る可能性が高まります。
(詳しくは、在籍校の先生への確認をお勧めします)
【支援学級はどんな子が通う?】まとめ

記事のポイントになります。
✅支援学級に通う子の
「2つの特徴」
・授業に支障を出す行動が出る子
・授業に全くついていけてない子
✅支援学級に通う
「3つのメリット」
・本人の特性に合った指導、環境
・居場所(安心/自己肯定感)になる
・普通学級の子と交流できる
✅支援学級に通う
「5つのデメリット」
・本人がネガティブに捉える
・学級の状況が本人に合わない
・先生に「専門スキルがない」
・在籍校に支援学級がない
・受験の選択肢が減る
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】
【支援級に偏見はある?】教育・療育の現場から見られる”実態”
【発達障害だけど普通学級で貫き通します】事例の紹介~学級選びのポイント~








































