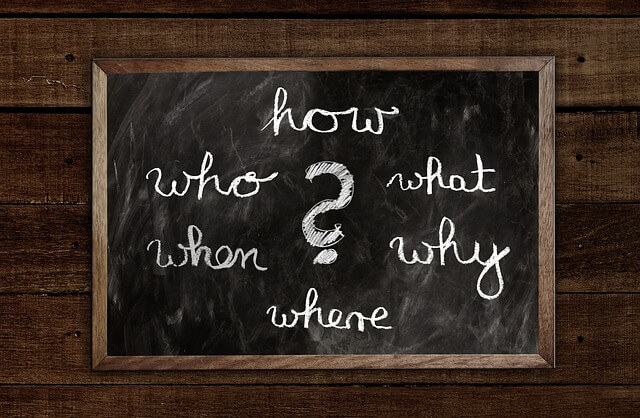

支援学級の担任で悩まれている方「支援学級の担任と相性が合わない。どこまでお願いをしていいか分からない。担任と合わない時にやるべきことが知りたい」
お子さんが支援学級に在籍中、もしくは、これから通うことを、検討されている方にとって、
「支援学級の担任」の存在は、重要ですよね。色んな噂話もあるので、実際に不安を感じる方も、多いかと思います。
私は、発達支援の相談/指導員を15年以上しており、特別支援学級についての相談を、多く受けてきました。
現在も携わってる支援経験を元に、本記事をまとめてます。
参考になれば幸いです。
支援学級の担任と関わる時に「大切なこと」

支援学級の担任と関わる上で「大切なこと」は、3つになります。
まず、担任とやりとりをする上で、「踏まえておきたい/知っておくべきこと」になります。
①:親が担任と子どもの「仲介役」になる
②:「担任と一緒」に作る
③:「支援学級の担任=特別支援のプロ」とは限らない
親が担任と子どもの仲介役になる

担任とお子さんとのやりとりを円滑にする為に、『親御さんが仲介役になる』ことが、大切になります。
理由は、実際に教室で一緒に過ごすのは担任とお子さんだからです。
あくまで、先生とお子さんのやりとりをスムーズにするために、親御さんが入るスタンスを持ちます。
担任と一緒に作る
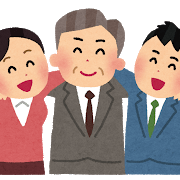
こちらもスタンスに近いのですが、
お子さんの過ごしやすい環境は「担任が作る」ではなく『親と担任で一緒に作る』方が、望ましいです。
担任の先生も人間です。業務に追われる忙しい日々の中、一方的に「先生これお願い」をされては、担任も協力しきれないことが、多くなる場合があります。
私たちも家事・仕事をするときに、「○○お願い」ばかりでは不満が溜まり、協力する気がなくなってしまいますよね。
支援学級の担任≠特別支援のプロ

支援学級の先生は、教員免許を持ったプロです。
ただ、発達障害などの特性を持ったお子さんの支援をする『特別支援のプロ』とは、限りません。
これは、先生がというより、制度の問題になります。制度上の問題などが理由もあり、
支援学級の担任は、全員が全員…
・専門性がある/ない先生もいる
・全員が全員、望んで支援学級の担任になったわけではない
ということを、踏まえておきましょう。
ここについて、詳しく知りたいは、【特別支援学級の担任】専門性がない人もいるって本当?実情とは をご覧ください。
担任と合わない時の「対処法」

学校内でできる、担任と合わない時の「対処法」を2つお伝えします。
①:担任と「話をする機会」を作る
②:「スクールカウンセラー/管理職」に相談する
担任と話をする機会を作る

この方法が一番早く/効果が高い方法になります。
担任と直接お話をして、上手くいくことが一番良いですよね。
連絡帳への記載、立ち話、電話ではなく、面談という形で1時間の時間があることが望ましいです。
先生も大人ですので、余程の先生ではない限り、こちらの言い分は、聞いてくれるとは思います。
ただ、先生も一人の人間です。伝え方次第で、本気で考えてくれるか、動いてくれるのか、は変わっていきます。
4つのポイントを踏まえると、お話が進みやすくなります。
相談のスタンスをもつ
親御さんが一方的に要望を言ったり、先生の指導の指摘などを、しないことです。
先生にネガティブに捉えられたら、協力してもらうことは難しくなるためです。
具体的には、
「○○のことで相談したいことがあるのですが、お時間いかがでしょうか。」
のように、最初に相談したい意思を伝えると、その後のお話が円滑になります。
担任のメリットを伝える
私たち親の気持ちとしては、「子どものために○○して!」と言いたくなりますよね。
ただここでは、グッと堪え、担任を主語にして、伝えることが大切になります。
具体的には、
「席を先生の目の前にして頂けると、子どもに指示が通りやすくなって、先生も個別で声掛けすることが減ると思います。そちらの方が、先生も授業を進めやすいと思います」
のようなイメージになります。
あくまで一例ですので、担任のタイプに合わせて、変えて頂ければ幸いです。
具体的+事実ベースで伝える
「子どもが授業中に、分からない所を先生に質問できなくて困ってる」「授業中は緊張して質問できないと、子どもが言っている」
のように、具体的な場面で事実ベースで伝えると、受け止めてくれる可能性が上がります。
先生によっては「本当にそうなのかな?」と疑問が生まれ、様子を見るといいつつ、
そのまま協力を得られなくなることを、避けるためです(このパターンが結構多いです)。
担任の考えと合わないなら一旦引く
上記の3つの伝え方をしても、担任が全く受け入れる様子がないときは、すぐに引きます。
ここまで工夫をして、理解を示さない場合は、担任自身に問題がある場合が多いです(残念ながら少なくないです…)。
時間を掛けた所で、「担任vs親」になり、関係性が悪化したり、親御さんが消耗したりと、デメリットの方が、多くなってしまいますので…。
スクールカウンセラー/管理職 に相談する

担任とのやりとりが、どうしても難しい場合は、スクールカウンセラー(SC)や学校の管理職(校長、教頭or副校長)に、担任の不安な点を伝えましょう。
スクールカウンセラーは、学校に非常勤として週数日配置されていることが多いです。
面談を申し込み、個別でお話することができます。
また管理職への相談ですが、担任がその学級を担当することは、校長先生の権限で決定されます。
そのため、校長先生に相談することは、筋が通っています。
学校側でも、先生の指導力は、おおよそ把握しています。問題がある先生の何かしらのトラブルは、管理職からすれば、想定の範囲内です。
例えば、対策の1つとして、ベテラン教師と一緒に組ませる、サポートの教員を付けるなど、できる範囲内で対策をしていることがあります。
このような『担任以外』に頼ることも、大切になっていきます。
また、校長からすると学級担当は、「自分が命じた」責任がありますので、その事に何かご意見が出れば、真剣に対応します。
管理職から担任への指導も期待できます。
注意点として、繰り返しになりますが、「クレーム(意見)」ではなく、『相談』というスタンスは、変えないことが重要になります。
子どもに担任の不満を言わない
親御さんが担任に不安を感じていることを、言葉に出してお子さんに伝えるのは、避けた方が良いです。
お子さんに、固定観念が入り、先生の全てを悪く見るようになり、「担任との関係性の悪化に繋がる可能性」があるためです。
もし、お子さんが担任に不安・不満を感じている場合は、「○○って思ったんだね」とお子さんの気持ちを受け止め、共感することをお勧めします。
ここで注意が必要なのは、同調しすぎないことです。
お子さんの中で、「やっぱり先生は悪いんだ!」いう、先生への嫌悪感が増すことになるので…(なかなか難しいのですが…)。
年度の途中で、先生は変えられないので、不必要にネガティブな感情を助長し、関係悪化は避けられた方が、良いです。
教育委員会への相談は、最終手段
校長(教頭or副校長先生)に、相談する前に教育委員会に相談することは、避ける方が良いと思います。
理由は、校長先生(学校側)との関係性を、悪化させる可能性がある為です。
教育委員会とは、校長先生に指導できる立場にあります。
ただ、校長先生としては、自分に相談される前に、教育委員会に相談され、指導を受けたら、良い気持ちはしません。
まずは校長に相談し、どうしても難しい場合は、教育委員会に相談が良いでしょう。
私の経験上、親御さんと学校が対立関係になったら、その後上手く言ったケースは、ほとんどありません。
それぐらい、学校との関係性は基盤になる、重要なものになります。
担任の理解が得られない時の「学習対策」

本記事の内容を実践されても、担任の理解や協力を得ることが困難なことはあります。
ここでは、学習面に心配がある子に向けて、担任の協力が得られない時の考え方、対策をお伝えします。
担任の理解が得られない以上、担任(学校)に期待して労力を割くよりも、割り切って家庭でできる学習対策を始めた方が良いです。
家庭で学習対策をする自信がない場合は、個別療育や家庭教師など、専門の先生に頼ることをお勧めします。
家庭では絶対できない!、という感じでなければ、まずは家庭でできる学習対策から始めるのが良いです。
なるべく、時間、お金、労力などを使わないに越したことはありませんので。
家庭でできる学習対策の1つとして、タブレット学習があります。
デジタル教材のため、学習の拒否感に繋がりづらく、良い意味で勉強感がない為、勉強の苦手意識がある子にも取り組みやすいです。
特性ある子の学習において、以下の3つが大切になります。
・小さな成功体験
・特性に合う学習方法
・学習しやすい環境
小さくても大丈夫ですので、学習でできた!という経験を積み、自分の特性に合う学習方法が把握できると、学習に取り組む時間が増え、結果的に学力の向上に繋がります。
特性ある子向け「タブレット学習」
学習の苦手意識がある、集団授業ではスピードが合わない、プリント教材では理解しにくい、などの特徴がある子向けになります。
ゲーム性が高い学習PGM、本人の理解度に合わせた学習課題の抽出、理解の手助けになるアニメーション学習など、特性ある子が学ぶ上で、大切な要素がいくつも含まれてます。
メリットデメリットなど、詳しく把握されたい方は、こちらの記事をご覧ください。
特性に関わらず、学習の困りを抱えた子に参考になる内容になります。
学習対策の1つとして、参考になれば幸いです。
【支援学級 担任と合わない時】まとめ

記事のポイントになります。
✅支援級の担任と関わる上で大切なこと
・担任と子どもの仲介役になる
・担任と一緒に作る
・支援級の担任=支援のプロとは限らない
✅担任と合わない時の
「対処法」~学校内でできること~
・担任と話をする機会を作る
・管理職に相談する
✅担任と合わない時の
「対処法」~学校外でできること~
・本人の特性の把握
・必要な配慮/環境の把握
・①②を担任へ相談
✅担任の理解が得られない時に
「備えたいこと」~学習面~
・学校以外での学習対策
・特性に合う学習方法
・学習の成功体験を積む
・タブレット学習
以上になります。
本記事が、お役に立てば幸いです。
【関連記事】








































[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点について […]
[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点 […]
[…] 担任とのやりとりで困っている方は、【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点をご覧ください。 […]
[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点について […]
[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策・注意点 […]
[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点 […]
[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点 […]
[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点 […]
[…] 【支援学級】担任と合わない時はどうする?2つの対策と注意点 […]